コンビニで働く外国人スタッフの姿を見かけるのも、すっかり珍しくなくなりました。
実際、多くの外国人がコンビニでアルバイトや就職を希望しており、企業側も積極的に採用を進めています。
しかし、外国人が日本で働くには在留資格や日本語能力など、満たすべき条件があり、採用する側も気をつけるべきポイントがあります。
この記事では、外国人がコンビニで働くために必要な在留資格の種類や、求められる日本語レベル、人気の理由、採用時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

外国人がコンビニで働くために必要な在留資格一覧

外国人が日本のコンビニで働くには、適切な在留資格(ビザ)を持っていることが前提となります。
資格の種類によって、働ける時間や仕事内容に制限があるため、事前の確認が欠かせません。
留学生(資格外活動許可が必要)
外国人留学生が利用しているのが「留学」ビザです。
この在留資格では、原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週に最大28時間までのアルバイトが認められます。
長期休暇中は、1日8時間・週40時間までの勤務が可能です。
ただし、この28時間の上限は他のアルバイトとの合算になるため、複数のバイトを掛け持ちしている場合は注意が必要です。
永住者・定住者・日本人の配偶者
この在留資格は、就労に関する制限がなく、日本人と同じようにフルタイムで働くことができます。
そのため、レジや品出しといった単純労働から専門業務まで問題なく行えます。
ただし、取得には厳しい条件があり、特に若年層には該当者が少ない傾向にあります。
特定活動46号
この在留資格は、日本の大学や大学院を卒業した外国人で、かつ日本語能力試験(JLPT)N1レベルを持っている人に対して認められるものです。
以前は、大学卒業後の就職ではサービス業のような単純作業を行う仕事に就くことは難しかったのですが、特定活動46号の導入によって、一定の要件を満たす場合にコンビニでの接客や業務に就くことが可能となりました。
ポイントとしては、「日本語での円滑なコミュニケーションが求められる業務」であることと、「大学で得た知識や応用能力を活かせる業務」であることが求められます。
これに該当する場合は、大学卒業後もコンビニで正社員として働くことができるようになります。
技術・人文知識・国際業務
このビザは、いわゆる「就職ビザ」の一つで、大学卒業者や実務経験者が日本で働くために取得する資格です。
ただし、コンビニにおいてはレジ打ちや商品の陳列といった単純作業には従事できません。
あくまでも、在庫管理や発注業務、スタッフ管理など、専門性が求められる業務のみが対象となります。
実際に雇用する場合は、その業務内容が「専門的である」と入管に認められるように、詳細な書類を提出する必要があります。
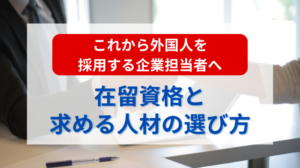
コンビニバイトは外国人に人気?

コンビニのアルバイトは、外国人に非常に人気があります。
コンビニが外国人に人気の理由には、以下のような点が挙げられます。
応募しやすく、求人が多い
コンビニは日本全国に多数存在し、人手不足が慢性的に続いているため、常に求人が出ている状況です。
そのため、外国人がアルバイトを探す際に、応募しやすい職場の一つです。
特に都市部では外国人スタッフの受け入れ体制が整っている店舗も多く、採用のハードルも比較的低めです。
日本語のスキルを実践的に学べる
接客業であるコンビニでは、日々の業務の中で多くの日本語を使う機会があります。
お客様へのあいさつやレジ対応、商品の案内などを通じて、日本語の聞き取りや発話のスキルが自然と身につきます。
このような環境で働くことで、教科書では学べない生きた日本語に触れることができ、語学学習にも大きな効果があります。
日本語能力が向上するほど、他の職場での就職チャンスも広がるため、今後のキャリアのステップアップにもつながります。
高時給を狙える深夜シフトも魅力
深夜勤務のあるコンビニでは、夜22時以降の時給が25%割り増しになります。
週28時間という制限のある留学生にとっては、効率よく収入を得られる点も大きなメリットです。
特に授業が終わった後の時間帯に働けることから、夜間にシフトを希望する留学生も多くいます。
廃棄弁当を持ち帰れることも
さらに、店舗によっては消費期限切れ間近の商品を廃棄せず、スタッフに提供することがあります。
食費を節約できる点も、外国人にとっては見逃せないポイントです。
ただし、この取り扱いは店舗によって方針が異なるため、事前に確認が必要です。
個人経営のコンビニは、比較的廃棄食品をもらいやすい傾向にありますが、大手コンビニの直営店は、原則禁止とされていることが多いです。
コンビニで働くために必要な日本語能力

コンビニでの仕事において、必要とされる日本語のレベルは、日常会話がある程度できる程度であることが一般的です。
日本語能力試験(JLPT)のN5〜N3程度の日本語力があれば、業務をこなせることが多いです。
難しい日本語はあまり必要ない
コンビニの業務内容はレジ対応、商品の陳列、掃除など、比較的シンプルな作業が中心です。
お客様との会話も基本的には定型文でやりとりされることが多く、複雑な語彙や文法を使う機会は少なめです。
例えば、レジでのやりとりでは「いらっしゃいませ」「〇〇円になります」「袋はご利用ですか?」といったフレーズが多く使われます。
これらの言葉を覚えてしまえば、業務はある程度スムーズにこなせるようになります。
日本語能力試験(JLPT)のレベルの目安
日本語能力試験(JLPT)は、日本語の理解度を測る検定試験で、N1からN5までの5つのレベルに分かれています。
N1が最も難しく、N5が最も簡単なレベルです。
- N5:あいさつや自己紹介ができる程度
-
もっとも初級のレベルで、基本的な日本語の文型や語彙を理解して使うことができます。
たとえば、「こんにちは」「名前は〇〇です」「これは何ですか?」といったシンプルな表現ができるレベルです。
日本語学習を始めたばかりの人向けで、読み書きも平仮名・片仮名・ごく簡単な漢字に限られます。
- N4:簡単な日常会話ができるレベル
-
身の回りのことについて、ある程度スムーズに会話できる力があります。
「駅はどこですか?」「お昼は何を食べましたか?」などのやりとりが可能です。
短い文章の読み書きもでき、日常生活で必要な情報を日本語である程度理解できるようになります。
- N3:ある程度まとまった会話が可能で、コンビニでも対応しやすい
-
日常的なシーンで使われる日本語を理解し、自分の意思を表現することもできる中級レベルです。
レジ業務や商品案内、クレーム対応など、コンビニでの基本的な接客に必要なやりとりも可能です。
「〇〇は売り切れです」「温めますか?」「お箸はご利用になりますか?」といったフレーズにも対応できるようになります。
多くのコンビニでは、このN3レベルを目安として外国人スタッフを採用することが多くなっています。
コンビニでは、N3〜N5程度のレベルを持つ外国人スタッフが多く働いており、実際の現場でも大きな支障はないことが多いです。
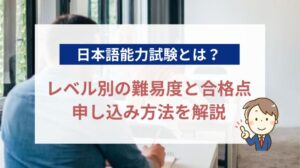
最低限の会話力は必須
一方で、お客様からの質問に対応したり、店内アナウンスを聞き取る場面もあるため、最低限のリスニング力や会話力は必要です。
特に、商品の場所や支払い方法などを尋ねられたときに、対応できるかどうかがポイントになります。
また、商品名を聞き間違えると誤ったものを販売してしまう可能性もあるため、「聞く」「話す」両方のスキルがある程度備わっていることが望ましいです。
働きながら日本語力を高めることも可能
実際にコンビニで働き始めた外国人の中には、日本語にあまり自信がなかったものの、働く中で自然に言葉を覚えていった人も多くいます。
毎日同じフレーズを使い、周囲のスタッフやお客様と話すことで、日本語スキルを実践的に身につけることができます。
また、コンビニ経験は「日本語で接客ができる」という証明にもなり、他のアルバイトや就職活動にも有利に働くことがあります。
コンビニで働く外国人は、最低限の会話力でも働けますが、実際には日本語能力試験(JLPT)のN2〜N3レベル程度の日本語力が求められることが多いです。
レジでの接客や商品案内、公共料金の支払い対応、宅配便の受付など、お客様と日本語で細かいやりとりをする場面が多いためです。
また、マニュアルや社内掲示、伝票などもすべて日本語で書かれていることが一般的です。
N3レベルでもある程度の会話力でも大丈夫ですが、敬語やクレーム対応、緊急時のやりとりなどにはN2以上の理解力があると安心です。
コンビニで外国人を採用する際の注意点

外国人スタッフをコンビニで採用することは、人手不足の解消や多様な人材の活用という点で非常に有効です。
しかし、採用にはいくつかの注意点があり、これを理解せずに雇用を進めてしまうと、トラブルや法令違反につながるおそれがあります。
在留資格の確認は必須
まず最初に確認すべきなのが、応募者の「在留資格」です。
外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格を持っている必要があります。
特に留学生の場合は「資格外活動許可」を取得していなければ、アルバイトであっても働くことはできません。
在留カードの裏面に記載されている内容をしっかりと確認し、許可の有無、労働可能な時間、在留期限などを把握することが重要です。
違法就労が発覚すると、雇用主側にも大きな責任が問われることになります。
労働時間の管理が必要
留学生の場合、1週間に働ける時間は最大28時間までと決まっています。
この制限を超えてしまうと、法律違反となってしまいます。
注意すべき点として、掛け持ちのアルバイトをしている留学生も多いため、合計で28時間を超えていないかの確認が必要です。
週のシフトを調整する際には、本人とこまめにコミュニケーションを取りながら管理するようにしましょう。
文化や価値観の違いに配慮する
採用後は、外国人スタッフと日本人スタッフとの円滑な関係づくりが大切です。
国によって文化や価値観が異なるため、誤解やトラブルが起きることもあります。
例えば、日本では食品を購入すると箸やスプーンを提供するのが一般的ですが、海外ではそのような習慣がない国も多くあります。
日本人にとって当たり前のことでも、外国人にとっては初めての経験であることが少なくありません。
研修では、業務内容だけでなく、日本の接客マナーや店舗のルールも丁寧に説明することが必要です。
日本人スタッフに対しても、多様な文化への理解を深める研修を行うことで、チーム全体の連携がスムーズになります。
外見に関する確認も忘れずに
一部の国では、タトゥーがファッションや文化の一部として受け入れられています。
しかし、日本ではまだタトゥーに対するイメージが厳しい場面も多く、店舗によってはお客様に不快感を与えてしまう可能性もあります。
採用前の面接や説明の中で、勤務中に見える位置にタトゥーがあるかどうか、ピアスや服装の規定を守れるかなども確認しておくと安心です。
雇用契約と労働条件の明確化
外国人スタッフにも、日本人と同様に労働基準法が適用されます。
したがって、雇用契約書の作成や労働条件の説明は非常に重要です。
言語の壁がある場合には、簡単な日本語や母国語での資料を用意するなど、理解しやすい工夫が求められます。
勤務時間、時給、休憩時間、残業の有無など、細かな条件を事前に共有しておくことで、トラブルの防止につながります。
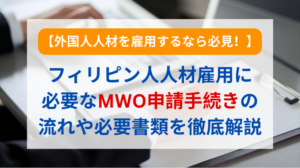
コンビニの外国人採用|まとめ

コンビニは、日本語の実践練習ができ、高時給のシフトも狙えることから、外国人にとって魅力的な職場です。
コンビニで働くためには、在留資格や日本語能力などの条件を満たしている必要があります。
また、採用する企業側も、就労時間の管理や文化の違いへの配慮など、慎重な対応が求められます。
制度や条件を正しく理解し、互いに気持ちよく働ける環境を整えることが、長期的な雇用の成功につながると言えるでしょう。












