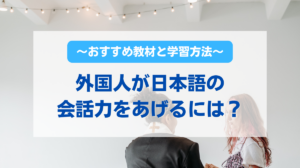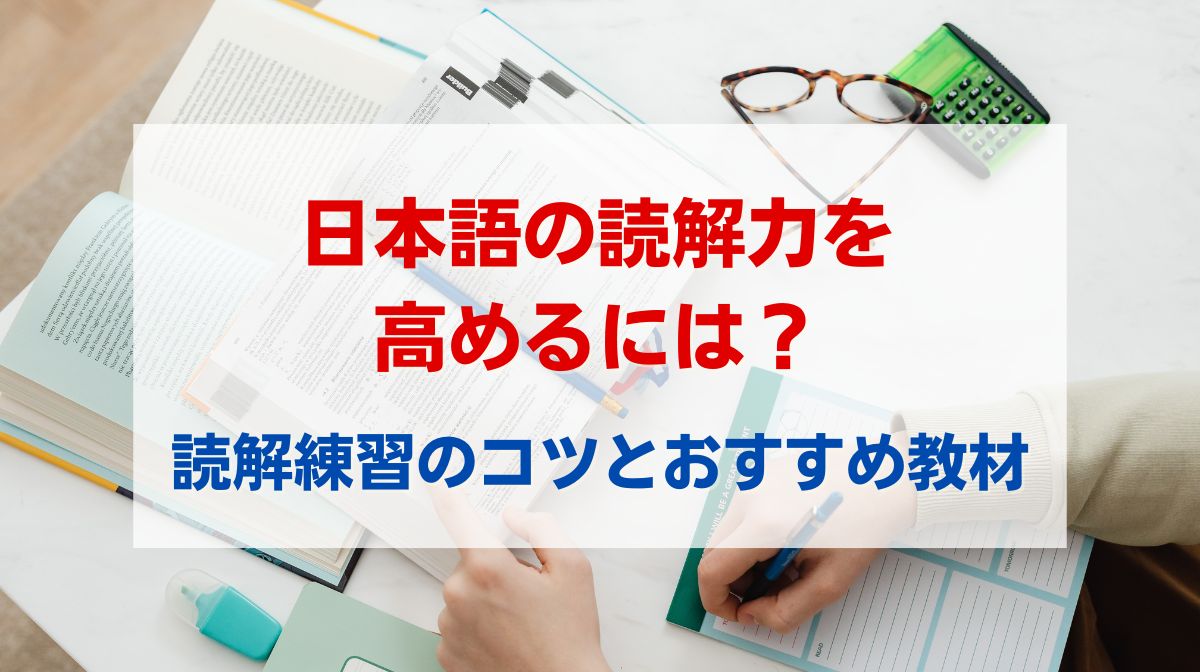日本語の読解力を伸ばすためには、日々の積み重ねがとても大切です。
言葉の意味をただ覚えるだけでなく、実際の文章の中でどのように使われているのかを理解しながら学ぶことで、より深い知識が身につきます。
この記事では、読解力の向上に役立つ読解練習のコツや、レベル別のおすすめ教材を紹介します。
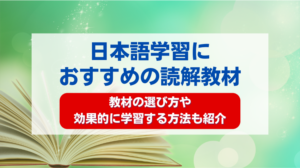
読解練習のコツは?
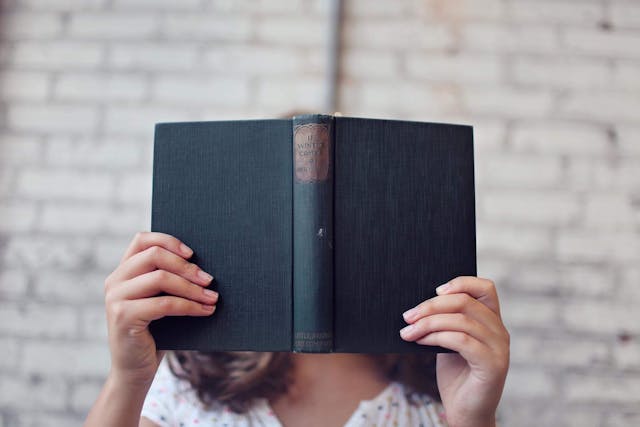
読解力は、ただ文章を読むだけではなかなか伸びません。
目的を持って読んだり、内容を整理したりすることで、理解力は格段に向上します。
ここでは、日本語の読解力を高めるための効果的な読解練習のコツを3つ紹介します。
知らない語句は文脈から推測する
日本語学習者にとって、読解中に知らない単語や初めて見る表現に出会うことはよくあることです。
そんなとき、すぐに辞書を引いてしまうと、読解の流れが止まり、集中力が切れてしまいます。
また、辞書で意味を見ただけでは、実際にその語がどう使われるのかを十分に理解するのは難しい場合があります。
そのため、単語の暗記と同じくらい重要なのが、文脈から意味を推測する力を鍛えることです。
前後の文や話の流れ、登場人物の気持ち、全体のトーンなどから、単語の意味を大まかに予想してみましょう。
たとえば、「~に夢中になっている」という表現が出てきたとき、「夢中」という言葉の意味がわからなくても、その前に「毎日ゲームばかりしている」などと書いてあれば、「何かに強く集中していることかな?」と見当をつけることができます。
このような習慣を続けると、知らない言葉が出てきても恐れずに読み進める力がつきます。
そして、推測→確認→記憶というプロセスを繰り返すことで、語彙はより確実に定着します。
もちろん、あとで正しい意味を辞書で確認することも大切ですが、まずは自分で考えてみるという姿勢を持っておくことも重要です。
精読と多読のバランスをとる
効果的な読解練習には、精読と多読の両方を進めていくのが効果的です。
精読とは、一つ一つの文を丁寧に読み、文法・語彙・構文を深く理解する読み方です。
難しめの教材やJLPTの読解問題などを用いて、「なぜこの文になっているのか」「接続詞の使い方は?」など、細かく考えながら読むトレーニングです。
精読を行うことで、「なんとなく読む」癖を直し、正確に日本語を理解する力がつきます。
特にJLPTのN3以上を目指す人には必要な方法です。
一方で多読は、細かい意味にこだわらず、たくさんの文章を読み流す方法です。
分からない単語があっても止まらず、とにかく最後まで読み進めることで、読解スピードと直感的な理解力が鍛えられます。
多読に適しているのは、物語、エッセイ、やさしいニュース記事、マンガ、ブログなどです。
「日本語に慣れる」「言語センスを育てる」という目的で、気軽に読むことがポイントです。
両者をどう使い分ける?
精読ばかりしていると疲れてしまい、多読ばかりでは正確さが欠けてしまいます。
理想は、週に数回は精読、毎日は多読というように、学習目的に合わせてメリハリをつけることです。
- JLPT対策 → 精読
- 読むことへの慣れ・楽しさ → 多読
このように、目的を意識しながらバランスよく読解練習を行うと、総合的な読解力が高まります。
読みながらメモを取り、内容を自分の言葉で要約する
文章を読むだけで終わらせてしまうと、内容が頭に残りにくいため、特に読解力を強化したい場合は、アウトプットを意識した読書をしてみましょう。
メモを取りながら読む
読書中に気づいたことを、箇条書きや短い文章でメモしておくことで、内容が整理され、記憶にも残りやすくなります。
たとえば、以下のような点をメモしながら読み進めていくとよいでしょう。
- わからなかった単語や表現
- 大事だと思ったポイント
- 筆者の主張や意見
- 自分の疑問や感想
こうしたメモを「読書ノート」としてまとめておくと、後から復習しやすくなり、自分だけの日本語学習ノートが作れます。
自分の言葉で要約してみる
読んだあとに、その内容を自分の言葉で説明する練習も非常に効果的です。
「この文章は何について書いてあったか」を1~2行でまとめてみましょう。
この練習は、読解問題だけでなく、論述や面接、スピーチなどにも応用できる力につながります。
JLPTレベル別の読解練習法
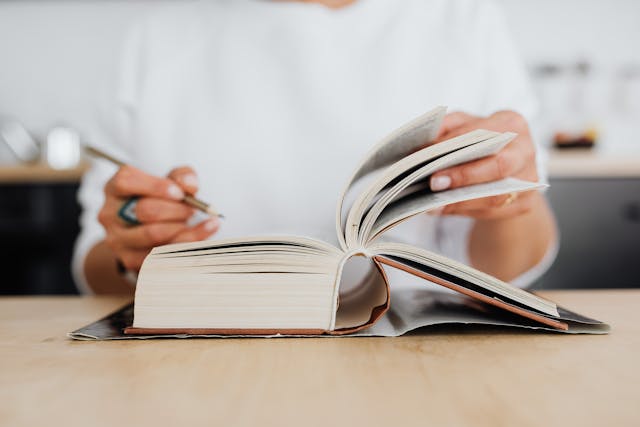
日本語の読解力は、JLPT(日本語能力試験)の得点に大きく関わるだけでなく、日本語全体の運用能力を高めるうえでも非常に重要なスキルです。
ただし、効果的な読解練習を行うには、自分の現在のレベルに合った方法と教材を選ぶ必要があります。
ここでは、JLPTの各レベル(N5~N1)に応じた日本語の読解練習の方法を詳しく紹介します。
初級レベル(N5〜N4)
やさしい日本語の短文からスタート
日本語学習を始めたばかりの初級者にとって、長文を読むのは非常にハードルが高く感じられるものです。
そのため、まずは1~3行程度のごく短い文章を読むことから始めるのが良いでしょう。
この段階では、やさしい日本語で書かれた教材や、日常生活に関わる表現(例:朝のルーティン、買い物、食事、天気など)を取り入れた読解素材がおすすめです。
意味がすぐに理解できる内容に触れることで、読むことへの抵抗感をなくすことができます。
また、ひらがなだけではなく、基本的な漢字が使われている文章を読むことも大切です。
初級者にとって最大の壁は、語彙力と漢字の知識です。
読解練習をしていて意味がわからない言葉が頻繁に出てくると、内容全体の理解が困難になります。
そのため、読んだ文章の中から知らない単語をピックアップし、自分専用の「語彙ノート」や「漢字帳」を作るのが効果的です。
語彙は、単語の意味だけでなく、例文と一緒に覚えることがポイントです。
たとえば、「たのしい(楽しい)」という言葉を覚えるなら、「きのうのパーティーはとてもたのしかったです」という文と一緒に記憶すると実用的です。
また、漢字に関しては、「書く練習」よりもまず「読む練習」を重視しましょう。
読解を通して漢字に繰り返し触れることで、自然と漢字に慣れてきます。
絵付きの教材やストーリーがおすすめ
初級者に最適なのが、絵やイラストが豊富に使われている読解教材です。
視覚情報があることで、文の意味がイメージしやすくなり、理解の助けになります。
特におすすめなのは「やさしい日本語絵本」や「まんがで学ぶ日本語」シリーズなど、ストーリー性のある読み物です。
物語形式の教材は先を知りたくなる「読みたい気持ち」を引き出してくれるため、継続的な読解練習につながります。
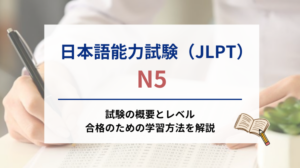
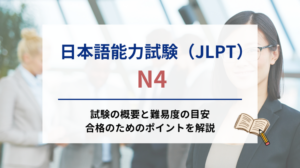
中級レベル(N3〜N2レベル)
ニュース記事を活用
中級者の読解力アップには、日常表現だけでなく、より実践的な日本語の読解練習が必要となります。
そこで活用したいのがやさしい言葉で書かれたニュースサイトです。
毎日1記事ずつ読む習慣をつけると、自然に語彙力と表現力が伸びていきます。
加えて、ニュースは「情報を正確に読み取る」ことが求められるため、論理的な読解力も鍛えられます。
段落ごとの要約と設問形式の練習
JLPTのN3~N2レベルでは、複数の段落で構成された文章を読み、「筆者が伝えたいこと」「要点」「具体例」を読み取る力が問われます。
したがって、段落ごとに要約練習を行うことが非常に効果的です。
たとえば、1つの段落を読み終えたら「この段落では何が言いたいか?」を自分の言葉で書いてみて、これを繰り返すことで、全体の構成を把握する力がついていきます。
さらに、市販のJLPT対策書にあるような設問形式の読解問題も積極的に取り入れましょう。問題を解くことで、読解の「癖」や「弱点」が見えてきます。
文構造の分析も取り入れよう
中級以上になると、単語や文法を知っているだけでは文章の意味を完全に理解するのが難しくなってきます。
そのため、「文の構造」や「つながり」を意識して読む必要があります。
特に接続詞(「しかし」「つまり」「なぜなら」「その結果」など)や、指示語(「それ」「このような」「あれ」など)の役割をきちんと把握できるようにしましょう。
また、構文の読み取りや「主語・述語の関係」に注目する練習を取り入れることで、JLPTの読解パートでも正確に答えられるようになります。
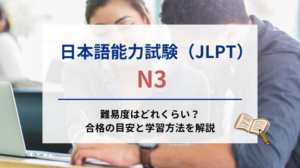
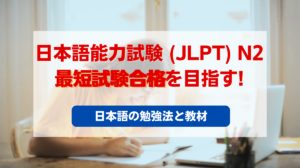
上級レベル(N1)
評論文・論説文・小説などで本格的な読解を
N1レベルでは、日常的な表現にとどまらず、高度な知識や思考を伴う読解力が求められます。
政治、哲学、環境、教育など、抽象度の高いテーマを扱った文章が出題されるため、読解の難易度は非常に高くなります。
そのため、学習教材としては評論文、論説文、専門的な記事、小説の一部などを取り入れるのが効果的です。
特に新聞の論説欄や、日本人向けの国語長文問題などは、実力アップに直結します。
長文を読む際は、「段落構成」「論点」「反論と主張」など、論理展開の流れを常に意識して読むことが大切です。
抽象語彙と論理構造を意識しよう
N1レベルになると、「具体的な出来事を述べる」よりも、「考え方・意見・仮説」を論じる文章が多くなります。
ここで重要なのが、抽象的な語彙とそれが文中で果たす役割を理解する力です。
たとえば、「客観性」「制度的枠組み」「合意形成」など、英語でも難解な抽象概念が登場します。
このような語彙は、繰り返し辞書で調べて例文で確認し、実際の文章の中でどのように使われているかを把握することが大切です。
さらに、文全体の論理構造を理解するために、「因果関係」「対比」「例示」などの論理的なつながりに着目して読む訓練をしましょう。
内容を「説明できる」レベルまで読解する
N1合格を目指す読解練習では、「なんとなく分かった」では不十分です。
読んだ内容を他人に説明できるレベルまで理解を深める必要があります。
読んだ文章を要約したり、内容について自分の意見を書いたりすることで、読解力と表現力の両方を同時に伸ばすことができます。
また、学習パートナーがいれば、お互いに読んだ文章を要約して発表し合う方法もおすすめです。
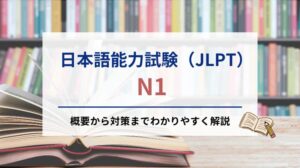
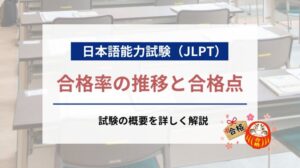
読解練習におすすめの教材
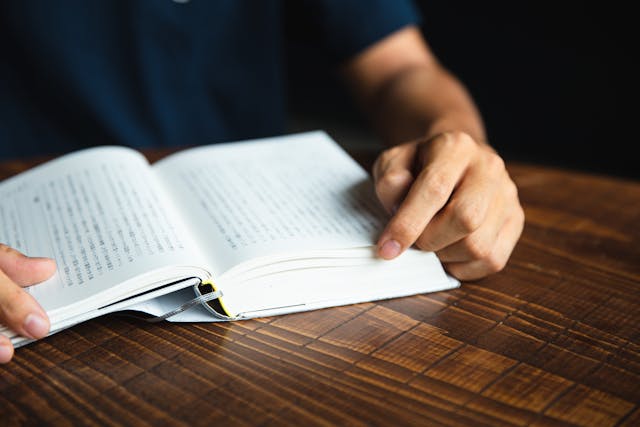
ここからは、読解練習におすすめの教材を紹介します。
初心者におすすめの短文読解
- にほんご多読ブックス(レベル0-2)
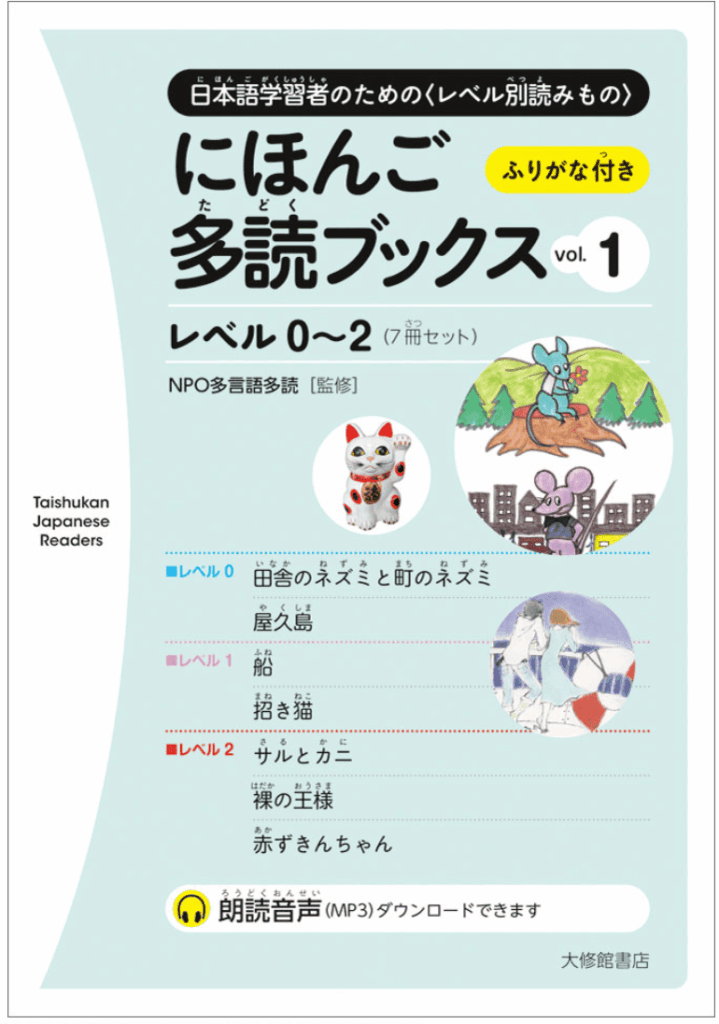
『にほんご多読ブックス〈vol.1〉』は、日本語を母語としない学習者のために作られた多読教材です。
本シリーズは、初級者でもスムーズに読めるよう、「レベル0」から「レベル2」まで段階的に難易度が分けられています。
Vol.1に含まれている7冊の本は、日本の昔話や世界の童話、創作ストーリーなど、バラエティ豊かなテーマを扱っており、学習者が飽きずに読み進められる工夫が施されています。
すべての文章には漢字にふりがなが付けられており、ひらがなしか読めない学習者でも安心して読めます。
また、イラストが豊富で、文章の内容を直感的に理解しやすいのも特徴です。
音声を無料でダウンロードできるため、読解とリスニングを同時に練習することもできます。
- 1日10分 初級からはじめる読解120
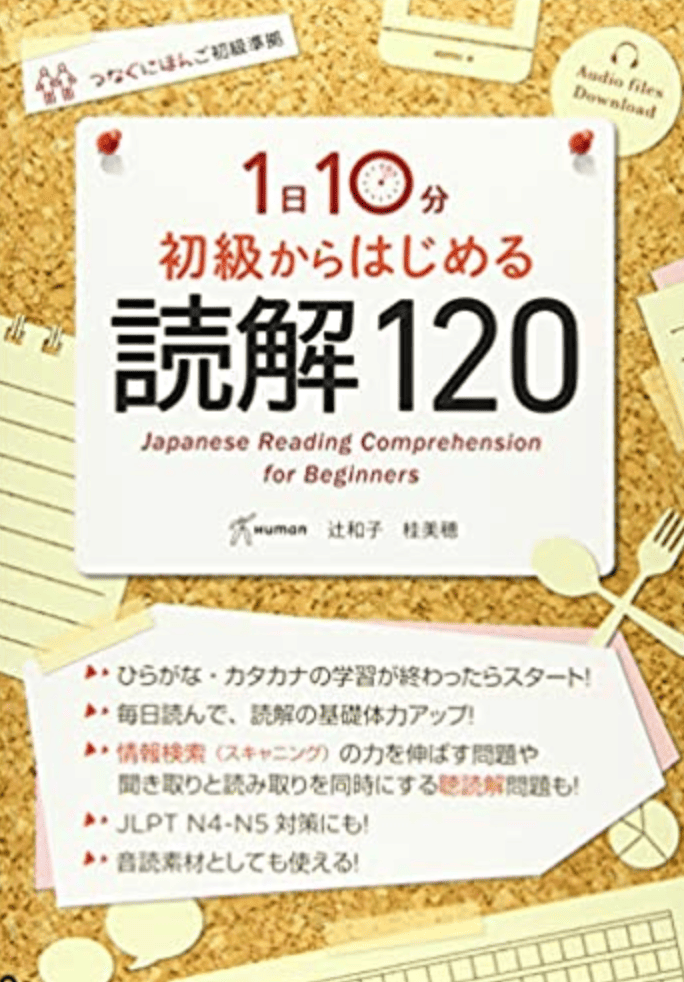
『1日10分 初級からはじめる読解120』は、日本語初級レベルの学習者が「読むこと」に自然と慣れ、短時間で正確に読み取る力を養うことを目指して作られた読解練習教材です。
取り上げられているテーマは、メモ、SNS投稿、新聞記事、お知らせなど、実際の生活で出会う場面を意識した内容ばかり。
毎日1トピック、約10分で取り組める分量になっており、無理なく「読解の基礎体力」を身につけられる設計です。
また、音声のダウンロードにも対応しており、リスニングの補助教材としても活用できます。読解練習を積みたい初級学習者に最適な一冊です。
- みんなの日本語初級Ⅱ第2版 初級で読めるトピック25
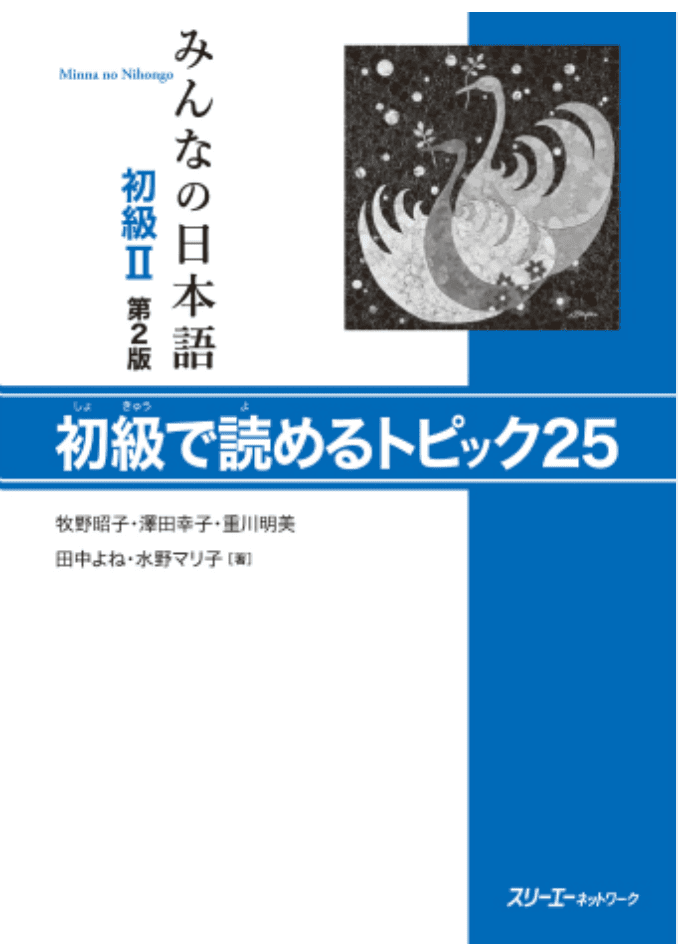
『読んでわかる にほんご読解 初級 中巻』は、日本語初級レベルの学習者が、早い段階から「読むこと」に慣れ、読解を楽しめるようになることを目的とした読解教材です。
日常生活でよく出会うトピックや、日本の文化・社会に関するテーマを扱い、実用性も兼ね備えた内容となっています。
物語、解説文、インタビュー、クイズ、アンケート、メール文など多様な形式で構成されており、学習者がさまざまな日本語に触れながら読解力を養うことができます。
また、文章の後には内容理解を確認する問題も付属しており、自分の理解を確かめながら読み進めることが可能です。
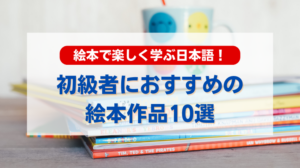
多読におすすめの教材
- NHKやさしいことばニュース NHK NEWS WEB EASY
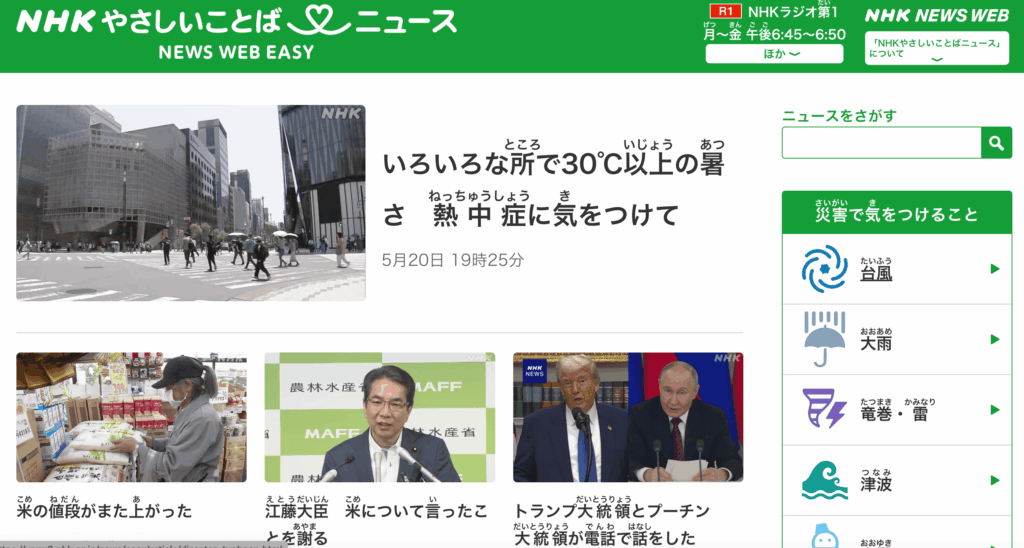
『NHKやさしいことばニュース NHK NEWS WEB EASY』は、NHKが運営する、日本語学習者や子どもを主な対象としたニュースサイトです。
このサイトでは、日々報道されている政治・経済・社会・文化などの幅広いニュースを、「やさしい日本語」に書き直して発信しており、日本語が母語でない人にも内容を理解できるよう配慮されています。
記事にはすべての漢字にふりがなが付いていて、漢字に不安のある初級者でも読みやすいように工夫されています。
また、各ニュースには音声の読み上げ機能があり、読む練習だけでなくリスニング練習にも活用することができます。
- 青空文庫
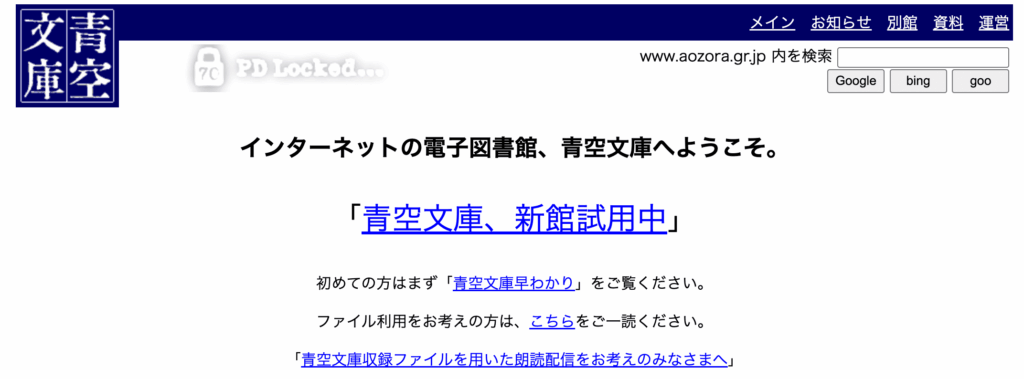
『青空文庫』は、インターネット上で無料公開されている日本語の電子図書館で、著作権が消滅した作品や、著者・訳者が公開に同意した作品を収集・公開しています。
夏目漱石、芥川龍之介、太宰治、宮沢賢治など、日本文学を代表する作家の作品が多数収録されています。
作品は作家名や作品名の50音順、分野別などで検索でき、テキスト版やXHTML版などの形式で閲覧・ダウンロードが可能です 。
いろんな物語をたくさん読んでみたい方におすすめです。
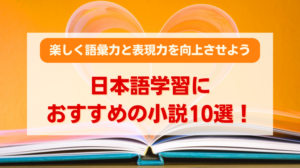
JLPT試験対策におすすめの教材
- 新完全マスター 読解
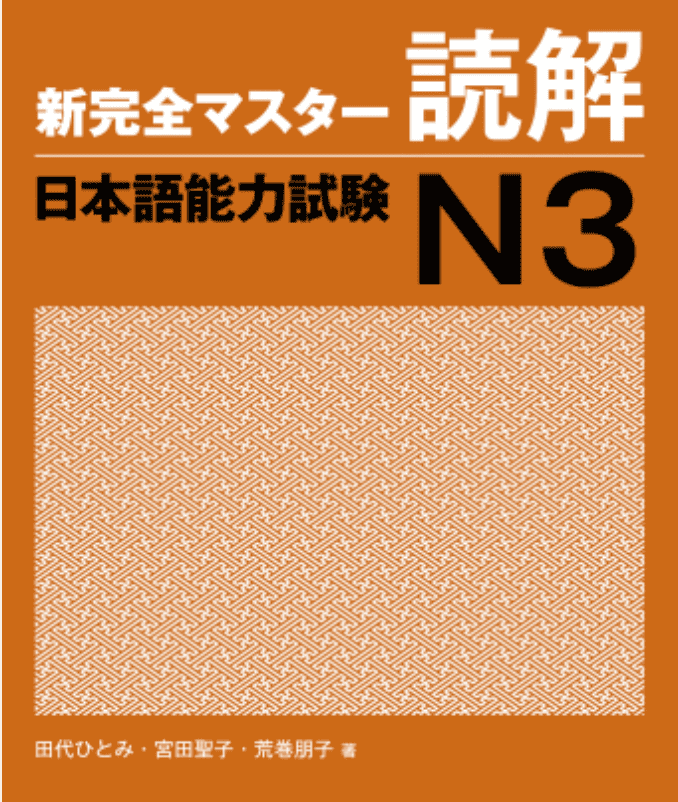
LPTの各レベルに対応した読解練習の定番シリーズです。
問題のタイプごとに戦略的な解き方を学べます。
実際の試験形式に慣れると同時に、日本語の読解力を総合的に高めることができます。
内容は「実力養成編」と「模擬試験(本試験1回分)」の2部構成になっています。
- スピードマスター 読解問題集
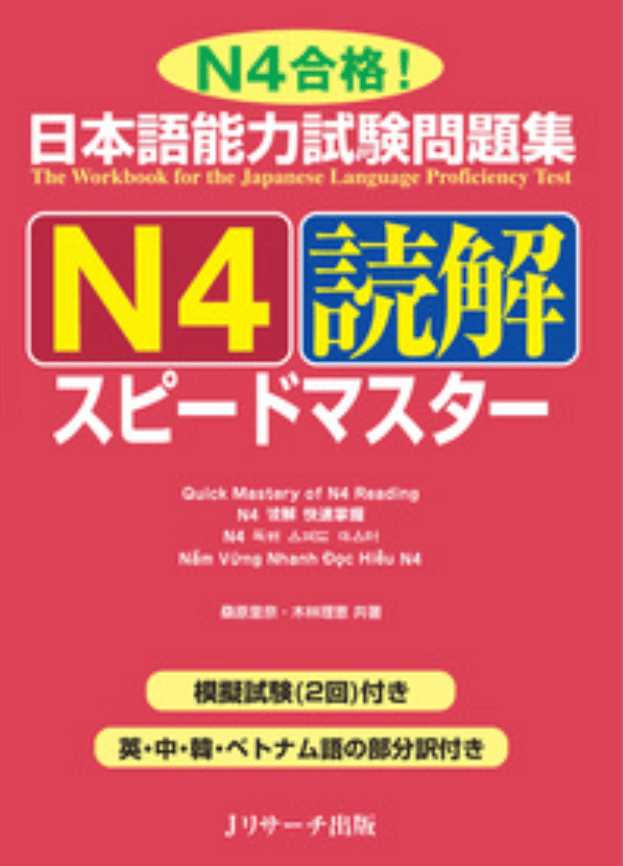
こちらも、JLPTの各レベルに対応した問題集がある定番シリーズです。
限られた時間内で読解問題を解く、スピード重視の実戦向け教材です。
本試験で必要な読解のスピードと正確さを磨きたい人におすすめの問題集です。
日本語カフェ

日本語カフェのJLPT対策コース(N1〜N5)は、試験合格だけでなく、実際の場面で使える日本語力の定着を重視したプログラムです。語彙・文法・漢字・聴解・読解など、総合的な日本語力をアップできます。
「読む力」は語彙力や文法理解とも密接に関係しており、JLPTの全レベルに共通して問われる重要なスキルです。日本語カフェのコースでは、文全体の意味を捉える練習や設問の意図を読み解く力を養うことで、読解問題への対応力を確実に高めます。
▼長文読解のトレーニング
次の文章(ぶんしょう)を読んで、質問に答えなさい。答えは、1・2・3・4から最もよいものを一つえらびなさい。
(1)
幸(こう)ちゃんと、清(きよ)ちゃんは、二つちがいでしたが、①毎日(まいにち)仲(なか)よく学校(がっこう)へゆきました。いつも幸(こう)ちゃんが迎(むか)えにきたのです。
「もう、幸(こう)ちゃんが、迎(むか)えにくる時分(じぶん)だから。」と、清(きよ)ちゃんは、早(はや)くご飯(はん)を食(た)べて、机(つくえ)の上(うえ)の本(ほん)や、筆入(ふでい)れをランドセルに入(い)れました。すると、
「清(きよ)ちゃん。」と、いって、はたして、幸(こう)ちゃんが、迎(むか)えにきました。
「いますぐ、待(ま)っていてね。」と、いうより早(はや)く、清(きよ)ちゃんは、家(いえ)から駆(か)け出(だ)して、二人(ふたり)は、話(はな)しながら、学校(がっこう)へいったのであります。
ある日(ひ)、いつも幸(こう)ちゃんがくる時分(じぶん)なのに、②どうしたのか、こなかったから、清(きよ)ちゃんはこちらから、幸(こう)ちゃんの家(うち)へ迎(むか)えにゆきました。すると、幸(こう)ちゃんは、かぜをひいて、昨夜(さくや)から熱(ねつ)が高(たか)くて、床(とこ)についているのでした。
「じきなおりますから迎(むか)えにきてくださいね。」と、幸(こう)ちゃんのお母(かあ)さんはおっしゃいました。
清(きよ)ちゃんは、③独(ひと)りさびしく学校(がっこう)へいったのです。しかし幸(こう)ちゃんのことが気(き)にかかって、いつものように、なにをして遊(あそ)んでも、愉快(ゆかい)になりませんでした。
いつもなら、帰(かえ)りにも待(ま)ち合(あ)わせて幸(こう)ちゃんといっしょにお家(うち)へ帰(かえ)ったのですけど、その日(ひ)ばかりはさびしく一人(ひとり)で帰(かえ)らなければなりませんでした。
小川未明「いちょうの木」
1 ①毎日(まいにち)仲(なか)よく学校(がっこう)へゆきました。とあるが、なぜか。
1.兄弟だから。
2.たまたまいつも同じ時間に家を出ていたから。
3.いつも一緒に行く約束をしていたから。
4.いつも幸(こう)ちゃんが迎(むか)えにきたから。
2 ②どうしたのかとあるが、何があったのか。
1.時間になっても幸(こう)ちゃんが迎(むか)えにこなかったから。
2.幸(こう)ちゃんがいつもより早く迎えに来たから
3.清(きよ)ちゃんが迎えに行ったから。
4.清(きよ)ちゃんが先に学校に行ってしまっていたから。
3 ③独(ひと)りさびしく学校(がっこう)へいったのです。とあるが、なぜか。
1.幸(こう)ちゃんとけんかをしてしまったから。
2.幸(こう)ちゃんが熱を出して、学校をお休みしてしまったから。
3.幸(こう)ちゃんが先に学校に行ってしまっていたから。
4.今日から独りで学校に行くことにしたから。
教材はスマホやタブレット、PCからアクセスできるため、時間や場所にとらわれず、自分のペースで学習を進められます。通勤・通学のスキマ時間や、ちょっとした空き時間にも取り組めるので、無理なく毎日継続できます。
無料体験を実施中なので、気になった方はぜひ体験してみてください。
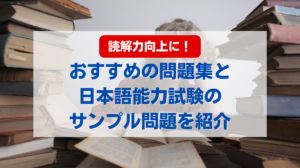
読解練習のコツ|まとめ

読解力を効果的に高めるためには、「日本語の文章に多く触れること」と「目的に合った練習を継続すること」が重要です。
様々な文章に触れることで、語彙や表現の豊かさ、自然な文の流れを理解する感覚などを養うことができます。
一方、試験対策としては、限られた時間の中で的確に情報を読み取る力や、さまざまな問題形式への対応力も求められます。
自分の目的や学習スタイルに合った読解練習の方法を見つけて、日本語の勉強を楽しみながら続けていくことで、読解力を着実に伸ばすことができるでしょう。