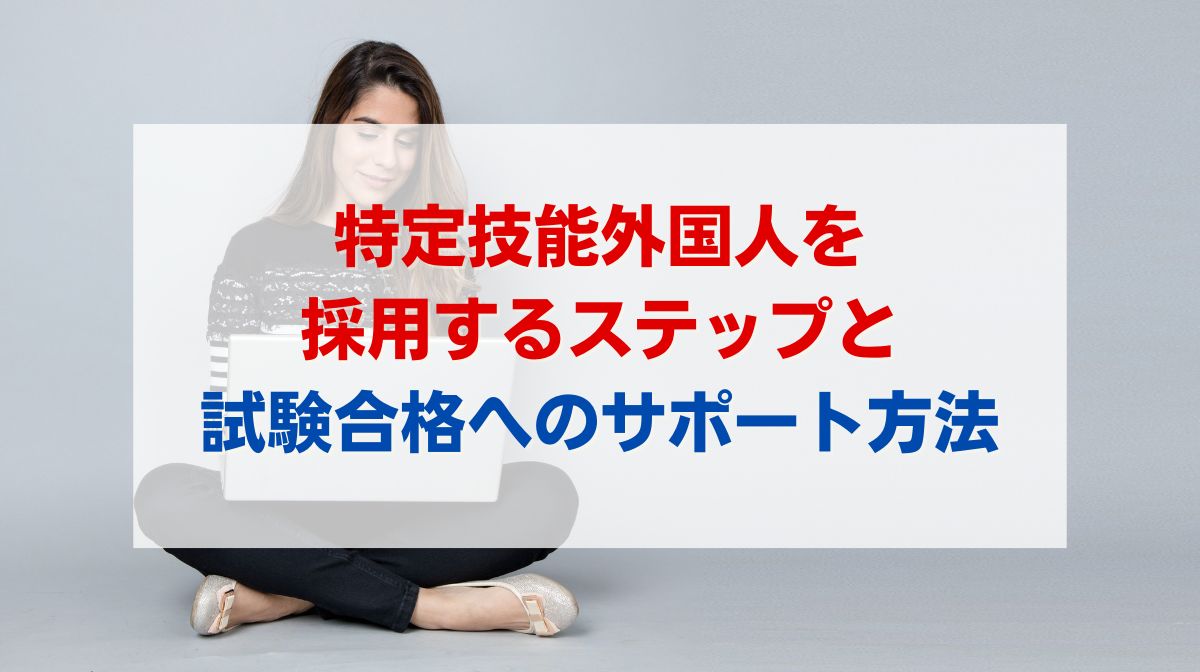外国人材採用を進めるうえで避けて通れないのが「特定技能試験」です。特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人を受け入れるための在留資格制度で、技能水準によって「1号」と「2号」に分かれています。
しかし、制度や試験の種類、企業が担うべきサポートを正しく理解していないと、せっかくの採用計画がうまく進まないこともあります。本記事では、特定技能試験の概要と1号・2号の違いや、企業が押さえるべき採用・サポートのポイントをわかりやすく解説します。
採用計画の基本|特定技能1号と2号の違いとは?

特定技能制度による外国人材採用を成功させるためには、まず制度の基本構造を正確に理解することが欠かせません。在留資格「特定技能」の全体像と、1号・2号の違いを明確に把握しましょう。
そもそも在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度として2019年に創設されました。従来の技能実習制度とは異なり、即戦力として働くことを前提とした制度設計となっています。
この制度の最大の特徴は、技能水準と日本語能力を客観的に測定する試験制度にあります。実際の業務に必要な技能と日本での生活に必要な日本語能力を有していることを、試験によって証明する仕組みです。
企業にとっては、一定水準以上の技能を持つ人材を確実に採用できるメリットがある一方で、候補者の試験合格をサポートする必要も生じます。
【2025年最新】特定技能1号・2号の違いと比較表
特定技能制度では、技能水準に応じて「1号」と「2号」の2つの在留資格が設けられています。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を要する技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年、1年又は6か月ごとの更新 (更新回数に制限なし) |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者・子) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 (介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く) |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 同一分野内で可能 |
| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援は不要 |
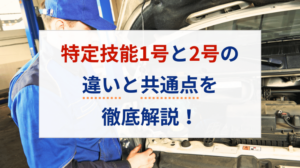
ポイント:2号の対象分野が大幅に拡大!
2024年の制度改正により、特定技能2号の対象分野は大幅に拡大されました。これにより、多くの産業分野で熟練人材の長期雇用が可能となり、企業の人材戦略に大きな影響を与えています。
特に注目すべきは、永続的な雇用の可能性です。2号では在留期間の更新回数に制限がないため、事実上の永住への道が開かれています。さらに家族帯同も認められるため、安定した生活基盤を提供できることから、優秀な人材の確保・定着に大きなメリットがあります。
長期的な人材育成計画を検討している企業にとって、1号から2号への移行制度を活用することで、継続的な人材確保と技能向上を両立できる戦略的な採用が可能となっています。
特定技能人材の採用で企業がすべき3つのこと

特定技能人材の採用において、受け入れ企業が「試験」に関してすべきことは、以下の3ステップです。
ここからは、この3つのステップを具体的にどう進めていけばよいのか、詳しく見ていきましょう。
【Step1: 分野の確認】特定技能の対象分野
特定技能の対象分野は2024年に見直され、全16分野に拡大・再編されました。貴社の事業が該当するのかをまず確認しましょう。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業

【Step2: 受験のサポート】企業の役割と合格必須の2つの試験
採用したい人材が決まったら、次はその候補者の受験をサポートするフェーズです。企業の積極的な関与が、採用成功の確率を高めます。
合格が必須!候補者が受けるべき2種類の試験
特定技能1号の資格を得るには、原則として以下の2種類の試験に合格する必要があります。企業は、候補者がこの両方の試験に合格できるようサポートしなければなりません。
採用したい分野の専門知識や実務能力を測る試験です。例えば、「外食業」で採用するなら「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。試験内容は分野ごとに異なり、各分野の業界団体などが作成・実施しています。
各分野の試験では、安全作業の知識、品質管理、専門技術等、実務に直結する技能が評価されます。試験形式は筆記試験と実技試験の組み合わせが一般的で、分野によって実施頻度や開催地が異なります。
日本での生活や業務に必要な基礎的な日本語能力を測る試験です。以下のいずれかに合格する必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):合格
- 日本語能力試験(JLPT):N4以上
※介護分野のみ、上記に加えて「介護日本語評価試験」への合格も必要です。
JFT-Basicは特定技能制度に特化した試験として開発され、日常生活で必要な日本語コミュニケーション能力に焦点を当てています。一方、JLPTは長年の実績を持つ汎用的な日本語能力試験で、より体系的な日本語学習の成果を測定します。
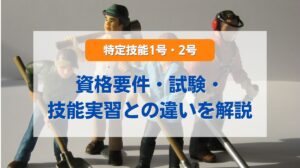
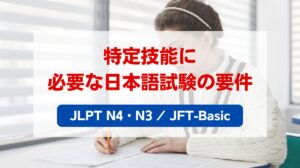
企業の試験対策サポートにおける3つの壁
この2つの試験合格をサポートする上で、多くのご担当者様が以下の3つの壁に直面します。
| ①コストの壁 | 「候補者一人ひとりに技能試験と日本語試験の教材を揃えるのは、人数が増えるほど費用がかさんでしまう…」 |
|---|---|
| ②管理の壁 | 「日々の業務が忙しい中、候補者全員がちゃんと勉強しているか、学習の進捗を管理するのは非常に大変…」 |
| ③専門性の壁 | 「自社の実務は教えられても、試験特有の問題傾向や合格のコツ、専門用語の解説までは指導できない…」 |
このような課題を放置すると、候補者の合格率が上がらず、採用計画そのものが停滞してしまう大きなリスクがあります。
その課題、日本語カフェの『特定技能合格コース』が全て解決します!

「コスト・管理・専門性」の壁を乗り越え、採用活動を効率化する最適なソリューションが、『特定技能1号・2号合格コース』です。
- 1. 圧倒的なコストパフォーマンス
-
教材を個別に購入する必要はもうありません。全分野の試験対策動画が使い放題で、採用人数が増えても大幅なコストカットを実現します。
- 2. 管理工数を“ゼロ”に近づける
-
管理画面で全スタッフの学習状況を一括で可視化。誰がどこまで進んでいるか一目瞭然で、進捗管理や報告の手間が激減し、ご担当者様は本来の業務に集中できます。
- 3. 学習の自走化を促進する「3ステップ学習法」
-
「①動画視聴 → ②ワークシート記入 → ③演習問題」という確立された学習サイクルにより、候補者が自発的に学習を進行。専門知識も体系的に習得できるため、貴社の教育負担を最小限に抑えます。
日本語教育のプロが監修した日本語能力試験(JLPT)対策コースも利用できます。 採用候補者の試験合格から入社後の日本語能力向上まで、ワンストップで強力にバックアップします。
「詳しい料金体系を知りたい」「自社のケースでどう活用できるか相談したい」など、まずはお気軽に資料請求・お問い合わせください。
\お問い合わせはこちらから/
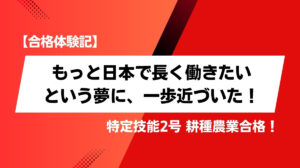
【Step3: 合格後の申請】採用決定から入社までの手続き
試験合格後の在留資格申請は、企業(受入れ機関)が主体となって進める重要なプロセスです。適切な準備と手続きにより、スムーズな採用を実現しましょう。
企業(受入れ機関)が主体となる在留資格申請
在留資格「特定技能1号」の取得申請は、候補者個人ではなく、受入れ機関である企業が主体となって行います。これは、受入れ企業の適格性や支援体制を入管が審査するためです。
申請の流れとしては、まず候補者の試験合格確認から始まります。技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格していることを証明書類で確認し、次に企業側の受入れ準備を整えます。
特定技能の雇用契約では、労働条件、報酬額、支援内容等を明記した雇用契約書を作成します。この契約は、同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等以上であることが要件となります。
続いて1号特定技能外国人支援計画の策定を行います。これは後述しますが、外国人材の日本での生活・就労をサポートするための具体的な計画書です。
最後に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出します。申請から許可まで通常1~3か月程度を要するため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
在留資格申請
大まかな流れは以下の通りです。
- 候補者と雇用契約を締結する
- 「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
- 必要書類を揃え、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請(海外在住者の場合)または在留資格変更許可申請(国内在住者の場合)を行う
- 許可後、ビザ発給・入国、または在留カードの切り替えを経て就労開始
企業が準備すべき必要書類リスト
申請には、候補者が準備する書類の他に、企業側で準備する書類が多数あります。代表的なものは以下の通りです。(※事案により異なります)
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 決算文書の写し
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 支援計画書の写し など
【重要】「1号特定技能外国人支援計画」の作成と義務
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、彼らが日本で安定して生活し、働けるように支援計画を作成し、実施することが法律で義務付けられています。 支援には、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援が含まれます。
この支援計画の作成・実施は、専門の「登録支援機関」に全て、または一部を委託することが可能です。自社での対応が難しい場合は、こうした外部機関の活用も有効な選択肢となります。
【採用成功事例】会社一丸の支援が「特定技能2号」合格を実現
特定技能人材の採用と育成において、企業のサポートがどのように合格へと結びつくのか、具体的な成功事例を見ていきましょう。
技能実習生として来日したインドネシア国籍の社員が、特定技能1号を経て、さらに熟練した技能が求められる「特定技能2号(建設分野)」の試験に見事合格しました。この快挙の裏には、会社一丸となった手厚いサポート体制がありました。
合格へ導いた具体的な支援内容
- 学習時間の確保と環境提供
業務時間内に毎日1時間の勉強時間を確保。さらに、業務後も集中して学習できるよう、会社の会議室を開放しました。 - 教材とツールの全面提供
試験対策に必要な参考書や問題集はもちろん、オンライン学習ツールも全て会社負担で提供。金銭的な心配なく学習に専念できる環境を整えました。 - 継続的なモチベーション維持
役員や周囲の社員が「頑張ってね」「勉強は進んでいる?」と積極的に声かけを実施。孤独になりがちな試験勉強において、こうした精神的なサポートが本人のモチベーションを高く維持する上で大きな力となりました。 - 実務を通じた実践的指導
学科試験だけでなく、実技試験も見据え、日々の業務の中で経験豊富な先輩社員が実践的な指導を行いました。
この事例は、単に制度を利用するだけでなく、企業が候補者一人ひとりに寄り添い、「伴走」することが、本人の努力を最大限に引き出し、採用成功、そしてその先の長期的な人材定着に繋がることを示しています。
参考: 特定技能 2号合格!日本一を目指した男|G.A.コンサルタンツ株式会社
特定技能試験に関するQ&A

ここでは、特定技能試験についてよくある質問に回答していきます。
特定技能と企業の役割まとめ

本記事では、特定技能人材の採用を検討されている企業ご担当者様に向けて、必須要件である「特定技能試験」の概要と、企業が担うべき3つのステップを解説しました。
2024年の制度改正で16分野にまで拡大した特定技能は、貴社の人材戦略における強力な選択肢となり得ます。優秀な外国人材の採用を成功させるには、この試験制度への深い理解と、候補者への効果的なサポート体制にあると言えるでしょう。しかし、そのサポートにはコストや管理工数といった課題が伴うのも事実です。
『特定技能1号・2号合格コース』は、そうした企業の課題を解決し、採用活動の負担を大幅に軽減するために開発されたサービスです。スムーズで確実な人材確保の第一歩として、ぜひ本サービスの導入をご検討ください。
\お問い合わせはこちらから/