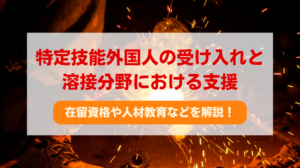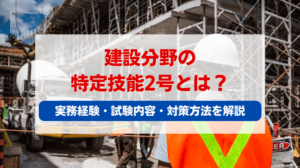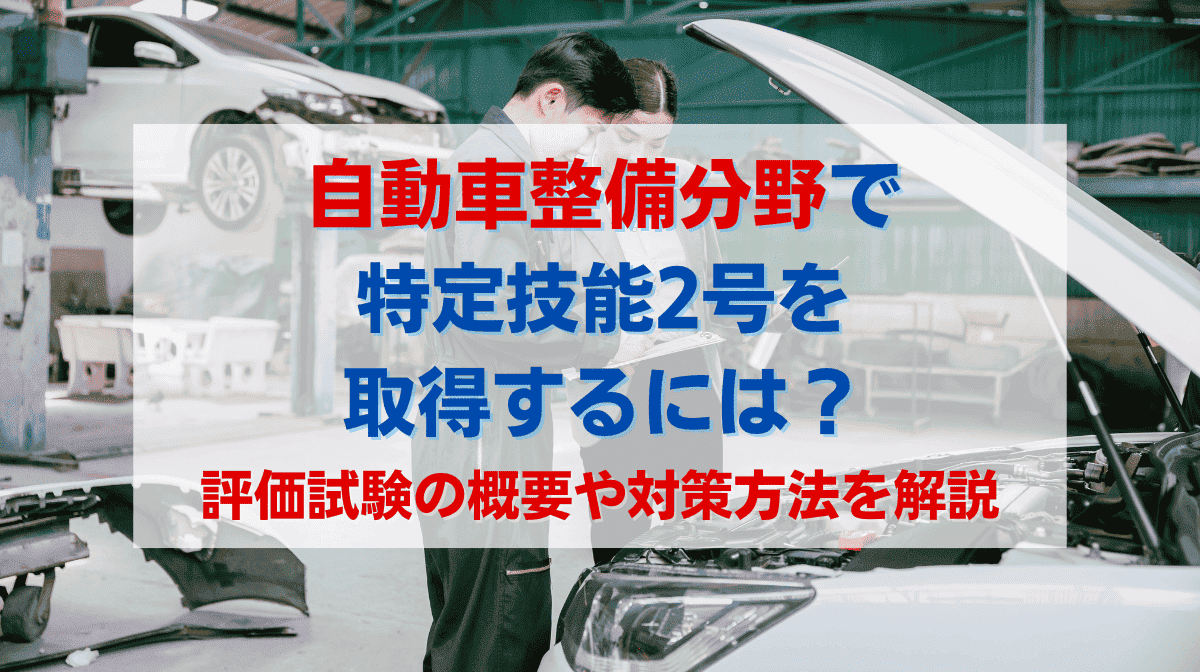自動車整備業界では近年、整備士の高齢化や若年層の減少により、深刻な人手不足が続いています。
こうした課題を解決するため、2024年7月から新たに自動車整備分野に「特定技能2号」が導入されました。
この特定技能2号は、外国人の整備士が日本国内で長期間安定して働くことを可能にする制度です。
本記事では、自動車整備分野の特定技能2号制度の詳細や取得要件、評価試験の概要などについて解説します。
制度の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
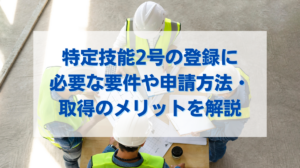
自動車整備分野の特定技能2号とは

自動車整備分野における特定技能2号とは、自動車整備業界の深刻な人手不足を解消する目的で、2024年7月から導入された新たな在留資格制度です。
特定技能2号は、これまでの特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が長期にわたり日本で働ける仕組みになっています。
自動車整備分野の特定技能1号・2号の違い
特定技能1号と特定技能2号の大きな違いは、在留可能期間、家族の帯同可否、求められる技能レベルです。
特定技能1号は最長でも通算5年までの在留期間しかありませんが、特定技能2号は在留期間の制限がなく、更新回数も無制限です。
また、特定技能1号では家族の帯同は原則認められていませんが、特定技能2号は家族(配偶者や子ども)を帯同できます。
さらに、特定技能1号は主に基本的な自動車整備業務を担当するのに対して、特定技能2号では高度な故障診断や修理、若手への指導業務が想定されています。
そのため、求められる技能水準も2号の方がはるかに高いと言えます。
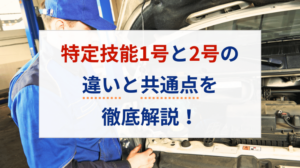
自動車整備分野の特定技能2号を取得するメリット・デメリット
外国人のメリット・デメリット
特定技能2号を取得するメリットは、長期間日本で安定して働けることです。
更新回数が無制限で、将来的に永住権を取得できる可能性もあるため、長期的なキャリア形成がしやすくなります。
また、家族を日本に呼び寄せて一緒に生活できるという点も、外国人にとって大きなメリットです。
一方、デメリットとしては、特定技能2号は高い技能水準が要求されるため、試験対策や実務経験の準備が容易ではありません。
さらに、単純な業務だけでなく、職場での後輩指導や管理業務などを行う必要がるため、業務上の責任やプレッシャーが増える可能性があります。
雇用主のメリット・デメリット
特定技能2号の外国人を雇用する企業側のメリットとして、人手不足の解消や人材の長期確保が可能になる点が挙げられます。
また、高度な技術を持つ外国人材が加わることで、整備業務の効率化や生産性向上、さらには日本人若手整備士への技術指導も期待できます。
人材育成が円滑に進むことは、企業全体の競争力強化にもつながるでしょう。
ただし、デメリットもあります。受け入れ時には特定技能協議会への加入や異文化への理解促進など、雇用企業側に一定の負担やコストが生じます。
さらに、特定技能2号の外国人材には高い技能や管理能力が求められるため、採用後も継続的な教育やサポートが必要になります。
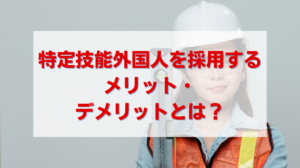
自動車整備分野特定技能2号を取得するための要件

自動車整備分野特定技能2号を取得するためには、「実務経験」と「試験への合格」という2つの要件を満たす必要があります。
ここではそれぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
必要な実務経験
自動車整備分野の特定技能2号を取得するには、「認証工場での実務経験が3年以上」必要です。
この実務経験は、地方運輸局長から正式に認証された整備工場において、自動車の点検・分解・修理・調整などの整備業務に従事した経験が対象です。
転職歴がある場合でも合計して3年以上の実務経験があれば認められますが、その際は各勤務先から実務経験証明書を発行してもらい、すべての書類をそろえて提出する必要があります。
なお、この実務経験期間は、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」を受験する日までに満たしている必要がありますので、受験予定日を基準に計画的に準備を進めていきましょう。
参考:国土交通省|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
申請に必要な試験
自動車整備分野で特定技能2号の資格を取得するためには、次のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験(2024年7月開始)
- 自動車整備士技能検定試験2級
②の「自動車整備士技能検定試験2級」に合格済みであれば、「特定技能2号評価試験」の受験は免除されます。
自動車整備分野特定技能2号評価試験の概要
「特定技能2号評価試験」は、特定技能2号専用の新しい試験であり、学科試験と実技試験の両方に合格することが求められます。
学科試験は、四択問題形式のコンピューター試験(CBT方式)で行われます。
問題数は40問で、試験時間は80分間です。
主な出題範囲としては、以下のような項目があります。
- 自動車の構造、機能、取り扱い方法などの知識
- 点検、修理、調整、完成検査に関する技術
- 整備で使用する機器、計測器、工具に関する知識
- 燃料や材料などの性質・取り扱いに関する知識
- 自動車整備に関連する法律や規則の知識
合格ラインは正解率60%以上です。
実技試験は、実際に整備工場で働く場面を想定した問題が出題されます。
ただし、実際の車両を使用するわけではなく、コンピュータを使ったCBT方式で行われます。
実技試験の出題範囲には以下のような項目があります。
- 基本工作(工具や測定器具の正しい取り扱い)
- 車両の点検、分解、組立、調整、完成検査などの実務知識
- よくある自動車の故障診断や修理対応
- 整備に使用する工具や計測機器の使用方法や管理方法
実技試験は3つの課題からなり、それぞれ複数の質問が設定されています。
試験時間は合計30分間で、こちらも合格基準は60%以上の正答が求められます。
自動車整備分野特定技能2号評価試験の対策方法
特定技能2号評価試験に合格するためには、適切な試験対策が重要です。
特に以下のポイントを押さえて対策しましょう。
- 自動車整備士技能検定試験(2級)の過去問題集を活用すると効果的です。
- 自動車の構造や機能、各種整備機器の使い方など基礎的な知識を正確に覚えることが重要です。
- 日本語の専門用語を理解するために、専門用語の一覧表や参考書を活用するとよいでしょう。
- 実際の整備業務をイメージしながら対策を進めましょう。
特に、よくあるトラブルや修理事例を参考に状況判断力を磨くことが効果的です。 - 過去に起きた故障事例をもとに、自分で故障診断を練習することをおすすめします。
特にエンジンや電装系のトラブルシューティングについて集中的に学習するとよいでしょう。
また、試験対策の参考書籍や模擬問題を利用し、試験に近い環境を想定した模擬問題を繰り返し解くことで、自信をつけることができます。
参考:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会|自動車整備分野特定技能評価試験
また、日本語カフェでは、特定技能対策講座を開講中です。
必要な知識を効率よく学べるので、特定技能試験に確実に合格したい人におすすめです。
自動車整備分野の特定技能2号の申請手続き
自動車整備分野で特定技能2号を取得するには、外国人材と雇用主の双方で必要書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請手続きを行います。
申請には一定の手続きや書類の提出が求められるため、手順やポイントを押さえておくことが重要です。
- 特定技能2号評価試験の合格証明書、または自動車整備士技能検定試験2級の合格証明書(コピー)
- 認証整備工場での実務経験証明書(日整連指定の様式)
- 在留資格変更許可のために必要な書類(申請書、パスポート、在留カード、写真など)
外国人本人が提出する書類は、自動車整備業務に従事できる技術力や経験を客観的に証明するためのものです。
特に実務経験証明書については、不備がないように準備を進めましょう。
勤務経験が複数の会社にまたがる場合は、それぞれの会社に証明書を書いてもらう必要があります。
また、受入れ企業側が用意する書類としては以下のものが必要です。
- 特定技能雇用契約書のコピー
- 報酬に関する説明書(賃金・労働条件などが分かる資料)
- 特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
- 自動車整備分野特定技能協議会への加入を証明する書類
- 企業情報を証明する書類(会社の登記事項証明書や損益計算書など)
申請手続きの流れ
特定技能2号の申請手続きは、以下の手順で進めていきます。
まず最初に、外国人材を受け入れる企業は特定技能協議会に加入する必要があります。
この協議会は、国や関係団体と協力して特定技能制度の円滑な運営を目的としており、加入が義務づけられています。
上記の書類を準備しましょう。
書類が不足していると、審査期間が延びたり不許可になることがあるため、漏れがないよう注意して作成してください。
準備した書類を外国人材の居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。
申請方法としては、直接窓口で申請する方法と、オンラインで申請する方法があります。
申請後、提出書類の内容をもとに審査が行われます。
審査が無事に完了すると、特定技能2号への変更許可が与えられ、新しい在留カードが交付されます。
申請手続きは書類が多く複雑なため、専門家の支援を受けることを検討してもよいでしょう。
特に初めて外国人材を受け入れる場合は、専門の行政書士やサポート機関に相談するとスムーズに進みます。

自動車整備の特定技能2号|まとめ

今回は、自動車整備分野における特定技能2号について、取得要件から試験内容、申請手続きまでを詳しく解説しました。
特定技能2号を取得することで、外国人の整備士は長期間安定して働きながらキャリアアップを目指せます。
また、企業にとっても、高度なスキルを持つ外国人材の雇用は、人手不足の解消や若手社員への技術伝承など多くの利点があります。
一方で、取得には試験と実務経験が必要で、受け入れ企業側にも一定の負担があるため、事前にしっかりと準備を進めておきましょう。
制度を理解して活用することで、外国人材と企業双方が長期的に安定した関係を築くことができます。