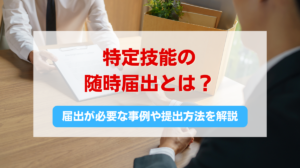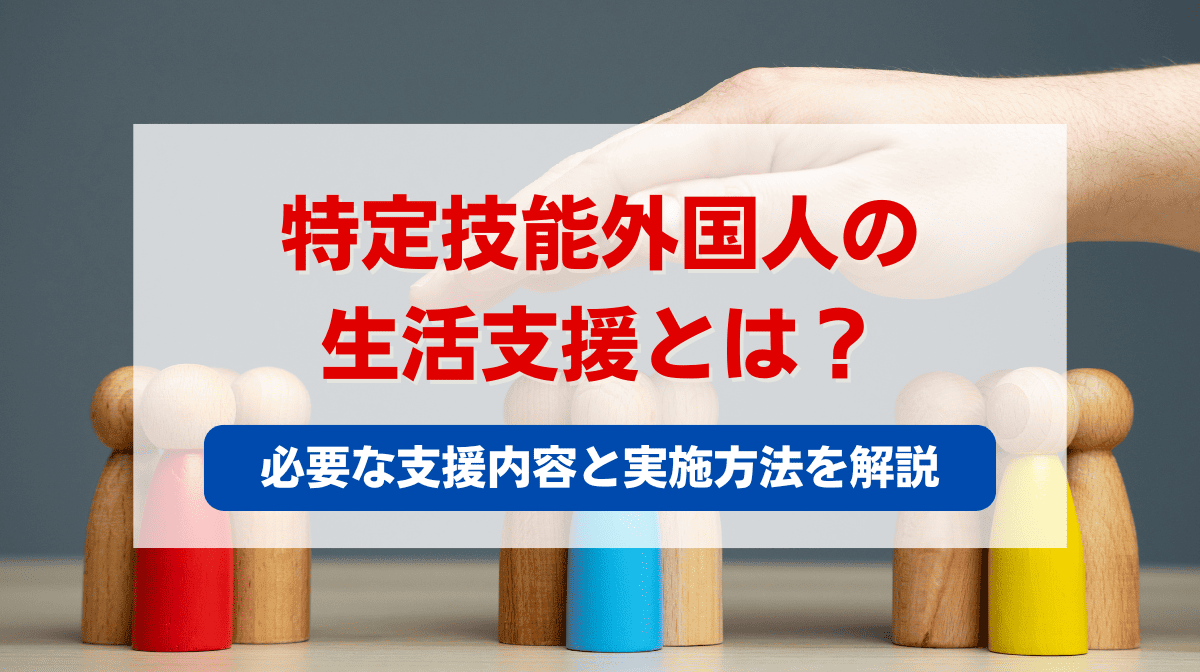特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人の生活支援をする義務があります。
特定技能制度は、日本での労働力不足を補うために導入された在留資格で、外国人労働者が日本で安心して働き、生活できる環境を整えることが求められています。
しかし、日本の文化や生活習慣に慣れていない外国人にとって、住居の確保や行政手続き、医療機関の利用方法などは大きなハードルとなることがあります。
こうした日常生活を送る上での課題を解決するため、雇用側は生活オリエンテーションを実施し、各種手続きのサポートを行わなければなりません。
また、支援の方法には自社で行うか登録支援機関へ委託するかの2つの選択肢があります。
適切な支援を実施することで、特定技能外国人の定着率が向上し、長期的な雇用の安定につながります。
この記事では、特定技能外国人に対する生活支援の内容と、その実施方法について詳しく解説します。

特定技能外国人の生活支援とは?

特定技能外国人の生活支援とは、日本で就労する特定技能外国人が安心して働き、生活できるように、企業が提供するサポートのことを指します。
支援内容は多岐にわたり、生活オリエンテーションの実施、住居の確保、行政手続きの補助、医療機関の案内、日本語学習の機会の提供などが含まれます。
特定技能1号の外国人を受け入れる際に、雇用側はこれらの支援を義務として実施しなければなりません。
支援の方法は、自社で行う場合と、登録支援機関に委託する場合の2つがあります。
自社で行う場合は、外国人材に関する知識を持つ担当者が必要となり、手間や時間がかかることが多いですが、直接サポートすることで信頼関係を築きやすくなります。
一方で、登録支援機関に委託する場合は、専門的な知識を持つ機関が代行するため、企業の負担を軽減できます。
なぜ生活支援が必要なのか?
特定技能外国人は、日本での生活や文化、制度に慣れていないことが多く、適切なサポートがなければ困難に直面する可能性があります。
特に、住居の契約や銀行口座の開設、公的手続き、医療機関の利用方法など、日本人にとっては当たり前のことでも、外国人にとっては複雑で分かりにくい場合があります。
また、生活習慣や文化の違いにより、地域住民とのトラブルが発生することもあります。
例えば、ゴミの分別方法や騒音に関するルール、日本の交通ルールを知らずに問題を起こしてしまうことも考えられます。
企業が適切な生活支援を行うことで、外国人労働者が安心して働ける環境を整え、長期間にわたって定着しやすくなります。
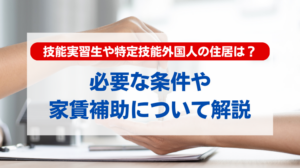
特定技能外国人の生活支援の概要

生活支援には、企業が必ず実施しなければならない「義務的支援」と、実施が望ましい「任意的支援」の2種類があり、それぞれ具体的な内容が定められています。
また、生活支援は、特定技能1号と2号で異なる点もあるため、対象者ごとの対応を理解しておくことが大切です。
さらに、企業は「特定技能外国人支援計画」を作成し、出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。
義務的支援とは?
特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国在留管理庁が定める義務的支援を必ず実施する必要があります。
義務的支援の目的は、外国人労働者が日本で安全に生活し、安心して働ける環境を整えることです。
義務的支援には、以下のような項目があります。
- 事前ガイダンスの実施
-
外国人が入国する前に、日本での生活や労働条件、支援内容を説明する必要があります。
- 入国時の迎えと帰国時の見送り
-
空港や港まで迎えに行き、職場や住居まで案内することが求められます。
- 住居の確保と手続きの支援
-
住居の契約サポートや社宅の提供、家賃の支払い方法の説明などを行います。
- 生活オリエンテーションの実施
-
日本の法律、生活習慣、交通ルール、金融機関の利用方法などを説明し、必要な情報を提供します。実施した後に書類にサインしてもらう必要があります。
- 公的手続きの補助
-
住民登録、マイナンバー取得、社会保険の加入手続きのサポートを行います。
- 日本語学習の機会の提供
-
日本語学校の紹介やオンライン学習の案内などを実施します。
- 相談・苦情対応
-
労働環境や生活面での悩みを相談できる窓口を設置し、適切な対応を行います。
- 日本人との交流促進
-
地域イベントへの参加支援や職場での交流の場を設けます。
- 転職支援(企業都合での雇用終了時)
-
ハローワークの案内や、次の就職先探しのサポートを行います。
- 定期面談・行政機関への報告
-
3か月に1回の面談を実施し、外国人の労働環境や生活状況を確認します。
義務的支援を怠ると、企業は出入国在留管理庁から指導を受けるだけでなく、最悪の場合、特定技能外国人の受け入れが禁止されることもあります。
そのため、適切に支援を行うことが重要です。
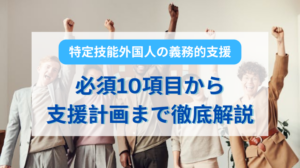
任意的支援とは?
任意的支援とは、企業が実施する義務はないものの、特定技能外国人が日本で快適に生活し、より良い労働環境を確保するために行うサポートです。
任意的支援を充実させることで、外国人労働者の定着率が向上し、企業の評判や採用活動にも良い影響を与えます。
主な任意的支援の内容には、以下のようなものがあります。
- 入国時の服装や気候、持ち物の案内
- 日本語学習の指導や補助
- 地域の交流イベント参加のための休暇提供
- 労災制度などについての説明
- 行政機関の窓口案内
このような任意的支援を積極的に行うことで、特定技能外国人がより働きやすい環境を整えることができます。
生活支援の対象者
特定技能外国人は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。
特定技能1号の外国人には、生活支援が義務付けられていますが、特定技能2号の場合は義務ではありません。
しかし、特定技能2号でも、日本の生活に不慣れな外国人には支援を行うことで定着率が向上します。
支援計画の作成と届出
特定技能外国人を受け入れる企業は、「特定技能外国人支援計画」を作成し、出入国在留管理庁へ届け出なければなりません。
支援計画には、義務的支援の内容や実施方法を具体的に記載する必要があります。
適切な支援計画を作成し、計画通りに支援を実施することで、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることができます。
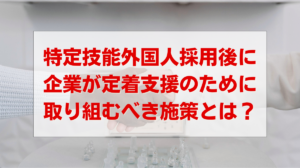
生活支援を適切に行うためのポイント

特定技能外国人に対して生活支援を適切に行うためには、支援内容をしっかり理解してもらうことが重要です。
そのため、言語の配慮やオンライン支援の活用、文化・生活習慣の違いへの対応など、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
ここでは、具体的な支援方法と注意点について解説します。
特定技能外国人が理解できる言語で説明する
特定技能外国人の多くは、日本語に慣れていない状態で入国します。
そのため、生活支援の説明は、外国人本人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。
法務省の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」においても、「生活オリエンテーションは、外国人が理解できる言語で実施することが望ましい」と明記されています。
日本のルールや法律を誤解なく理解してもらうためには、可能な限り母国語で説明することが理想的です。
例えば、生活オリエンテーションの内容には「日本で違法とされる行為」「税金や保険の仕組み」など、重要な事項が含まれます。
これらの内容を正確に伝えられなければ、外国人が法律を知らずに違反してしまうリスクもあります。
トラブルを防ぐための注意点
文化・生活習慣の違いを考慮する
特定技能外国人は、出身国によって文化や生活習慣が異なります。
そのため、日本の生活ルールやマナーを理解してもらうためには、具体的な事例を交えて説明することが大切です。
例えば、日本では以下のようなルールが一般的ですが、外国人にとっては馴染みがないこともあります。
- ゴミの分別ルール:自治体ごとに細かく分かれているため、具体的な分別方法を説明する。
- 騒音問題:特にアパートや寮では、夜間の騒音に注意するよう指導する。
- 交通ルール:日本では左側通行であること、自転車にも交通ルールが適用されることを説明する。
このような文化の違いを考慮し、具体的なシチュエーションを想定しながら支援を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
住居や税金関連の誤解を防ぐ説明が必要
特定技能外国人が日本で生活するうえで、特にトラブルになりやすいのが「住居」と「税金」に関する問題です。
これらについては、事前に十分な説明を行い、誤解を防ぐことが重要です。
- 住居に関する注意点
-
- 契約の際に敷金・礼金が発生することを説明する。
- 家賃の支払い方法や期限を明確に伝える。
- 退去時に原状回復費用が発生する可能性があることを伝える。
- 税金に関する説明
-
- 給与から所得税や住民税が天引きされることを説明する。
- 社会保険料の負担について理解してもらう。
- 確定申告が必要なケース(副業をしている場合など)について案内する。
これらの説明を怠ると、「給与から勝手にお金が引かれている」「退去時に高額な費用を請求された」などの不満につながり、トラブルの原因になります。
外国人労働者が安心して生活できるよう、事前に丁寧な説明を心がけましょう。
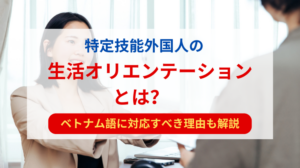
自社で行うか登録支援機関へ委託するかを決める

特定技能外国人を採用する側は、生活支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するかを選択できます。
支援業務には、生活オリエンテーションの実施や公的手続きのサポート、相談窓口の設置など、時間と手間がかかる業務が含まれるため、企業の状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わり、義務的支援を実施する機関です。
企業が特定技能外国人の受け入れを行う場合、生活支援を適切に実施する責任がありますが、登録支援機関を利用することで、支援の一部またはすべてを外部に委託できます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に正式に登録された機関のみが認められています。
支援を委託するメリット
負担を軽減できる
特定技能外国人の生活支援を自社で行う場合、担当者を配置し、必要な知識を学ぶ負担が生じます。
登録支援機関に委託すれば、企業は本業に集中でき、支援の専門家に任せることで負担を大幅に軽減できます。
専門家による適切な支援
登録支援機関には、外国人支援の経験が豊富なスタッフが在籍しているため、適切な対応が可能です。
特に、生活オリエンテーションの実施や、トラブル対応、法律に関する説明は専門的な知識が必要となるため、支援の質を高めるためにも登録支援機関の活用が有効です。
また、外国人が母国語で相談できる環境を提供できる機関もあり、特定技能外国人が安心して働ける環境を整えることができます。
支援を委託するデメリット
登録支援機関に支援を委託することには多くの利点がありますが、いくつかのデメリットも理解しておく必要があります。
委託を検討する際は、以下の点にも注意しましょう。
費用が発生する
登録支援機関を利用する場合、支援業務の代行にかかる委託費用が必要です。
支援内容や契約形態によって異なりますが、定期的な支払いが発生するため、特に中小企業にとってはコスト面での負担を感じることがあります。
複数人を受け入れる場合は、費用が大きくなるケースもあるため、予算と相談しながら検討することが大切です。
通訳者が必ずしも常駐しているわけではない
多くの登録支援機関では、多言語対応のサポートを提供していますが、常に通訳者がいるとは限りません。
緊急時に即座に母国語で対応できないこともあり、外国人本人が不安を感じる場面も出てきます。
実際の通訳対応方法や時間帯、言語範囲などは、事前にしっかり確認しておきましょう。
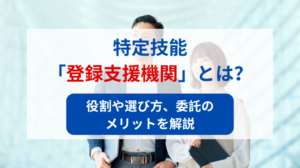
特定技能外国人の生活支援|まとめ

特定技能外国人の生活支援は、外国人労働者が日本で安心して働き、円滑に生活するために不可欠なものです。
企業には義務的支援が課されており、生活オリエンテーションの実施、住居の確保、行政手続きのサポート、相談窓口の設置など、多岐にわたる支援が求められます。
企業は支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するかを選択できます。
自社で支援を行う場合、外国人との信頼関係を築きやすい一方で、業務負担が増加します。
一方、登録支援機関を活用すれば、専門家による適切な支援が受けられ、企業の負担を軽減できます。
適切な支援を行うことで、特定技能外国人が快適に暮らし、長期間にわたって安定して働ける環境を整えることが可能です。
企業としても、労働力の確保と職場の円滑な運営につながるため、適切な支援体制を構築しましょう。