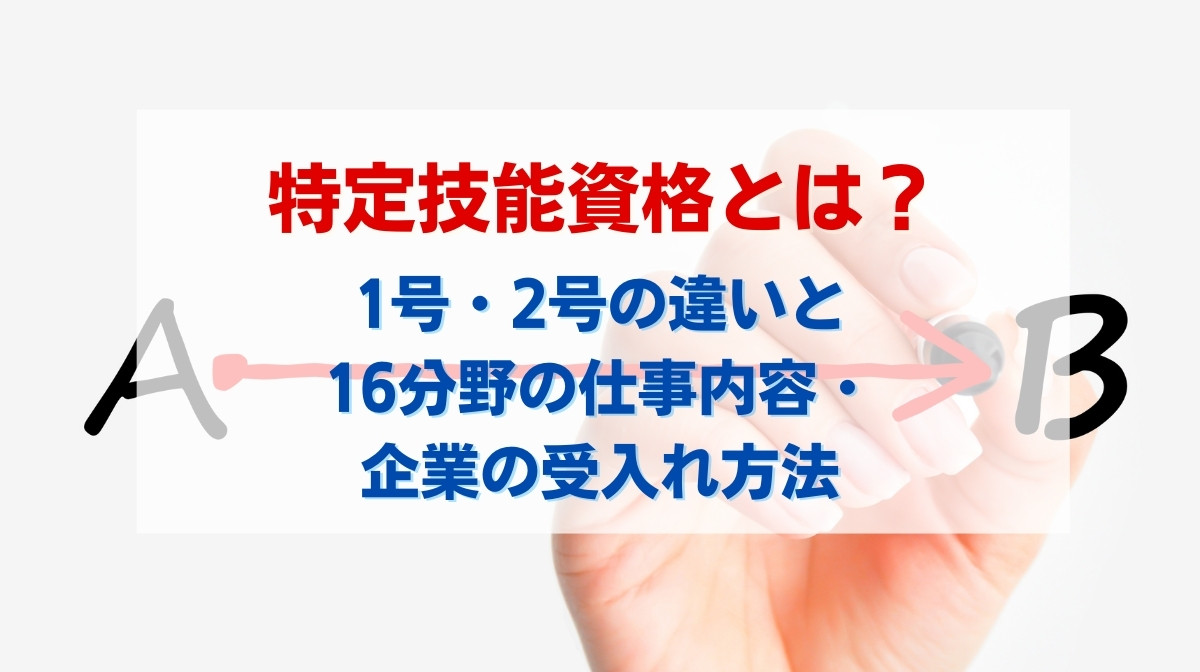深刻化する人手不足への対応策として、外国人材の採用を検討している方も多いのではないでしょうか。
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、即戦力となる外国人材を確保するための制度です。この記事では、特定技能制度の概要から、混同しやすい「技能実習」との違い、そして「特定技能1号」と「2号」の違いについて、2025年の最新情報をもとに分かりやすく解説します。
対象となる16分野の仕事内容から、企業の受け入れ手続き、資格取得の支援方法まで、担当者が知りたい情報をまとめました。
在留資格「特定技能」の概要

まずは、特定技能制度がどのような在留資格なのか、その基本的な目的と、よく比較される技能実習制度との違いから見ていきましょう。
特定技能制度が創設された背景
特定技能制度が創設された直接の理由は、国内の労働力不足です。少子高齢化が進む中、特に一部の産業分野では人材の確保が大きな課題となっています。
この状況に対応するため、一定の専門性や技能を持ち、すぐに業務に従事できる外国人材を受け入れる目的で、新たな在留資格として「特定技能」が導入されました。
企業にとっては、必要なスキルを持つ人材を確保し、事業の継続と発展を図るための重要な仕組みとなっています。
「技能実習」との違いは?
特定技能とよく比較される在留資格に「技能実習」がありますが、両者は制度の目的が根本的に異なります。
技能実習は、日本で培われた技能や技術、知識を開発途上地域へ移転し、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際貢献を目的としています。一方、特定技能は、国内の人材確保が難しい産業分野における労働力を補うことが目的です。
この目的の違いから、技能実習では原則として転職が認められないのに対し、特定技能では同一の業務区分内であれば転職が可能という大きな相違点があります。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の具体的な違い

特定技能の在留資格は「1号」と「2号」の2種類に分かれており、この違いを正確に把握しておくことが大切です。在留期間や家族の帯同など、両者には明確な違いがあります。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 目的 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事 |
| 在留期間 | 通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新) | 上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新) |
| 技能水準 | 各分野が定める試験等で確認 | 各分野が定める試験等で確認(1号より高い水準) |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な水準(日本語能力試験N4程度)を確認 | 試験は免除 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 | 登録支援機関または自社による支援計画の実施が必要 | 支援計画の実施は不要 |
特定技能1号は、特定の分野で即戦力として働ける技能を持つ人材を対象とし、在留期間は通算で5年が上限です。一方、特定技能2号は、1号よりもさらに熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間に上限がありません。
また、2号では一定の要件を満たすことで配偶者や子供といった家族の帯同も認められるため、より長期的な就労が可能となります。
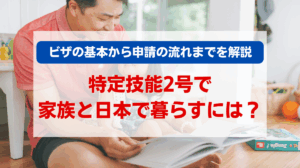
外国人材が資格を取得するための要件
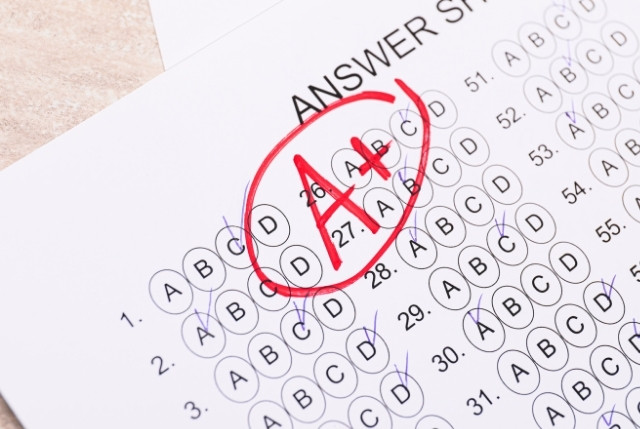
特定技能の在留資格を得るためには、大きく分けて2つの方法があります。
ルート①:技能試験と日本語試験に合格する
一つ目の方法は、それぞれの産業分野が設定する「技能評価試験」と、日本語能力の基準となる試験に合格することです。技能評価試験では、これから従事する業務に必要な知識や経験が問われます。
日本語試験では、業務上および日常生活で求められるコミュニケーション能力を測るため、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」への合格が求められます。
ルート②:技能実習2号を良好に修了する
二つ目の方法は、技能実習制度を活用するルートです。日本で技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行することができます。
ただし、移行が認められるのは、技能実習で従事していた職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性がある場合に限られます。このルートは、既に日本での生活や就労経験がある人材を採用できる点で、企業側にも大きな意味を持ちます。

企業が特定技能外国人を受け入れる流れ

外国人材の採用を決めてから就労を開始するまでには、いくつかの手続きを踏む必要があります。ここでは、企業側が行うべきこと4つのステップで解説します。
国内外で人材の募集と採用活動を行います。ハローワークや民間の人材紹介サービスなどを通じて、自社の求める技能を持つ候補者を探します。
候補者が決まれば、特定技能雇用契約を締結します。この契約では、報酬額を日本人と同等以上とすることや、労働条件を明確に定めることが求められます。同時に、特定技能1号の外国人に対しては、日本での生活や業務を円滑に行えるよう「支援計画」を作成することが義務付けられています。
契約と計画の準備が整ったら、出入国在留管理庁へ在留資格の申請手続きを行います。海外から新たに外国人を呼ぶ場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を、既に日本に在留している外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
無事に許可が下りれば、外国人材の受け入れと就労が始まります。支援計画の実施は、自社で行うこともできますが、専門の「登録支援機関」に委託することも可能です。

特定技能の対象となる産業分野

特定技能では、定められた特定の産業分野でのみ就労が認められています。
特定技能1号の対象分野
2024年の制度改正で4分野が追加され、特定技能1号の対象は合計16分野に拡大しました。それぞれの分野と主な業務内容は以下の通りです。
| 1. 介護 | 身体介護、レクリエーションの実施など |
|---|---|
| 2. ビルクリーニング | 建物内部の清掃 |
| 3. 工業製品製造業 | 鋳造、溶接、機械加工など(※旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」を統合・再編) |
| 4. 建設 | 型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げなど |
| 5. 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工など |
| 6. 自動車整備 | 日常点検整備、定期点検整備など |
| 7. 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備など |
| 8. 宿泊 | フロント、接客、レストランサービスなど |
| 9. 農業 | 耕種農業全般(栽培管理など)、畜産農業全般(飼養管理など) |
| 10. 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修など)、養殖業(養殖水産動植物の育成管理など) |
| 11. 飲食料品製造業 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工など |
| 12. 外食業 | 飲食物調理、接客、店舗管理など |
| 13. 自動車運送業 | バス・タクシー・トラックの運転 |
| 14. 鉄道 | 運転士・車掌、駅係員、指令員など |
| 15. 林業 | 育林、木材の生産など |
| 16. 木材産業 | 木材加工、合板製造など |
特定技能2号の対象分野
従来は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2025年現在は、特定技能2号の対象分野も大幅に拡大されています。
- 建設
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これにより、多くの分野で熟練した人材が、在留期間の制限なく日本で働き続けられる道が開かれています。

特定技能1号から2号への移行について

特定技能1号の在留期間は通算5年ですが、2号へ移行することで、より長期的に日本で活躍してもらうことが可能です。ここでは、その移行手続きと双方にとっての価値を説明します。
2号への移行に必要なこと
企業が育成した人材に長く活躍してもらうためのキャリアパスとして、特定技能1号から2号への移行は非常に重要です。移行するためには、外国人材本人が、それぞれの分野で定められた、より高度な技能評価試験に合格しなくてはなりません。
この試験は、現場のリーダーや監督者として求められる水準の技能を測るもので、1号の試験よりも難易度が高く設定されています。
移行がもたらす双方のメリット
1号から2号への移行は、外国人材本人と受け入れ企業の双方にとって大きな意味があります。
本人にとっては、在留期間の上限がなくなり、安定した生活設計を描けるようになります。また、要件を満たせば母国から家族を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能です。
企業にとっては、時間とコストをかけて育成した熟練の人材に、事業の中核として永続的に活躍してもらえるという、大きなメリットがあります。
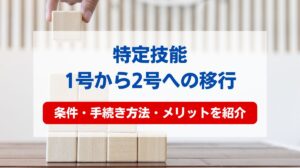
【導入事例】国籍や経験は問わない!実力主義で事業を拡大する農業法人の挑戦

特定技能制度は、実際にどのように活用され、企業にどのような変化をもたらしているのでしょうか。ここでは、国籍を問わず多様な人材を積極的に登用し、事業を大きく成長させている「株式会社Farm大越」の事例をご紹介します。
- 企業名
-
株式会社Farm大越(栃木県)
- 分野
-
農業(いちご、オクラ、アスパラガスなど)
- 導入の背景:人手不足と、外国人材の高いポテンシャル
-
同社は事業拡大に伴う人手不足という課題を抱えていました。日本人従業員の確保が難しい中、家の手伝いなどで農作業経験を持つ外国人材は、農業の辛さや大変さを理解しており、日本人よりも飲み込みが早いケースが多かったといいます。
そこで、技能実習を修了した人材や、国内外の試験に合格した人材を、特定技能として積極的に採用する方針を固めました。
- 導入後の成果:労働力アップが売上増に。日本人従業員の働き方にも良い変化
-
特定技能外国人を受け入れた結果、労働力が大幅にアップし、事業規模の拡大と売上増加に直結しました。
さらに、年末年始など日本人が長期休暇を取りたい時期に、暦の習慣が異なる外国人材が出勤してくれることで、日本人従業員が休みやすくなり、労働時間の適正化にもつながっています。
- Farm大越の取り組み:明確なキャリアパスと、実力本位の評価制度
-
同社が特に力を入れているのが、外国人材のキャリアアップ支援です。国籍に関係なく、実力のある人材を「外国人リーダー」として配置。3ヶ月ごとの面談で目標設定を行い、それを達成することで時給が段階的に上がっていく明確な昇給制度を設けています。
将来的には、農場長や管理者への登用も検討しており、重機やフォークリフトの免許取得費用は会社が100%補助するなど、能力開発を強力に後押ししています。
このように、特定技能制度を戦略的に活用し、外国人材を単なる働き手としてではなく、共に成長する仲間として受け入れることで、株式会社Farm大越は大きな成長を遂げています。
出典;一般社団法人 全国農業会議所「農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集(令和5年度版)」
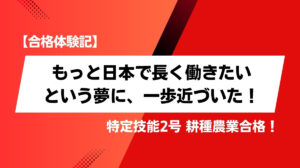
日本語カフェ 特定技能1号・2号合格コースのご案内
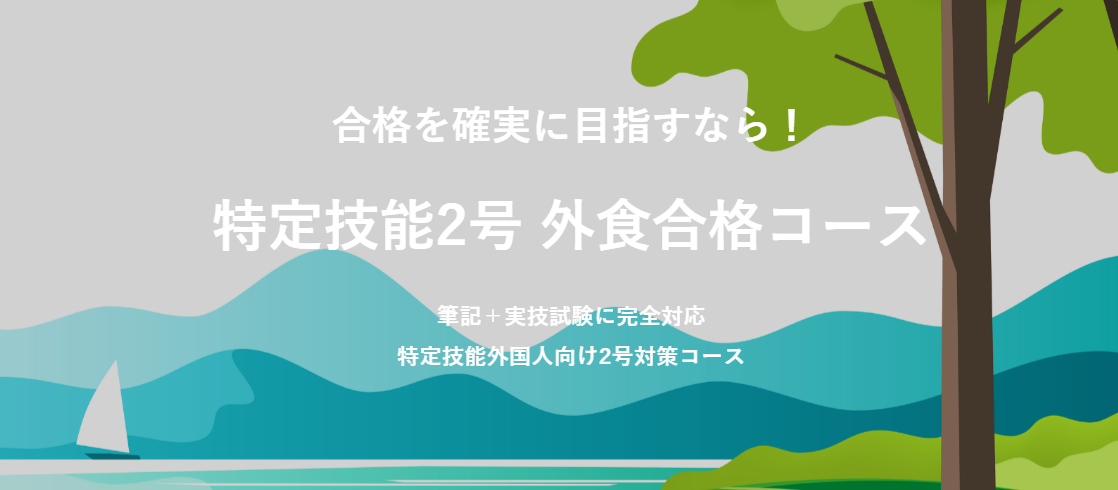
制度の理解は深まったものの、外国人スタッフにどうやって試験勉強を進めてもらうか、頭を悩ませていませんか。
「モチベーションの維持や管理が大変…」
「受け入れ人数が多く教材費が馬鹿にならない…」
「自発的に学習を進めてくれる教材が欲しい…」
といった声は、多くの担当者から聞かれます。
もし外国人スタッフの特定技能の習得をもっと効率的に、それでいて大幅なコストカットを実現したいなら、日本語カフェの『特定技能1号・2号合格コース』の利用がおすすめです。
このコースには、試験合格に特化した動画カリキュラムが用意されており、学科・実技試験の出題範囲をすべてカバーしています。専門知識が求められる内容も、母語のスライドと音声解説で分かりやすく学べるため、外国人スタッフの理解が深まります。
また、管理システムを通じて利用者一人ひとりの学習状況を一目で確認できるので、管理にかかっていた時間もぐっと短縮できます。
- 日本語カフェ独自の「3ステップ学習法」
-
まず1本15分程度の解説動画を視聴し、次に動画と連動したワークシートに記入して知識の定着を図ります。最後に、本番同様の形式で作成された演習問題を解くことで、実践力を養います。このサイクルで、どんな問題が出ても対応できる実力と自信を育てます。
さらに、一流の日本語の先生が監修した日本語能力試験(N5~N1)コースも併せて利用でき、総合的な日本語能力の向上もサポートします。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
特定技能制度の活用、費用や導入までの流れ、そして外国人材の学習サポートについて、貴社が抱える疑問や課題をぜひお聞かせください。
専門のスタッフが、状況に合わせた最適なプランをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
\ お問い合わせはこちら/
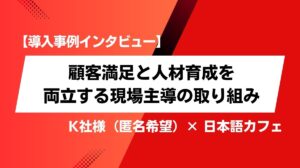
特定技能の資格まとめ

本記事では、2025年時点の最新情報として、特定技能制度の基本的な概要から、1号・2号の具体的な違い、対象となる16分野、そして企業が外国人材を受け入れるまでの一連の流れを解説しました。
この制度は、技能実習制度とは異なり、長期的な雇用とキャリア形成を視野に入れた仕組みであり、特に2号へ移行すれば、在留期間の上限なく、家族と共に日本で生活しながら企業の基幹人材として活躍してもらうことも可能です。これは、貴社の事業の継続性を高め、将来の成長を支える安定した労働力の確保につながります。
しかし、その一方で、在留資格の申請手続きや、採用後の外国人材に対する生活支援、そして資格取得に向けた学習サポートには、多くの時間と専門的な知識が求められることも事実です。
本記事が、特定技能制度へのご理解を深め、貴社にとって最良の人材戦略を考える一助となれば幸いです。貴社にとってどのような人材が必要か、ぜひ具体的な検討を始めてみてはいかがでしょうか。
\ ご相談はこちらから/