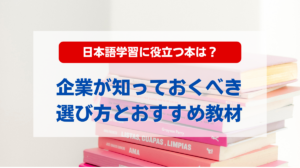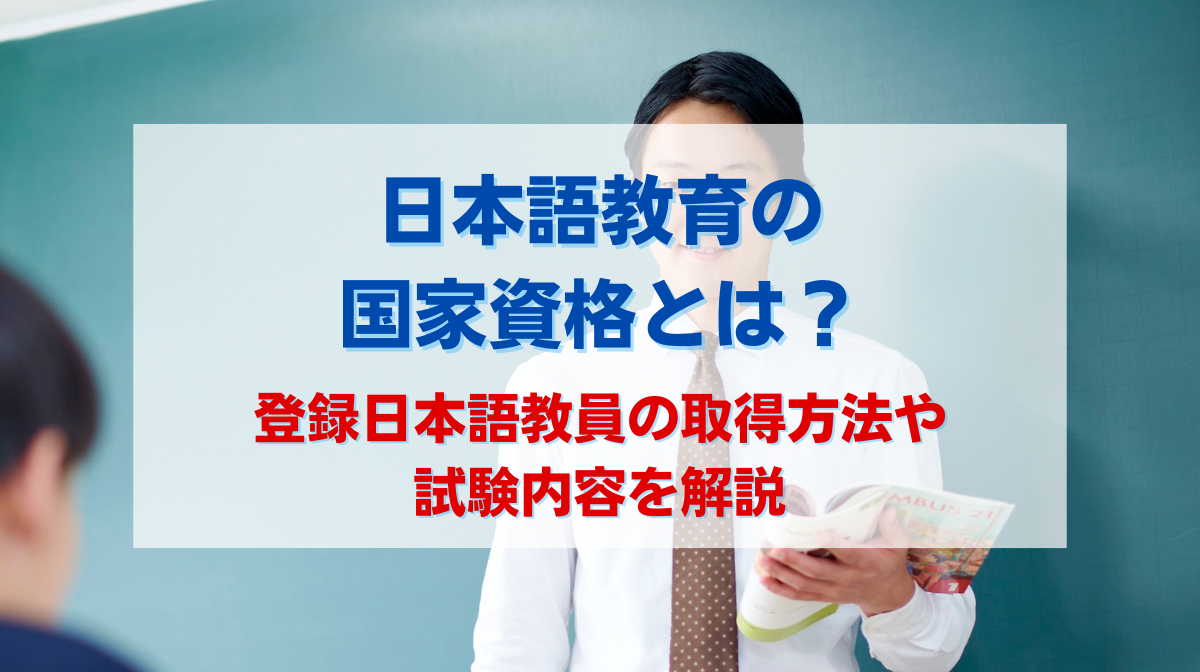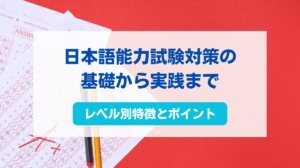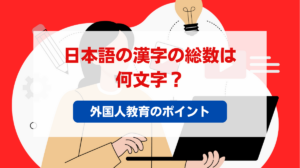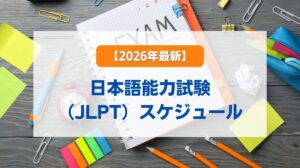近年、日本国内の外国人の増加に伴い、日本語教育の需要が高まっています。
その中で、日本語教師の専門性を向上させ、日本語教育の質を確保するために、新しい国家資格「登録日本語教員」が2024年4月から始まりました。
これまで日本語教師として働くためには、特定の資格が必須ではありませんでした。
しかし、新たに設けられた「登録日本語教員」は、認定日本語教育機関(文部科学大臣認定)で日本語教師として働く際に必要となります。
この記事では、「登録日本語教員」について、その概要や取得方法、従来の資格との違いを詳しく解説します。
日本語教師を目指している方はもちろん、今後のキャリアを考えている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
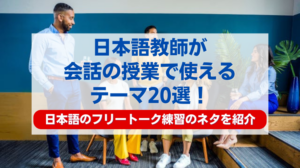
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは

登録日本語教員とは
「登録日本語教員」とは、日本語を外国人に教える専門家としての国家資格です。
この資格は、2023年に成立した「日本語教育機関認定法」に基づき、2024年4月に正式に導入されました。
これまで日本語教師の国家資格はありませんでしたが、制度の整備により、国家資格として「登録日本語教員」が新設されました。
この資格が生まれた背景には、日本国内での外国人労働者や留学生の増加があり、日本語教育の質の向上が求められるようになりました。
特に、留学生の受け入れを行う認定日本語教育機関においては、登録日本語教員資格を持っていないと日本語教師として働けません。
そのため、日本語の教師を目指す方にとって、この資格の取得は今後必須の選択肢となる可能性があります。
これまでの日本語教師との違いは?
これまで、日本語教師として働くためには以下のいずれかを満たすことが一般的でした。
- 大学または大学院で日本語教育に関する課程を修了する
- 日本語教師養成講座(420時間)を修了する
- 日本語教育能力検定試験に合格する
しかし、登録日本語教員制度が導入されたことで、認定日本語教育機関で仕事をする場合は、国家資格が必須となりました。
これにより、日本語教師の資格要件が統一され、より明確な基準が設けられることになります。
日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違い
従来からの日本語教育能力検定試験と、新しく始まった日本語教員試験には、以下のような違いがあります。
| 日本語教員試験 | 日本語教育能力検定試験 | |
|---|---|---|
| 資格の種類 | 国家資格 | 民間資格 |
| 試験内容 | 基礎・応用試験 | 日本語教育に関する基礎知識 |
| 活用範囲 | 認定日本語教育機関での就職に必須 | 民間スクールや海外就職に活用可能 |
| 試験の実施主体 | 文部科学省 | 公益財団法人日本国際教育支援協会 |
日本語教育能力検定試験は民間資格であり、国家資格ではありません。
一方、日本語教員試験に合格すれば、公的に登録日本語教員として認められます。
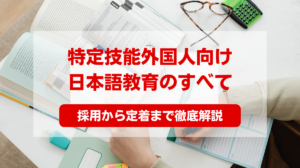
登録日本語教員を取得するメリット・デメリット

登録日本語教員の資格は、日本語教師としてのキャリアを築く上で多くのメリットがあります。
しかし、一方で取得にかかる負担や業界の変化による影響も考慮する必要があります。
ここでは、メリットとデメリットについて整理しておきましょう。
- 公的な資格としての信頼性向上
-
登録日本語教員は国家資格であり、日本語教育業界での認知度が高まります。
これにより、就職の際に有利になる可能性があります。
- 質の高い日本語教育の提供が可能
-
一定の知識や教育スキルを証明するための試験・研修を経て資格が付与されるため、日本語教育の質の向上につながります。
- 学歴・国籍を問わず取得可能
-
これまでの要件と異なり、「学士(大学卒業)」が不要になったため、より多くの人が資格取得を目指せるようになりました。
- 資格取得に時間と費用がかかる
-
養成機関に通う場合、授業料や試験費用が発生します。
また、独学での取得を目指す場合も、試験対策に相応の時間を要します。
- 既存の日本語教師との格差が生じる可能性
-
すでに日本語教師として働いている場合は、一定期間の経過措置が設けられています。
そのため、新たに資格を取得する人との間で条件に差が出ることも考えられます。
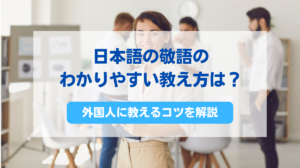
登録日本語教員になるには?

登録日本語教員になるためには、主に以下の3つの方法があります。
それぞれの方法には異なる要件があります。
自分の状況や目標に応じて適したルートを選びましょう。
基本ルート①:養成機関に通う
登録日本語教員になるための最も確実な方法が、「登録日本語教員養成機関」に通うルートです。
- 養成機関での学習内容
-
登録日本語教員養成機関では、日本語教育に関する専門知識や指導スキルを学ぶことができます。
特に、教育実習や実践的な指導方法について学べる点が特徴です。
また、養成機関を修了後は、基礎試験が免除されます。
応用試験・実践研修のみで資格を取得できるため、試験の負担を軽減することができます。
- 養成機関に通う場合の流れ
-
- 登録日本語教員養成機関に入学
- 課程を修了(養成機関によってカリキュラムは異なる)
- 応用試験を受験
- 実践研修を修了(登録実践研修機関は免除)
- 登録日本語教員として申請
- 養成機関に通うメリット・デメリット
-
メリット デメリット 体系的に学べるため、教育の基礎をしっかり身につけられる
基礎試験が免除されるため、試験の負担が軽減される
実習や実践的な指導経験を積める
学費がかかる(養成機関によって費用は異なる)
通学の必要があるため、働きながら取得するのが難しい場合がある
基本ルート②:独学で試験を受ける
養成機関に通わずに、独学で日本語教員試験に合格する方法もあります。
この方法では、基礎試験・応用試験の両方に合格した後、実践研修を受講する必要があります。
- 独学での取得プロセス
-
- 基礎試験に合格
- 応用試験に合格
- 登録実践研修機関で実践研修を修了
- 登録日本語教員として申請
- 独学のメリット・デメリット
-
メリット デメリット 養成機関に通う必要がないため、費用を抑えられる
自分のペースで学習を進められる試験範囲が広いため、効率的な勉強が必要
教育実習の経験がなく、実践的なスキルを学びにくい
実践研修の受講が必須
独学で合格を目指す場合は、市販の試験対策教材やオンライン講座を活用するのがおすすめです。
また、過去問を繰り返し解くことで、試験の出題傾向に慣れることが重要です。
基本ルート③:経過措置を活用
2024年4月の資格制度開始に伴い、既に日本語教師として働いている方に向けた経過措置が設けられています。
この措置を活用すると一部の試験や研修が免除されるため、現職の日本語教師にとっては資格取得の負担が軽減されます。
経過措置にはC・D・E・Fルートなど複数の区分があり、対象者の経歴や資格に応じて免除される試験・研修が異なります。
経過措置を活用するメリットとしては、以下の点があげられます。
- 試験や研修の負担を軽減できる
- これまでのキャリアを活かして資格を取得できる
- 短期間で登録日本語教員になることが可能
ただし、経過措置は期間限定で、Cルートは2034年3月31日まで、D~Fルートは2029年3月31日までの適用期間となっています。
該当する方は早めに申請しましょう。
- 経過措置Cルート
-
Cルートは、学士以上の資格が必要です。
「日本語教員試験」の基礎試験・実践研修は免除となります。また、日本語教員養成機関の課程を修了後、応用試験に合格すると、登録日本語教員になれます。
このCルートに対応している機関は、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」(文部科学省)で公開されています。
- 経過措置D-1ルート
-
経過措置D-1ルートを活用するには、以下の3つの条件があります。
- 現職者である
- 日本語教員養成課程等を修了している(文部科学省の確認を受けたもの)
- 学士、修士、または博士の学位を有す
D-1ルートでは、日本語教員試験の基礎試験・実践研修が免除されます。
基礎試験の免除を受けるには、文部科学省が実施する講習Ⅱを受ける必要があります。
- 経過措置D-2ルート
-
経過措置D-2ルートが適用されるには、以下の条件があります。
- 現職者である
- 現行告示基準教員要件の日本語教員養成課程等を修了している
- 学士、修士、または博士の学位を有することの計3点を満たしている
D-2ルートでは、日本語教員試験の基礎試験・実践研修が免除されます。
ただし、文部科学省実施の講習Ⅰ・講習Ⅱを修了する必要があります。
- 経過措置E-1ルート
-
経過措置E-1ルートが適用されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 現職者である
- 公益財団法人日本国際教育支援協会の日本語教育能力検定試験(昭和62年4月1日〜平成15年3月31日に実施されたもの)に合格
E-1ルートでは、日本語教員試験の基礎試験・応用試験・実践研修が免除されます。
ただし、講習Ⅱ(文部科学省実施)を修了する必要があります。
- 経過措置E-2ルート
-
経過措置E-1ルートが適用されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 現職者である
- 公益財団法人日本国際教育支援協会の日本語教育能力検定試験(平成15年4月1日〜令和6年3月31日)に合格
E-2ルートでは、日本語教員試験の基礎試験・応用試験・実践研修が免除されます。
ただし、講習Ⅱ(文部科学省実施)を修了する必要があります。
- 経過措置Fルート
-
経過措置C・D・Eルートのどれにも該当しない、現職者に適用されるルートです。
Fルートを利用すると、基礎試験・応用試験の合格が必要です。ただし、実践研修は免除されます。
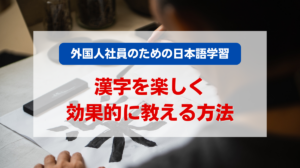
登録日本語教員試験の内容と試験のスケジュール

日本語教員試験は、文部科学省が定めたカリキュラムに基づいて出題されます。
試験は「基礎試験」と「応用試験」の2種類があり、それぞれ異なる分野を評価します。
受験資格
- 年齢、学歴、国籍などの制限なし
- 誰でも受験可能
登録日本語教員の資格は、日本人だけでなく、外国籍の方でも取得できます。
また、学歴要件もないため、高卒や専門学校卒でも受験可能です。
試験科目と出題範囲
日本語教員試験は、基礎試験・応用試験の2つがあります。
それぞれの試験の特徴や出題範囲を詳しく見ていきましょう。
- 基礎試験
-
基礎試験では、日本語教育に関する基本的な知識を問われます。
試験範囲は「養成課程コアカリキュラム」に基づき、以下の5分野から出題されます。
- 社会・文化・地域(日本の文化や社会的背景、外国人支援の知識)
- 言語と社会(言語の社会的役割や日本語の特性)
- 言語と心理(第二言語習得や学習者の心理)
- 言語と教育(日本語教育の方法論や教材の活用)
- 言語(文法や語彙、音声などの言語学的知識)
- 試験時間:120分
- 出題数:100問(選択式)
- 合格基準:5分野すべてで6割以上、かつ総合得点で8割以上
- 応用試験
-
応用試験では、基礎知識をもとにした実践的な教育スキルを評価されます。
学習者とのやり取りや授業の進め方を想定した問題が出題され、実際の指導現場での対応力が問われます。
- 試験時間:
- 音声問題(50問):50分
- 文章問題(60問):50分
- 出題形式:選択式(合計110問)
- 合格基準:総合得点6割以上
- 試験時間:
令和7年度の試験スケジュール
令和7年度の試験日程は以下のようになっています。
- 試験日
-
令和7年11月2日(日曜日)
- 出願期間
-
令和7年7月中旬から1か月程度
- 受験料
-
- 通常
基礎試験及び応用試験 18,900円
- 試験免除を受ける場合
(1)基礎試験免除
免除資格の確認及び応用試験受験料 17,300円(2)基礎試験及び応用試験の双方の免除
免除資格の確認手数料 5,900円 - 結果通知
-
令和7年12月中旬予定

登録日本語教員のまとめ

日本語教員の国家資格化により、日本語教師の業界は大きく変化しました。
認定日本語教育機関で働くには、これまでは必要なかった資格が不可欠になり、日本語教師としての専門性や質の向上が求められるようになっています。
今後、日本語教師として働きたい場合は、登録日本語教員の資格を取得すると有利です。
養成機関を利用するのか、独学で試験を受けるのか、自分に合ったルートを選び、計画的に資格取得を目指しましょう。
また、すでに日本語教師として活動している方は、経過措置を活用することで試験や研修の負担を軽減できる可能性があるため、制度の詳細を確認し、できるだけ早めに資格取得の準備を進めることをおすすめします。
登録日本語教員資格を取得することにより、日本語教育の分野でのキャリアが広がるだけでなく、より多くの学習者に質の高い日本語教育を提供できるようになります。
今後の動向も注視しながら、自分にとって最適な道を選びましょう。