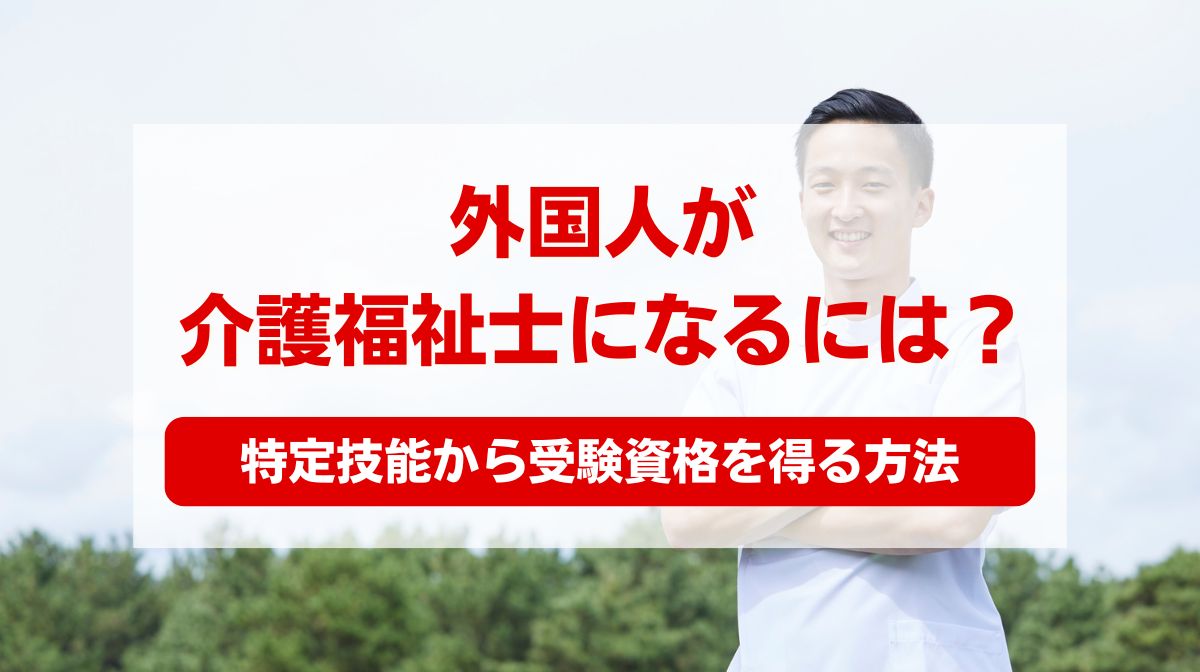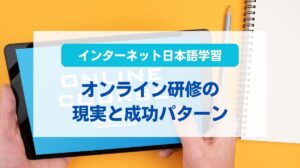介護業界は今、かつてないほど深刻な人手不足に直面しており、外国人材の受け入れは喫緊の課題となっています。特に「特定技能」の在留資格を持つ外国人材は、現場の即戦力として大きな期待が寄せられています。
特定技能の外国人材がさらなるスキルアップを目指し、介護福祉士の国家資格を取得することは、単に個人のキャリアアップに留まらず、企業のサービス品質向上、ひいては経営基盤の強化に大きく貢献します。
本記事では、特定技能「介護」の外国人材が介護福祉士資格を目指す主要な道筋である「実務経験ルート」に焦点を当て、企業がどのように支援できるか、そしてその支援が企業にもたらす具体的なメリットについて、介護福祉士国家試験の概要も交えながら詳しく解説します。

特定技能外国人材が介護福祉士になるには?

特定技能外国人材が介護福祉士国家試験を受験するための最も一般的なルートは「実務経験ルート」です。
このルートは、以下の2つの要件を満たすことで介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。
- 3年以上の実務経験
- 実務者研修の修了
介護等の業務に3年以上従事すること
特定技能「介護」の在留資格で従事している介護の実務経験は、この「3年以上」の期間にカウントされます。
勤務期間がそのまま受験資格に繋がるため、外国人材にとっては最も現実的です。
企業としては、外国人材が介護福祉士国家試験の受験に必要な実務経験を安定して積めるよう、長期的な雇用を前提とした計画的な配置や、適切な業務割り当てを行うことが重要です。
実務者研修を修了すること
実務者研修は、介護の専門知識と技術を体系的に学ぶための必須の研修です。
厚生労働大臣が定める基準を満たす養成施設で、450時間(約6ヶ月~1年程度)のカリキュラムを修了する必要があります。
介護の基礎知識から医療的ケアまで幅広い内容が含まれます。
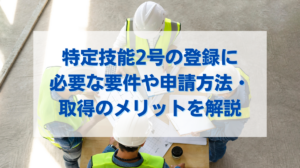
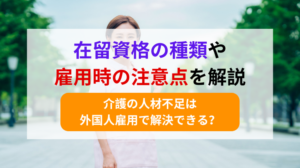
介護福祉士国家試験の概要

介護福祉士国家試験は、日本の介護現場で働く上で必須となる専門的な知識と技術を問う試験です。
筆記試験のみで構成されますが、出題範囲が広く、日本語の読解力も求められます。
| 試験日程 | 例年1月下旬に筆記試験が実施されます。 |
|---|---|
| 申込期間 | 例年9月上旬頃から受験申し込みが開始されます。 所定の期間内に受験申請を行い、必要書類を提出した上で、受験者としての登録を完了させる必要があります。 |
| 試験形式 | 筆記試験のみで、選択方式のマークシート形式です。実技試験は、実務経験ルートの場合は実務者研修を修了していれば免除されます。 |
| 試験時間・問題数 | 午前の部と午後の部に分かれ、合計で約4時間(240分)、問題数は125問程度です。 |
| 合格基準 | 総得点の約60%程度を基準に、問題の難易度で補正されます。 また、全13科目群のうち、指定された一部の科目群で得点がない場合は不合格となります(科目群の合計点が満点の40%未満でも不合格)。 |
| 主な試験科目 | 人間の尊厳と自立、介護の基本 社会の理解 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 生活支援技術 こころとからだのしくみ 発達と老化の理解 認知症の理解 障害の理解 医療的ケア 介護過程 総合問題 |
- 外国人材が受験する際の配慮
試験問題の漢字にはすべてふりがなが付いています。
これは外国人受験者にとって大きな助けとなりますが、専門用語の理解や長文の読解力は依然として重要です。
介護福祉士国家試験に関する最新の情報は、毎年厚生労働省や試験実施団体(社会福祉振興・試験センター)から公開されています。
受験を希望する外国人材や企業担当者は、公式サイトを通じてスケジュールや出題範囲などの詳細を確認しておきましょう。
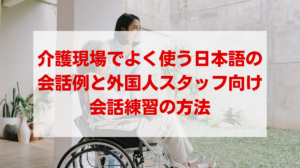
介護福祉士資格取得が企業にもたらすメリット

外国人材が介護福祉士の資格を取得することは、単なる個人の目標達成に留まらず、企業にとって多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。
外国人材の定着率向上
外国人スタッフが「介護福祉士」を目指すはっきりとしたキャリアパスがあると、将来の見通しが立てやすくなります。
その結果、会社への信頼や愛着が高まり、不安が減ることで、日本で長く働きたいという気持ちも強くなります。
また、介護福祉士の資格を取ることで在留資格の面でも、大きなメリットがあります。
たとえば、「特定技能1号」では在留期間が最長5年と決まっていますが、介護福祉士になればこの制限がなくなります。
つまり、実質的に日本にずっと住み続けることも可能になります。
さらに、家族も一緒に日本で暮らすことができるため、生活がより安定し、仕事も長く続けやすくなります。
将来的には、永住権の取得も視野に入れられるようになり、外国人スタッフが安心して働き続けられる土台となるのです。
質の高い介護サービスの提供
介護福祉士は、国家資格を持つ専門職で、介護に関する高い知識と技術を備えています。
そうした人材が職場にいることで、サービスの質が向上し、利用者からの信頼を得ることができます。
また、資格を持ったスタッフは、将来的に他の外国人スタッフの指導やチームリーダーとして活躍することも期待できます。
これにより、多国人材が協力し合える環境が整い、職場全体がより活気づいていきます。
優秀な人材が集まる職場づくり
外国人材のキャリアアップを積極的に支援している企業は、求職者にとって非常に魅力的です。
特に「資格取得をサポートしてくれるかどうか」は、多くの外国人求職者が重視しているポイントです。
このような取り組みは、他社との差別化になり、優秀な人材の確保に繋がります。
さらに、実際に資格を取得した外国人スタッフの体験や口コミは、新たな人材の採用にも良い影響を与え、良い循環を生み出します。
経営の安定と事業拡大への効果
外国人スタッフが長く働いてくれるようになれば、人材の入れ替えが少なくなり、採用や教育にかかるコストを減らすことができます。
その結果、安定的に質の高い人材を確保できるようになり、介護サービスの提供体制もより強固なものになります。
さらに、信頼される介護サービスを提供できる人材が増えることで、新しい事業の展開や施設の拡大など、将来に向けた経営基盤の強化にもつながります。
資格取得のために企業ができる支援

外国人スタッフが「介護福祉士」の資格を取得するには、業務と並行しての勉強や試験への備えが必要となり、非常に大きな努力が求められます。
企業がその努力をサポートする体制を整えることで、スタッフのやる気を引き出すことができます。
以下のような支援が効果的です。
専門用語や長文に対応できる日本語学習の提供
試験で頻出される介護関連の専門用語に特化した日本語研修を行うことは、非常に効果的です。
例えば、「認知症」「誤嚥」「自立支援」など、日常生活ではあまり使わない用語も多く、こうした語彙に慣れるためのトレーニングは不可欠です。
また、試験問題には長い文章を読み取って内容を理解する力も求められます。
文章を最後まで正確に読み解くには、語彙力だけでなく読解スピードや論理的思考力も必要です。
そのため、模擬試験や読解練習を取り入れた実践的な日本語学習プログラムを用意することが望まれます。
勉強と仕事を両立できる環境づくり
外国人スタッフは、普段の業務をこなしながら資格取得のための勉強を進めなければなりません。
これが過重な負担になると、心身に大きなストレスがかかり、勉強が継続できなくなる可能性もあります。
企業としては、そうしたリスクを減らすために、学習時間を確保できるような柔軟な勤務シフトの調整や、残業を減らす工夫が必要です。
また、場合によっては試験前に有給休暇を取得しやすくするなど、勉強に集中できる時間を設けることも有効です。
このように、働きながらでも無理なく学べる体制を整えることで、外国人スタッフの努力をしっかりと後押しすることができます。
教材費の補助と快適な学習環境の整備
外国人スタッフが安心して勉強に取り組めるように、学習に必要な教材の提供や費用補助も有効です。
たとえば、介護福祉士試験の過去問題集や最新の対策テキスト、分野別の参考書などを会社で用意する、あるいは購入費用を一部補助することで、経済的な負担を軽減できます。
また、自宅で集中して勉強することが難しい人もいます。そうした場合には、社内に静かで集中できる学習スペースを用意するのも効果的です。
図書室のような環境や、休憩時間にも勉強できるスペースを整えることで、自然と学習の習慣が身につきやすくなります。
メンタル面のサポート
慣れない日本で働きながら勉強することは、精神的にも大きな負担となります。
言語や文化の違いだけでなく、試験への不安やプレッシャーなど、さまざまなストレスを抱えている外国人スタッフも多くいます。
そうした状況に対して、企業側ができることは、定期的に面談やヒアリングを行い、スタッフの学習状況や悩みを把握しながら、適切な声かけや励ましをすることです。
単に学習の進み具合をチェックするだけでなく、「困っていることはないか」「体調や生活は問題ないか」といった細やかな気配りが、安心して勉強に取り組める環境づくりに繋がります。
目標達成に向けて前向きな気持ちを保てるよう、企業が精神的なサポートを行うことは非常に重要です。
先輩の成功体験を共有してモチベーションを高める
すでに介護福祉士の資格を取得した外国人スタッフがいる場合は、その人の体験談を社内で共有することが非常に効果的です。
「どんな勉強をしたか」「どのような壁があったか」「どのように乗り越えたか」といった具体的な話を聞くことで、まだ資格を目指しているスタッフにとって大きな励みになります。
「自分も頑張ればできるんだ」という前向きな気持ちが生まれ、学習に対する意欲や資格取得の目的を再確認できます。
また、成功者がメンターのような役割を果たすことで、より実践的なアドバイスが受けられる機会にもなり、職場全体の学習文化が自然と育まれていきます。
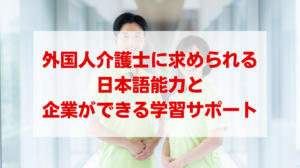
外国人材が介護福祉士になるその他のルート

特定技能外国人材が介護福祉士になるためのルートは、実務経験ルート以外にも主に以下の2つがあります。
これらのルートも、企業が外国人材のキャリア支援を考える上で理解しておくべき重要な選択肢です。
EPA(経済連携協定)ルート
EPAルートは、日本と外国との経済連携協定(Economic Partnership Agreement:EPA)に基づいて、日本で介護福祉士を目指す外国人材の受け入れ制度です。
この制度では、母国で事前に日本語や介護の基礎知識を学んだ「EPA介護福祉士候補者」が来日し、日本の介護施設で実際に働きながら、介護福祉士の国家資格取得を目指します。
この制度を利用できるのは、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国からの人材に限られています。
候補者は母国で一定期間の日本語研修を受けた後、日本に入国します。
日本語能力については国ごとに基準が設けられています。
来日後、介護施設などで3年以上の実務経験を積みながら、介護福祉士の国家試験に向けた準備を進めます。
働きながら勉強するというハードな環境の中で、職場の支援や日本語力のさらなる向上が重要となります。
就労期間は原則4年間とされており、この期間内に介護福祉士の国家試験に合格することが求められます。
試験に合格すれば、「介護福祉士」として日本での就労や在留を継続することが可能になります。
| EPAルートのメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | 就労しながら資格取得を目指せるため、経済的な心配が少ないです。 筆記試験では試験時間が1.5倍に延長されるなど、外国人材への配慮があります。 実技試験がありますが、「実務者研修」や「介護技術講習会」を受講することで免除も可能です。 |
| デメリット | 対象国が限られています。 基本的に4年間の就労期間中に合格する必要があり、受験機会は通常1回です。不合格の場合は原則帰国しなければなりません。 日本語能力の初期要件が比較的低い国もあるため、来日後の日本語学習支援がより重要になります。 |
養成施設ルート
外国人が日本で介護福祉士の国家資格を取得するためのルートの一つに、「養成施設ルート」があります。
これは、日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)に入学し、所定の課程を修了することで国家試験の受験資格を得る方法です。
このルートで受験するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 文部科学大臣および厚生労働大臣、または都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設で学び、2年以上の課程を修了すること。
- 入学の際には、日本語能力試験(JLPT)N2程度の日本語力を求められることが一般的です。これは、授業や実習、国家試験の内容を理解するために十分な日本語力が必要とされるからです。
| 養成施設ルートのメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | 体系的かつ専門的な知識・技術を習得できるため、国家試験の合格率が高い傾向にあります。 養成施設でしっかりとした教育を受けるため、卒業後すぐに即戦力として活躍しやすいです。 実技試験が免除されるため、筆記試験に集中できます。 |
| デメリット | 学費がかかるため、経済的な負担が大きい場合があります。 養成施設に通うための時間が必要であり、就労しながらでは難しい場合があります(在留資格が「留学」となるため、原則として就労は制限されます)。 |
介護福祉士に合格した事例を紹介
介護福祉士試験に合格された外国人介護職の方の体験をご紹介します。

- 介護福祉士を目指した理由
-
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
-
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- 教材だけでなく、現場からも学ぶ
-
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
- 介護の現場でますます求められる人材に
-
日本の高齢化が進む中、介護の現場では外国人材の力がますます必要とされています。
介護福祉士は、利用者の身体介護だけでなく、生活支援・チーム連携・記録・家族対応など幅広い役割を担います。
日本語力と介護の専門知識を兼ね備えた人材は、現場においても非常に重宝され、将来的にはリーダー的な存在としての活躍も期待されています。
今回の合格はゴールではなく、次のステップの始まりです。
今後は日本語能力試験N1の合格と永住権取得を目指し、さらに深く介護の知識を身につけ、長く地域に貢献できる存在を目指していくそうです。
- 最後に
-
資格取得までの道のりは決して平坦ではありません。
しかし、「正しい学習法」と「継続する力」があれば、夢は必ず実現できます。
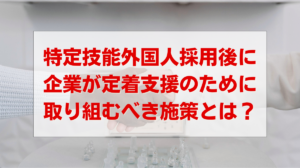
日本語カフェの「介護福祉士 合格対策集中講座」
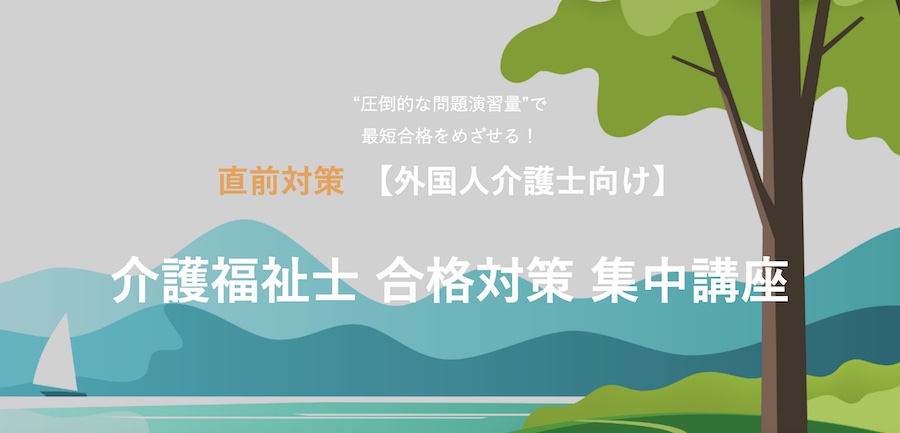
「何から勉強すればいいかわからない…」「仕事と両立できるか不安…」そんな悩みを抱える方にこそおすすめしたいのが、日本語カフェの介護福祉士 合格対策集中講座です。
この講座では、以下のようなポイントで合格まで徹底サポートします。
- 現役の介護福祉士講師が、重要ポイントをわかりやすく解説
- 豊富な過去問・模擬試験で、本番に強くなる!
- 試験に出る日本語もしっかりカバー(JLPT教材も使い放題)
- 動画学習で、24時間いつでもどこでも勉強できる!
4ヶ月の集中カリキュラムで、介護福祉士試験の合格を目指しましょう!
外国人が介護福祉士になる方法|まとめ

外国人材が介護福祉士の資格を取得することは、単なるスキルアップにとどまらず、企業と働く人双方にとって大きな価値をもたらす取り組みです。
資格取得によって在留資格の安定が得られ、生活基盤が整うことで、外国人材の長期定着や安心感、仕事へのモチベーションが向上します。
その結果、介護サービスの質が高まり、職場には経験豊富で専門性の高い人材が増え、企業全体の信頼性と競争力が強化されていきます。
企業ができるサポートは多岐にわたります。
日本語教育、学習時間の確保、教材支援、精神的フォローなど、「学び続けられる環境づくり」が極めて重要です。
これからの介護現場では、単なる人材確保にとどまらず、「人を育てる視点」が経営の柱となります。
外国人材の介護福祉士資格取得を企業がしっかりと支援することは、未来の介護業界を支える重要な一歩と言えるでしょう。