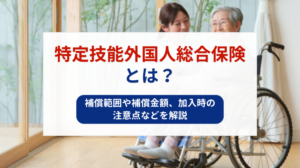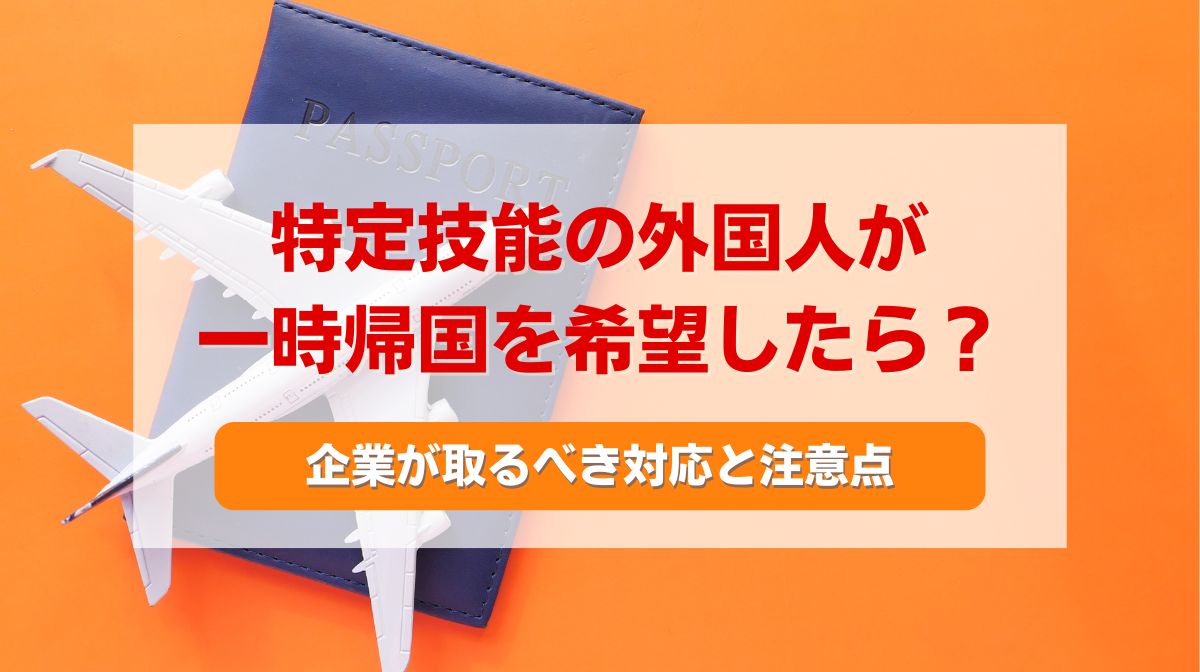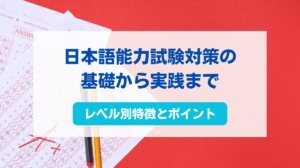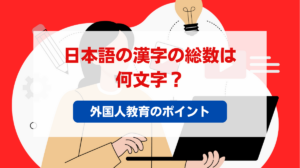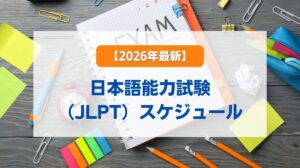特定技能の外国人労働者が日本で働く中で、一時帰国を希望することは珍しくありません。
家族に会うため、母国での手続きのため、あるいは一時的な事情によって母国へ戻りたいという要望が生じることがあります。
このようなとき、企業はどのように対応すべきなのでしょうか。
一時帰国は外国人労働者の正当な権利として認められており、企業にはその希望に配慮する義務があります。
しかし、実際の運用となると、休暇の取り扱いや手続き、費用負担の判断など、多くの注意点が存在します。
この記事では、外国人から一時帰国の申し出があった場合に、企業が行うべき対応や手続き、費用の負担に関するポイントを分かりやすく解説していきます。

外国人が一時帰国を希望したら?

特定技能の外国人労働者から一時帰国の希望があった場合、企業はその申し出を尊重し、柔軟に対応する必要があります。
これは労働基準法に基づいた正当な権利であるため、企業側の理解と準備が求められます。
有給休暇を取得してもらう
基本的には、有給休暇を活用して一時帰国してもらう形になります。
労働基準法に基づいて、外国人労働者にも有給休暇の取得権が認められており、その利用目的に制限は設けられていません。
したがって、「一時帰国」は正当な理由として認められるべきものです。
例えば、実家の家族に会うためや法的な手続きを行うための帰国など、個人的な事情であっても、企業は業務との調整を図ったうえで、有給休暇の取得を促すことが求められます。
このとき重要なのは、業務に支障が出ることを理由に、一方的に帰国を拒否することはできないという点です。
あくまで「業務上やむを得ない事情」がある場合に限り、日程の再調整を相談することが許されます。
有給休暇がない場合
一方、有給休暇をすでに使い切っている場合でも、一時帰国の希望を拒否することはできません。
このようなケースでは、無給での休暇を認める形で対応するのが一般的です。
たとえ有給休暇消化済みであっても、企業が休暇を認めない場合には、労働者の権利を侵害することになりかねません。
これは法的な問題に発展する可能性もあり、最悪の場合、企業としての信頼や今後の外国人雇用の許可にも影響が出ることがあります。
このような事態を防ぐためにも、雇用契約の段階で一時帰国の際の取り扱いについて明記しておくと安心です。
また、外国人労働者が制度を正しく理解できるよう、母国語ややさしい日本語での説明資料を用意しておくと、よりスムーズに対応できます。
いずれにしても、一時帰国は労働者の当然の権利であるという認識を持ち、企業として丁寧に対応していくことが大切です。
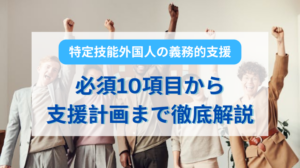
外国人の一時帰国で必要な手続き

特定技能の外国人労働者が一時帰国する際には、出国後も再び日本での就労を継続できるよう、「みなし再入国許可」の手続きをしましょう。
みなし再入国許可を申請する
一時帰国する外国人労働者が、日本へ再び戻ってくる予定がある場合には、「みなし再入国許可」の申請が必要です。
これは、通常の再入国許可とは異なり、特別な手続きなしで短期間の出国と再入国を可能にする制度です。
この手続きを行うには、出国時に空港で「再入国出入国記録(EDカード)」の該当欄にチェックを入れる必要があります。
チェックを入れたEDカードとともに、「在留カード」と「パスポート」を入国審査官に提示します。
これだけで申請は完了するため、簡単に手続きできます。
この制度を利用することで、最長1年間であれば、出国中も在留資格を維持したまま再入国することができます。
ただし、1年を超えてしまうと再入国扱いにならず、改めてビザを取得しなければならなくなるため、帰国期間の管理には注意が必要です。
みなし再入国許可の手続きをしなかった場合
一方で、みなし再入国許可の手続きを行わずに出国してしまった場合、その時点で現在の在留資格は失効となります。
つまり、日本へ再入国するには、もう一度新たにビザを申請し直さなければならないということです。
これは本人だけでなく、企業にとっても大きな負担となります。
再雇用までの手続きに時間がかかるほか、状況によっては再入国が認められない可能性もあるからです。
また、本人が再入国許可を受けていたとしても、「旅券」や「在留カード」を紛失してしまった場合は、空港での確認が取れず、再入国が困難になります。
このような場合は、地方出入国在留管理局で「再入国許可期限証明願」を提出し、許可の証明書を取得する必要があります。
このように、みなし再入国許可は、一時帰国をスムーズに行うための重要な制度です。
企業としても、出国前に本人が正しく手続きを行っているかどうかを確認し、必要に応じてサポートすることが求められます。
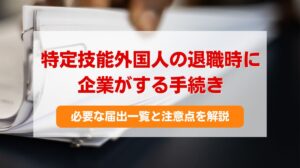
一時帰国の期間は在留期間に入る?

一時帰国している期間も、在留期間に含まれます。
つまり、日本にいない期間も在留資格の有効期間としてカウントされるため、注意が必要です。
一時帰国中も日数は消費される
特定技能の在留期間は、日本を離れて一時的に母国へ帰っている期間も含めて、在留期間として計算されます。
例えば、在留期間が「3年間」である外国人が、その途中で10日間の一時帰国をした場合でも、3年間の終了日が延びることはありません。
10日分も在留期間の一部として使われたとみなされます。
在留期間の通算上限に注意
特定技能1号では、最長で5年間までしか在留することができません。
この5年という上限には、一時帰国の期間も含まれる点を理解しておく必要があります。
もし、本人が「日本にいないから在留期間が延長されるだろう」と誤解してしまうと、気づかないうちに上限を超えてしまい、不法滞在と判断される可能性もあります。
これは本人にとっても企業にとっても大きなリスクになります。
正確な管理がトラブルを防ぐ
在留期間の管理は、外国人本人だけでなく、受け入れ企業の責任としても非常に重要です。
特に長期の一時帰国を予定している場合は、出国日と帰国日をきちんと記録し、在留期限と照らし合わせて確認しておく必要があります。
また、在留資格更新や延長申請を行う際にも、一時帰国の有無とその期間を正確に報告できるようにしておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。
在留期間があとどれくらい残っているか正確な情報を知りたい場合は、入国管理局に開示請求すれば確認できます。請求後、1ヶ月程度で結果がわかります。
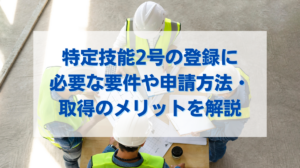
一時帰国の費用は誰が負担する?

特定技能の外国人労働者が一時帰国する場合、その費用は原則として本人が負担することになります。
ただし、状況によっては企業側の対応が求められるケースもあるため、あらかじめルールを明確にしておくことが重要です。
基本は本人負担
通常の一時帰国、例えば家族に会うためや個人的な理由による帰国の場合は、航空券などの渡航費用は労働者本人が支払うことになります。
これは日本人社員と同様、私的な都合での帰省に企業が関与しないという考え方に基づいています。
そのため、雇用契約の締結時やオリエンテーションの段階で、一時帰国時の費用は自己負担であることを明示しておくと、後々の誤解を防ぐことができます。
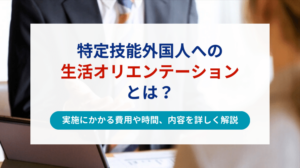
経済的に困難な場合の対応
ただし、本人が経済的な理由で帰国費用を用意できない場合、企業側には一定のサポートが求められます。
例えば、航空券の手配や、必要に応じて費用の立て替えなどを行い、円滑な帰国を助ける必要があります。
この対応は義務ではなく、あくまで必要な措置として求められているものですが、受け入れ機関としての信頼性や今後の外国人雇用への影響を考えると、柔軟な対応が望ましいとされています。
明確なルールづくりがトラブルを防ぐ
こうした費用負担の取り決めは、口頭ではなく契約書や就業規則などに明記しておくと安心です。
また、外国人本人にも分かりやすい言語で説明することで、後になって「聞いていない」といったトラブルを避けることができます。
一時帰国にかかる費用は基本的に本人負担ですが、企業も一定の責任を持って対応する場面があるため、事前の準備と理解が重要です。
特定技能外国人の一時帰国まとめ

一時帰国は、特定技能の外国人材にとって当然の権利であり、会社にはそれを適切に支援する姿勢が求められます。
まず、有給休暇を活用して対応し、仮に有給が残っていない場合でも無給休暇で配慮する必要があります。
また、一時帰国をスムーズに進めるためには、「みなし再入国許可」の申請が不可欠です。
これを怠ると在留資格が失効し、再入国ができなくなるおそれがあります。
さらに、空港までの送迎費用は企業の負担とされており、この点も見落とされがちな義務の一つです。
一時帰国に伴う渡航費用は原則として本人が負担しますが、経済的に困難な場合は、企業による支援が期待される場合もあります。
一時帰国についての取り扱いを事前に明確にしておくことで、誤解やトラブルを避けることができます。
安心して働ける環境を整えることは、外国人労働者にとっても企業にとっても大きなメリットとなります。
一時帰国への対応もその一環として、しっかりと備えておきましょう。