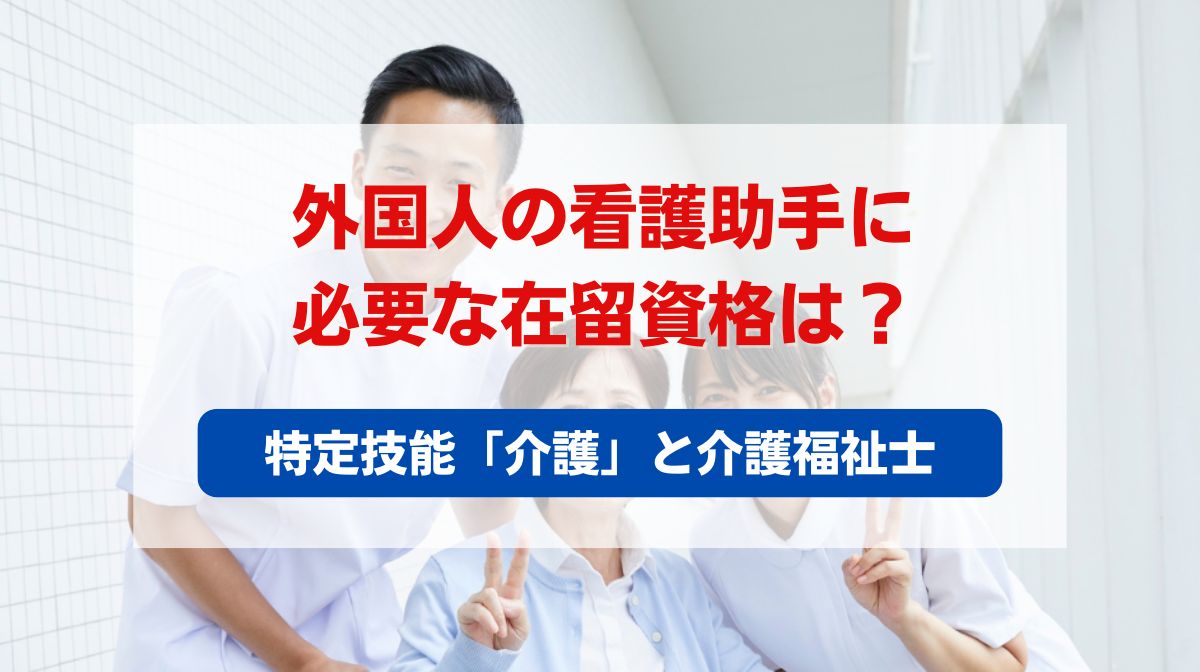日本の医療現場では、慢性的な人手不足が続いており、とくに看護助手の確保は多くの病院にとって重要な課題です。近年、この課題を解決する新たな戦力として注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人看護助手の採用です。
特定技能「介護」は、病院での看護補助業務と親和性が高く、即戦力として受け入れやすい在留資格のひとつです。
本記事では、外国人が看護助手として働くために必要な主要在留資格の違いや、採用・定着のポイント、さらに介護福祉士へのキャリアアップにつながる具体的な方法までをわかりやすく解説します。
\ 日本語学習システム/
外国人が看護助手として働くための主要な在留資格

外国人を病院で看護助手として雇用する際、最初に確認すべきは「在留資格」です。在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うことを法的に認める地位のことで、資格ごとに就労可能な業務内容が厳格に定められています。
看護助手業務に従事可能な主要な在留資格は複数ありますが、ここでは特に重要な「医療」「介護」「特定技能」を比較します。
在留資格「医療」
在留資格「医療」は、日本の看護師、准看護師等の国家資格を有する外国人が対象となります。業務範囲としては、看護師として医療行為全般に従事可能であり、もちろん看護助手としての雇用もできます。
しかし、現実的には採用のハードルが非常に高い資格です。この資格を得るには、まず日本の看護師国家試験に合格する必要がありますが、外国の資格は通用しません。
この国家試験のハードルは非常に高く、出入国在留管理庁のデータ(令和6年6月末)によれば、在留者数はわずか2,677名。採用ターゲットとしては非常に数が限られています。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、日本の「介護福祉士」の国家資格を有する外国人が対象です。主な業務範囲は介護施設での業務となりますが、医療機関での介護的業務(看護助手業務と重なる部分)も可能です。ただし医療行為は行えません。
2017年に新設された資格で「医療」資格より多くなっています。長期的なキャリアパスとして非常に有力な選択肢です。
在留資格「特定技能(介護)」
特定技能「介護」は、介護分野の「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格した外国人を対象としています。業務範囲は介護分野(病院での看護助手業務を含む)での身体介護や支援業務です。
2019年の導入以来、在留者数は急速に増加しています。在留期間は通算5年までという制限がありますが、採用の門戸としては最も広いのが特徴です。
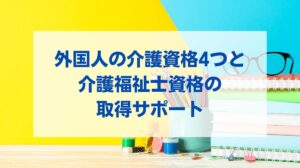
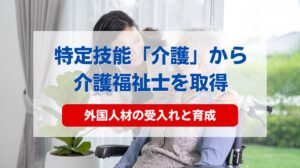
最も現実的な選択肢は「特定技能」

特定技能制度において、なぜ「介護」分野の外国人が病院の「看護助手」として働けるのか。それは、看護助手が行う業務(患者の身の回りの世話、移乗・入浴・食事の介助、環境整備など)が、特定技能「介護」分野の業務内容とほぼ一致するためです。
外国人材がこの「特定技能(介護)」資格を取得するには、以下の「3つの試験」に合格する必要があります。
介護技能評価試験
これは、介護現場で必要とされる基本的な知識と技能を測る試験で、コンピュータ・ベース・テスティング(CBT)方式により行われます。試験時間は60分、問題数は40問(択一式)で、出題分野は「介護の基本」「こころとからだのしくみ」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」です。
現在、フィリピン、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマーなど12カ国で実施されています。
日本語能力要件
介護業務は、患者やスタッフとの日本語でのコミュニケーションが必須なため、「日本語能力試験(JLPT)N4」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかの合格が求められます。
JLPT N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベル、JFT-BasicはそれとA2相当(N4相当)のレベルで、CBT方式により受験機会が多く設定されています。
介護日本語評価試験
一般的な日本語力に加え、介護現場特有の日本語能力を測る試験も別途必要となります。これもCBT方式で、試験時間は30分、問題数は15問程度です。
出題内容は「介護の言葉と漢字(専門用語)」「介護の会話・声かけ(利用者とのコミュニケーション)」「介護の文書(記録や連絡帳の理解)」となっています。
この3つの試験に合格することで、外国人材は看護助手業務に必要な基礎スキルと、現場での実践的な日本語コミュニケーション能力を有していることが証明されます。

特定技能の受け入れ事例を紹介|済生会横浜市南部病院

神奈川県にある済生会横浜市南部病院では、日本人看護補助者の採用難を背景に、ミャンマー出身の特定技能人材4名を看護補助者として採用しました。
採用にあたっては、単なる人員補充ではなく「外国人が安心して働き、成長できる環境づくり」を重視。入職前から「やさしい日本語講座」を開催し、日本人スタッフも一緒に参加することで、文化や言語の違いを越えた相互理解を育みました。住居や生活支援の体制も整備し、来日直後から安心して生活をスタートできるよう支援しています。
現場ではプリセプター制度を導入し、1対1で丁寧に指導を行うほか、日常業務を通じたOJT教育を徹底。食事介助やベッドメイキング、検査案内など、看護補助業務全般を担当しながら、業務への理解と日本語力を着実に高めています。
患者からも「丁寧で優しい」「話す努力が伝わる」といった好意的な声が多く、現場の雰囲気が明るくなったと評価されています。
今後は夜勤やリーダー補助など、より責任ある業務にも段階的に挑戦していく予定です。病院全体としても、外国人材の育成を通じて“多様な人材が共に支え合う職場文化”を目指しており、看護補助者の安定的な定着とチーム力の強化に大きな成果を上げています。
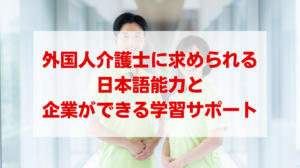
長期的なキャリアを目指すなら 在留資格『介護』

「特定技能」が5年という期限付きの即戦力確保の手段であるのに対し、より長期的な視点で人材に定着してもらうための選択肢が「在留資格『介護』」です。この資格を取得するためには、日本の国家資格である「介護福祉士」の試験に合格する必要があります。
「特定技能」と比較した際の最大のメリットは、キャリアパスの将来性です。「特定技能」が通算5年までという制限があるのに対し、「在留資格『介護』」は在留期間の更新回数に制限がありません。
さらに、一定の条件を満たせば永住許可申請の道も開かれます。これは、外国人材本人にとって大きな魅力であり、病院側にとっても、教育・投資した人材に永続的に活躍してもらえる可能性が生まれます。
一方で、難易度はかなり高くなっています。「介護福祉士」は日本人の受験者も多い国家試験です。合格には、より高度な専門知識と日本語読解能力が求められます。
したがって、まずは「特定技能」で入職・就労しながら実務経験を積み、日本語能力を高め、将来的に「介護福祉士」の国家試験合格を目指してもらう、というキャリアプランを提示することが、優秀な人材を定着させる上で非常に有効な戦略となります。
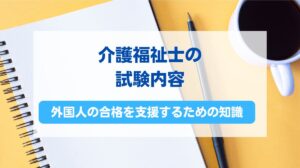
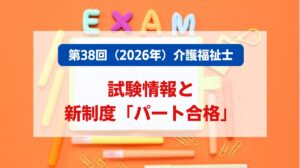
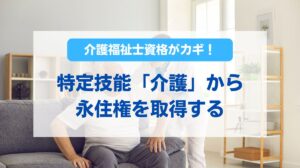
外国人看護助手の採用方法3つ

では、実際に特定技能「介護」の要件を満たす外国人をどこで探せばよいのでしょうか。主な採用方法は3つあります。
国内転職者からの採用
既に日本国内で「特定技能」や「技能実習」の資格で働いている外国人材を採用する方法です。日本の職場環境や文化に既にある程度適応しており、日本語での実務コミュニケーションも経験済みです。
受け入れ手続きは「在留資格変更許可申請」のみです。採用方法としては、介護・医療分野に特化した人材紹介会社の活用が最も一般的です。
ただし注意点として、前職での勤務状況や転職理由を詳細に確認することが重要です。また、介護施設(老人ホームなど)での経験と、病院での看護助手業務は動き方が異なる場合があるため、経験してきた具体的な業務内容を面接でしっかり確認しましょう。
海外からの直接採用
まだ来日していない海外の人材を直接採用する方法で、自社の経営理念や働き方をゼロから教育できるため、長期的な就労と定着が期待できます。国内転職者は都市部(東京・大阪など)を目指す傾向がありますが、海外からの直接採用の場合、地方の病院であっても定着が見込めるケースがあります。
採用方法は、現地の送り出し機関や、海外連携に強い人材紹介機関との連携が主流です。 ただし、手続きに6ヶ月程度の時間がかかることがあり、来日後の生活支援(住居の確保、生活必需品の準備、銀行口座開設など)を、病院側が手厚くサポートする必要があります。
専門機関(人材紹介会社・登録支援機関)の活用
特定技能制度の複雑性を考慮すると、専門機関の活用は非常に有効な選択肢です。登録支援機関は、法的に必須である外国人への支援業務(定期面談、相談対応、生活支援、役所手続きの同行など)を病院に代わって実施するため、病院側の管理負担を大幅に軽減できます。
人材紹介会社は、病院のニーズと外国人材のスキル・希望をマッチングし、採用プロセスを効率化します。採用後の定着サポートまで提供する会社も多くあります。 医療・介護分野での実績、支援内容の充実度、費用の透明性を基準に、自院の規模や特性に合ったパートナー機関を選定することが成功の鍵となります。
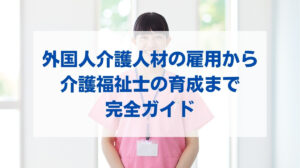
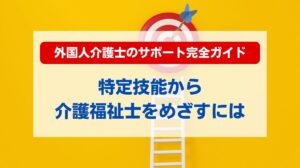
受け入れ後に病院が取り組むべき3つのポイント

採用はゴールではなく、スタートです。外国人看護助手に長く活躍してもらうためには、受け入れ後の「定着支援」が最も重要です。
文化への配慮
多様な文化背景を持つ人材への配慮は、良好な職場環境の構築に不可欠です。例えば、イスラム教徒の祈祷時間(1日5回)や食事制限(ハラール)、ヒンドゥー教徒の牛肉の摂取禁止など、可能な範囲での配慮が求められます。
また、入職時だけでなく、日本語能力向上研修、専門技能向上研修、安全衛生教育、ハラスメント防止研修などを定期的に実施します。これらの研修は、受け入れ側の日本人職員も対象とすることで、相互理解が飛躍的に進みます。
患者とのコミュニケーションの支援
医療現場でのコミュニケーションは、患者の安全と満足度に直結します。「おはようございます(お変わりありませんか)」「体調はいかがですか」「お手伝いしましょうか」といった基本的な声かけ、敬語・丁寧語の使い方、緊急時の報告・連絡・相談(報連相)の訓練を徹底します。
また、多言語対応の基本フレーズ集、指差し会話シート、翻訳アプリ、ピクトグラム(絵文字)などを病棟に常備し、コミュニケーションの補助として活用するのも有効です。
働きやすい環境づくり
長期的な人材確保のためには、働きやすい環境づくりが求められます。経験豊富な日本人職員をメンターとして指名し、業務指導だけでなく、日本での生活面の相談にも乗れる「メンター制度」の導入は非常に効果的です。定期的な面談で、悩みや不安を早期に把握し、解決します。
また、明確な評価基準を設定し、能力向上に応じた昇給制度を導入することも重要です。「特定技能」から「介護福祉士」への資格取得支援制度などを設け、キャリア開発の機会を提供することが、将来への希望につながります。

効率的な日本語学習・資格取得をサポートするeラーニング講座

外国人材の採用・定着には、特定技能の要件を満たすための初期学習や、入職後のさらなるキャリアアップ(介護福祉士など)のための継続的な学習サポートが不可欠です。
しかし、多忙な病院業務と並行して、現場で日本語教育を行うのは容易ではありません。

「日本人講師の採用や管理が大変…」
「講師の毎月の人件費が馬鹿にならない…」
といったコストや管理の課題は、多くの病院が直面する現実です。
こうした課題に対し、コストを抑えつつ外国人材の自発的な学習を促進できる「eラーニング講座」の活用が、今、非常に注目されています。
特定技能の取得や、その後の日本語力向上を目指すなら、「日本語カフェ」のJLPT合格コースがおすすめです。
厳しい審査をパスした一流の日本語講師が監修した、N5~N1までのレベル別に最適化された「合格特化カリキュラム」が使い放題。高品質な動画講義と反復練習ドリルにより、スマホやPCからスキマ時間を使って、一人ひとりのペースで繰り返し学習できます。
実際に、全くの初心者から3ヶ月でN3に合格した実績もあります。 また、企業の管理者はスタッフの学習状況を一目で把握できるため、管理にかかっていた手間とコストを大幅に削減できます。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格


「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
さらに、「特定技能」からのステップアップとして、在留資格「介護」の取得(=介護福祉士国家試験の合格)を目指す人材をサポートするための、専門対策講座として「日本語カフェ「介護福祉士 受験対策講座」」も提供しています。
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!


- ■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- ■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- ■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
外国人スタッフの日本語教育や資格取得サポートを低コストで実現したい病院・医療機関の方は、ぜひ一度「日本語カフェ」までお問い合わせください。
\ ご相談はこちらから /
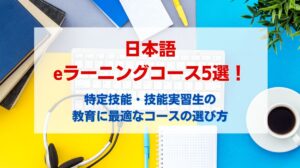
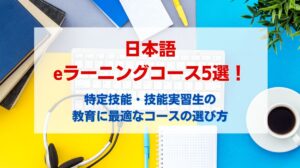
まとめ


特定技能「介護」は、外国人材が看護助手として日本の医療現場で活躍するための最も現実的な入り口です。制度を正しく理解し、教育・支援体制を整えることで、病院は安定した人材確保と現場の活性化を実現できます。
さらに、特定技能で入職した人材が経験を積み、介護福祉士資格を取得して長期的にキャリアを築くことで、医療機関全体の成長にもつながります。
人手不足を「外国人の力でどう補うか」ではなく、「共に成長する仕組みをどう作るか」として捉えることが、これからの医療現場に求められる視点です。
\ お気軽にお問い合わせはください!/