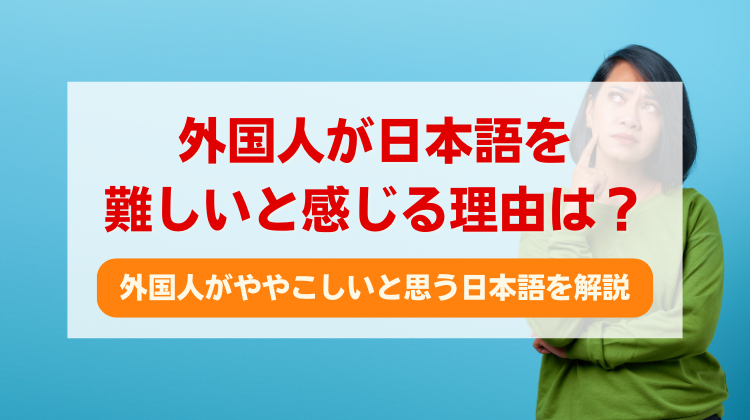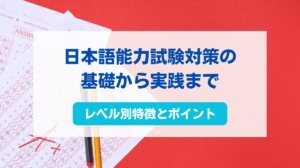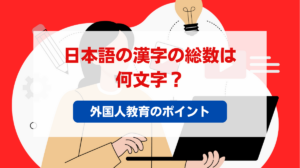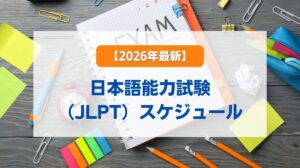多くの外国人従業員にとって、日本語の学習は難しいと感じることが多いようです。
この記事では、外国人従業員が日本語を学ぶ際に直面する日本語特有の難しさについて詳しく解説します。
また、企業が外国人従業員の日本語学習を支援するために理解しておくべき点についても紹介します。
外国人従業員が感じるややこしい日本語4選

日本語には、外国人にとって特に理解が難しい要素がいくつか存在します。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
主語が省略される
日本語では、会話や文章の中で主語が省略されることが多く、これが外国人にとって大きな難関となります。
英語などの言語では主語が常に明示されるため、話者がどの人を指しているのかが明確です。
しかし、日本語では「私」や「あなた」などの主語が省略されることが多く、文脈からそれを推測しなければなりません。
ビジネスの場面でも、主語がわからず会話の内容を理解するのが難しくなる場合があります。
例えば、業務報告の中で「もう対応しました」や「次はどうしますか?」のような表現が使われると、外国人には「誰が」「何を」したのかを理解するのが困難です。
そのため、まだ日本語学習を始めて間もない外国人従業員に対しては、主語が不明瞭にならないように、主語を入れて会話をするなどの工夫が求められます。
敬語の使い分けが複雑
敬語は日本語の中でも特に複雑で、外国人にとっては使いこなすのが非常に難しいです。
尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があり、相手との関係性や状況に応じて適切な敬語を使い分ける必要があります。
例えば、上司に対して「おっしゃる」を使い、自分に対しては「申す」を使うなど、微妙なニュアンスを適切に使い分けることが求められます。
ビジネスシーンでは、敬語の間違いが失礼に当たる可能性があり、外国人従業員はそのプレッシャーを感じがちです。
企業としては、敬語の使い分けに関する研修や指導を行うことで、外国人従業員の負担を軽減することができるでしょう。
同音異義語の難しさ
日本語には同音異義語が多く、発音は同じでも意味が異なる単語が多く存在します。
例えば、「髪(かみ)」「紙(かみ)」「神(かみ)」のように、同じ音でも意味が異なる言葉を正しく理解するには文脈を考慮する必要があります。
この同音異義語の多さが、外国人にとって日本語を学ぶ際の障壁の一つとなっています。
企業側としては、こうした同音異義語が混乱を招かないよう、具体的な例示や状況の説明を追加するなどの工夫をすると良いでしょう。
文法の柔軟性と語順
日本語の文法は比較的柔軟で、語順も自由度が高いのが特徴です。
例えば、「私がごはんを作る」という文章は、「ごはんを私が作る」や「作る、ごはんを私が」といった語順でも意味が通じます。
この柔軟さが、外国人従業員にとって混乱を招く原因となっています。
また、日本語では助詞が重要な役割を果たしており、それによって語順の自由度が保たれています。
しかし、助詞を間違えると全く違う意味になってしまうため、外国人にとっては難しく感じられる点です。
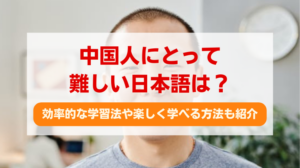
文化的背景が影響する日本語理解

日本語の理解には、単に言語の知識だけではなく、日本特有の文化的な背景を理解することが非常に重要です。
空気を読む文化
日本語で会話する際は、日本の文化に根ざした「言葉にされない部分を読む力」、つまり「空気を読む」力が求められます。
この「空気を読む」という行為は、日常のコミュニケーションにおいても、ビジネスシーンにおいても欠かせないスキルです。
また、日本の文化には、直接的な表現を避け、あえて遠回しに言うことが美徳とされる価値観があります。
しかし、この遠回しな表現は外国人には非常に理解しづらく、特にビジネスの現場では混乱を招く原因となることが多いです。
例えば、日本人がよく使う「考えておきます」という表現は、実際には「断る」意味を含んでいることが多く、直接的に「ノー」と言わないことで相手の気持ちを尊重しています。
しかし、外国人従業員にとっては、このような曖昧な表現が本当の意図を理解する障壁となり、誤解を生む原因にもなります。
このような曖昧さがビジネスの交渉や日常のやり取りの中で誤解を生むことも少なくありません。
また、業務上の指示やフィードバックを曖昧に伝えると、外国人従業員は何を求められているのか正確に理解することが難しくなり、結果としてパフォーマンスの低下や誤解を引き起こすことがあります。
例えば、上司が「もう少し考えた方が良いかもしれない」と伝える場合、これは「変更が必要」という意味合いを含むことが多いですが、外国人にとっては単なるアドバイスとして受け取られる可能性があり、その真意を理解するのが難しいことが多いです。
和を重んじる文化
さらに、日本では「和」を重んじる文化があり、「みんなと協力してやっていく」ことや「対立を避ける」ことが望ましいと考えられる傾向にあります。
そのため、ビジネスシーンにおいても、チーム内での調和を重視し、あまり自己主張を強くしないことが推奨される場合があります。
しかし、これが外国人従業員にとっては意図を正確に理解するのが難しくなる要因となりえます。
例えば、意見を求められた際に、日本人は「皆さんの意見に賛成です」とあえて強く主張しない態度を取ることがありますが、外国人にはこれが自分の意見を持っていないと受け取られることもあります。
こうした曖昧さを理解し適切に対応するためには、日本の文化的背景やビジネスマナーを学ぶことが不可欠です。
企業側もこの点を認識し、外国人従業員がスムーズに業務を遂行できるように、文化的な理解を深めるための研修やサポート体制を整えることが望ましいです。
双方の文化の違いを理解し、コミュニケーションを円滑に行うためには、企業全体での取り組みが必要であり、そのための環境づくりが外国人従業員の働きやすさにつながります。
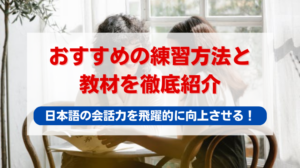

まとめ

この記事では、外国人従業員が日本語を学ぶ際に感じる難しさと、その背景にある文化的要因について紹介してきました。
外国人にとって難しいと感じられる要素として、主語の省略、敬語の複雑さ、同音異義語、文法の柔軟性などが挙げられます。
また、日本特有の文化的な背景である「空気を読む」ことや遠回しな表現の習慣も、外国人にとって理解しづらい要因となっています。
企業はなぜ理解しづらいのかを理解し、外国人従業員が働きやすい環境を作るための学習支援やサポートを行うことが求められます。