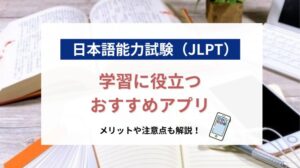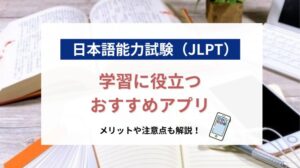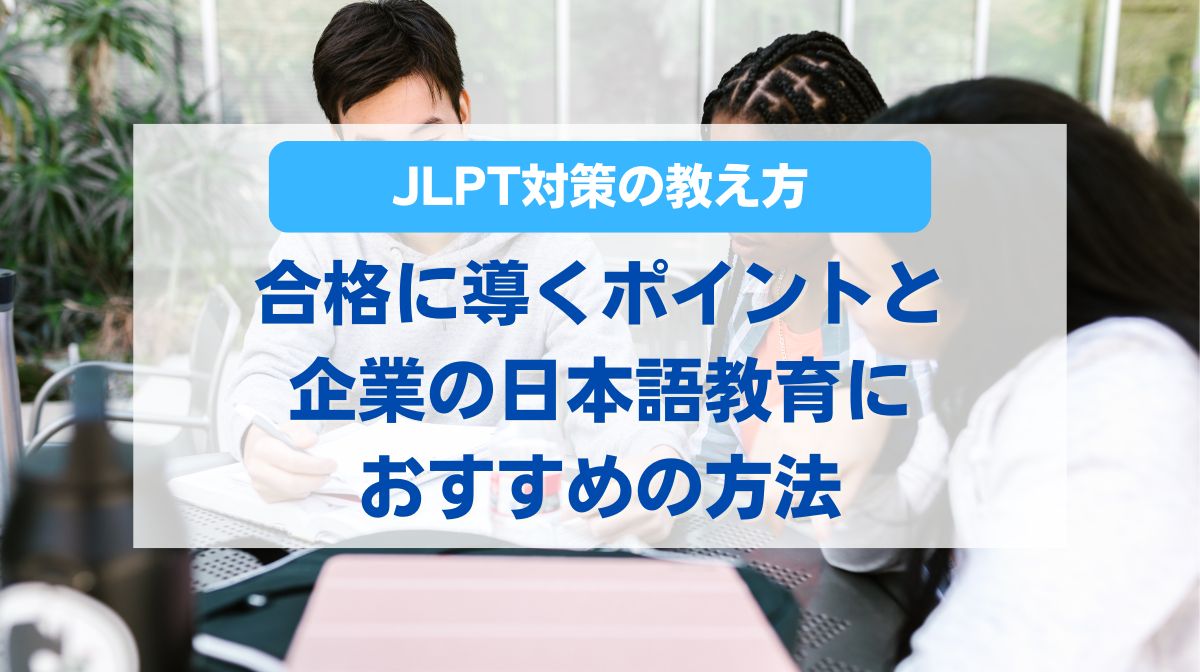企業の教育担当者や日本語教師の方からは、「どうやって日本語を教えたらいいかわからない」「忙しくて試験対策まで手が回らない」「学習者によってレベル差がありすぎる…」といった声をよく聞きます。
日本語能力試験(JLPT)にはN1~N5までのレベルがあり、必要とされる力もさまざま。文法・語彙・読解・聴解と、学習すべき内容も多岐にわたるため、きちんとした指導の方針がないと、学習者が迷子になってしまうこともあります。
この記事では、JLPTの基本的な仕組みから、技能ごとの効果的な教え方、学習者の悩みに寄り添ったサポート方法まで、やさしく解説していきます。企業での教育担当、講師としての指導がもっとスムーズになり、学習者が「合格できた!」「日本語が楽しくなった」と感じられるようなサポートのヒントをお届けします。
JLPT(日本語能力試験)の概要
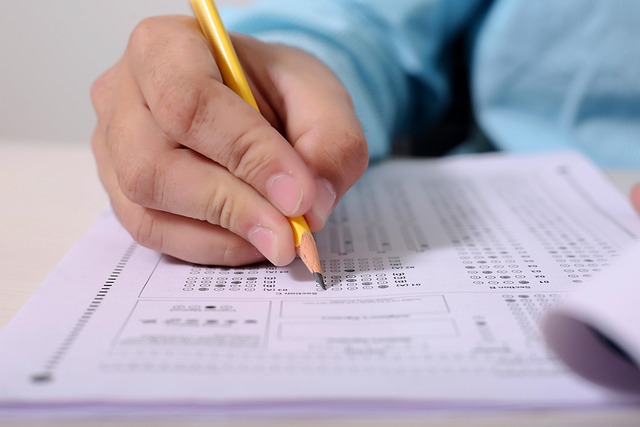
指導を始める前に、まずはJLPTの概要を簡単に確認しておきましょう。
JLPT(日本語能力試験)は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し、認定することを目的とした試験です。N1からN5までの5段階のレベルに分かれており、N5が最もやさしく、N1が最も難しくなっています。
J試験は主に「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」の3つのセクションで構成されています。合格するためには、総合得点と、各セクションの基準点の両方をクリアする必要があります。それぞれのレベルで求められる能力の特徴を理解しておくことが大切です。
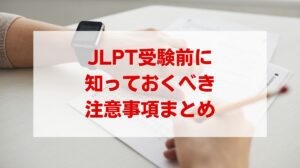
【STEP1】指導の前に!まず準備すべき3つのこと

効果的な指導をするには、事前の準備が大切です。指導を始める前に、以下の3つの点を必ず押さえておくようにしましょう。
1. 学習者のレベルを正確に把握する
まず一番にすべきことは、学習者の現在の日本語レベルを正確に確認することです。過去問や簡単なレベルチェックテストなどを使い、何が苦手で、どのくらい理解しているのかを把握します。目標レベルと現状のギャップを考え、埋めるべき課題を明確にしましょう。
2. 学習者本人と一緒に学習計画を考える
一方的に教えるのではなく、学習者本人と一緒に合格までの計画を立てることが重要です。 「いつ試験を受験するのか」「1日にどのくらいの学習時間を確保できるのか」などを話し合い、無理のないスケジュールを立てます。どの技能(語彙・文法・読解・聴解)に重点を置くか意識させるだけでも、学習効果は変わってきます。
3. 適切な教材を準備する
学習者のレベルに合った教材を選ぶことは非常に重要です。市販の問題集はたくさんありますが、解説がわかりやすいか、練習問題が豊富かなどの点で選びましょう。最近では、オンライン教材やアプリも充実しており、多くの学習者が活用しています。動画コンテンツなどは、視覚と聴覚の両方から日本語に慣れることができるのでおすすめです。

【STEP2】技能別!明日から使えるJLPTの教え方と実践ポイント

ここからは、日本語能力試験(JLPT)の各技能に対応した、具体的かつ効果的な指導方法と授業内での実践ポイントをご紹介します。ただ知識を教えるだけでなく、「学習者が使える日本語を身につける」ことを目指した指導が重要です。
【言語知識(文字・語彙)】の教え方
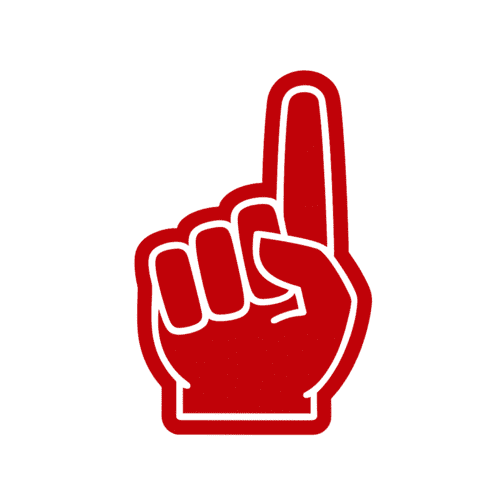 ポイント
ポイント関連づけと文脈を通じて、生きた語彙として学ばせる
語彙の指導は、最初に取り組みやすい分野ですが、覚えた語彙が実際の会話や文章の中で使えなければ意味がありません。単語の意味だけを暗記させるのではなく、「どんな場面で、どんな文脈で使われるのか」ということを意識させることが重要です。
- 絵や写真、ジェスチャーなど視覚的・身体的な要素を活用することで、言葉のイメージが定着しやすくなります。特に初級ではこのアプローチが効果的です。
- 対義語や類義語をセットで教えることで、語彙の意味を立体的に理解でき、語彙同士の関連性が自然と頭に入ります。例えば、「静か」と「にぎやか」、「寒い」と「暑い」などの組み合わせを通じて、語彙を広げましょう。
- 例文の中で単語を使う練習は、語彙の運用能力を高めるうえで非常に重要です。できるだけ学習者自身に例文を考えさせることで、理解の深まりが期待できます。
【言語知識(文法)】の教え方
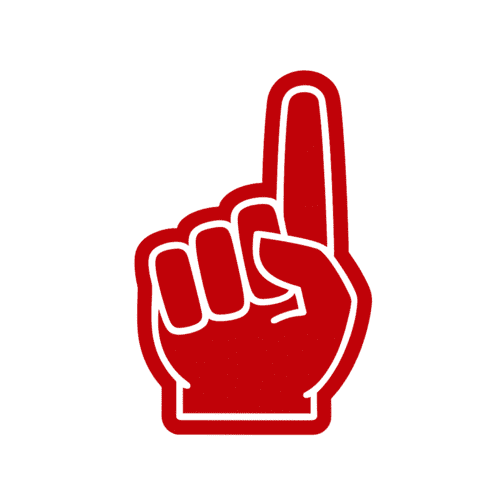
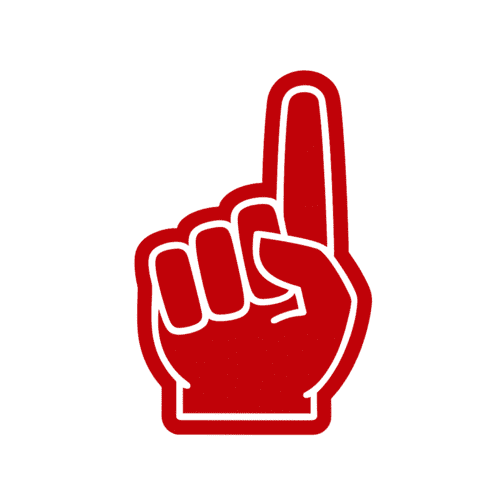
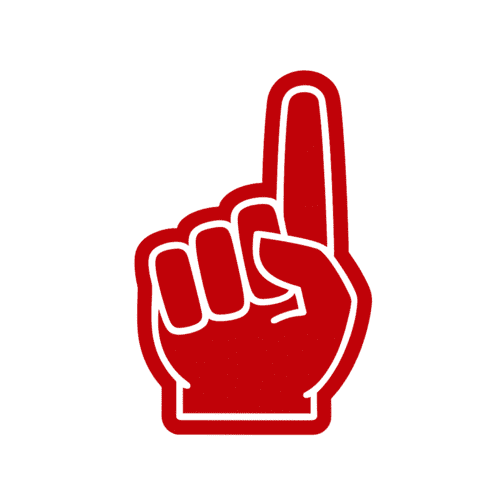
文法の形だけでなく、意味や用法の背景まで丁寧に説明する
文法は、日本語学習者がつまずきやすい分野の代表格です。特に中上級になると、似たような文型の違いに混乱しがちです。単なるパターン練習に終始せず、「なぜこの形になるのか」「どういう場面で使うのか」という“意味の理解”が非常に重要です。
- 「導入→練習→応用」のステップを踏む授業展開が基本です。まず簡単な例を通して導入し、文型の構造を確認。次にパターン練習で形に慣れさせ、最後は自由作文や会話などで応用的に使わせます。
- 似た文法の違いを明確に比較すると学習者にわかりやすいです。たとえば、「~ために(目的)」と「~ように(目標)」の違いを、図解や状況設定などを使って説明すると理解が進みます。
- 学習者自身に例文を作らせることを取り入れましょう。これは理解の定着だけでなく、誤用のチェックやアウトプット能力の育成にもつながります。
【読解】の教え方:読み方の「戦略」を身につけ、本番形式に慣れる
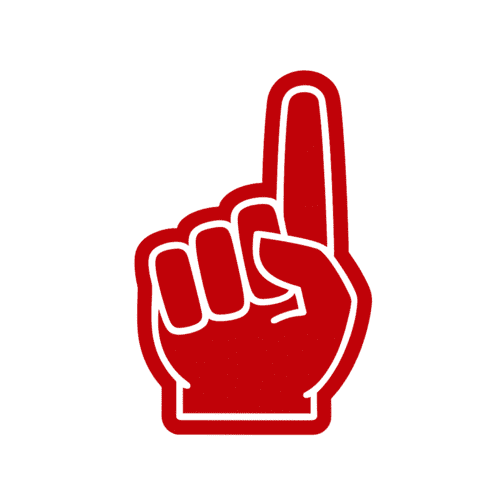
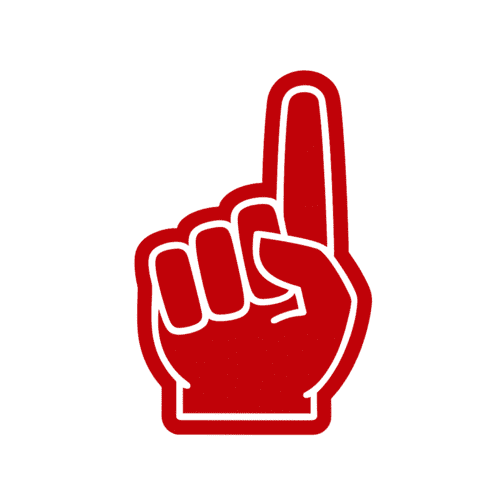
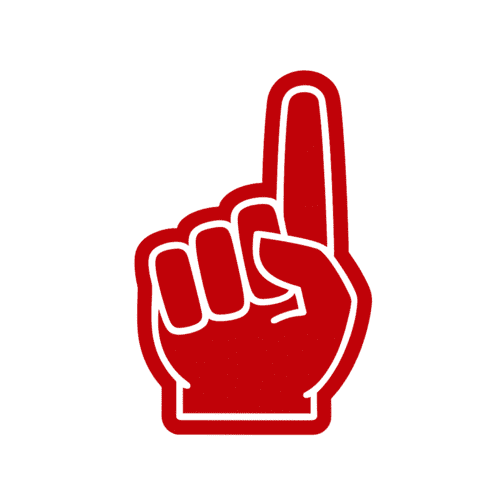
時間内に要点をつかみ、設問の根拠を明確にするトレーニングを重視
読解は、内容理解に加えてスピードも求められる技能です。特にJLPTでは設問数が多く、時間管理が合否を左右します。ただ読むのではなく、「何をどう読むか」という戦略的な読み方を指導しましょう。
- 本文を読む前に設問と選択肢を確認させ、何を探して読むのかを明確にさせます。
- 接続詞や指示語、対比表現などのキーワードに印をつけながら読む習慣をつけさせることで、文脈の流れや筆者の主張を把握しやすくなります。
- 模擬問題を使って「時間を計って解く」練習を繰り返すことで、実戦感覚を身につけます。復習時にはなぜその選択肢が正解(または不正解)なのかを検討する時間も取りましょう。
【聴解】の教え方
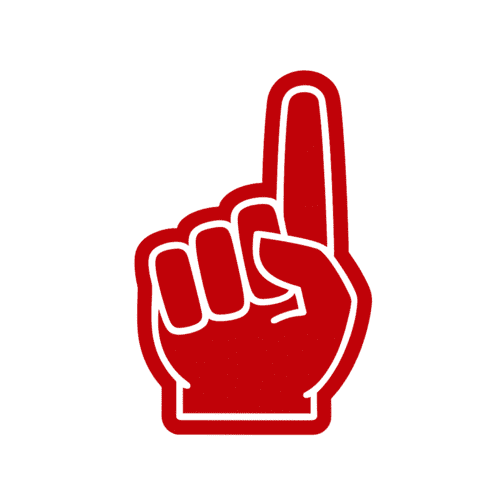
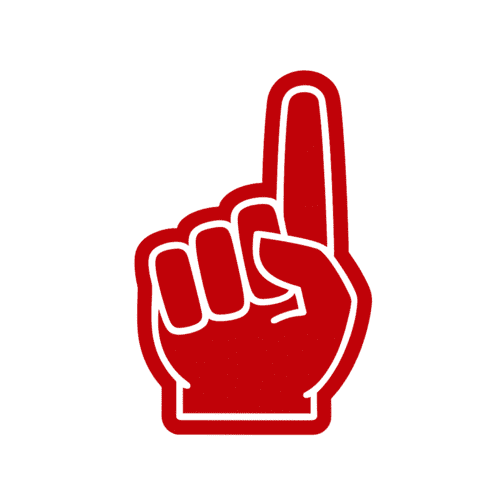
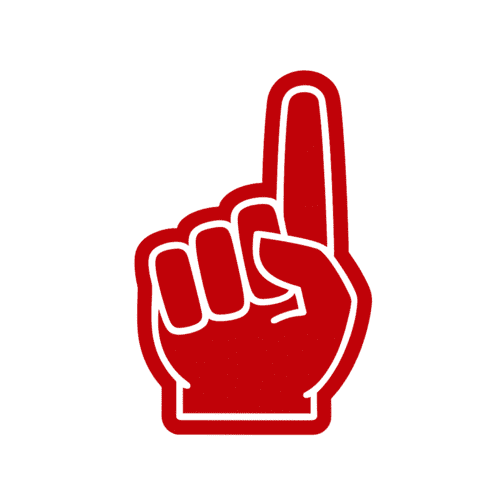
音声形式に慣れ、キーワードの拾い方を体得することが上達の近道
聴解は苦手意識を持つ学習者が多い技能ですが、コツをつかめば確実にスコアアップが望める分野です。「聞こえるようになる」には、量と質の両面でのトレーニングが不可欠です。
- シャドーイングは、聞く力・話す力の両方を鍛える効果的な方法です。最初はスクリプトを見ながら、徐々に音声のみで練習するように段階を踏んで進めましょう。
- 音声を聞く前に問題文と選択肢を読み、どんなやりとりが展開されそうか、どういう情報が必要そうかを予測させることで、聞き取りの準備が整います。
- 音声を聞き終わった後は、スクリプトと照らし合わせて確認し、「なぜ聞き取れなかったのか」「どこで取りこぼしたのか」を一緒に分析しましょう。聞き取れなかった原因を明確にすることで、今後の学習にもつながります。
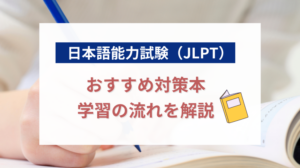
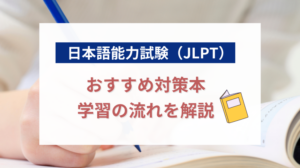
【STEP3】レベル別!指導で特に意識すべきポイント


JLPTはN5からN1まで、難易度に大きな差があります。そのため、学習者のレベルに応じて、指導の内容や重点を変える必要があります。ここでは、各レベルごとに「教師が特に意識すべきポイント」と「効果的な指導アプローチ」を詳しくご紹介します。
N4・N5レベルの教え方:日本語学習の「土台」を築く
- 「日本語=難しい言語」というイメージを払拭するよう、ゲーム・歌・ロールプレイなどを積極的に活用し、楽しさを感じられる授業を心がけましょう。
- 語彙や文法は文脈の中で繰り返し使うことで、自然に定着させます。例:「~です」「~ます」など基本文型を使った自己紹介の練習。
- 書く力よりも「聞く・話す」を優先し、簡単な会話のキャッチボールを目指します。やり取りを通じて“使える”日本語にしていきましょう。
- 誤りを必要以上に指摘するよりも、「伝わった!」という体験を重視する姿勢が、学習意欲の向上につながります。
N3レベルの教え方:表現力を広げる段階
- 新しい語彙や文法を導入する際は、実際の生活や場面と結びつけて教えることで、記憶の定着が期待できます(例:「~てもいいですか」「~たほうがいい」など)。
- 文の長さや構造が少し複雑になるため、主語・目的語・動詞などの位置関係を図解しながら理解を助けましょう。
- 長文読解や会話練習では、情報を整理しながら要点をつかむ力を育てる必要があります。「この文章は何が言いたいのか?」を問いかける癖をつけさせましょう。
- 音読やシャドーイングを取り入れることで、リズムやイントネーションの習得と同時に、語彙・文法の復習にもなります。
N2・N1レベルの教え方:実践力と抽象的な思考力を鍛える
- 語彙のニュアンスや文法の用法の違いを的確に説明することが求められます。たとえば、「~に違いない」と「~はずだ」の意味の違いや、使える場面の違いを明確に示します。
- 論説文・評論文などを読む機会を増やし、筆者の主張を要約したり、背景知識と結びつけて考える力を養います。ディスカッションや文章作成も効果的です。
- 聴解ではスピードが速く、情報量が多い問題に対応する必要があるため、「聞き取りながらメモを取る練習」「必要な情報だけに集中するコツ」を伝えます。
- 模擬試験を通して、本番の時間配分や出題傾向に慣れさせることも重要です。ただし、間違いの分析や復習に重点を置き、「どうすれば次は正解できるか」という視点を育てましょう。
レベルが上がるにつれて、「教える内容」も「教え方」も高度になっていきますが、共通して重要なのは学習者一人ひとりのニーズと課題を見極める観察力です。
単にJLPTの出題傾向に合わせるのではなく、「この学習者には今、何が必要か?」という視点を常に持つことで、より効果的な指導につながります。
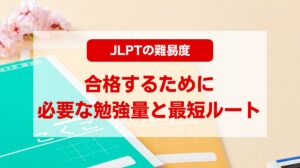
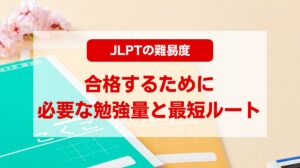
【お悩み別】学習者がつまずきやすい点と指導のヒント


JLPTの指導において、学習者の「つまずき」や「伸び悩み」は避けて通れない課題です。しかし、その多くは学習の進め方や意識の持ち方を少し変えるだけで、着実に改善が可能です。
ここでは、学習者からよく聞く悩みを取り上げ、それぞれの背景にある原因と、教師としてどのようにサポートすればよいかについて、具体的なヒントを交えて解説します。学習者の気持ちに寄り添いながら、前向きに乗り越えていける指導を目指しましょう。
悩み1:「読解問題に時間がかかりすぎる…」
- 主な原因
読解問題に時間がかかってしまう主な理由として、語彙力や文法力の不足が挙げられます。文中に知らない単語や構文が多いと、内容理解に時間がかかり、結果として最後まで読み切れないというケースがよく見られます。
また、文章の構成や論理展開に慣れていない場合、読み進めながら情報を整理することが難しくなります。さらに、「すべての文を丁寧に読もう」としてしまう傾向があり、設問に対する意識が薄いまま読み進めてしまうことも原因の一つです。
悩み2:「聴解の点数が伸びない…」
- 主な原因
聴解力が伸びない原因の多くは、日常的に日本語の音声に触れる機会が少なく、学習者の耳が日本語のリズムやスピードに慣れていないことにあります。特に初中級の学習者は、すべての音を聞き取ろうと集中しすぎるあまり、肝心なポイントを聞き逃すことも少なくありません。
また、音声を聞く前に問題の選択肢を確認せず、漠然と聞き始めてしまうことで、情報を効果的に整理できない場合もあります。
悩み3:「勉強しているのに合格できない…」
- 主な原因
勉強時間をしっかり確保しているにもかかわらず合格できない場合、実は自分の苦手分野を避けて勉強しているということが多く見られます。好きな分野や得意な技能に偏って学習を続けていると、総合力が求められるJLPTでは思うようにスコアが伸びません。
また、学習方法そのものが非効率であったり、模擬試験や過去問演習を十分に行っていない場合も、試験本番で実力を発揮できない原因となります。
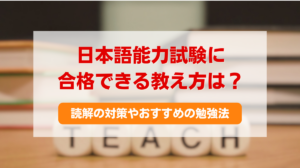
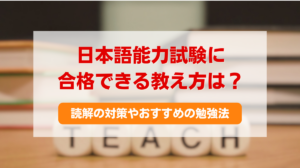
管理コストを削減し効率的に学べる「日本語カフェ」とは?


「教え方はわかったけれど、日々の業務と並行して手厚い指導をする時間がない…」
「指導者によって教え方の質にバラつきが出てしまう…」
「もっと効率的に、かつコストを抑えてスタッフに日本語を学習してほしい…」
もしあなたが外国人スタッフの日本語教育をもっとシンプルで簡単に、それでいて効果的に行いたいなら、「日本語カフェ」の『JLPT 合格コース』がその悩みを解決します。
一流の講師監修による合格特化カリキュラム
厳しい審査をパスした一流の日本語の先生が監修した、合格に特化した動画カリキュラムを提供しています。そのため、企業の担当者が日本語教育の専門家になる必要はありません。
既に体系化された質の高い教育コンテンツがそのまま利用できるため、専門知識がなくても効果的な日本語教育を実施できます。
学習はオンラインの動画講義形式なので、何度でも好きなタイミングで繰り返し学習でき、一人ひとりに合った学習ペースで無理なく続けられます。
管理にかかる時間を削減できる
利用者一人ひとりの学習状況を一目で確認できる管理画面により、管理にかかっていた時間をぐっと短縮できます。
学習状況の把握が容易になることで、適切なタイミングでのサポートや指導が可能になり、より効果的な人材育成を実現できます。
圧倒的なコストパフォーマンス
オンライン講座は月額固定料金で利用でき、講師にかかる人件費や教材費、教室の確保などの従来のコストと比較して、圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。
特に中小企業にとって、継続的な教育投資は大きな負担となりますが、日本語カフェのシステムなら予算を抑えながら質の高い教育を提供できます。初期投資も最小限に抑えられ、すぐに教育を開始できる点も大きなメリットです。
学習習慣を身につけて長期的な効果を実現
従来の集合研修や講師による指導では、受動的な学習になりがちでしたが、日本語カフェのシステムでは自発的に学習を進められる教材が揃っています。明確な目標設定と段階的な達成感により、モチベーションを維持しながら長期的な学習を継続できます。
日本語カフェのJLPT合格コースは、企業が抱える日本語教育の課題を包括的に解決し、コスト削減と教育の品質向上の両立により、企業の競争力の強化に直接貢献します。
\無料体験はこちらから/
JLPT対策の教え方 まとめ


今回は、JLPT対策の効果的な教え方について、準備段階から技能別・レベル別の具体的な指導ポイントまで解説しました。
- 教え方の基本は、学習者のレベルと課題の正確な把握から始める
- 技能別(語彙・文法・読解・聴解)にポイントを押さえた指導を実践する
- 学習者が継続できるよう、計画を立ててモチベーションを維持する
このようなポイントを実践するだけでも、学習者の反応は大きく変わるはずです。
そして、もし指導のリソースや管理に課題を感じているのであれば、「日本語カフェ」のオンライン講座の活用もぜひ検討してみてください。
\ お問い合わせはこちらから /