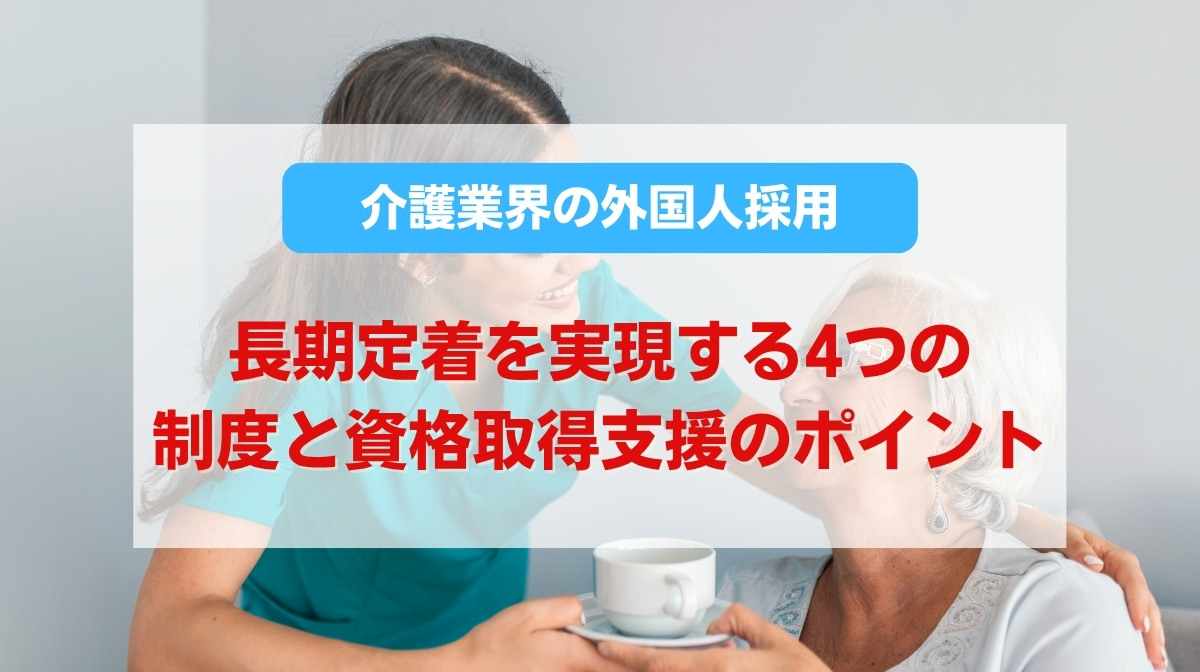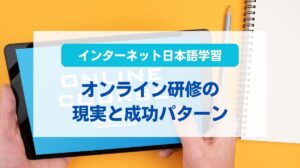「せっかく採用した外国人職員がすぐに辞めてしまう」
「日本語でのコミュニケーションに苦労している」
「介護福祉士の資格を取らせたいが、どう支援すればよいかわからない」
このような悩みを抱えている介護施設の経営者や人事担当者は決して少なくありません。厚生労働省の調査によると、外国人介護職員の離職率は日本人職員よりも高い傾向にあり、その主な要因として日本語能力の不足とキャリアアップへの不安が挙げられています。
しかし、適切な支援体制を構築することで、外国人職員の長期定着と介護福祉士資格の取得は十分に実現可能です。実際に、計画的な日本語教育と資格取得支援を行っている施設では、外国人職員の定着率が大幅に改善し、施設全体のサービス品質向上にもつながっています。
本記事では、外国人介護職員の定着率向上と介護福祉士資格取得を成功させるための具体的な方法を、4つの在留資格制度の活用法から効率的な教育支援まで、包括的にお伝えします。
\ 日本語学習システム/
外国人介護職員受け入れの4つの制度を徹底比較

外国人介護職員の受け入れには複数の制度があり、それぞれ特徴や要件が大きく異なります。施設の状況に最適な制度を選択するための情報をご紹介します。
| 制度 | 在留期間 | 転職 | 家族帯同 | 主な要件 |
|---|---|---|---|---|
| EPA | 4年間 (資格取得後は「介護」へ移行) | 不可 | 不可 | 施設要件あり、母国での資格・経験 |
| 在留資格「介護」 | 更新制限なし | 可能 | 可能 | 介護福祉士資格必須 |
| 技能実習 | 最長5年間 | 原則不可 | 不可 | 年齢制限あり |
| 特定技能 | 最長5年間 | 可能 | 不可 | 技能試験合格等 |
EPA(経済連携協定)の特徴と要件
EPA(経済連携協定)は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から候補者を受け入れる制度です。
候補者は母国で看護学校卒業または介護施設での実務経験を有しており、一定の日本語能力を身につけてから来日します。受け入れ施設では4年間の研修期間中に介護福祉士国家資格の取得を目指し、合格すれば引き続き「介護」の在留資格で勤務することができます。
ただし、受け入れには常勤介護職員40名以上などの厳しい施設要件があります。
在留資格「介護」の安定性
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を有する外国人が取得できる在留資格です。更新回数に制限がなく、家族の帯同も可能であるため、最も安定した雇用形態を実現できます。
しかし、この在留資格を取得するためには、まず他の制度で来日し、日本で介護福祉士資格を取得する必要があります。
技能実習制度と特定技能制度の比較
技能実習制度は、開発途上国の人材育成を目的とした制度で、最長5年間の受け入れが可能です。比較的受け入れやすい制度である一方、実習生の転職は原則として認められておらず、技能移転が主目的であるため長期雇用には適していません。
特定技能制度は、2019年に創設された比較的新しい制度で、介護分野では最長5年間の就労が可能です。技能実習制度と異なり転職が可能である点が特徴的ですが、家族の帯同は認められていません。
介護福祉士資格の重要性
長期的な安定雇用を重視するなら、最終的に「介護」の在留資格取得を目指す道筋を描くことが重要です。
そのためには、まず技能実習や特定技能で受け入れ、計画的な日本語教育と資格取得支援を通じて介護福祉士資格の取得を支援する戦略が効果的です。
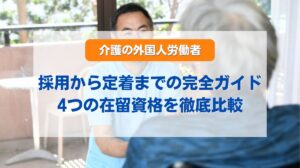
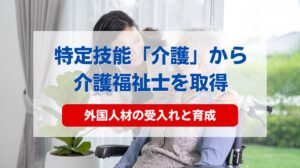
外国人介護職員の受入れで直面する2つの課題

外国人介護職員の離職につながる根本的な原因を正しく理解することが、効果的な対策の第一歩です。多くの施設で共通して発生している課題を詳しく見ていきましょう。
日本語能力のバラつきが現場に与える深刻な影響
外国人介護職員を受け入れた多くの施設が直面するのが、日本語能力のバラつきという課題です。同じ施設内でも、職員によって日本語能力試験N3レベルの方もいれば、まだN4レベルにも達していない方もいるのが現実です。
このような状況では、利用者との適切なコミュニケーションが困難になるだけでなく、日本人職員が通訳や説明に多くの時間を割かれ、本来の業務に支障をきたすケースが頻発しています。
特に問題となるのが、緊急時の対応や医療従事者との連携場面です。「痛い」「苦しい」といった利用者の訴えを正確に理解し、適切に記録・報告することができなければ、利用者の安全に関わる重大な問題に発展する可能性があります。
外国人の資格取得率の低さとその影響
もう一つの深刻な問題が、資格取得率の低さです。外国人の介護福祉士国家試験合格率は約30〜40%程度にとどまっており、これは日本人受験者の合格率70%前後と比較して大幅に低い数値となっています。この背景には、試験問題の理解に必要な日本語読解力の不足、専門用語への対応困難、受験勉強と実務の両立の難しさなどがあります。
資格取得ができないことで、外国人職員は在留資格「介護」への変更ができず、技能実習や特定技能などの在留資格で決められた期間しか働けません。これにより、長期的なキャリア形成への不安が高まり、より良い条件を求めて他施設への転職や帰国を選択するケースが後を絶ちません。
このような課題が相互に関連し合うことで、悪循環が生まれているのが現状です。日本語能力の不足により業務遂行に困難を感じた職員は、自信を失い学習意欲も低下しがちになります。その結果、資格取得への挑戦を諦め、最終的に離職に至るケースも多く見られます。
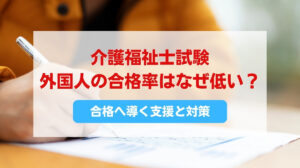
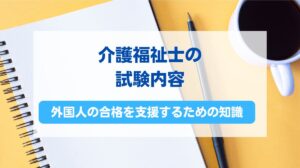
介護で求められるレベルと効果的な教育方法

外国人介護職員の成功には日本語能力の向上が不可欠です。介護現場で実際に必要とされる日本語レベルと、効率的に能力を伸ばす具体的な方法をご説明します。
介護現場で求められる日本語レベル
介護現場で求められる日本語レベルは、業務内容によって段階的に異なります。基本的な介護業務を行うためには最低限N3レベルが必要とされていますが、利用者や家族との円滑なコミュニケーション、正確な記録作成、他職種との連携を考慮すると、N2レベルが理想的です。
N2レベルに到達することで、複雑な説明や抽象的な概念も理解できるようになり、介護職員として求められる専門的なコミュニケーション能力を身につけることができます。
現場で頻発するコミュニケーション問題
現場で頻発する日本語コミュニケーション問題の多くは、語彙力不足と表現方法への理解不足に起因しています。
例えば、利用者が「だるい」と訴えた際に、それが身体的な疲労なのか、精神的な不調なのか、あるいは痛みの表現なのかを正確に理解し、適切に記録・報告することは決して簡単ではありません。
段階的学習計画の重要性
効果的な日本語教育を実現するためには、段階的な学習計画が不可欠です。多くの外国人職員は来日当初、基本的な挨拶や簡単な指示理解程度の日本語力からスタートします。
この状態からN2レベルに到達するまでには、一般的に800時間から1200時間の学習時間が必要とされています。これを現実的なペースで進めるためには、毎日2時間程度の学習を1年から1年半継続する必要があります。
継続学習を支援するオンライン学習の活用
近年、オンライン学習の活用が注目されている理由は、継続学習を支援する仕組みが充実していることにあります。
スマートフォンやタブレットを使用して通勤時間や休憩時間にも学習でき、個々の進度に合わせて繰り返し学習することが可能です。また、学習履歴が自動的に記録されるため、管理者側も職員の学習状況を把握し、必要に応じてサポートを提供することができます。
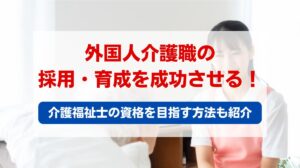
現場の負担を軽減する効率的な教育システム

従来の教育方法では限界があります。現場の負担を大幅に軽減しながら、より効果的な教育を実現するシステムの特徴と導入メリットをご紹介します。
従来の教育方法の限界
従来の外国人職員教育方法には多くの課題があります。外部講師を招いた集合研修は、全職員のスケジュール調整が困難で、受講できない職員が出てしまうことが頻繁にあります。
また、講師の交通費や謝礼などのコストも継続的な負担となります。個別指導を日本人職員が行う場合は、指導する側の負担が大きく、本来の業務に支障をきたすケースも少なくありません。
オンライン学習システムの管理面でのメリット
オンライン学習システムでは、学習管理システムを通じて各職員の学習時間、進捗状況、理解度を一目で確認することができます。
これにより、学習が滞っている職員には個別のフォローアップを提供し、順調に進んでいる職員にはさらなるチャレンジ機会を与えることができます。
効果的なシステムの特徴
効果的なオンライン学習システムの特徴として、レベル別のカリキュラムが整備されていることが挙げられます。
初級者向けの基礎的な日本語学習から、上級者向けの専門的な内容まで段階的に学習できる環境が整っていれば、職員のレベルに関係なく適切な教育を提供することができます。
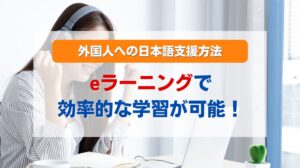
外国人職員の介護福祉士資格取得を成功させる4つのステップ

介護福祉士資格の取得は外国人職員の長期定着に直結する重要な要素です。多くの施設で実践されている成功パターンを4つのステップに整理してお伝えします。
現状把握と目標設定
成功への第一歩は、個々の職員の現状把握と目標設定です。まず日本語能力試験のレベル確認を行い、現在の日本語力を客観的に評価します。
介護福祉士試験に合格するためには、最低でもN3レベル、できればN2レベルの日本語能力が必要とされています。現在のレベルと目標レベルの差を明確にし、どの程度の期間と学習量が必要かを具体的に算出することが重要です。
段階的な学習計画の策定
多くの施設で失敗しがちなのが、いきなり介護福祉士試験対策から始めてしまうことです。日本語の基礎力が不十分なまま専門的な試験対策に取り組んでも効果は限定的です。
まずは日本語能力試験N3またはN2の合格を目指し、その後に介護福祉士試験対策に移行するという段階的なアプローチが成功のポイントとなります。
効率的な学習環境の整備
従来の集合研修や講師派遣による指導は、スケジュール調整が困難で継続性に課題があります。
近年注目されているオンライン学習システムを活用すれば、職員が自分のペースで繰り返し学習でき、管理者側も学習進捗を一元的に把握できるメリットがあります。
学習継続のためのモチベーション管理
資格取得までには長期間を要するため、途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
定期的な面談による進捗確認、小さな達成に対する承認、将来のキャリアパスの明確化などを通じて、学習意欲を維持する仕組みづくりが必要です。
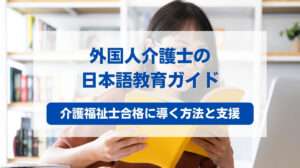
日本語カフェのオンライン講座で効率的な資格取得支援を実現

日本語カフェには、日本語能力向上から介護福祉士資格取得まで、一貫した支援体制を実現できる、オンライン講座があります。
JLPT合格コース
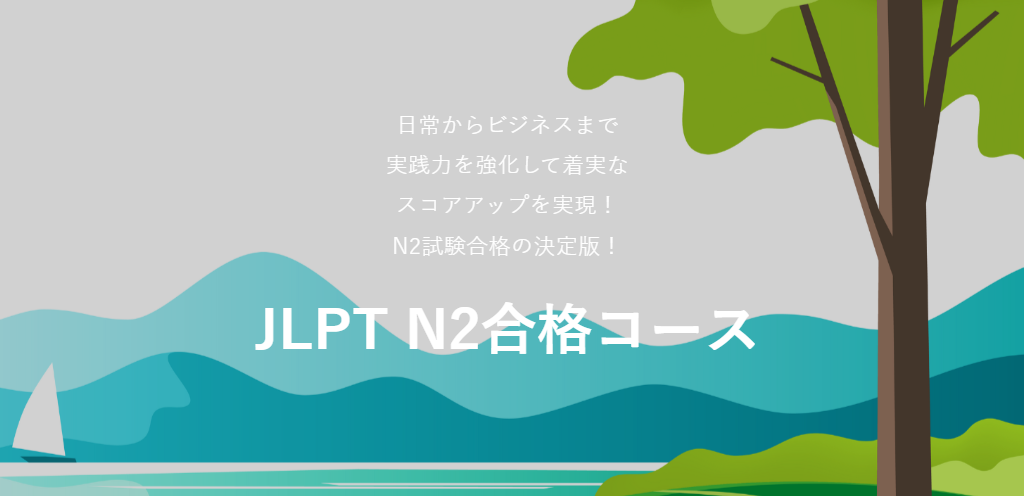
外国人介護職員の日本語能力向上と資格取得支援において、
「日本人講師の採用や管理が大変」
「講師の毎月の人件費が高すぎる」
「自発的に学習を進めてくれる教材が欲しい」
といった課題を抱えている施設が数多くあります。これらの課題を解決し、効率的な資格取得支援を実現するのが、日本語カフェの「JLPT合格コース」です。
JLPT合格コースの特徴
日本語カフェのJLPT合格コースは、厳しい審査をパスした一流の日本語教師が監修した、合格に特化した動画カリキュラムを提供しています。レベル別に最適化された完全カリキュラムでN5からN1まで対応しています。
それぞれのレベルごとに語彙・文法・読解・聴解のバランスを最適化し、「何を、どの順番で学べば合格できるか」がすべて整理された学習プランにより、最短ルートで合格を目指すことができます。
効率的な学習方法とスケジュール
学習方法も効率性を重視した設計となっています。まず単語をながら学習で覚えることから始まり、その後文法を動画と演習で習得し、単語と文法の基礎が固まってから読解・リスニング問題の演習に取り組みます。
移動時間や隙間時間を活用して、ずっとアプリの動画を流すことで、1日2時間程度でもストレスなく自然に日本語を覚えることができます。
管理画面による進捗管理
利用者一人ひとりの学習状況を一目で確認できる管理画面も大きな特徴です。これまで管理にかかっていた時間をぐっと短縮でき、浮いた時間を他の業務に活用することができます。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
\ 無料体験はこちらから/
介護福祉士合格対策集中講座
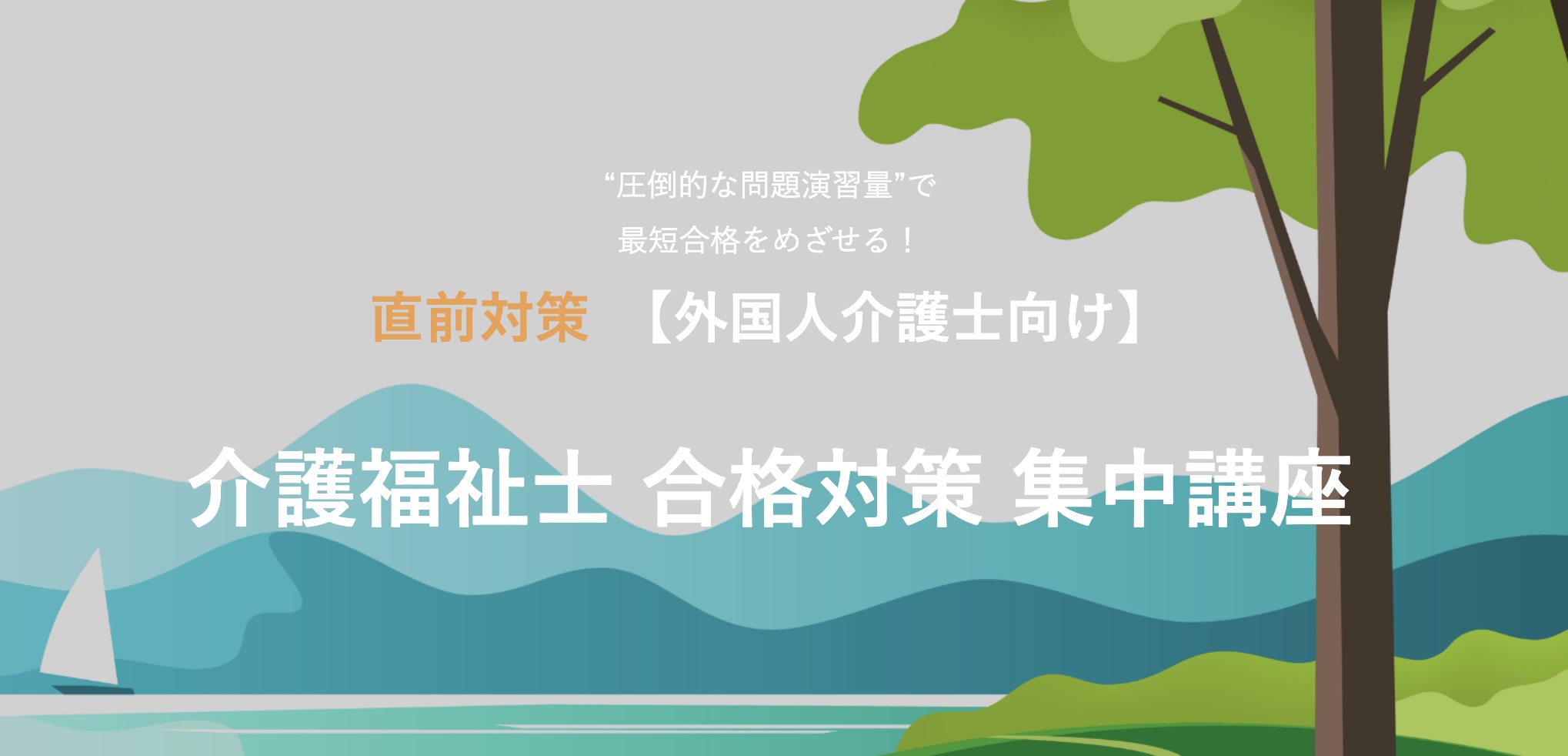
介護福祉士資格取得を目指す職員には、「介護福祉士合格対策集中講座」も提供しています。試験まで時間がない、仕事と勉強の両立は難しい、日本語も不安といった悩みを抱える外国人介護士向けに、4ヶ月で介護福祉士合格を目指せる集中講座として設計されています。
知識豊富な介護福祉士の講師による徹底サポートのもと、集中すべきポイントを効率的に学習できます。
圧倒的な模擬試験と過去問数で本番を徹底的にシミュレーションし、豊富な過去問を一緒に解きながら解説する講義により、試験対策も万全です。
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!

- ■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- ■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- ■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
推奨される学習ルート
推奨される学習ルートは、まずJLPTコースで日本語能力試験N2レベル合格を目指し、その後介護福祉士受験対策講座で国家資格取得に取り組むという段階的なアプローチです。
このような体系的な学習支援により、外国人職員の確実なスキルアップと資格取得を実現することができます。
\ 詳しくはこちらから/
外国人介護職員の定着には日本語教育と資格取得支援が重要

外国人介護職員を採用すること自体は比較的容易になりましたが、真の課題は「採用した人材をいかに長く定着させ、介護福祉士資格の取得まで導けるか」という点にあります。
離職率の高さや資格取得率の低さは、現場の人材不足をさらに深刻化させる大きな要因です。しかし、その背景には「日本語能力の不足」と「キャリア形成への不安」という共通した問題が考えられます。
採用した人材を一時的な労働力として捉えるのではなく、長期的なキャリア形成を共に歩む「仲間」として育成していく視点が欠かせません。日本語教育と資格取得支援にしっかり投資することで、施設全体の人材基盤が安定し、利用者に提供するサービスの質も向上していきます。
今後の介護業界においては、「採用」から「定着・育成」へと視点を転換することが、生き残りのための必須条件となるでしょう。今こそ、制度の正しい理解と効果的な支援体制の構築に取り組み、外国人介護職員とともに持続可能な介護現場を実現していきましょう。
\ ご相談はお気軽に/