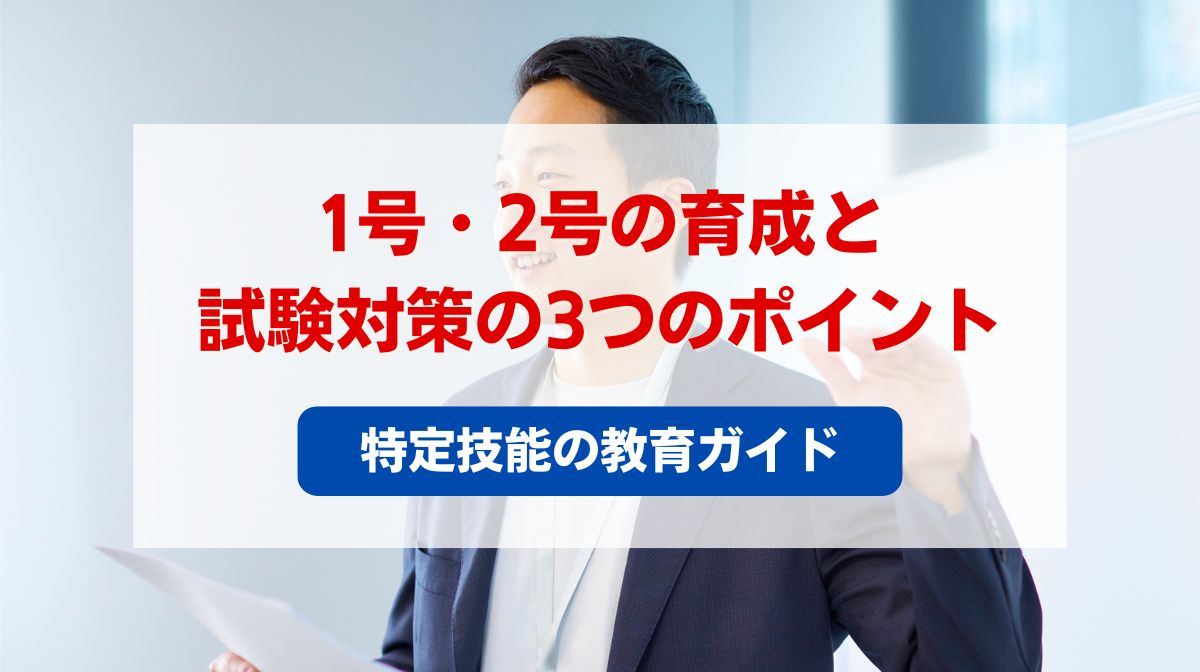「特定技能外国人を採用したものの、どんな教育をすれば良いのだろう?」 「1号スタッフの在留資格を更新し、2号へステップアップさせたいが、試験対策はどう進めるべきか…」
特定技能制度を活用して外国人材の受け入れを行う多くの企業が、採用後の教育に関する具体的な進め方について、さまざまな悩みや疑問を抱えています。
本記事では、特定技能外国人の教育計画の立て方から、外部サービスの賢い活用法まで、企業の担当者様が知りたい情報を解説していきます。外国人材が安心して能力を発揮し、企業の戦力として成長していくための体制づくりに、ぜひお役立てください。
特定技能制度における「教育」と企業の役割

特定技能外国人の教育について考える上で、まず制度における企業の役割を正確に理解しておくことが重要です。特定技能外国人は研修生ではなく、企業の生産性を担う一人の「労働者」です。そのため、教育のアプローチも、企業の戦力として育成し、生産性を向上させるという視点で行うことが求められます。
受入れ企業に求められる「支援」とは
特定技能外国人を受け入れる企業(または委託を受けた登録支援機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに基づいた支援を実施する義務があります。この支援計画には、外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるようにするための支援内容が定められています。
例えば、雇用契約の内容や日本での活動内容を本人が理解できる言語で説明する「事前ガイダンス」や、日本での生活に不可欠な住居の確保、銀行口座開設などを手助けする「生活に必要な契約の支援」が含まれます。さらに、業務や生活上の悩みを聞く「相談・苦情への対応」や、「日本語学習の機会の提供」も重要な支援項目です。
その他、出入国時の送迎や定期的な面談の実施など、合計10項目にわたるきめ細やかなサポートが企業には求められており、この中の「日本語学習の機会の提供」は教育体制の基盤となる支援です。
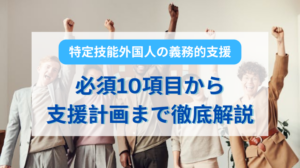
義務的支援と「育成」としての教育
企業が持続的に成長していくためには、上記の義務的な支援に加えて、外国人材の能力をさらに引き出し、生産性を向上させるための積極的な「育成」としての教育がとても重要になります。技能レベルの向上や、特定技能2号へのステップアップを目指す試験対策などが、この「育成」に当たります。
特定技能1号と2号|求められる能力と教育内容の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、求められる技能水準や待遇が異なります。長期的な人材育成を考える上で、この違いを理解しておくことはとても大切です。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 求められるレベル | 特定の分野で相当程度の知識・経験を持ち、即戦力として業務を遂行できる水準 | 特定の分野で熟練した技能を持つ、現場のリーダーとして他の作業員を指導できる水準。 |
| 在留期間 | 通算で上限5年。1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新が必要 | 上限なし。3年、1年または6ヶ月ごとの更新で、長期就労が可能 |
| 家族帯同 | 原則として認められない | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
特定技能1号で受け入れ可能な分野は、2024年の制度改正を経て、以下の16分野に拡大されています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
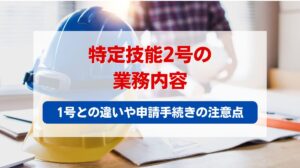
特定技能1号から2号へ|移行を実現する3つの教育の柱

特定技能1号から2号へのステップアップは、在留期間が更新されるだけでなく、求められる役割が「一人の作業員」から「現場のリーダー」へと大きく変化することを意味します。この移行を円滑に進めるためには、企業による計画的な教育サポートが欠かせません。
ここでは、移行に必要な教育を「日本語能力」「技能評価試験」「実務経験」の3つの柱に分けて、具体的なポイントを解説します。
① 日本語能力
特定技能2号には、一部の分野を除き、特定の日本語能力試験のスコアが必須要件とされているわけではありません。しかし、現場のリーダーとして他の作業員に指示を出したり、作業の進捗を管理したりするためには、1号の時よりも格段に高いレベルの日本語運用能力が求められます。
教育のポイントは、日常会話レベルから一歩進んだ、「指導・伝達のための日本語」を身につけさせることです。
具体的には、以下のような能力の育成をサポートします。
- 作業手順の明確な説明
-
後輩や他のスタッフに対して、業務の手順や注意点を分かりやすく説明する練習をさせます。
- 報告・連絡・相談
-
自身の業務報告だけでなく、チーム全体の状況を把握し、上長に的確に報告する能力を養います。
- ミーティングでの発言・調整
-
朝礼やミーティングの場で、作業計画の提案や、他のメンバーへの指示出しなどを担当させ、人前で話すことに慣れさせます。
これらの能力は、単語や文法を覚えるだけでは身につきません。社内で模擬ミーティングを実施したり、ビジネス日本語の研修に参加させたりするなど、実践的なアウトプットの機会を企業が提供していくことが大切です。
② 技能評価試験
2号への移行には、各分野で定められた「特定技能2号評価試験」に合格しなくてはなりません。この試験は、1号の試験と比べて難易度が格段に高く、より高度で専門的な知識と、管理能力が問われます。
教育のポイントは、「学科」と「実技」の両面から計画的な試験対策を行うことです。
- 学科試験対策
-
2号の学科試験では、単なる作業知識だけでなく、工程管理、品質管理、原価管理、安全衛生管理といったマネジメントに関する知識が問われます。
市販の教材やテキストを用いた自己学習を促すだけでなく、なぜその管理が必要なのかという背景理論まで含めて社内で勉強会を開くなど、深い理解を促すアプローチが求められます。
- 実技試験対策
-
実技試験では、複数の作業員を適切に配置し、指示を出しながら一つのプロジェクトを完成させるような、段取り能力や指導能力が評価されます。合格のためには、実際の職場で試験内容を想定した模擬訓練を繰り返し行うことが非常に良い練習になります。
自社だけでの対策が難しい場合は、過去の出題傾向を分析し、専門的なカリキュラムを持つ外部の対策講座やオンライン学習サービスを積極的に活用することを検討しましょう。
実務経験
試験合格に必要な能力は、日々の実務経験を通じて養われます。2号への移行を見据えた教育では、OJTの進め方を「作業を教える」ステージから「責任を委譲する」ステージへと移行させる必要があります。
教育のポイントは、意図的にリーダーとしての経験を積ませることです。
- 小規模チームのリーダーを任せる
-
まずは2~3人のチームをまとめる役割を与え、作業の段取りや人員配置を本人に考えさせます。
- 後輩の指導役を任命する
-
新しく入った技能実習生や特定技能1号のスタッフの教育係を任せることで、人に教える難しさと責任感を学ばせます。
- 問題解決の機会を与える
-
現場で軽微なトラブルが発生した際に、すぐに答えを教えるのではなく、「君ならどうする?」と問いかけ、本人に解決策を考えさせることで、主体性と判断力を育成します。
このような経験を計画的に積ませることで、作業員からチームを牽引するリーダーへと成長していきます。企業は、日々の業務の中に、こうした成長の機会を意図的に組み込んでいくことが求められます。
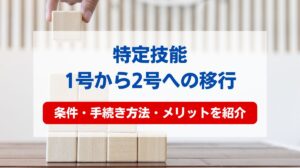
【分野別】1号から2号への移行に向けた教育ポイント
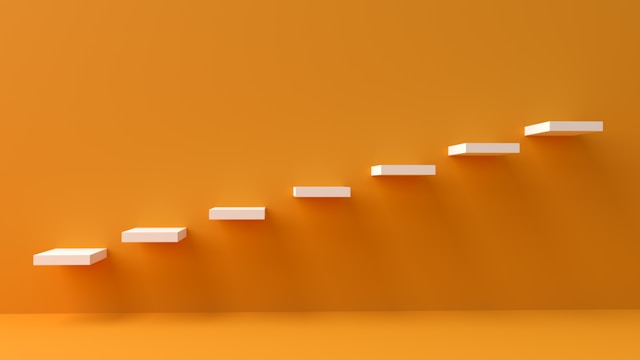
ここでは主要な分野を例に、1号から2号へステップアップするために必要な教育のポイントを解説します。
建設分野
建設分野の2号は、一人の熟練作業員から、チームを率いる職長や班長の役割を担うことが期待されます。
教育のポイントは、施工管理能力と指導能力の育成です。
日々の業務の中で、作業全体の工程表や複雑な図面を読み解き、資材の段取りや人員配置を考えさせる機会を与えます。また、朝礼でのKY(危険予知)活動で進行役を任せたり、小チームのリーダーとして安全指示を出させたりすることで、現場を管理する能力を養います。
2号移行の試験対策としては、施工計画書を作成する筆記問題や、現場でのトラブル対応を問うような実技問題が出題される傾向にあります。そのため、過去問題を参考にしながら、模擬的な施工計画書を作成する練習や、さまざまな状況を想定したロールプレイングを行うことが合格への近道となります。
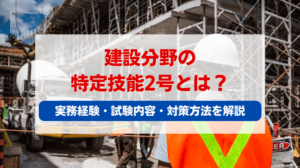
外食業分野
外食業分野の2号は、調理や接客のプロであることはもちろん、店舗運営を担うシフトリーダーや店長代理のような役割が求められます。
教育では、日々の調理・接客業務に加え、店舗マネジメントに関する知識と経験を積ませます。
例えば、食材の在庫管理や発注業務、売上データに基づいたメニュー改善の提案、アルバイトスタッフのトレーニングなどを担当させます。
2号の試験対策では、原価率や人件費率といった数値管理や、適切な勤務シフト表の作成能力が問われます。日々の業務から店舗の計数管理に意識を向けさせると共に、模擬試験などで具体的な計算問題やシフト作成問題に繰り返し取り組むことが重要です。
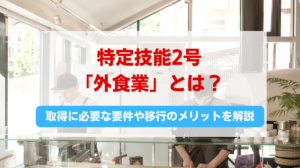
飲食料品製造業分野
この分野の2号は、一人のライン作業員から、製造ライン全体を監督するラインリーダーや品質管理の担当者へとステップアップします。
教育のポイントは、品質管理と工程管理の視点を身につけさせることです。
HACCPに基づいた衛生管理を徹底するだけでなく、「なぜこの工程が必要なのか」という理由を理解させ、製造ラインで発生した不具合の原因究明や改善提案(カイゼン活動)に参加させます。
2号の試験対策としては、品質管理(QC)の手法や、生産性向上に関する知識が問われます。特性要因図や管理図といったQC七つ道具の使い方を学び、実際の生産データを用いて改善策を立案するような、より実践的な学習を進めていく必要があります。
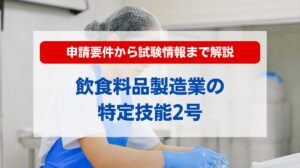
ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野の2号は、清掃作業員から、現場全体を管理する現場責任者(スーパーバイザー)の役割を担います。
教育では、個々の清掃技術の向上に加え、現場管理能力を育成します。
清掃チームの作業スケジュールの作成、資材や清掃用具の在庫管理と発注、作業完了後の品質チェックなどを任せます。
2号の試験対策では、現場全体の作業計画の立案能力や、スタッフへの指導能力が評価されます。そのため、特定の建物や状況を想定した詳細な清掃作業計画書を作成する練習や、新人スタッフに指導するという設定でのロールプレイングを行うことが、実践的な試験対策となります。
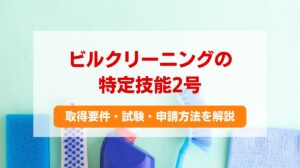
農業分野
農業分野の2号は、一人の農作業員から、生産工程全体を管理する農場長や生産リーダーへと成長することが期待されます。
教育では、日々の農作業に加え、生産管理の視点を持たせることが重要です。
年間を通した栽培計画や飼養計画の立案、肥料や農薬の在庫管理と使用計画の作成、日々の生産記録の管理などを任せてみます。
2号の試験対策は、こうした管理能力を評価する内容が中心です。例えば、天候リスクや病害の発生を踏まえた上で、年間の生産計画と収支計画を作成させるような課題が出されます。日頃から経営的な視点を意識させ、計画立案とリスク管理の訓練を積ませることが合格に繋がります。
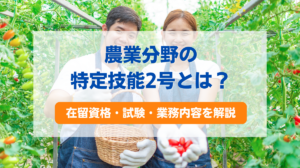
介護分野
現時点では、介護分野に特定技能2号の区分は設けられていません。しかし、事業所内でチームリーダーや指導役といったキャリアアップを目指す上での教育は、他の分野の2号移行教育と共通する部分が多くあります
個別の介護技術の習熟に加え、介護計画書の作成への参画、後輩スタッフへのOJT指導、利用者家族とのカンファレンスへの同席といった経験を積ませることが、介護職員としての総合的な能力向上に繋がります。
また、国家資格である「介護福祉士」の取得を目標に設定し、その試験対策を支援することも、本人の技能を客観的に証明し、モチベーションを高める上でとても良い方法です。

人材の定着と育成に繋がる教育計画の立て方 3ステップ

場当たり的な指導ではなく、計画的な教育を行うことが、外国人材の能力を最大限に引き出し、定着に繋げるための道筋です。ここでは、具体的な教育計画の立て方を3つのステップで紹介します。
現状のスキルレベルと日本語能力の確認
教育計画を立てるための最初の仕事は、対象となる外国人材の現在の状況を正確に把握することです。採用時の試験結果や職務経歴書だけでなく、受け入れ後に簡単な作業を任せてみて、その習熟度や安全意識を確認します。業務ごとに「一人でできる」「指導があればできる」「まだできない」といったチェックリストを作成して評価するのも良い方法です。
日本語能力については、日本語能力試験(JLPT)等の客観的な指標に加え、朝礼でのスピーチや日報の記述、同僚との会話の様子などから、実践的なコミュニケーション能力を把握します。
育成ゴールの設定と本人との共有
次に、企業としての人材育成方針と、本人のキャリアアップへの希望をすり合わせ、具体的な目標を設定します。企業として「まずは1号の在留期間5年を上限に安定して業務をこなせる人材に育てる」のか、「本人の希望と能力があれば2号への移行を積極的に支援する」のか、方針を明確にしておきましょう。
その上で、定期的な面談の場で本人の仕事への満足度や将来の希望を聞き、「半年後までに〇〇の作業を一人でできるようになる」「次回の技能測定試験に合格する」といった、具体的で測定可能な目標を一緒に立てます。本人が納得した目標を持つことは、学習意欲の源泉となります。
具体的な教育内容とスケジュールの決定
目標が決まったら、そこから逆算して日々の教育スケジュールに落とし込みます。OJT(On-the-Job Training)では、どの業務を、誰が、いつまでに教えるかを明確にした指導計画を作成します。並行して、Off-JT(Off-the-Job Training)として、試験対策の勉強時間や外部の講習会への参加などをスケジュールに組み込みます。
例えば、試験日が半年後であれば、「最初の3ヶ月でテキスト全体を学習し、次の2ヶ月で問題演習、最後の1ヶ月で模擬試験と苦手分野の復習」といった大まかな計画を立て、それを月間、週間の学習目標に分解します。学習計画表を作成し、進捗を本人と共有することが、学習のペースメーカーとなります。
自社?それとも外部委託?教育の実施方法とそれぞれの特徴

特定技能外国人の教育や支援は、自社で全て行う方法と、登録支援機関のような外部の専門機関に委託する方法があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った方法を選びましょう。
自社で教育を行う場合、外部への委託費用がかからず、自社の業務内容や社風に合わせたきめ細やかな指導がしやすいという側面があります。しかしその反面、教育担当者の業務負担が大きくなったり、分野ごとの専門的な試験対策や最新の法改正に関する情報収集のノウハウが少なかったりといった課題も生じがちです。
一方、登録支援機関等に委託すると、専門的なノウハウを持つ機関に任せられるため、企業の教育担当者の負担を大幅に軽減できます。支援計画の作成から各種手続き、生活サポートまで一括で依頼できる場合も多くあります。ただし、当然ながら委託費用が発生し、団体によってサービスの質や内容に差があるため、慎重な選定が求められます。
自社に教育のノウハウがあり、受け入れ人数が少ない場合は自社実施も一つの手ですが、担当者の負担軽減や教育の質を重視するなら、専門機関への委託や、後述するオンラインサービスの部分的な活用が賢明な選択肢となるでしょう。
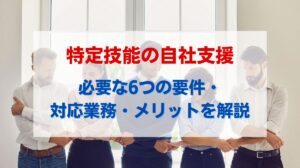
自社での教育に限界を感じたら「日本語カフェ」という選択肢
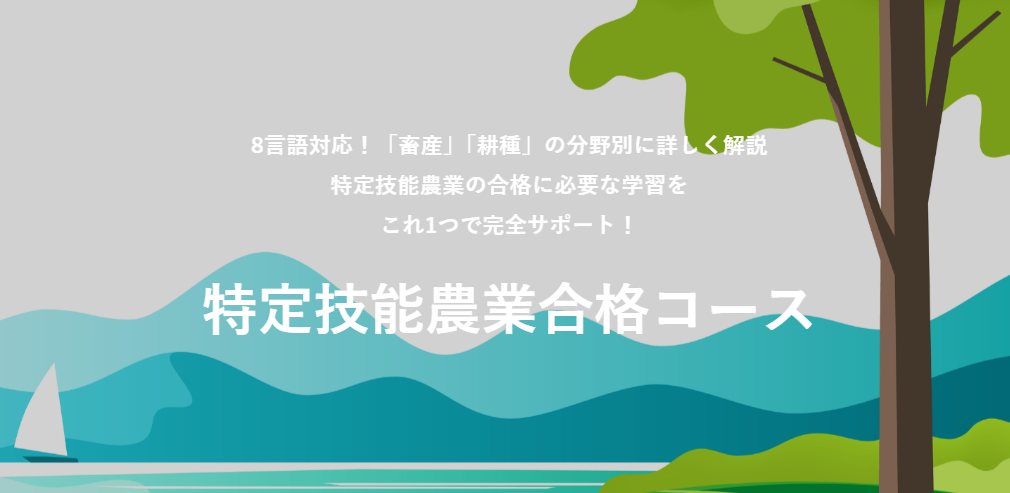
「スタッフの学習モチベーションの維持や、進捗の管理が大変…」
「受け入れ人数が増え、教材の費用が負担になってきた…」
「本人に任せているが、自発的に勉強を進めてくれない…」
このような悩みは、多くの受け入れ企業が直面する現実です。自社での教育体制構築に限界を感じている場合、オンラインで完結する学習サービスの活用が、状況を打開する一手になります。
『特定技能1号・2号合格コース』は、学科・実技試験の合格に特化した動画カリキュラムと、日本語能力試験(N5〜N1)対策コースを、いつでもどこでも、そして何度でも学習できる環境で提供します。貴社の教育に関する負担を大幅に軽減し、外国人材の自発的な学びを強力に後押しします。
日本語カフェでは、学習効果を最大化するために設計された、独自の「3ステップ学習法」を採用しています。
- まず最初のステップは「解説動画の視聴」です。専門知識が必要で複雑な内容も、母語のスライドと音声解説(日本語と各国語に対応)によって、直感的に、そして体系的に理解できます。1本あたり15分程度の動画コンテンツなので、通勤中や休憩時間といったスキマ時間を活用して、無理なく学習を進められます。
- 次のステップは「ワークシートへの記入」です。「見る」だけのインプットでは、知識はなかなか定着しません。動画と完全に連動した穴埋め式のワークシートを使って、視聴した内容をすぐにアウトプットします。実際に自分の手を動かして記入することで、記憶が強化され、理解度が一層高まります。
- 最後のステップが「演習問題の実践」です。本番の試験形式を想定して制作された、豊富なオリジナル演習問題に挑戦します。何度も繰り返し問題を解くことで、知識の使い方に慣れ、どんな問題が出ても落ち着いて対応できる実践力と自信を育てます。
企業の管理負担も大幅に軽減
受講者一人ひとりの学習時間、動画の視聴状況、演習問題の進捗といったデータは、企業の管理者様向け専用ページで一目で確認可能です。「誰がどこまで進んでいるか」が一元管理できるため、これまで進捗確認の面談などに費やしていた時間を大幅に削減。客観的なデータに基づいた、的確な指導や声かけが行えます。
コストを抑えながら、外国人スタッフの自発的な学習を促し、着実な技能向上と試験合格を目指しませんか?
\お問い合わせはこちらから/
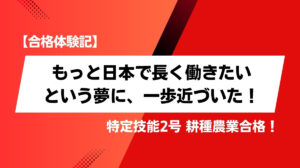
まとめ:計画的な教育が外国人材育成の基盤に
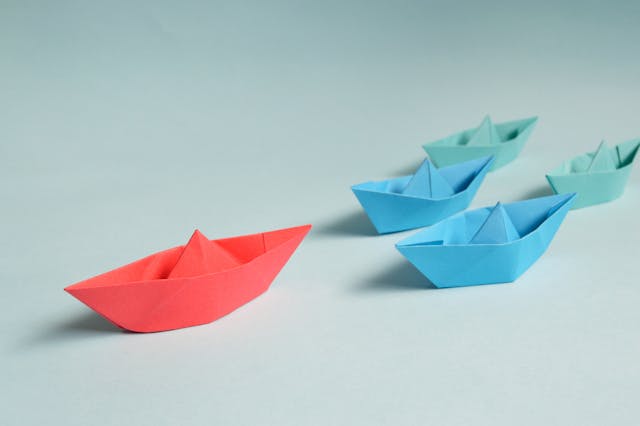
本記事では、特定技能外国人の教育について、企業の役割から具体的な計画の立て方、分野別のポイント、そして効率的な学習方法まで幅広くご案内しました。
特定技能制度では、業務や生活に関する情報提供や日本語学習機会の提供が、受入れ企業に求められます。そして、1号から2号への移行には、分野ごとの専門性が高い技能測定試験への対策が重要になります。
個々のレベルに合わせた計画的な育成と、本人の意欲を引き出すための面談や目標共有が、人材の定着に繋がるでしょう。
外国人材の採用と育成は、これからの日本企業にとって、事業の継続と成長を支えるとても重要な取り組みです。計画的な教育体制を整え、外国人スタッフが日本で、そして貴社で、安心して長く活躍できる環境を築いていきましょう。