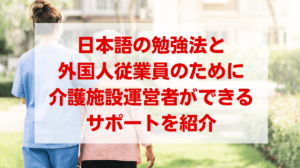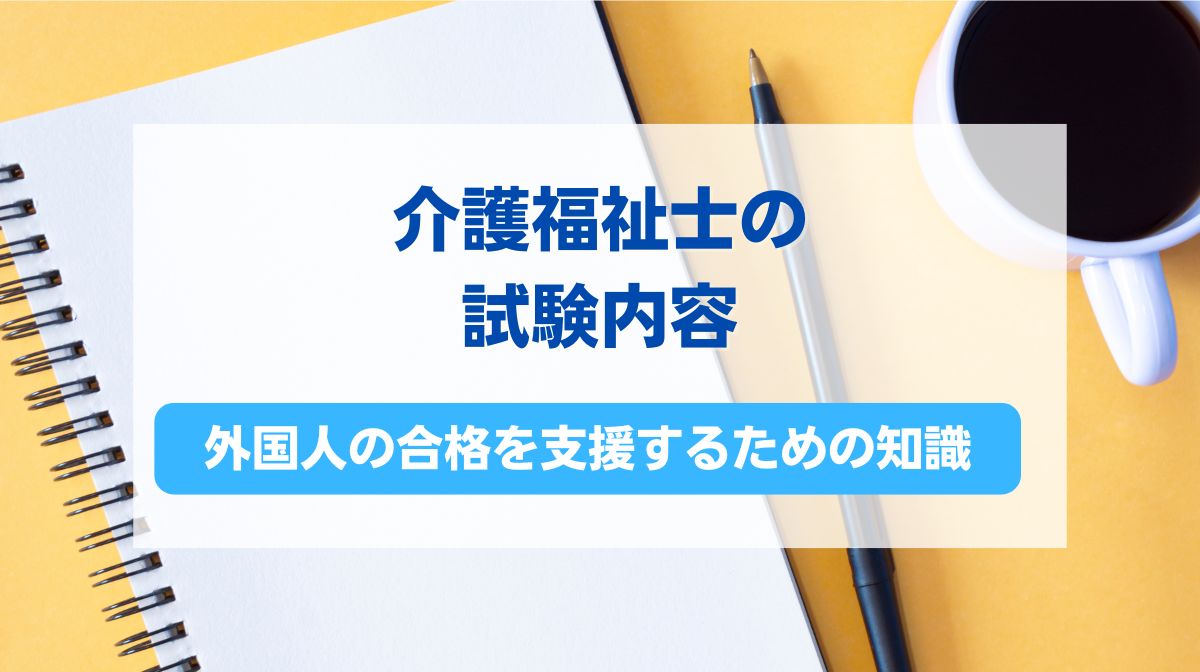「外国人スタッフに、これからも長く活躍してほしい。そのために、介護福祉士の国家資格取得を施設として後押ししたい。」そうお考えの施設の担当者様は多いのではないでしょうか。
しかし、いざサポートを始めようとすると、「そもそも試験内容は?」「日本語の壁をどう乗り越えさせればいいのだろう?」「具体的に何から手をつければいいのか分からない」といった、数々の疑問や課題に直面するかと思います。
介護福祉士の国家試験は13科目と学習範囲が広く、特に外国人受験者にとっては専門用語や長文読解など、日本語の壁が大きなハードルとなります。しかし、試験の全体像を正確に把握し、つまずきやすいポイントを理解した上で、適切なサポートを行えば、合格は決して不可能な目標ではありません。
この記事では、介護福祉士の試験内容から、外国人スタッフが合格するためにできる具体的なサポート方法について解説します。
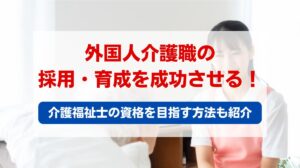
介護福祉士国家試験の概要

まず、試験の基本的な情報を正確に把握しましょう。2026年の試験日程は以下のようになっています。
試験日程(第38回・2026年)
| 筆記試験 | 2026年1月25日(日) |
|---|---|
| 受験申込期間 | 2025年8月6日(水)〜9月5日(金) |
| 「受験の手引」請求期間 | 2025年6月27日(金)〜9月3日(水) |
| 合格発表 | 2026年3月16日(月)[結果通知は3月19日発送] |
実技試験廃止と「パート合格制度」の導入
第38回試験からは、パート合格制度が新たに導入されました。試験科目がA・B・Cの3つのパートに分けられ、それぞれで合否を判定します。
- 合格したパートは翌年・翌々年の受験で免除(有効期間2年間)
- 初回受験時は全パート受験が必要
- 再受験時は不合格パートのみ受験可能
この制度により、一度にすべての科目をクリアする必要がなくなり、学習負担が軽減されます。
受験資格(外国人材・実務経験ルート)
外国人スタッフの場合、多くは「実務経験ルート」での受験になります。
| 実務経験 | 3年以上(1,095日以上かつ従事日数540日以上) |
|---|---|
| 実務者研修の修了 | 450時間カリキュラム |
以前は「実務者研修の修了」により実技試験が免除されていましたが、実技試験が廃止された現在も、受験資格としては必須です。
試験科目と出題範囲
筆記試験はマークシート形式で行われ、合計125問が出題されます。学習範囲である13科目の内容を見ていきましょう。
2026年(第38回)試験からは、筆記試験の13科目がA・B・Cの3つのパートに分かれ、パートごとに合否が判定されます。ここでは、パート別に科目を紹介していきます。
Aパート:介護の理念・人間理解・制度知識
- 人間の尊厳と自立
利用者の人格や価値観を尊重し、可能な限り自立した生活を送れるよう支援するための基本理念を学びます。現場での判断や態度の基礎となる重要分野です。 - 介護の基本
介護の目的、役割、職業倫理、専門性について理解します。介護職の社会的責任やチーム内での役割分担も含まれます。 - 人間関係とコミュニケーション
利用者や家族、多職種との信頼関係を築くための対人関係スキルを学びます。言葉の選び方や関係の維持方法もポイントです。 - コミュニケーション技術
傾聴、共感、非言語的表現など、状況に応じた適切なやり取りの方法を学びます。認知症や障害のある方との会話技術も含まれます。 - 社会の理解
介護保険制度、障害者総合支援法、生活保護制度など、日本の社会保障制度を体系的に理解します。制度を活用した適切な支援の基礎となります。
Bパート:介護実践とプロセス管理
- 生活支援技術
食事、入浴、排泄、移動、着脱衣など日常生活の援助方法を、理論と実技の両面から学びます。安全確保や感染予防も重要な内容です。 - 介護過程
情報収集から課題分析、計画立案、実施、評価までの一連の流れを体系的に理解します。記録の取り方や多職種連携も学びます。 - こころとからだのしくみ
人体の構造や機能、老化や疾患による変化、心と体の関係などを理解します。異常の早期発見や健康管理の基礎知識となります。 - 発達と老化の理解
乳幼児期から高齢期までの発達の特徴と、老化に伴う心身の変化を学びます。ライフステージごとの課題や支援方法も含まれます。
Cパート:専門的ケアと総合力
- 認知症の理解
認知症の種類や症状、進行の特徴、適切なケア方法、家族支援の方法を学びます。地域資源の活用も含まれます。 - 障害の理解
身体障害、知的障害、精神障害などの特性や生活上の課題を理解し、それぞれに応じた支援方法や制度を学びます。 - 医療的ケア
喀痰吸引や経管栄養など、介護福祉士が実施可能な医療行為の知識と手順を習得します。医療職との連携や緊急時対応も含まれます。 - 総合問題
複数科目にまたがる事例を通じて、現場での判断力や応用力を問います。知識を実践に結びつける総合力が試されます。
気になる合格基準と合格率
合格のボーダーラインは毎年変動しますが、基準を正しく理解しておくことが重要です。
合格基準は以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。
- 総得点125点に対し、総得点の60%程度(75点前後)を基準とし、問題の難易度で補正した点数以上の得点であること。
- 以下の11科目群すべてにおいて、1点以上の得点があること。
ここで、「11科目群」という部分が最大のポイントです。1科目でも0点の科目群があると、たとえ合計点が合格ラインを大幅に超えていても、その時点で不合格となってしまいます。
【合格基準で用いられる11科目群】
試験科目は全部で13科目ですが、合格基準の判定においては、以下の通り一部の科目がセットで1つの「科目群」として扱われます。
| No. | 科目群 |
|---|---|
| 1 | 人間の尊厳と自立・介護の基本 |
| 2 | 人間関係とコミュニケーション・コミュニケーション技術 |
| 3 | 社会の理解 |
| 4 | 生活支援技術 |
| 5 | 介護過程 |
| 6 | こころとからだのしくみ |
| 7 | 発達と老化の理解 |
| 8 | 認知症の理解 |
| 9 | 障害の理解 |
| 10 | 医療的ケア |
| 11 | 総合問題 |
合格率
近年の合格率は高く、第37回(2025年1月実施)試験では82.8%でした。しかし、この数字に安心は禁物です。
これは、十分な準備をしてきた受験者の合格率であり、日本語や学習環境にハンディキャップを抱える外国人受験者にとっては、依然として厳しい試験であることに変わりはありません。全科目で着実に得点するための、計画的な学習が合否を分けます。

外国人スタッフがぶつかる「3つの壁」と支援策

試験内容がわかったところで、次に外国人スタッフ特有の課題と、施設として何ができるのか、具体的な支援策を見ていきましょう。
壁①:日本語の壁(専門用語・漢字・長文読解)
日本語は、最も大きな壁です。日常会話は流暢でも、試験問題となると話は別です。「尊厳」「受容」「共感」「エンパワメント」といった抽象的な専門用語や、普段使わない漢字の読み書きでつまずきます。
また、「介護過程」や「総合問題」で出題される長い事例問題では、登場人物の関係性や状況を正確に読み解く高い読解力がなければ、正答にたどり着くことすら困難です。
- ふりがな(ルビ)付きの教材や過去問を用意する。
- OJTの中で意識的に専門用語を使い、平易な言葉で意味を解説する。
- 例:「利用者の自己決定を尊重しましょう」→「利用者さんが『自分で決めたい』という気持ちを大切にしようね」
- 日本語の学習そのものを支援する。
- 根本的な対策として、専門知識の学習と並行して、日本語能力(特に読解力)の基礎を固める学習機会を提供することが最も効果的です。
壁②:学習時間の確保の壁
日勤や夜勤を含む不規則なシフトの中で、疲れた体で学習時間を確保することは、日本人にとっても容易ではありません。慣れない異国での生活や業務は、心身ともに想像以上の負担がかかっています。帰宅後にまとまった勉強時間を確保するのは至難の業です。
- 資格取得を応援するシフト体制を組む。
- 例:研修や勉強会がある日は日勤にする、試験直前期は夜勤を減らすなど
- 学習費用を補助する制度を設ける。
- 例:教材費や受験料、研修費用などを施設が一部または全額負担する
- スキマ時間を活用できるオンライン教材を導入する。
- スマートフォン一つで通勤中や休憩中に10分でも学習できれば、スタッフの負担を減らし、学習の習慣化を促せます。
壁③:日本の介護文化・制度の理解の壁
日本の介護は、「利用者の尊厳の保持」「自立支援」といった独自の理念に基づいています。これらの概念は、文化や価値観の異なる外国人スタッフにとって、すぐには理解しにくい場合があります。
なぜ「おむつゼロ」を目指すのか、なぜ「見守り」が重要なケアなのか、その背景にある文化的な文脈を理解することが、事例問題などを解く鍵となります。
- OJTやカンファレンスで、ケアの根拠を丁寧に説明する。
- 「なぜこのケアを行うのか」という背景理念を繰り返し伝えることで、知識と実践が結びつきます。
- 日本人スタッフも交えた勉強会やディスカッションの場を設ける。
- 過去問の事例問題を題材に、「あなたならどう対応する?」と問いかけ、多様な意見を交換することで、理解が深まります。
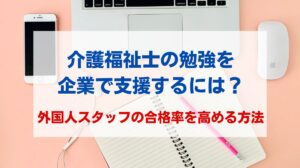
合格への最短ルート!まずは日本語能力試験(JLPT) N2を目指そう
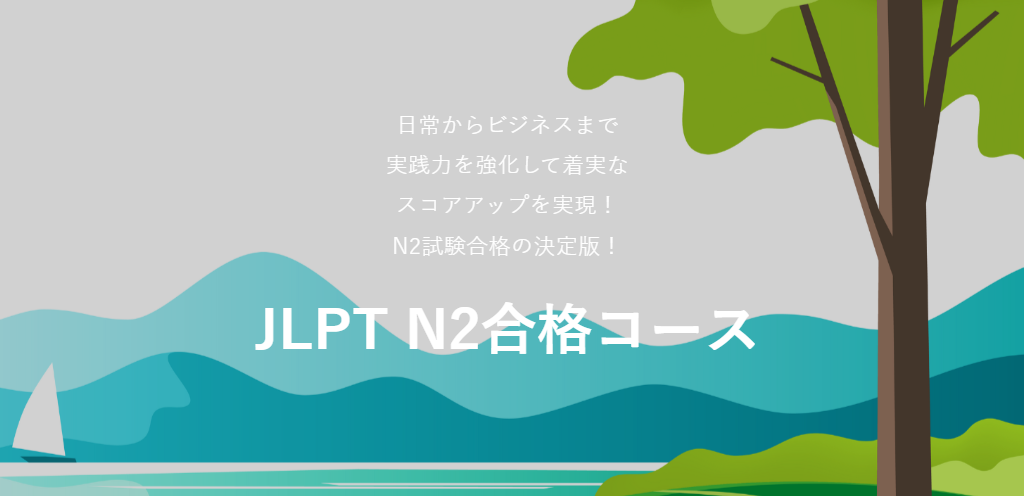
外国人スタッフの合格を本気で考えるなら、専門知識の勉強と並行して、あるいはその前に日本語能力の底上げが必要です。その目安となるのが「日本語能力試験(JLPT) N2」です。
なぜN2レベルが必要なのか?
介護福祉士の試験問題は、JLPT N2レベルの日本語能力(特に読解力)があることを前提に作られていると言っても過言ではありません。新聞の解説や平易な評論などが読めるN2レベルの力があって初めて、あの長く複雑な事例問題の意図を正確に読み解き、適切な選択肢を選ぶことができるのです。闇雲に専門用語を暗記させるだけでは、この壁は越えられません。
施設での日本語教育は難しい…オンライン講座がおすすめな理由
そうは言っても、
「施設内に日本語を教えられる人材がいない」
「講師を雇うコストや管理が大変」
「スタッフの学習進捗をどう管理すればいいか分からない」
というのが多くの施設の本音ではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、オンライン講座の活用です。プロの講師による体系的なカリキュラムで、スタッフは自分のペースで学習できます。そして施設側は、管理画面で進捗を簡単に把握できるため、教育担当者の負担を大幅に削減できるのです。
「自発的に学習を進めてくれる教材が欲しい…」「管理コストを大幅に削減したい…」 もし、外国人スタッフの日本語教育をもっとシンプルで簡単に、それでいて効果的に行いたいなら、『JLPT 合格コース』の利用が最適です。
- POINT1: 合格への最短カリキュラム
-
厳しい審査をパスした一流の日本語講師が監修。N5~N1まで各レベルに最適化されており、「何を、どの順番で学べば合格できるか」が明確です。スタッフは迷うことなく、最短ルートで合格を目指せます。
- POINT2: 高品質な動画+ドリルで実力がつく
-
プロ講師による分かりやすい動画講義に加え、反復練習できるドリルも充実。インプットとアウトプットを繰り返すことで、「わかる」が「使える」力に変わります。
- POINT3: スマホでいつでもどこでも学習可能
-
スマートフォンやタブレットに対応しており、1回10分からのスキマ学習も可能です。忙しい業務の合間や通勤時間を有効活用し、無理なく学習を続けられます。
- POINT4: 学習状況の管理が驚くほどラクに
-
管理画面でスタッフ一人ひとりの学習時間や進捗が一目瞭然。誰がどこでつまずいているかを把握し、的確な声かけができます。教育担当者の管理負担と時間を大幅に削減します。
まずはJLPT N2合格で確かな日本語力の土台を作り、自信を持って介護福祉士試験に臨むのが、外国人スタッフの合格を確実にするための、最も賢明なステップです。
\詳しくはこちらから/
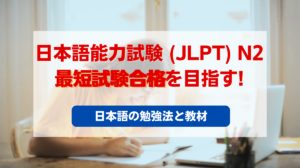
日本語に自信がついたら「介護福祉士 受験対策講座」
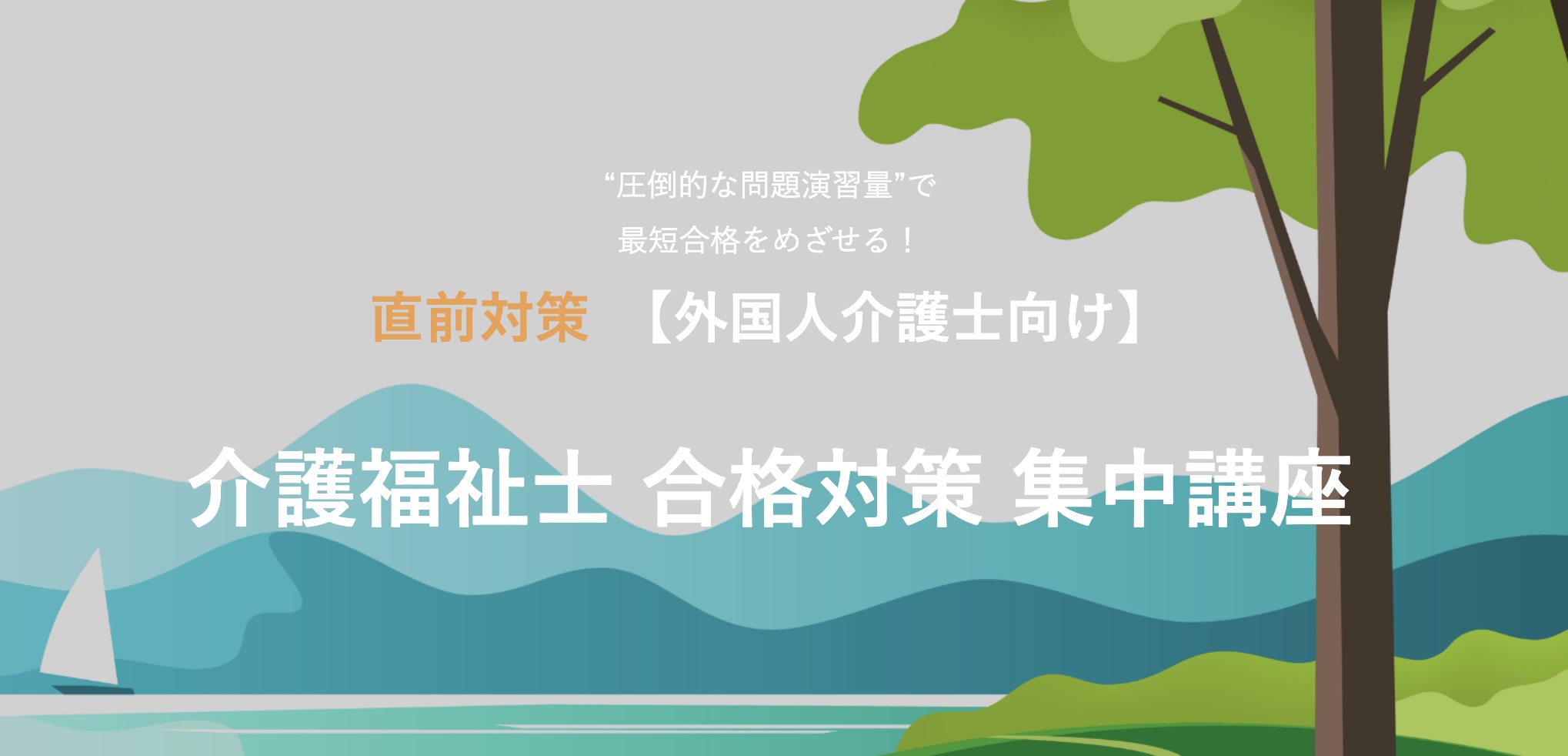
すでにN2相当の日本語力があるスタッフや、より専門的な対策を短期間で集中して行いたい場合は、こちらの講座が最適です。
「試験まで時間がない」「仕事と勉強の両立が難しい」そんな悩みを解決します。
- POINT1:介護福祉士のプロ講師が徹底サポート
-
介護現場と試験を知り尽くした講師が、出題傾向を分析し、集中すべきポイントを効率的に指導します。
- POINT2:圧倒的な過去問演習と模擬試験
-
豊富な演習量で本番のシミュレーションを繰り返し、時間配分や解答のペースを体に叩き込みます。
- POINT3:日本語学習もフルサポート
-
講座期間中は、なんと**日本語カフェのJLPTコースも使い放題。**専門知識の学習中に生じた日本語の疑問も、すぐに解決できます。
- POINT4:24時間いつでも学習可能
-
忙しい介護士の生活リズムに合わせて、好きな時間に好きな場所で学習を進められます。
\詳しくはこちらから/
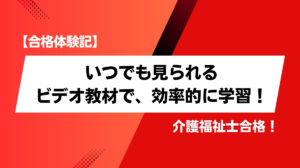
外国人スタッフの合格をサポートしよう!

今回は、介護福祉士の試験内容から、外国人スタッフが合格するために施設ができるサポート体制までを網羅的に解説しました。
- 介護福祉士試験は13科目と範囲が広く、全11科目群で得点するための計画的な学習が不可欠。
- 外国人スタッフにとって最大の壁は「日本語力」。特にN2レベルの読解力が合否を分ける。
- 合格への近道は、まず日本語能力試験(JLPT) N2レベルの日本語力を確実に身につけること。
- 施設は、シフト調整や費用補助に加え、効率的なオンライン講座を導入することで、スタッフの学習環境を劇的に改善できる。
外国人スタッフが国家資格である介護福祉士を取得することは、本人のキャリアアップとモチベーション向上に繋がるだけでなく、施設全体のサービス品質の向上、そして利用者様やご家族からの信頼獲得にも直結する、非常に価値のある投資です。
最初の一歩は、スタッフの現在の日本語レベルを正確に把握し、最適な学習環境を整えることです。
「日本語カフェ」では、外国人スタッフの日本語レベルや施設の状況に合わせた最適な学習プランをご提案します。教育に関するお悩み、ぜひ一度お聞かせください。
\ご相談はこちらから/