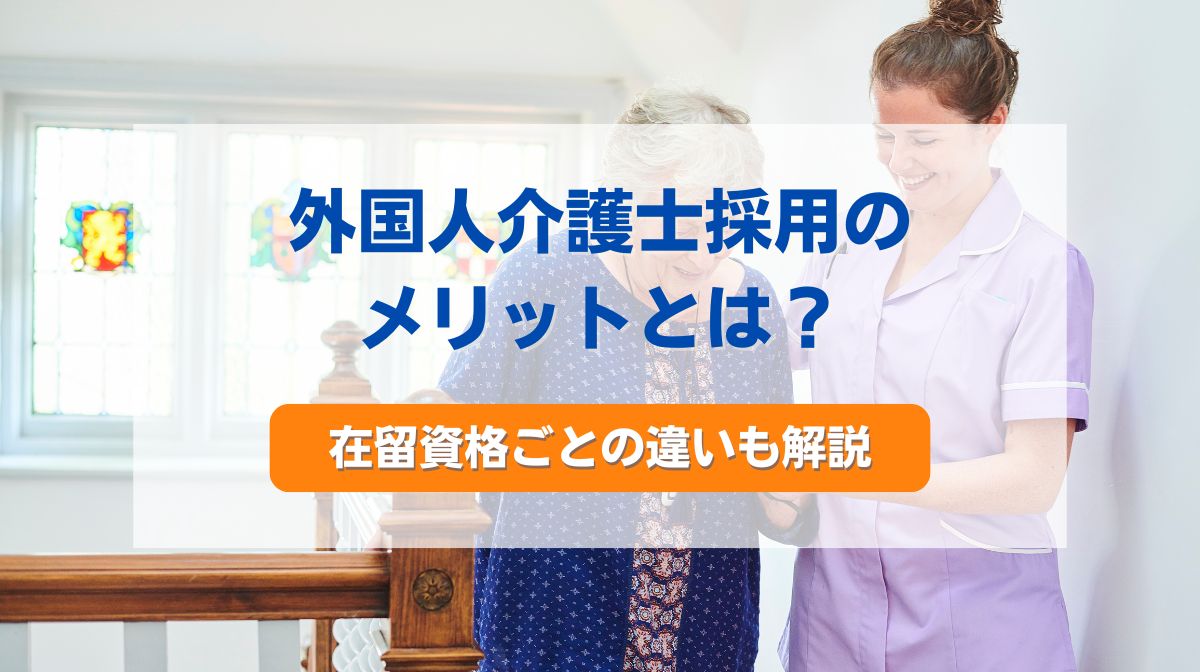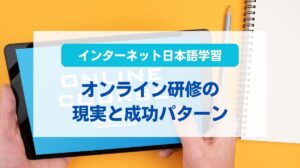日本の介護業界は、深刻な人材不足に直面しています。「募集をかけても人が集まらない」「職員の高齢化が進んでいる」といった悩みは、多くの介護事業所にとって喫緊の課題ではないでしょうか。
その打開策の一つとして、今あらためて注目されているのが外国人介護士の受け入れです。意欲あふれる若い人材が現場に加わることで、職場が活性化し、人手不足が緩和されるといった期待が高まっています。
しかしその一方で、「手続きが複雑そう」「文化や言葉の違いは大丈夫だろうか」「どの在留資格で受け入れるのが合っているのか分からない」といった不安や疑問を感じている採用担当者の方も多いかもしれません。
この記事では、外国人介護士を採用する際のメリットや注意点を解説します。さらに、複雑な在留資格制度を分かりやすく整理し、採用から定着支援までの具体的な流れもご紹介します。外国人材の受け入れを検討する第一歩として、ぜひ最後までご一読ください。
外国人介護士を採用する4つのメリット

外国人介護士の受け入れは、喫緊の課題である人手不足を解消するという直接的な側面だけでなく、長期的に見て事業所にとって多くの良い影響をもたらす可能性があります。ここでは、主な4つのメリットをより詳しくご紹介します。
1. 安定した人材の確保
最大のメリットは、やはり人材不足の緩和です。特に、日本の若年層の労働力確保が難しい中で、介護という仕事に強い目的意識と意欲を持つ海外の若者は、事業所にとって非常に貴重な存在です。
彼らの多くは、母国の家族への仕送りや、日本でのキャリア形成といった明確な目標を持って来日します。その高いモチベーションは、仕事への真摯な姿勢や定着率の向上につながる傾向があります。
人員を補充するだけでなく、計画的に採用活動を行うことで、数年先を見据えた安定的な人員体制の構築が可能になり、採用と教育を繰り返すコストの削減も期待できます。
2. 日本人職員の負担軽減
人員が充足することで、日本人職員一人当たりの業務量が減り、心身両面での負担軽減が期待できます。常に人手が足りない状況では、職員は日々の業務をこなすだけで精一杯になりがちです。
しかし、人員にゆとりが生まれれば、精神的なプレッシャーが和らぐだけでなく、有給休暇も取得しやすくなります。空いた時間を研修への参加や資格取得の勉強にあてるなど、個々のスキルアップのための機会も確保しやすくなるでしょう。
結果として、職場全体の労働環境が改善され、専門職としてのキャリアを継続しやすくなるため、日本人職員の定着にも良い影響を与えます。
3. サービスの質向上
サービスの質の向上も大いに期待できます。外国人スタッフは、利用者一人ひとりと心から向き合おうとします。最初は言葉の壁があるかもしれませんが、その分、豊かな表情や身振り手振り、そして何よりも優しい眼差しで、心を込めてコミュニケーションを取ろうと努力します。
そのひたむきな姿勢は、特に言葉での意思疎通が難しい利用者にも伝わり、大きな安心感を与えることがあります。また、多文化への理解が深まることで、職員全体が「利用者一人ひとりの背景は違う」という意識を強く持つようになり、より個別性を尊重した、きめ細やかなケアを提供する力が高まります。
4. 職場の活性化
異なる文化や価値観を持つ人材が職場に加わることで、組織に新しい風が吹き込まれ、良い意味での効果が生まれます。
例えば、日本人同士では当たり前になっていた業務手順やコミュニケーション方法に対して、外国人スタッフから素朴な疑問が投げかけられることがあります。それがきっかけとなり、業務改善や、より分かりやすい情報共有の方法を考えるなど、組織全体が活性化します。
また、日本人職員が海外の文化や習慣に直接触れることで視野が広がり、多様性を受け入れる土壌が育まれます。一生懸命に日本語や介護技術を学ぼうとする外国人スタッフの姿は、周りの職員にとっても「自分たちも頑張ろう」という良い刺激となるでしょう。
採用前に把握すべき4つの注意点と対策

多くのメリットがある一方で、外国人材の受け入れを成功させるには、事前に準備しておくべき点や注意すべき課題もあります。ここでは、代表的な4つの注意点と、その対策をより具体的に解説します。
1. 言葉の壁とコミュニケーション
最も大きな課題は、やはりコミュニケーションです。介護現場では、利用者の「いつもと少し違う」という体調を正確に把握したり、職員間で重要な情報を申し送ったりするために、繊細な言葉のニュアンスが求められる場面が少なくありません。
- 「やさしい日本語」の活用
-
これは、単に簡単な単語を使うことだけではありません。難しい専門用語を避け、一文を短く区切り、ゆっくり、はっきりと話すことを職場全体で意識します。また、イラストや図を指し示しながら視覚的に説明したり、指示を出した後に内容を復唱してもらったりするのも、認識のズレを防ぐための良い方法です。
- 継続的な学習支援
-
勤務時間内に日本語学習の時間を設けたり、日本語能力試験や介護福祉士試験の受験費用を補助したりするなど、本人の学習意欲を会社として具体的にサポートする姿勢が大切です。本人の努力だけに任せるのではなく、組織として成長を支える体制が、信頼関係の構築にもつながります。
2. 文化や生活習慣の違い
食事、宗教、時間に対する考え方、仕事への価値観など、育ってきた環境によって文化や習慣は大きく異なります。例えば、日本ではチームワークや協調性が重んじられますが、国によっては個人の役割が明確に分かれていることを好む文化もあります。こうした違いへの無理解が、職員間の思わぬ摩擦や、本人への過度なストレスにつながることがあります。
- 異文化研修の実施
-
外国人スタッフに日本のルールを教えるだけでなく、受け入れる日本人職員も対象に、彼らの国の文化や宗教、国民性などを学び合う研修会を定期的に開くことが望ましいです。相互理解は、一方的な適応の要求ではなく、双方向の歩み寄りから生まれます。
- 相談しやすい環境づくり
-
本人が困ったときに、仕事のことだけでなく、日本の生活での不安や悩みを気軽に相談できる担当者(メンター)を定めておくと、孤立を防ぎやすくなります。定期的に面談の機会を設け、「何か困ったことはない?」と積極的に声をかけることが重要です。
3. 手続きの複雑さと管理
外国人材を雇用するには、在留資格認定証明書の取得、在留資格の更新、各種届出など、出入国在留管理庁への複雑な手続きが伴います。これらの手続きには専門的な知識が必要で、書類の準備も多岐にわたります。もし手続きに不備があれば、本人が日本で働き続けることができなくなるという重大な事態にもなりかねません。
- 専門家の活用
-
行政書士や登録支援機関など、専門的な知識を持つ外部の専門家や機関に手続きを依頼することで、担当者の負担を大幅に軽減でき、法令遵守の観点からも安心です。専門家に任せることで、社内の担当者は本来の業務や外国人スタッフのサポートに集中できます。
- 管理体制の構築
-
誰が、いつまでに、どの手続きを行うのかを明確にし、各スタッフの在留カードの期限などを一覧表で管理する仕組みを社内で作っておくことが重要です。担当者一人だけに任せるのではなく、複数人でチェックする体制を整えることで、更新忘れなどのミスを防ぎます。
4. 受け入れ体制の構築と教育
外国人スタッフが安心して働き、その能力を最大限に発揮するためには、事業所側の受け入れ体制が整っていることが大前提となります。「人手が足りないから来てもらう」という考え方だけでは、早期離職につながりかねません。
- 教育プログラムの整備
-
日本の介護の基本的な考え方(自立支援など)や、認知症ケアの理念、具体的な介護技術などを体系的に学べる研修プログラムを用意します。OJT(現場研修)では、指導担当者を一人決め、マンツーマンで丁寧に業務を教える体制が望ましいです。指導者によって言うことが違う、という状況は本人を混乱させます。
- 生活面のサポート
-
住居の確保や賃貸契約の連帯保証、銀行口座の開設、携帯電話の契約といった初期の生活基盤の整備はもちろん、ゴミの分別方法や公共交通機関の乗り方、病気になった際の病院のかかり方など、日本で生活する上での細かなルールや習慣についても情報提供を行うことが、本人の不安を和らげる上で非常に重要な役割を果たします。
外国人介護士を受け入れる4つの在留資格

外国人介護士を受け入れるための在留資格は、主に4種類あります。それぞれの制度で目的や要件が異なるため、自社の目的や状況に合った制度を選ぶことが大切です。
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 | 在留資格「介護」 | EPA(経済連携協定) |
|---|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足の分野での人材確保 | 日本の技能の移転による国際貢献 | 専門職としての就労 | 二国間の経済連携強化 |
| 在留期間 | 通算で最長5年 (1号) | 最長5年 | 更新の上限なし | 4年間 (その後「介護」へ移行可) |
| 日本語能力の要件 | N4程度+介護日本語評価試験 | N4程度 (入国時要件) | N2程度 (介護福祉士養成校卒業) | N3程度 (候補者による) |
| 介護福祉士資格の要否 | 不要 | 不要 | 必要 | 最終的に取得を目指す |
| 家族の帯同 | 不可(1号) | 不可 | 可能 | 不可 |
特定技能:即戦力としての活躍が期待される
「特定技能」は、深刻な人手不足に対応するため創設された在留資格です。一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
介護分野では、日本語能力と介護技能の両方の試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで資格を得られます。事業者にとっては、比較的スピーディーに現場で活躍できる人材を確保できるのが大きな特徴です。
技能実習:国際貢献を目的とした人材育成
「技能実習」は、日本の技術や知識を母国に持ち帰ってもらう「国際貢献」を目的とした制度です。受け入れ企業は、実習計画に基づいて技能の指導を行います。
特定技能と異なり、あくまで「実習」という位置づけですが、実習2号を良好に修了すれば、「特定技能1号」へ移行することが可能です。人材育成に時間をかけられる場合に適した制度といえるでしょう。
在留資格「介護」:介護福祉士資格を持つ専門人材
国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人が対象となる在留資格です。専門知識と技術を体系的に学んでいるため、非常に質の高い人材といえます。
在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能なため、長期的に日本でキャリアを築きたいと考える人が多く、事業所の中核を担う人材としての活躍が期待できます。
EPA(経済連携協定):二国間協定に基づく受け入れ
日本がインドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で結んでいる経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士候補者を受け入れる制度です。
候補者は、日本の施設で働きながら研修を受け、介護福祉士の国家資格取得を目指します。国家資格に合格すれば、在留資格「介護」へ移行し、日本で働き続けることが可能です。

採用から就労開始までの5ステップ
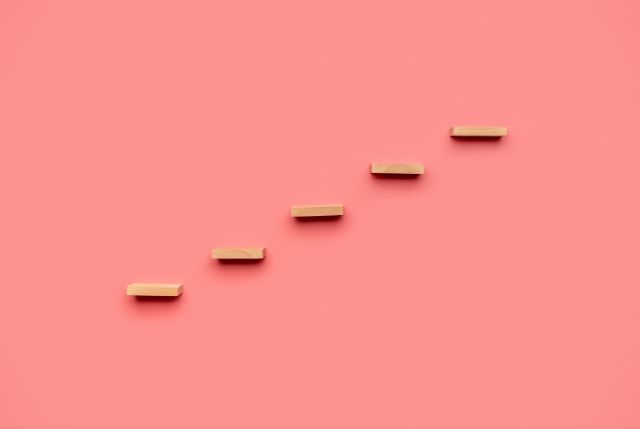
実際に外国人介護士を受け入れるには、どのような流れで進めるのでしょうか。ここでは、採用決定から就労開始までの基本的な流れを5つのステップで解説します。
受け入れ計画の策定 最初に、どのような人材を、何名、どの部署で受け入れるのか、社内の計画を明確にします。求める日本語レベルやスキル、そしてどの在留資格で受け入れるかを決定し、サポート体制についても具体的に検討します。
候補者の募集・選考 海外の送り出し機関や、国内の人材紹介会社を通じて候補者を募集します。書類選考の後、オンラインなどで面接を行い、候補者の人柄や仕事への意欲、日本語でのコミュニケーション能力などを確認します。
在留資格関連の申請手続き 採用する人材が決定したら、日本の地方出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。事業所の規模や受け入れる在留資格の種類によって、必要な書類が異なります。
入国準備と生活環境の整備 証明書が交付されたら、本人に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けます。並行して、企業側は住居の確保やライフラインの契約など、本人が来日後すぐに生活を始められるよう準備を進めます。
就労開始と定着に向けた支援 来日後、役所での住民登録や銀行口座の開設などの手続きをサポートします。その後、就労を開始し、作成した教育計画に基づいて研修やOJTを進めていきます。就労開始後も、定期的な面談を行うなど、継続的なサポートが不可欠です。
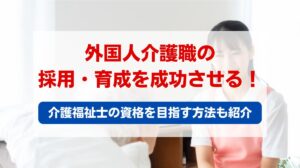
スタッフの定着と活躍を促すための支援

外国人材の受け入れは、採用したら終わりではありません。むしろ、入社後、いかに日本での仕事と生活に慣れ、能力を発揮してもらうかが最も重要です。定着と活躍を促すための支援は、「仕事」「生活」「精神」の3つの面から考えると分かりやすいでしょう。
- 仕事面のサポート
-
明確なキャリアパスを示すことは、本人のモチベーション維持に大きく寄与します。例えば、「3年後には介護福祉士の資格取得を目指そう」「将来的にはリーダーとして活躍してほしい」といった具体的な目標を共有し、そのための研修や学習支援を会社として行う姿勢が大切です。
- 生活面のサポート
-
ゴミ出しのルール、公共交通機関の利用方法、病気になった際の病院のかかり方など、日本人にとっては当たり前のことでも、外国人にとっては分からないことばかりです。こうした生活上の細かな不安を解消するための相談窓口を設けたり、マニュアルを作成したりするなどの配慮が求められます。
- 精神面のサポート
-
異国の地で一人働くことは、想像以上に孤独やストレスを感じやすいものです。同じ国の出身者との交流会を開いたり、日本人職員との懇親会を企画したりして、本人が孤立しないようなコミュニティづくりを支援することも、事業所の重要な役割です。
「介護福祉士」の資格取得による長期雇用への道

「特定技能1号」の在留期間は通算で最長5年と定められていますが、介護分野で経験を積んだ優秀な人材に、その後も長く活躍してもらうための道が用意されています。それが、国家資格である「介護福祉士」を取得し、在留資格を「介護」へ変更する方法です。
在留資格「介護」とは
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設などで専門職として働くための資格です。この資格を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たし続ける限り日本で働き続けることが可能になります。
事業者にとっては、現場を熟知し、技能を習得した貴重な人材に、定年まで中核スタッフとして長く活躍してもらえるという大きなメリットがあります。
資格取得に向けた企業の役割
特定技能1号として働きながら介護福祉士の国家試験に合格するには、実務経験に加えて専門的な学習が不可欠です。本人にとって簡単な挑戦ではないため、企業側のサポートが重要になります。
資格取得に向けた学習時間の確保や、受験費用の補助、学習教材の提供など、企業が積極的に支援することで、本人の学習意欲は高まります。スタッフのキャリアアップを会社全体で応援する文化を醸成することが、結果として優秀な人材の長期確保につながり、企業の成長を支える力となります。
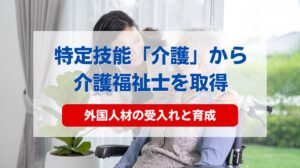
日本語教育と資格取得、オンライン講座で一挙に解決しませんか?

外国人スタッフの長期定着の鍵が、国家資格である「介護福祉士」の取得にあることは、多くの事業所様が認識されていることでしょう。しかし、日々の業務と並行して難関試験の勉強を進めるのは、本人にとって大きな負担です。
特に、「専門用語が多くてテキストが理解できない」「試験問題の日本語が難しい」といった言葉の壁は、本人の意欲を削いでしまう大きな原因となります。また、事業者様にとっても、現場で働きながら一人ひとりの日本語レベルや学習進捗を管理し、適切な教育を行うのは簡単なことではありません。
もし、スタッフのキャリアアップ支援と、事業所全体の日本語教育の課題を、もっと効率的に、かつコストを抑えて解決したいとお考えなら、「日本語カフェ」のオンライン講座がそのお悩みを解決します。
4ヶ月で合格へ導く「介護福祉士 受験対策講座」
仕事と勉強の両立が難しく、日本語にも不安を抱える外国人スタッフのために、4ヶ月で介護福祉士合格を目指せるオンライン集中講座をご用意しました。
介護福祉士の専門講師が、合格に必要なポイントを動画と演習問題で分かりやすく解説。豊富な過去問演習を通して、本番の試験で確実に得点できる力を養います。「これさえやれば合格できる」というカリキュラムで、貴社のスタッフが挫折することなく、合格までの最短ルートを歩めるよう徹底的にサポートします。
講座期間中は「JLPTコース」も使い放題!
さらに、この介護福祉士対策講座の大きな特徴は、講座期間中、日本語能力試験(N5〜N1)に対応した「JLPTコース」が使い放題になる点です。
介護福祉士を目指すスタッフの日本語力を底上げするのはもちろん、新しく採用したスタッフの基礎的な日本語教育(N4合格など)まで、事業所全体の日本語学習をトータルでサポートできます。
「日本語カフェ」のJLPTコースは、プロ講師が監修した高品質な動画カリキュラムと豊富な演習ドリルが特徴です。スマホ一台あれば、いつでもどこでも学習可能。スタッフ一人ひとりの学習状況は管理画面で簡単に把握できるため、教育担当者様の管理負担を大幅に削減し、「スタッフが自発的に学習を進めてくれる環境」を構築します。
専門職としてのキャリアアップ(介護福祉士)と、日々の円滑なコミュニケーション(JLPT)の両方を、「日本語カフェ」がワンストップで支えます。
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!

■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
スタッフの成長と定着のために、まずはオンライン講座の詳しい内容について、お気軽にお問い合わせください。
\お問い合わせはこちらから/
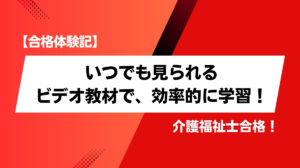
外国人材と共に、未来を築くために

本記事では、外国人介護士の採用がもたらす様々な側面について、メリットから具体的な手続き、そして長期的な定着支援の方法まで詳しく解説してきました。
外国人材の受け入れは、人手不足という喫緊の課題への対応策であると同時に、多様な価値観を取り入れることで、事業所の文化やサービスの質そのものを向上させる大きな機会でもあります。
もちろん、言葉や文化の壁、複雑な行政手続きといった乗り越えるべきハードルも存在します。しかし、それらの課題一つひとつに対して、事前の計画的な準備と、受け入れ後の丁寧なサポート体制を構築することで、着実に乗り越えていくことが可能です。
採用して終わりではなく、スタッフ一人ひとりのキャリア形成に寄り添い、介護福祉士資格の取得といった成長を後押しする仕組みを整えること。その姿勢こそが、定着を促し、事業所にとってかけがえのない財産となる人材を育てるのです。
多様性を受け入れ、国籍を問わず誰もが働きがいを感じられる職場環境を築くことは、これからの時代に利用者や地域から「選ばれる施設」となるための重要な一歩です。この記事が、皆様の事業所にとって、その新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
\お問い合わせはこちらから/