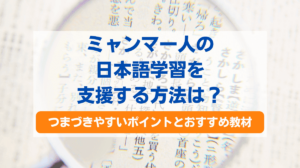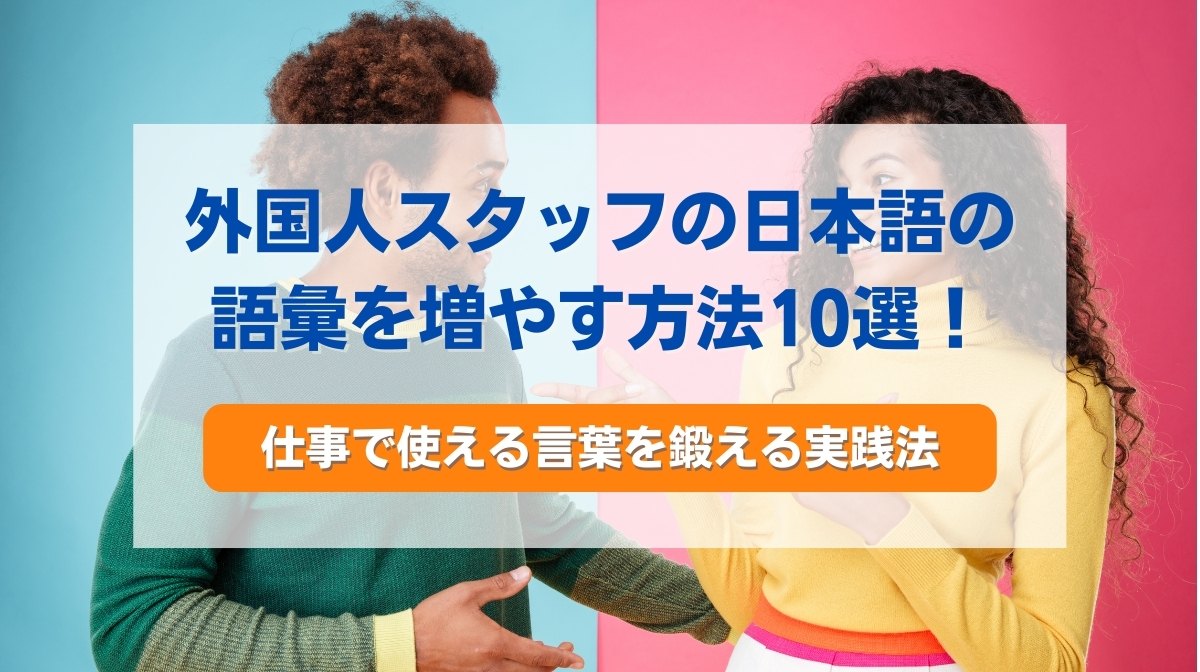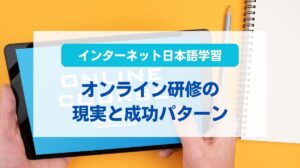「新しく採用した外国人スタッフとのコミュニケーションで、時折言葉の壁を感じる…」 「指示した内容が、思っていたニュアンスで伝わっていないことがある」 「メールの文章を読むのに時間がかかっているようで、業務効率が上がらない」
外国人材と共に働く企業の経営者や教育担当者の方であれば、一度はこのような悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。業務への意欲も能力も高いスタッフが、言葉の壁、特に「語彙力」が原因で本来のパフォーマンスを発揮しきれないのは、会社にとっても本人にとっても非常にもったいない状況です。
この記事では、外国人スタッフの日本語の語彙がなぜ増えにくいのかという根本的な原因を解き明かし、明日から現場で実践できる具体的な学習方法を詳しくご紹介します。
外国人スタッフの日本語の語彙が増えにくい3つの原因

効果的な対策を講じるためには、まず「なぜ語彙が増えにくいのか」という原因を正しく理解することが大切です。多くの外国人スタッフが直面する壁は、大きく分けて3つあります。自社のスタッフがどのケースに当てはまるか、イメージしながら読み進めてみてください。
原因1:インプットの量と質が偏っている
一つ目の原因は、新しい言葉に触れる機会、つまりインプットの量と質に課題があるケースです。来日してしばらく経つと、日常生活や特定の業務で使う言葉はある程度固まってきます。同僚との会話も、いつも同じような内容になりがちです。そうなると、本人が意識的に学ぼうとしない限り、新しい語彙に触れる機会は自然と減ってしまいます。
また、真面目な方ほど単語帳やアプリを使ってたくさんの言葉を覚えようとしますが、それだけでは「使える語彙」にはなりません。なぜなら、単語学習は、日本語と母国語を1対1で暗記する方法に偏りがちだからです。
しかし、言葉には文脈によって微妙なニュアンスの違いがあります。例えば「考える」と「思う」の違いを単語だけで理解するのは非常に難しいでしょう。
このように、言葉が実際にどのような場面で、どんなイメージで使われるのかを知らないままインプットを続けても、語彙はなかなか増えていかないのです。
原因2:覚えた言葉を「使える」機会が少ない
二つ目の原因は、覚えた知識を実践で使うアウトプットの機会が不足していることです。単語を「知っている」状態と、会話や文章で自在に「使える」状態の間には、大きな隔たりがあります。多くの学習者はインプットに時間をかけますが、それを使う練習を十分にできていません。
特に、職場という環境はアウトプットのハードルを上げてしまうことがあります。「間違った使い方をしてしまったらどうしよう」「相手にうまく伝わらなかったら恥ずかしい」という気持ちから、新しく覚えた言葉を使うことに躊躇してしまうのです。
結果として、いつも使い慣れた簡単な表現ばかりを選んでしまい、語彙力が鍛えられる機会を逃してしまいます。会社側が安心してアウトプットできる環境を提供できていない場合、この傾向はさらに強くなるでしょう。
原因3:学習が習慣化できず、記憶が定着しない
三つ目の原因は、学習の継続、つまり習慣化の難しさです。慣れない環境での仕事は、私たちが想像する以上に心身のエネルギーを使います。一日の業務を終えて疲れている中で、毎日日本語の勉強時間を確保するのは、強い意志がなければ非常に困難です。
また、一人での学習はモチベーションの維持が難しいという側面もあります。自分の成長が実感できなかったり、わからないことがあってもすぐに誰かに聞ける環境がなかったりすると、次第に勉強から足が遠のいてしまいます。
せっかく覚えた言葉も、定期的に復習し、実践で使わなければ、すぐに記憶から消えていってしまいます。学習が習慣化できないことは、語彙が増えない直接的な原因となるのです。
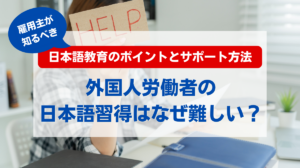
【インプット編】語彙の量を増やす効果的な方法5選

原因がわかったところで、ここからは語彙力を高めるための具体的な方法をご紹介します。まずは、言葉の引き出しを増やす「インプット編」です。ただ暗記するのではなく、「質」を意識した方法をぜひ試してみてください。
方法1:文脈の中で言葉の意味をイメージする
単語とその意味を1対1で覚える作業から一歩進んで、言葉が実際に使われている「文脈」の中で意味を捉える習慣をつけましょう。
最も効果的な方法のひとつが読書です。いきなり難しい本を読む必要はありません。子供向けの簡単なニュース記事や、本人の趣味に関するウェブサイトの記事、易しいビジネス書など、興味を持って読めるものから始めるのがポイントです。
文章の中で言葉に触れると、「ああ、この表現はこんなときに使うのか」「こんな言葉と一緒に使われることが多いんだな」という具体的なイメージが湧きます。それこそが「使える語彙」のもとになります。
わからない言葉が出てきてもすぐに調べるだけでなく、「この文脈だと、どんな意味になるだろう?」と一度推測してみる癖をつけると、思考力が鍛えられ、記憶にも残りやすくなります。
方法2:類義語・対義語・関連語をセットで覚える
一つの言葉を覚えるときに、それに関連する言葉を芋づる式に覚えていくと、語彙のネットワークが一気に広がります。これは記憶の定着にも非常に効果的です。
例えば、「重要」という言葉を覚えたら、それだけで終わらせずに、以下のように広げていきます。
| 元になる言葉 | 類義語 (似た意味) | 対義語 (反対の意味) | 関連語 |
|---|---|---|---|
| 重要(な) | 大事(な) 大切(な) 肝心(な) | 些細(な) 軽微(な) | 重要性 重視する |
| 増やす | 増加させる 拡大する | 減らす 縮小する | 増減 増える |
| 難しい | 困難(な) 複雑(な) 厄介(な) | 簡単(な) 容易(な) | 難易度 難問 |
このように、言葉を点で覚えるのではなく、関連する言葉とセットで線や面として捉えることで、表現の幅が格段に豊かになります。相手や状況に応じて言葉を使い分ける力は、円滑なコミュニケーションに不可欠です。
方法3:「耳」からインプットする習慣をつける
私たちは母国語を覚えるとき、まず親や周りの人の話す言葉をたくさん聞いて覚えます。日本語学習においても、「耳」からのインプットは非常に重要です。文字情報だけでなく、音声情報とセットで言葉をインプットすることで、正しい発音やイントネーション、言葉が話されるスピード感も自然に身につきます。
おすすめなのは、通勤時間や休憩時間などの「スキマ時間」を活用することです。日本語のニュース、ポッドキャスト、オーディオブックなどをBGMのように聞き流すだけでも効果があります。
最初は内容がすべて分からなくても構いません。日本語の音のリズムに耳を慣らすことが第一歩です。慣れてきたら、スクリプト(台本)を見ながら聞いたり、シャドーイング(音声に少し遅れて影のようについていく練習)に挑戦したりすると、リスニング力とスピーキング力が同時に鍛えられます。
方法4:自分の興味・関心がある分野から言葉を増やす
学習を継続させる最大の秘訣は「楽しむこと」です。仕事に必要な言葉を覚えるのはもちろん大切ですが、そればかりでは勉強が苦痛になってしまいます。ぜひ、本人が好きなこと、興味がある分野を語彙力アップに活用してください。
例えば、アニメが好きなら、好きな作品のセリフを真似してみる。J-POPが好きなら、歌詞を読んで意味を調べてみる。サッカーが好きなら、日本のサッカーニュースを読んでみる。このように、自分の「好き」という気持ちは、新しい言葉を吸収するための強力なエンジンになります。
趣味を通じて覚えた言葉は忘れにくく、日本人スタッフとの雑談のきっかけにもなり、コミュニケーションの輪を広げる助けにもなるでしょう。
方法5:言い換え表現を意識する
日本語の豊かさの一つに、同じ意味でもさまざまな言い回しができる点が挙げられます。一つの事柄を別の言葉で説明する「言い換え」を意識することで、語彙力は飛躍的に向上します。
例えば、会議で「問題があります」と言うだけでなく、「課題が残っています」「懸念事項が一つあります」「改善すべき点が見つかりました」など、状況に応じて表現を変えられれば、より正確で丁寧なコミュニケーションが可能になります。
日頃から、メールや資料で使われている言葉に対して、「これを別の言葉で言うとどうなるだろう?」と考える癖をつけるよう促してみてください。多様な表現を知ることは、相手の言うことの微妙なニュアンスを理解する力にも繋がります。

【アウトプット編】覚えた語彙を「使える言葉」にする実践術3選
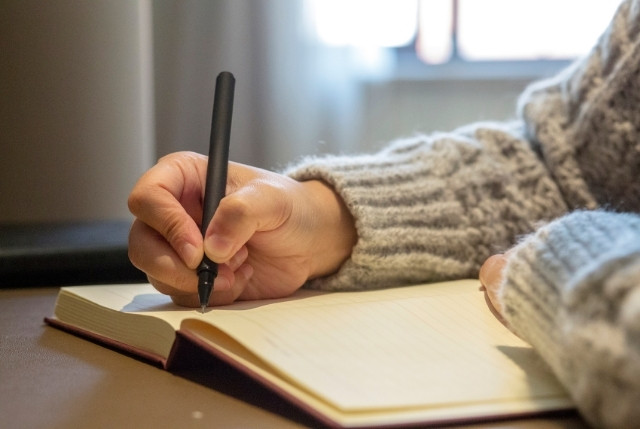
インプットで知識を蓄えたら、次はそれを「使えるスキル」に変えるアウトプットの段階です。ここでは、会社で実践できる具体的なトレーニング方法をご紹介します。
方法6:短い文章でいいので毎日「書く」
覚えた言葉を定着させる最も確実な方法の一つが「書く」ことです。頭の中にある曖昧な知識も、文字にすることで整理され、記憶に深く刻まれます。
業務日報や週報を日本語で書く習慣を取り入れるのは非常に良い方法です。その日の業務内容を報告するだけでなく、「今日新しく覚えた言葉」や「使ってみて難しかった表現」などを一言添える欄を設けるのも良いでしょう。
担当者がそれに目を通し、「この使い方、自然でいいね!」「ここは、こう言うともっと良くなるよ」と簡単なフィードバックを返すだけで、本人のモチベーションは大きく向上します。プライベートな日記やSNSへの短い投稿でも構いません。毎日少しずつでも書く習慣をつけることが大切です。
方法7:意識的に新しい言葉を使って「話す」
インプットした言葉は、意識して使わなければ、いつまでも「知っているだけ」の宝の持ち腐れになってしまいます。会話の中で積極的に新しい言葉を使ってみるチャレンジを促しましょう。
ここで重要になるのが、会社全体の雰囲気作りです。外国人スタッフが多少間違った日本語を使っても、それを笑ったり指摘したりするのではなく、「新しい言葉に挑戦していて素晴らしいね」と温かく受け止める文化を醸成することが大切です。
例えば、朝礼の短いスピーチや、チームミーティングの中で、意識的に新しい言葉を一つ使うといった小さな目標を設定するのも効果的です。アウトプットの機会を意図的に作り、成功体験を積ませてあげることが、自信を持って話す力に繋がります。
方法8:わからない言葉を放置しない「調べる」習慣
会話や会議、メールの中などで知らない言葉や表現に出会ったとき、それをそのまま放置しないことが語彙力アップのポイントです。その場ですぐに意味を調べる習慣を徹底しましょう。
スマートフォンに辞書アプリを入れておき、気になったらすぐに調べる。あるいは、手帳やメモ帳に書き出しておき、後でまとめて調べる。どちらの方法でも構いません。会社としては、スタッフが「すみません、今おっしゃった〇〇という言葉の意味を教えていただけますか?」と気軽に質問できる雰囲気を作ることが大切です。
「知らないことを聞くのは恥ずかしいことではない」というメッセージを伝え、知的好奇心をサポートする姿勢を見せましょう。調べた言葉は、自分だけのオリジナル単語帳にまとめていくと、後で見返したときに大きな財産になります。
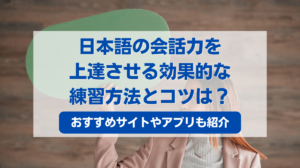
【企業サポート編】仕事で使える語彙力を鍛える2つのポイント

スタッフ個人の努力だけに頼るのではなく、会社として学習をサポートする仕組みを整えることで、語彙力アップの効果とスピードは格段に上がります。
方法9:業務マニュアルや社内用語集を整備する
特に専門的な用語が多い業界や職種の場合、会社独自の「用語集」を作成することを強くおすすめします。仕事で頻繁に使う言葉や、社内だけで使われる特殊な言い回しなどをリストアップし、それぞれの意味や使い方、可能であれば英語などの対訳も添えておくと非常に親切です。
これは、新しく入社した外国人スタッフにとって、業務を覚える上での強力なガイドになります。また、教育内容を標準化できるため、教える側の負担が減り、誰が教えても一定の品質を担保できるというメリットもあります。
一度作成してしまえば、今後入社する全てのスタッフに活用できるため、長期的に見れば教育コストの削減にも繋がる、非常に価値のある投資です。
方法10:定期的な1on1で言語学習の進捗を確認し、実践の場を設ける
上司や教育担当者が、定期的に1on1ミーティングの時間を設けることも非常に有効です。業務の進捗確認だけでなく、その時間の一部を日本語学習に関する対話に使いましょう。
「最近、何か新しく覚えた言葉はある?」「仕事で言葉に困っていることはない?」といった質問を通じて、本人が何に悩み、どこでつまずいているのかを把握します。そして、そのミーティング自体を、安心して日本語を話せる実践の場として活用しましょう。
例えば、最近の業務について説明してもらったり、簡単なロールプレイングを行ったりするのも良いでしょう。大切なのは、評価するのではなく、本人の学習に寄り添い、サポートするという姿勢です。このような定期的な関わりが、学習のモチベーションを維持する上で大きな支えとなります。
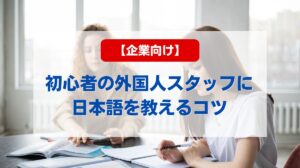
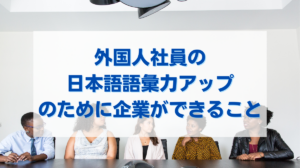
企業の日本語教育を効率化!プロに任せるという選択肢
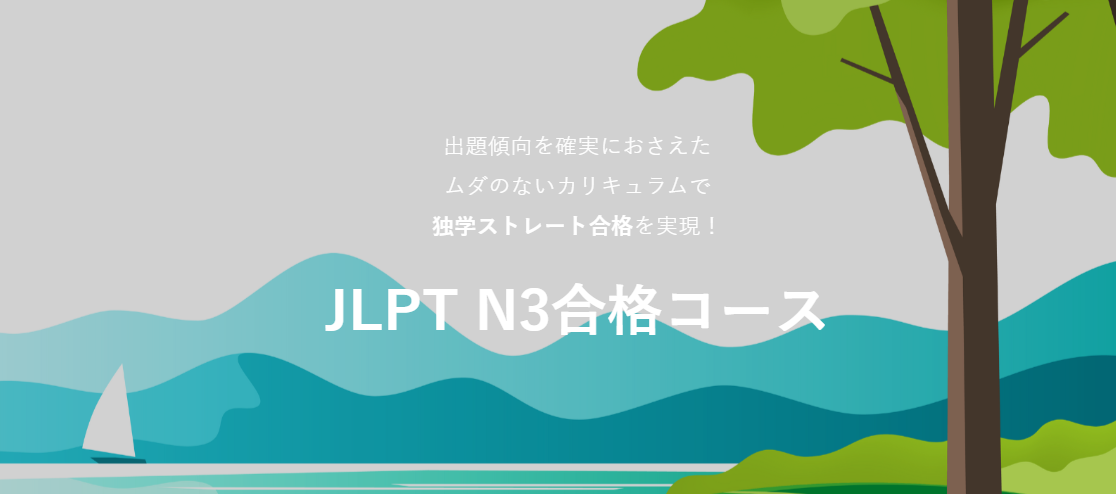
ここまで、社内で実践できる様々な方法をご紹介してきました。しかし、多くの担当者の方がこう思われたかもしれません。
「理想はわかるが、日々の業務に追われ、ここまで手厚く教育する時間もノウハウもない…」
そのお気持ちは非常によくわかります。社内での教育には限界があり、担当者の負担が大きくなりすぎてしまうのが現実です。自己流の教育では、どうしても学習効果にムラが出てしまい、スタッフの成長スピードも思うように上がらないかもしれません。
体系的な学習なら「日本語カフェ」のJLPT合格コースがおすすめ
「日本語カフェ」のJLPT合格コースは、まさに企業の悩みを解決するために設計されたオンライン講座です。実際に、全くの初心者からスタートしてわずか2ヶ月で日本語能力試験(JLPT)N4に合格したり、3ヶ月でビジネス会話の基礎となるN3レベルに合格したりといった、驚くべき実績が多数報告されています。
- 管理・コストの大幅削減
-
日本人講師の採用や管理にかかる手間や、毎月の高額な人件費はもう必要ありません。スタッフの学習状況は専用の管理画面で一目で把握できるため、管理工数を劇的に削減できます。
- 自発的な学習の促進
-
一流の日本語教師が監修した、合格に特化した動画カリキュラムが使い放題。「何を、どの順番で学べばいいか」が明確なので、スタッフが自発的に学習を進めてくれます。
- 最短ルートで合格を目指せる
-
レベル別(N5〜N1対応)に語彙・文法・読解・聴解のバランスが最適化されており、迷うことなく効果的に学習を進められます。
- 「わかる」が「使える」に変わる
-
プロ講師による分かりやすい動画講義に加え、豊富な演習ドリルでアウトプット練習も万全。インプットと実践を繰り返すことで、使える日本語が身につきます。
- 忙しくても続けられる
-
スマートフォンやPCさえあれば、いつでもどこでも学習可能。1回10分からのスキマ学習に対応しており、忙しい仕事の合間でも無理なく続けられます。
社内教育の負担を減らし、スタッフには質の高い学習環境を提供する 「日本語カフェ」は、企業とスタッフ双方にとってメリットの大きい、日本語教育の新しいスタンダードです。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
まずはお気軽に、貴社の状況に合わせた活用プランをご相談ください。
\ ご相談はこちらから/
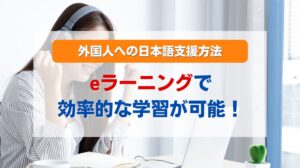
まとめ

今回は、外国人スタッフの日本語の語彙を増やすための具体的な方法について、原因の分析からインプット、アウトプット、そして企業のサポート体制まで、幅広く解説しました。
重要なポイントを改めて整理します。
- 語彙が増えない原因は「インプットの偏り」「アウトプット不足」「学習が習慣化できない」ことにある。
- インプットでは、文脈や関連語を意識し、耳や自分の興味を活用して「質」を高めることが大切。
- アウトプットでは、書く・話すといった実践の機会を意識的に作り、間違いを恐れない環境が重要。
- そして何より、これらを継続するための「習慣化」の仕組みが不可欠である。
外国人材は、これからの日本企業にとってなくてはならない大切なパートナーです。彼らが言葉の壁を乗り越え、能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、企業の成長に直結する重要な投資と言えるでしょう。
個人の努力と社内のサポート、そして時には「日本語カフェ」のような専門家の力を借りながら、スタッフ一人ひとりの成長を力強く後押ししていきましょう。この記事が、その一助となれば幸いです。
\ お問い合わせはこちらから/