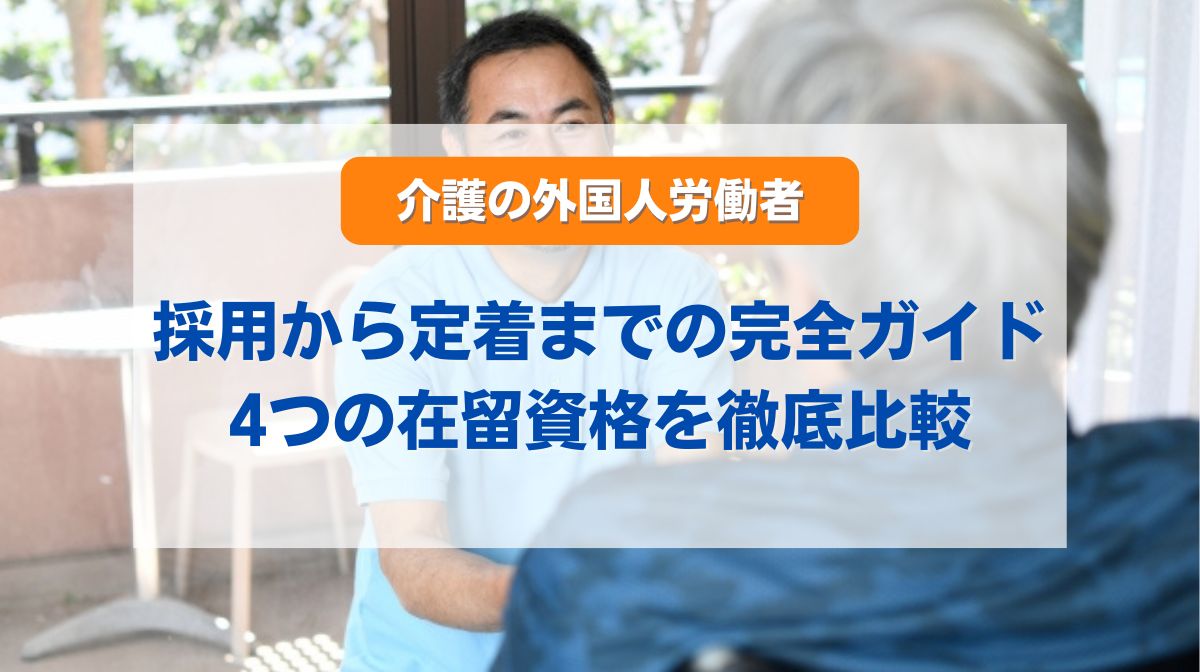介護の現場では、人手不足が深刻な問題になっています。その解決策の一つとして、近年は外国人材の採用が注目されています。ただし、一口に外国人材の受け入れといっても、「特定技能」や「技能実習」など、在留資格の制度はいくつもあり、その内容はとても複雑です。
「自分の事業所にはどの制度が向いているのか」「採用手続きはどう進めればいいのか」「採用した外国人が長く働き続けるには、どんなサポートが必要なのか」こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。
この記事では、介護の仕事で外国人材の採用を考えている方や、すでに採用を始めている事業所の方に向けて、知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
外国人介護士の受け入れで押さえるべき3つの視点

外国人介護士の受け入れをスムーズに進め、お互いにとって良い関係を築くためには、いくつかの重要な視点があります。
特に大切なのは、数ある受け入れ制度から自社に合ったものを選ぶこと、採用後も安心して働き続けられる環境を整えること、そして日本語能力の向上を継続的に支援することです。
以下の3つの視点を意識することで、受け入れがより円滑になり、定着率やサービスの質の向上につながります。
1. 自社に合った在留資格を見極める
介護分野で外国人材を受け入れる場合、主に「特定技能」「技能実習」「EPA(経済連携協定)」「在留資格『介護』」の4つの制度があります。それぞれの制度には、創設の目的、受け入れ条件、在留期間、従事できる業務範囲などに大きな違いがあります。
例えば、ある程度日本語や介護スキルを持つ人材を即戦力として採用したい場合は「特定技能」が向いています。 一方で、未経験者を育成し、日本の介護技術を母国に持ち帰ってもらうことを目的とする場合は「技能実習」が適しています。
選択を誤ると、事業所の方針や人員計画と合わず、定着につながらない可能性があります。そのため、それぞれの特徴や事業所側の負担、必要なサポート内容を正確に理解し、自施設の理念や将来計画に合った制度を選ぶことが重要です。
2. 安心して長く働ける支援体制を整える
採用活動を終え、外国人職員が来日・就労を開始した段階は、ゴールではなくスタートです。慣れない日本での生活や職場環境に不安を抱える職員も多く、放置すれば離職につながる恐れがあります。
事業所は、介護業務の指導はもちろん、生活面のサポートも行う必要があります。具体的には、住居の確保、銀行口座の開設、公共交通の利用方法、地域のルールなど日常生活の案内が挙げられます。
また、日本人職員とのコミュニケーションを円滑にするための橋渡しも欠かせません。文化や価値観の違いから生まれる誤解を防ぎ、お互いを尊重できる職場環境をつくることで、離職防止と定着率向上が期待できます。
3. 継続的な日本語学習の機会を提供する
介護の現場では、利用者とのコミュニケーション、職員同士の情報共有、介護記録の作成など、日本語を使う場面が非常に多くあります。そのため、日本語能力の向上は業務の質を高めるだけでなく、外国人職員が日本で安心して生活し、自信を持って仕事に取り組むための基盤となります。
さらに、介護福祉士などの国家資格取得を目指す場合、試験問題を理解できる日本語力が必須です。しかし、日々の業務に追われる中で施設が独自に質の高い日本語教育を続けるのは難しいこともあります。
そこで、外部の日本語教育サービスやオンライン講座を活用するのがおすすめです。これにより、時間やコストの負担を減らしながら、効率的かつ継続的に学習の機会を提供できます。結果として、職員本人の成長と事業所の安定運営の両方に良い影響をもたらします。
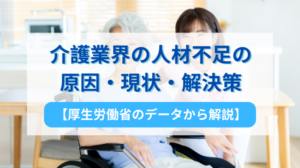
どの制度で受け入れる?4つの在留資格を一覧で比較

外国人介護士を受け入れるためには、まず国が定める在留資格制度を正しく理解することが必要です。制度の内容を知らないまま進めると、採用後に想定外の制約や手続きの負担が生じる可能性があります。
現在、介護分野で外国人材を受け入れる際に利用できる主な在留資格は以下の4種類です。
この4つの制度は、受け入れの目的、対象となる人材、従事できる業務範囲、日本での滞在期間などが大きく異なります。例えば、特定技能は一定の日本語能力や介護スキルを持つ人材を対象とし、即戦力を求める場合に適しています。 一方、技能実習は国際貢献や人材育成を目的としており、未経験者を育てることを前提とした制度です。
また、EPAは政府間の協定に基づき来日する人材で、来日前に日本語や介護の研修を受けていることが多く、資格取得を目指す人も少なくありません。在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が対象で、長期的な就労が可能です。
どの制度を選ぶかは、自施設の人材育成方針や求めるスキルレベルによって異なります。即戦力を求めるのか、長期的な人材育成を重視するのかによって、最適な制度は変わります。
メリットや注意点を正しく把握し、自施設の状況や理念に合った制度を選択することが、円滑な受け入れと定着につながります。
【比較表】特定技能・技能実習・EPA・在留資格「介護」の違い
4つの在留資格の主な違いを以下の表に整理しました。各項目を比較し、自社の人材計画にどの制度が最も合致するか検討するための参考にしてください。
| 特定技能 「介護」 | 技能実習 「介護」 | EPA (経済連携協定) | 在留資格 「介護」 | |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 人手不足分野での人材確保 | 日本の技能の移転による国際貢献 | 経済連携の強化、将来の介護福祉士候補者の育成 | 介護福祉士としての専門業務への従事 |
| 在留期間 | 通算で最長5年 | 最長5年 (1号・2号) | 最長4年 (介護福祉士合格後は在留期間更新可) | 更新の上限なし |
| 日本語能力要件 | 一定レベルが必要 (日本語能力試験N4程度 等) | 不要 | 協定に基づく (N3~N5程度) | 不要 |
| 介護スキル要件 | 必要 (介護技能評価試験に合格) | 不要 (入国後に研修で習得) | 協定に基づく (看護師資格保持者や大学卒業者等) | 介護福祉士資格が必須 |
1. 特定技能「介護」:即戦力となる人材を確保
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。介護分野も対象のひとつで、人手不足解消に直接つながる制度として注目されています。
この制度の大きな特徴は、受け入れ時点で一定の介護技能と日本語能力が求められることです。そのため、現場に早くなじみ、即戦力として活躍できる人材を確保しやすくなります。
受け入れには、候補者が「介護技能評価試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の両方に合格している必要があります。在留期間は通算で最長5年と比較的長く、安定雇用につながりやすいのも特徴です。
また、一定の条件を満たせば訪問系介護サービスにも従事可能で、業務の幅が広がります。事業者は、生活面や職場環境のサポートを盛り込んだ支援計画を作成・実施する義務があり、登録支援機関に委託することもできます。
2. 技能実習「介護」:国際貢献を通じた人材育成
技能実習制度は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転し、経済発展を支える人材育成を目的とした制度です。介護分野も対象職種のひとつで、日本の質の高い介護技術を学んでもらうことが主な目的です。
特定技能と異なり、入国前に介護の実務経験がなくても受け入れが可能です。 日本での実習を通して、少しずつ技能を身につけていきます。
実習は1年目の「技能実習1号」から始まり、試験合格で2・3年目の「技能実習2号」に進めます。条件を満たせば4・5年目まで延長することも可能です。
受け入れは監理団体を通じて行うのが一般的で、事業所は監理費を支払います。なお、この制度は人材確保の側面もあるため、2024年に成立した新制度「育成就労制度」への移行が決まっています。
3. EPA(経済連携協定):介護福祉士候補者の受け入れ
EPAは、国同士の経済・人材交流を促進する協定で、介護分野ではインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から介護福祉士候補者を受け入れています。
最大の特徴は、日本で働きながら学び、介護福祉士国家資格を取得することを目指す点です。候補者は母国で看護師資格を持っていたり、大学を卒業していたりと、高い基礎教育を受けた人が多く含まれます。
入国後は施設で働きつつ研修を受け、在留4年目までに国家試験に合格する必要があります。合格すれば在留資格「介護」に切り替えて日本で長期就労が可能ですが、不合格の場合は原則帰国となります。
参考:EPA看護・介護受入事業
4. 在留資格「介護」:国家資格を持つ専門人材
在留資格「介護」は、介護福祉士として専門業務に就くための資格です。対象は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家資格を取得した外国人材です。
この資格を持つ人は、専門知識と技術に加えて、日本での学習を通じた高い日本語力を備えています。在留期間の更新に制限はなく、条件を満たせば家族帯同も可能です。
訪問介護を含むすべての介護業務に従事でき、施設の中心的な存在として活躍が期待されます。ただし、対象者は限られており、採用競争は激しくなりやすい傾向があります。
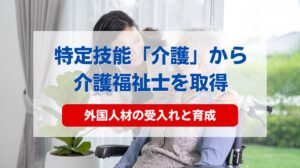
募集から入社後まで、外国人採用の具体的な流れ

受け入れる在留資格の制度を決めたら、次は実際に外国人材を採用し、就労を開始するまでの手続きを進めていきます。外国人材の採用は、日本人を採用する場合とは異なり、在留資格の申請など、出入国在留管理庁とのやり取りが必要となるため、計画的に進めることが大切です。
ここでは、募集を開始してから、実際に入社して業務を始めるまでの一般的な流れを8つのステップに分けて解説します。各ステップで必要な手続きや注意点を確認し、スムーズな受け入れ準備を進めましょう。
前の章で解説した4つの在留資格の中から、自施設の目的や方針に合った制度を決定します。その上で、何人の人材を、いつ頃までに、どの部署で受け入れるのか、具体的な計画を立てます。特に「特定技能」の場合は、外国人材への支援計画の作成が義務付けられています。
外国人材を募集する方法はいくつかあります。海外にネットワークを持つ人材紹介会社を利用する方法、技能実習生の場合は監理団体を通じて紹介を受ける方法、特定技能の場合は登録支援機関に相談する方法などがあります。ハローワークや自社の採用サイトで直接募集することも可能です。
募集を開始し、応募があった候補者と面接を行います。海外在住の候補者とは、オンラインでの面接が一般的です。面接では、介護への意欲や経験だけでなく、日本語でのコミュニケーション能力や日本の文化・習慣への理解度も確認することが重要です。
採用する人材が決まったら、雇用契約を締結します。賃金や労働時間などの労働条件を明確に記載した雇用契約書を作成し、候補者が十分に内容を理解できるよう、母国語の翻訳を付けるなどの配慮が求められます。
日本で就労するための在留資格を得るために、事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。事業所の概要や雇用契約の内容など、多くの書類が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することも一つの方法です。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる候補者本人に送付します。候補者はその証明書を持って、現地の日本大使館や総領事館でビザ(査証)の発給を申請します。
ビザが発給されれば、来日の準備は完了です。航空券を手配し、日本へ入国します。入国後は、住居への入居や市区町村での住民登録、銀行口座の開設など、生活を始めるための手続きをサポートします。
就労を開始する前に、オリエンテーションや介護業務に関する研修、日本の生活ルールに関する研修などを実施します。また、事業所はハローワークや地方出入国在留管理局への届出が必要になる場合があります。
「採用して終わり」ではない。長く活躍してもらうための支援策

言葉や文化、生活習慣の違いから生じる戸惑いや不安を取り除き、安心して働き続けられる環境を整えることは、受け入れ事業所の重要な役割です。ここでは、外国人介護士が定着し、日本人職員と共に成長していくために、事業所ができる5つの具体的な支援策を紹介します。
ポイント1:言葉の壁を超えるコミュニケーションの工夫
介護の現場では、職員間の連携や利用者との対話など、正確で円滑なコミュニケーションがサービスの質に大きく関わります。外国人職員が日本語の壁を感じることなく業務に取り組めるよう、職場全体でサポートする姿勢が大切です。
例えば、指示を出す際には、専門用語を避け、短い文章で分かりやすく伝える「やさしい日本語」を心がけることが有効です。また、口頭での説明だけでなく、写真やイラスト、図を多用した業務マニュアルを作成することで、視覚的に仕事内容を理解しやすくなります。
定期的に1対1の面談の時間を設け、仕事の悩みや生活の不安などをじっくりと聞く機会を作ることも、信頼関係の構築につながります。
ポイント2:明確なキャリアパスと公正な評価制度
誰でも将来の目標を持って働きたいと考えます。これは外国人職員にとっても同じで、施設で働き続けることでどのようなキャリアを歩めるのかを具体的に示すことは、仕事への意欲を保つうえでとても重要です。
例えば、介護福祉士など上位資格の取得を促し、受験料の補助や学習時間の確保といった支援を行えば、スキルアップへの意欲が高まります。
さらに、日本人職員と同じ基準で評価する公平な人事制度を整え、技能や勤務態度を正しく評価して昇給や昇進に反映させることで、仕事へのやりがいも向上します。
ポイント3:日本人職員との相互理解を深める環境づくり
外国人職員が職場で孤立せず、チームの一員として受け入れられるためには、日本人職員の理解と協力が欠かせません。習慣や文化、価値観の違いから、思わぬ誤解が生じることもあります。
これを防ぐには、お互いの文化を知る機会を作ることが大切です。例えば、外国人職員に母国の文化を紹介してもらう勉強会を開いたり、食事会やレクリエーションなどの交流イベントを企画したりすることで、職員同士の距離が縮まります。
こうした取り組みを重ねることで、お互いの違いを尊重し、認め合う風土が生まれ、風通しの良い職場環境が育まれます。
ポイント4:生活面でのきめ細やかなサポート
日本での生活に不慣れな外国人職員は、仕事以外の日常生活でも多くの不安を抱えがちです。そのため事業所は、業務面だけでなく生活面でのサポートにも配慮することが、日本で安心して生活基盤を築く大きな助けとなります。
さらに、困ったときにいつでも相談できる担当者を決めておくことで、本人の安心感を一層高めることができます。
ポイント5:継続的な日本語学習の支援体制
これまでの4つのポイントを効果的に機能させる土台となるのが、日本語能力の向上です。コミュニケーション、キャリア形成、同僚との関係づくり、そして日本での生活、そのすべてに日本語力は深く関わります。
特に介護の現場では、利用者のわずかな体調変化を聞き取ったり、認知症の方の気持ちに寄り添ったり、緊急時に正確な報告を行ったりと、状況に応じた適切な日本語表現が求められます。日本語力が高まれば、より質の高い介護サービスを提供できるようになり、職員自身の自信や仕事への満足度も向上します。
そのため、事業所は継続的に日本語を学べる環境を整え、学習を支援する体制を構築することが、外国人職員の定着と活躍を促すうえで非常に重要です。
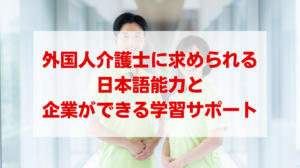
日本語教育の重要性は分かるけど…施設で教えるのは難しい?
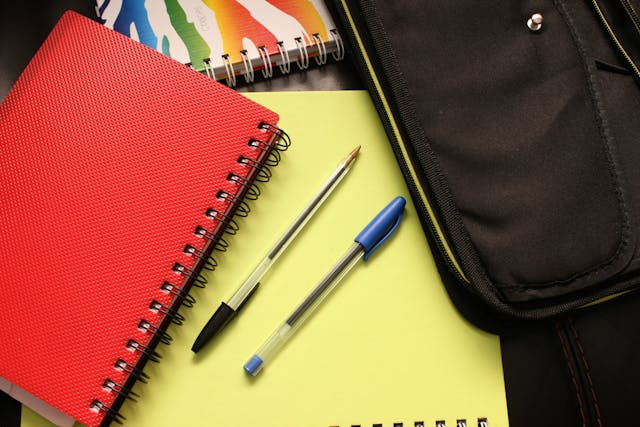
外国人材の定着と活躍のために、日本語教育が大切であることは多くの事業所が認識しています。しかし、その重要性を理解していても、日々の多忙な業務の中で、施設が独自に教育体制を整えることには多くの壁が立ちはだかります。
時間、コスト、そして教育ノウハウの不足は、日本語教育を進めたくても進められない大きな要因となっています。ここでは、多くの施設が直面する日本語教育の具体的な課題と、その解決策について考えていきます。
多くの施設が抱える日本語教育の悩み
介護施設が自前で日本語教育を行おうとした場合、さまざまな課題に直面します。まず挙げられるのが、「教育にあてる時間と人材の不足」です。現場の職員は日々の介護業務で手一杯なことが多く、日本語を教えるためのまとまった時間を確保することは容易ではありません。
また、日本語を母語とする日本人職員なら誰でも教えられるわけではなく、外国人にとって分かりやすく、効果的に教えるための専門的な知識や技術が必要となります。さらに、教材の選定や準備、学習カリキュラムの作成にも手間がかかります。
外部から日本語講師を招くという方法もありますが、その場合は講師料という形で継続的なコストが発生し、事業所の経営を圧迫する一因にもなりかねません。
解決策は「オンライン講座」の活用
こうした施設内教育の課題を乗り越えるための一つの選択肢が、外部の日本語教育サービス、特に「オンライン講座」の活用です。オンライン講座であれば、スマートフォンやパソコンを使って、休憩時間や通勤時間、帰宅後など、自分の好きなタイミングで学習を進めることができます。
これにより、施設側が研修のために勤務シフトを調整したり、特別な時間を設けたりする必要がなくなります。また、施設側が教材を準備したり、教え方に悩んだりすることもありません。月額制などのプランを選べば、講師を直接雇用するよりも費用を抑えられ、多くの職員に学習機会を提供することも可能です。
外国人介護士の日本語教育なら「日本語カフェ」にお任せください
日々の業務に追われる中で、効果的な日本語教育を継続するのは容易ではありません。そうした介護事業者様のお悩みを解決できるのが、オンライン日本語学習サービス「日本語カフェ」です。ここでは、外国人職員の日本語レベルや目標に合わせて選択できる、2つの主要な講座をご紹介します。
まずは日本語の基礎固めから!「JLPT合格コース」
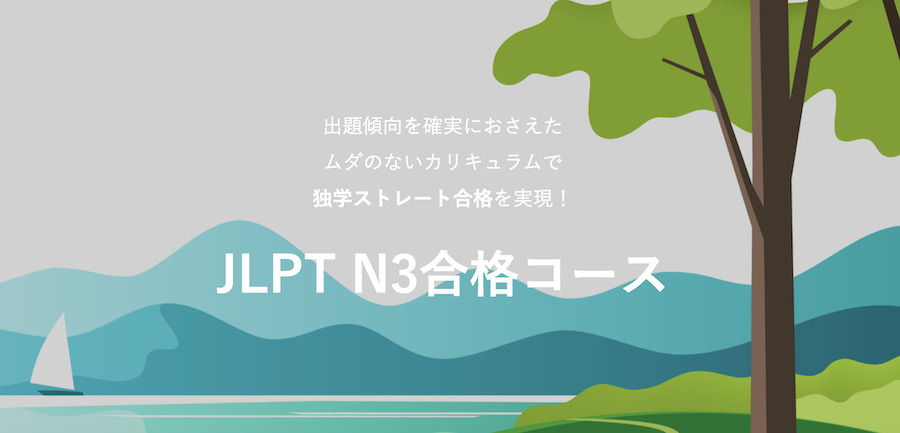
「日本人講師の採用や管理が大変…」
「自発的に学習を進めてくれる教材が欲しい…」
「日本語教育のコストを大幅にカットしたい…」。
もし、あなたが外国人スタッフの日本語教育をもっとシンプルで、それでいてコストを抑えたいと考えているなら、『JLPT 合格コース』の利用をおすすめします。
厳しい審査をパスした一流の日本語講師が監修した、日本語能力試験(JLPT)の合格に特化した動画カリキュラムが使い放題。レベル別に最適化された学習プランで、職員は迷うことなく最短ルートで合格を目指せます。
学習はスマホやPCでいつでもどこでも可能なため、忙しい業務の合間を縫って自分のペースで進められます。また、事業者様は管理画面で利用者一人ひとりの学習状況を一目で確認できるので、管理にかかっていた時間を大幅に短縮できます。
国家資格を目指す人材に!「介護福祉士 合格対策集中講座」
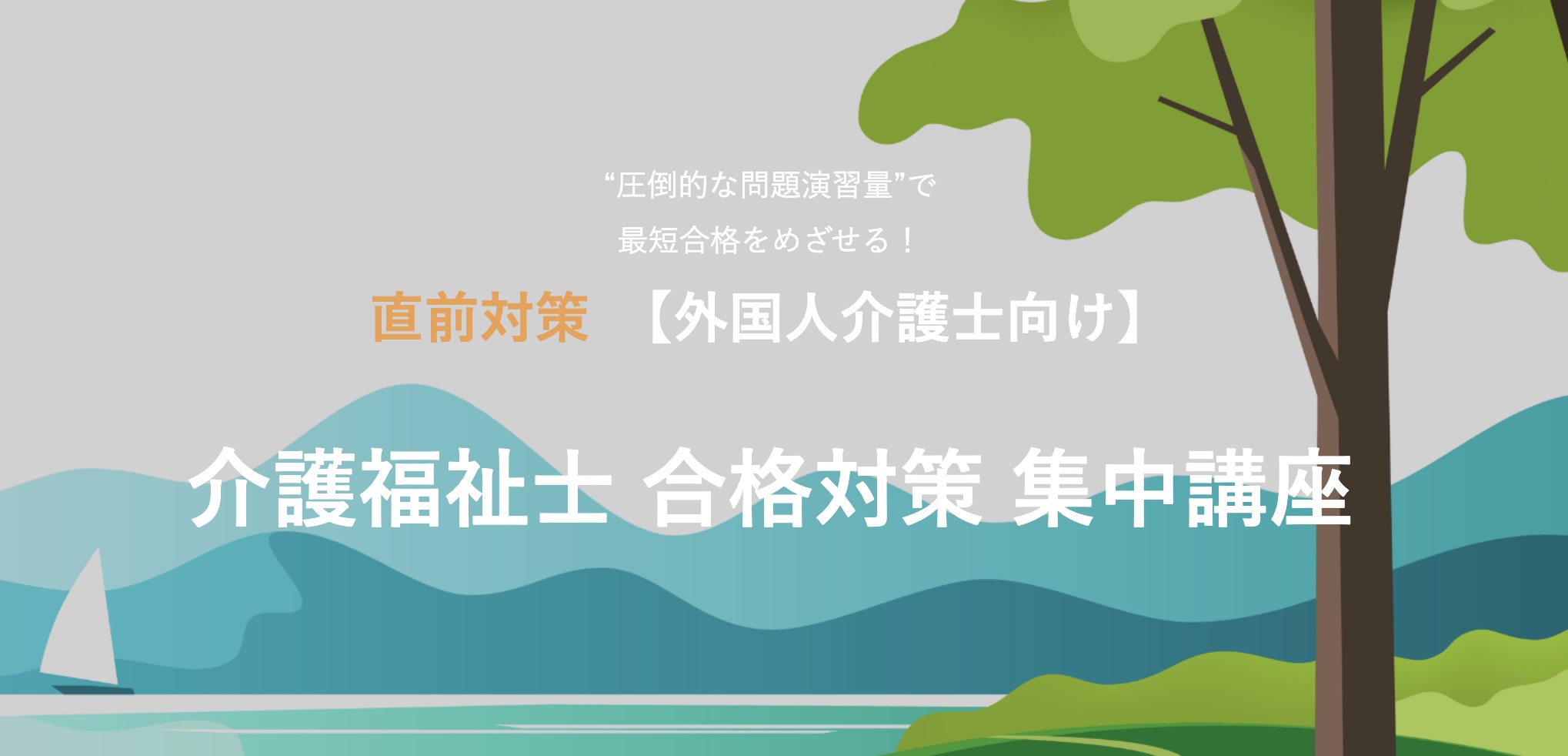
「仕事と勉強の両立は難しい…」
「試験まで時間がない、効率よく学びたい…」
「日本語での試験内容に不安がある…」。
そんな悩みを抱える外国人介護士の皆さんをサポートするのが、「介護福祉士 合格対策集中講座」です。
この講座は、4ヶ月で国家試験合格を目指せる集中プログラムです。介護福祉士の専門講師によるきめ細かいサポートのもと、試験合格に必要な知識を動画と豊富な演習問題で効率的に習得します。
特に、豊富な過去問を講師と一緒に解きながら解説する講義は、試験本番での実践力養成に役立ちます。さらに大きな特徴として、この講座の期間中は、前述の「JLPTコース」も使い放題。介護の専門知識と並行して日本語能力も強化できるため、一石二鳥の学習環境を提供します。
おすすめの学習ステップ:JLPT N2合格から介護福祉士へ
私たちは、外国人介護士のキャリア形成において、段階的な学習ステップを踏むことを推奨しています。まず、介護現場での円滑なコミュニケーションや、介護記録の正確な読解・記入のためには、日本語能力試験N2レベルの日本語力があることが望ましいです。
そこで、最初に「JLPT合格コース」で日本語の基礎を固め、N2合格を目指します。その上で、次に「介護福祉士 合格対策集中講座」に進むことで、専門用語が多く含まれる試験問題への理解度が格段に上がり、スムーズに試験対策に取り組むことができます。
このステップを踏むことで、国家試験の合格率を高めるだけでなく、合格後も現場の中核人材として活躍できる、真の実力を身につけることが可能になります。
\お問い合わせはこちらから/
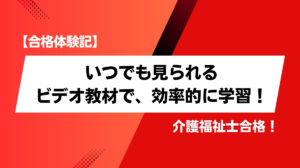
外国人材と共に、選ばれる介護事業所へ

この記事では、介護分野における外国人材の受け入れについて、在留資格の比較から採用の流れ、そして定着支援のポイントまでを解説しました。人手不足という大きな課題に直面する中で、意欲あふれる外国人材は、もはや労働力という側面だけでなく、日本の介護現場に新しい風を吹き込み、組織を活性化させてくれる大切なパートナーです。
外国人材が安心して能力を発揮し、長く働き続けられる環境を整えることは、簡単な道のりではないかもしれません。
しかし、言葉の壁を乗り越えるためのコミュニケーションの工夫や、将来のキャリアを見据えた支援、そしてその土台となる日本語学習の機会を提供することは、回り道のようでいて、事業所の持続的な成長への一番の近道です。外国人職員の成長は、日本人職員への刺激となり、職場全体のサービス向上へとつながっていきます。
外国人職員の日本語教育やキャリアアップ支援に関して、少しでもご興味や課題をお持ちでしたら、ぜひ一度「日本語カフェ」にご相談ください。状況に合わせた最適な学習プランをご提案します。
\お問い合わせはこちらから/