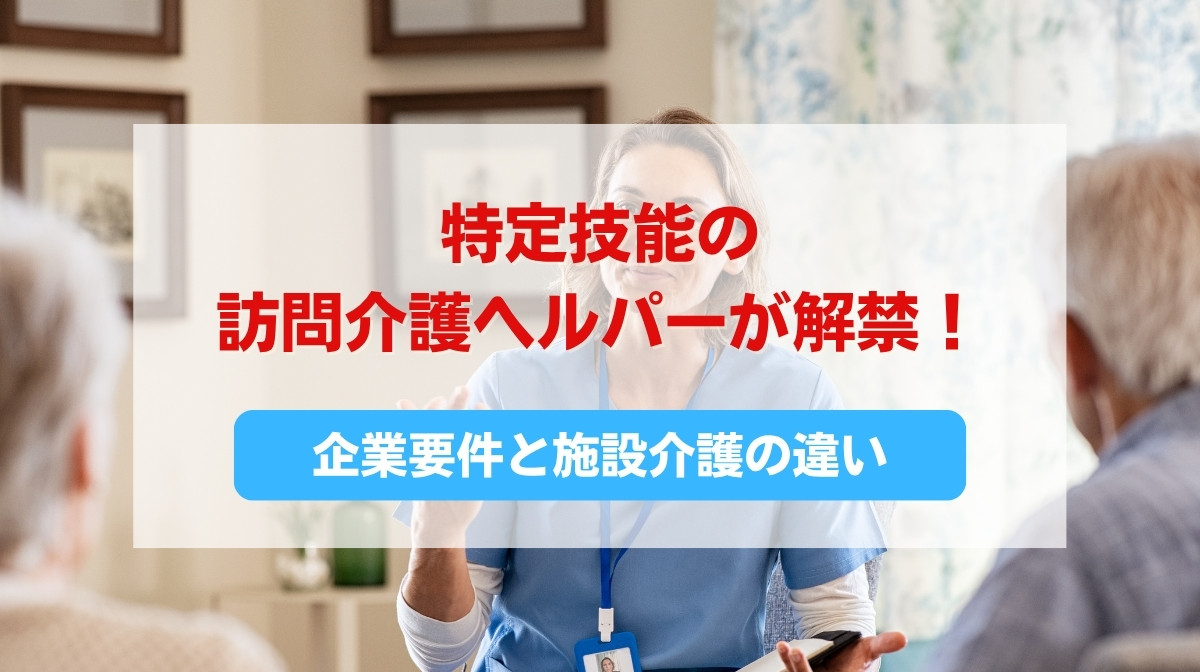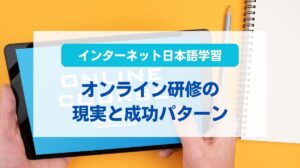介護業界、特に地域の高齢者の生活を支える訪問介護事業所では、記録的な人手不足が事業継続をも揺るがす喫緊の課題となっています。「求人広告費をかけても応募が全くない」「既存職員の高齢化が進み、身体的な負担が限界に近い」といったお悩みを抱える経営者様、採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような厳しい状況の中、介護現場の新たな担い手として期待される外国人材の活躍の場が、さらに大きく広がりました。2025年4月より「特定技能 1号」の在留資格を持つ外国籍の方が、これまで認められていなかった訪問介護での就労が可能になりました。
施設介護とは異なり、常に一人での対応が求められる訪問介護の現場では、これまで就労できる外国籍の方が非常に限られていました。今回の制度改正は、まさに歴史的な転換点であり、深刻な人手不足に悩む訪問介護事業所にとって大きなチャンスとなります。
ただし、これに伴い、外国人材を受け入れる事業所には、利用者とスタッフ双方の安全とサービスの質を守るための、より厳格な企業要件が求められます。
今回は、特定技能人材を訪問介護で受け入れるために必須となる5つの企業要件を一つひとつ解説していきます。
\ 日本語学習システム/
特定技能の訪問介護を受け入れるための企業要件

利用者様のご自宅というプライベートな空間で、多くの場合一人でサービスを提供することになる訪問介護。これは、常に同僚の目があり、すぐに助けを求められる施設介護とは根本的に異なる環境です。
そのため、特定技能人材を受け入れる事業所には、サービスの質を担保し、起こりうる様々なリスクを管理するための、より高度で具体的な体制構築が不可欠となります。
事前研修の実施
まず、外国人スタッフが現場に出る前に、訪問介護に特化した知識とスキルを徹底的に習得してもらうための研修が必須です。
この研修では、利用者宅で行う訪問サービスの基本事項や生活支援の技術はもちろん、利用者様やそのご家族と円滑な関係を築くためのコミュニケーション技術も学びます。
さらに、日本の生活様式や文化、習慣について深い理解を促し、不測の事態に備えて緊急時の対応方法や事前の連絡先確認の重要性も徹底します。
同行OJTの実施
事前研修で得た知識を、実際の現場で「使える」スキルへと昇華させるのが、この同行OJT(On-the-Job Training)です。外国人スタッフが一人で訪問介護を適切に行えるようになるまで、経験豊富な先輩職員が同行し、マンツーマンで現場での実地指導を行います。
個々の習熟度や性格に合わせて、自信を持って独り立ちできるまで十分な期間を設けることが、サービスの質と安全性を確保する上で極めて重要です。
キャリアアップ計画の策定
外国人スタッフに長く活躍してもらうためには、目先の労働力としてではなく、将来を共に歩む大切なパートナーとして迎え入れる姿勢が不可欠です。
まず、業務内容や注意点を事前に丁寧に説明し、本人の意向を確認することから始めます。その上で、本人と十分にコミュニケーションを取りながら、習得すべきスキルや将来的な役割(例:介護福祉士取得、サービス提供責任者)を明確にし、それに基づいたキャリアパスを設定します。
そして、キャリアアップの目標達成に向けた具体的な計画を本人と共に策定し、その内容を共有することで、本人のモチベーションを飛躍的に高め、長期的な定着へと繋げます。
ハラスメント対策
残念ながら、利用者やその家族から、外国人であることを理由とした差別的な言動などが発生する可能性もゼロではありません。スタッフが安心して働ける環境を守ることは、事業所の法的な義務であり、最も重要な責務の一つです。
そのために、ハラスメントを未然に防ぐための対応マニュアルを作成して全職員と共有し、管理者の役割を明確にしてハラスレーションが発生した場合の対応ルールを整備・共有しておく必要があります。
また、利用者様やご家族へ契約時にハラスメントに関する基本的な理解を周知することも重要です。
万が一ハラスメントが発生した際は、定められたルールに基づいて速やかに対応し、外国人スタッフが安心して相談できる窓口を設けてその存在を周知することが求められます。
ICTを活用した環境整備
一人で業務にあたる時間が長い訪問介護において、スタッフの安全確保と業務効率化を両立させる強力なツールがICT(情報通信技術)です。
緊急時の連絡先や対応フローをまとめたマニュアルをスマートフォンなどからいつでも確認できるようにし、他の職員がすぐに駆け付けたり指示を出したりできる体制を整備します。
さらに、サービス提供記録や申し送り事項をスマートフォンやタブレットのアプリ等を活用して全職員でリアルタイムに共有できる仕組みを整えることで、サービスの質向上と業務効率化を同時に実現します。
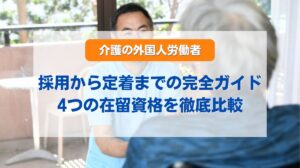
「訪問介護」と「施設介護」の人材要件の違い

訪問介護で働く特定技能人材には、どのような要件が求められるのでしょうか。これまで一般的だった施設介護の要件と比較してみましょう。
| 要件項目 | 訪問介護 | 施設介護 |
|---|---|---|
| 必須資格 | 初任者研修修了(見込み可) | なし |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N3相当以上(見込み可) | 日本語能力試験 N4以上または日本語基礎テストに合格 |
| 実務経験 | 施設介護での1年以上の実務経験 | なし |
訪問介護で就労する特定技能人材には、施設介護に比べて格段に高いハードルが設定されています。その背景には、訪問介護特有の業務の難しさがあります。
施設介護であれば、常に周囲に先輩や同僚がおり、分からないことがあればすぐに質問したり、緊急時には応援を呼んだりできます。しかし、訪問介護は基本的に一人で利用者のご自宅に伺います。
そこで求められるのは、利用者様のささいな体調の変化に気づき、的確な判断を下し、必要であれば関係各所に正確に報告・連絡・相談できる自己完結型の能力です。
そのため、介護の基礎知識(初任者研修)、一定水準以上の日本語でのコミュニケーション能力(N3)、そして実際の介護現場での経験(実務経験)が必須とされているのです。
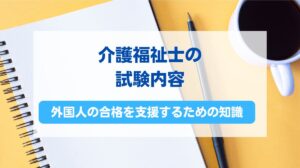
よくある懸念「言葉の壁」はどう乗り越える?

外国人材の採用を検討する際、多くの方が懸念されるのが「言葉の壁」、特に重度の認知症の方や、高齢者の方とのコミュニケーションではないでしょうか。
訪問介護では、利用者様と1対1で向き合う時間が長く、「腰がずきずき痛む」「胸がもやもやする」といった身体の不調を表す繊細な表現や、心の機微を汲み取る高度なコミュニケーション能力が求められます。
だからこそ、特定技能の要件として、施設介護よりも高い日本語能力「N3相当以上」が設定されているのです。しかし、N3はあくまで「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルです。
資格を持っていても、現場で使われる専門用語、利用者様一人ひとりの話し方の癖、文化的背景からくる価値観の違いなどを乗り越え、深い信頼関係を築くには、採用後の継続的な学習が欠かせません。
とはいえ、「日々の業務に追われ、現場で日本語を教える時間的な余裕がない」「日本語教育のノウハウがなく、何から教えればいいか分からない」というのが、多くの事業所の実情ではないでしょうか。
スタッフの日本語力向上は、サービスの質の向上、介護事故のリスク低減、そしてなにより本人の定着率アップに直結する重要な経営課題です。この課題を効率的に解決する方法として、企業向けの日本語学習サービスを活用する選択肢があります。
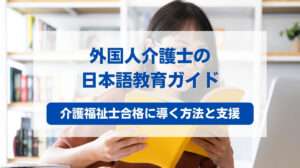
採用後の日本語教育はプロに任せる!「日本語カフェ」で学習を効率化
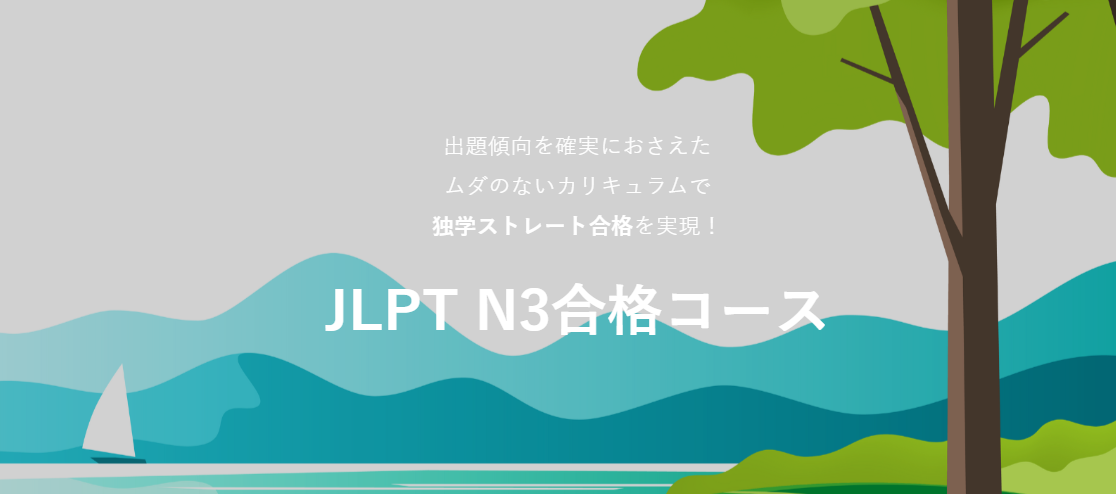
「日本語カフェ」の JLPT合格コース は、多忙な介護現場で働くスタッフが、効率的に日本語能力を向上させられるよう設計されています。実際に、全くの初心者からスタートして2ヶ月でN4合格、3ヶ月でN3合格を達成した実績もあり、訪問介護で求められる日本語レベルへの到達を強力にサポートします。
それぞれのレベルごとに「何を、どの順番で学べば合格できるか」が体系化されています。自己流の学習で遠回りすることなく、最短ルートでN3以上の合格を目指せるため、教育担当者の負担も大幅に軽減されます。
厳しい審査をパスしたプロの日本語講師が監修した動画講義は、何度でも視聴可能。インプットとアウトプットを繰り返すことで、試験に合格するためだけでなく、現場で実際に「使える」日本語が着実に身につきます。
1回10分から学べるため、訪問の合間や通勤中、休憩時間などのスキマ時間を有効活用できます。スタッフが自分のペースで無理なく学習を続けられる環境は、学習意欲の維持に不可欠です。
「日本人講師の採用や管理が大変…」「毎月の教育コストが負担…」といったお悩みを解決します。管理画面でスタッフ一人ひとりの学習進捗を簡単に把握できるため、管理の手間とコストを大幅に削減できます。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
特定技能人材の受け入れを成功させる鍵は、採用後の教育体制にあります。サービスの質を高め、スタッフに長く活躍してもらうために、「日本語カフェ」の導入をぜひご検討ください。
\ 詳しくはこちら/
万全の準備で外国人材を迎え入れよう

2025年4月から解禁される特定技能外国人の訪問介護への従事は、深刻化する介護業界の人手不足を解消する、まさに「待ったなし」の重要政策です。
この大きなチャンスを活かすためには、今回解説した制度上の5つの必須要件をクリアすることはもちろん、採用した人材を「実務上でいかに育て、支えていくか」という視点が不可欠です。
特に、サービスの質と利用者様との信頼関係に直結する「日本語能力」の向上は、事業所が積極的に支援すべき最重要ポイントと言えるでしょう。
自社での教育リソースに課題を感じている場合は、「日本語カフェ」のような外部の専門サービスをうまく活用し、効率的かつ効果的な教育体制を構築することが、成功への近道となります。
今から準備を始めることで、競合に先んじて優秀な人材を確保し、地域にさらに必要とされる事業所へと成長していけるはずです。万全の受け入れ体制を整え、新たな仲間を迎え入れましょう。
\ ご相談はお気軽に/