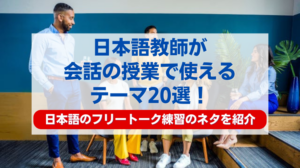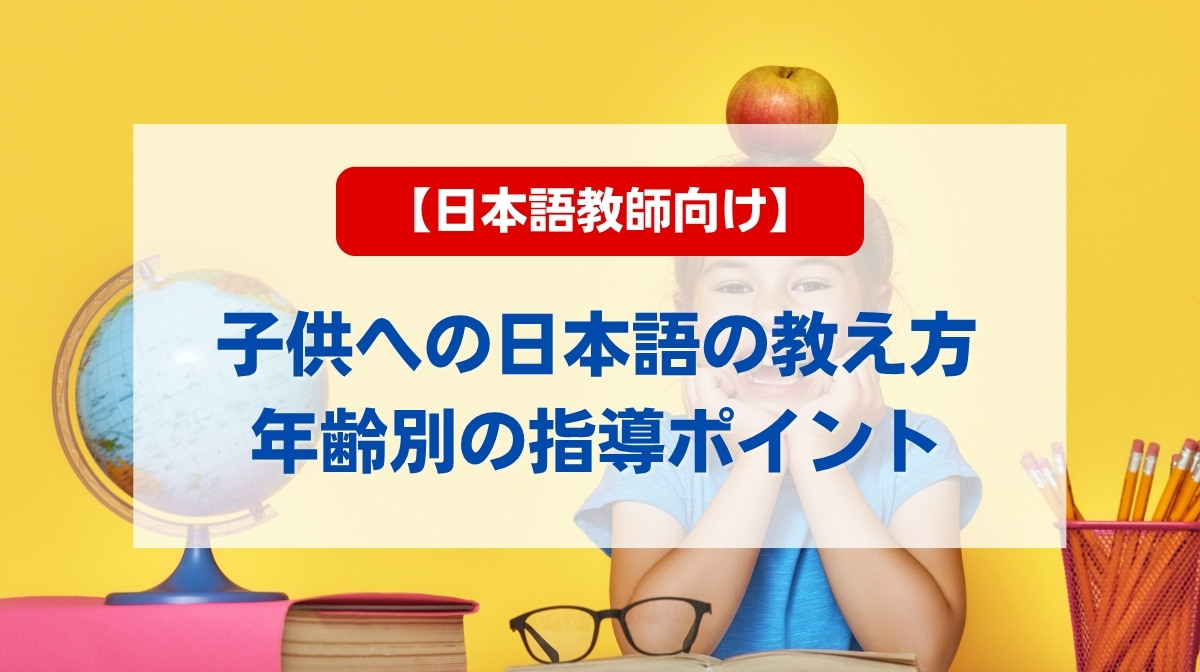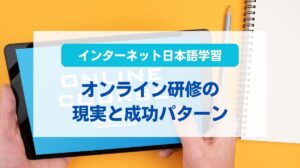子供たちに日本語を教えている先生方は、日々、どうすれば子供たちが楽しく日本語を学んでくれるか、試行錯誤されていることと思います。子供向けの日本語教育は奥が深く、大人の学習者と同じやり方ではうまくいかない場面も多いのではないでしょうか。
熱意を持って指導すればするほど、「どうして伝わらないんだろう」「もっと良い方法はないだろうか」と悩むことも少なくありません。
この記事では、子供に日本語を教える上での基本的な考え方から、具体的な指導のポイントを年齢別に整理して情報をまとめました。このガイドを参考に、ご自身の指導のヒントを見つけていただき、明日からの授業がさらに充実したものになれば幸いです。
\ 日本語学習システム/
まず押さえたい!子供への日本語指導 3つの基本方針

子供たちへの日本語指導を始める前に、心構えとして持っておきたい3つの基本方針があります。テクニックや教材の前に、この土台となる考え方を共有することが、子供たちの健やかな言語習得の環境を整えます。
方針1:勉強ではなく「コミュニケーションの手段」と伝える
子供たちにとって、日本語はテストの点数を取るための「教科」であってはなりません。日本語が話せると、新しい友達と話せるようになったり、日本の面白いアニメを字幕なしで見られるようになったり、日本へ旅行したときにお店の人と会話ができたりと、自分の世界がもっと広がる素晴らしい「コミュニケーションの手段」なのだと伝えていくことが大切です。
授業の中では、ドリルや暗記に偏るのではなく、学んだ言葉をすぐに使って誰かとやり取りする活動を多く取り入れましょう。例えば、「りんご」という単語を覚えたら、それを使って「りんごは好きですか?」「りんごをください」といった会話練習をしましょう。
言葉が通じる喜びを一度でも体験すると、子供たちは「もっと話したい」という気持ちを自然に抱くようになります。
方針2:たくさん褒めて「話したい」気持ちを育てる
子供たちは、大人が思う以上に周囲の評価に敏感です。特に、慣れない外国語を話すときには、緊張や不安を感じています。その繊細な気持ちを汲み取り、まずは日本語で伝えようとしたその姿勢そのものを、温かく認めてあげてください。
たとえ文法が少し間違っていたり、発音が完璧でなかったりしても、まずは「話してくれてありがとう」「今の気持ち、よく伝わったよ」と受け止めることが重要です。褒めるときには、「上手!」という一言だけでなく、「今の『ありがとう』の言い方、とても気持ちがこもっていて素敵だったよ」というように、具体的にどこが良かったのかを伝えると、子供は自分の言葉に自信を持ちます。
この自信の積み重ねが、「次も話してみよう」という前向きな意欲を育てていくのです。
方針3:間違いを恐れない、安心できるクラスの雰囲気作り
言語の習得過程において、間違うことは当たり前のことであり、むしろ成長のために必要なプロセスです。子供たちが「間違えたらどうしよう」「笑われたら恥ずかしい」と感じる環境では、自由に言葉を発することができません。
先生は、子供たちがどんな間違いをしても、それを決して否定したり、笑ったりしないという絶対的な安心感をクラスの中に作る必要があります。
そのためには、先生自身が完璧でない姿を見せることも一つの方法です。「あれ、この単語、先生も時々忘れちゃうんだ」とオープンに話すことで、子供たちは「間違えても大丈夫なんだ」と感じることができます。
誰かが間違えたときには、他の子がそれを指摘するのではなく、「〇〇って言いたいのかな?」「私はこう思うよ」と助け合えるような文化を育むことが、子供たちの自発的な発話を促す温かい土壌となります。
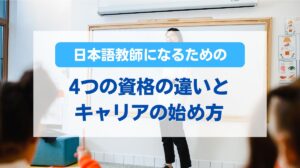
【年齢別】子供の発達に合わせた日本語の教え方

子供の言語習得は、その年齢における心身の発達段階と密接に関わっています。幼児期、小学校低学年、高学年といったステージごとに、子供たちの興味や学び方は大きく異なります。
それぞれの年代の特性に合わせたアプローチを行うことで、学習の質は格段に向上します。
| 年齢(目安) | 発達段階の特徴 | 日本語学習の主な目標 | 指導のポイント |
|---|---|---|---|
| 幼児期 (0-5歳) | 五感が豊かで、遊びを通して学ぶ。 模倣が得意。 | 日本語の音やリズムに親しむ。 簡単な単語を日常の文脈で理解する。 | 歌、絵本、手遊び、ごっこ遊びをふんだんに取り入れる。 |
| 小学校低学年 (6-8歳) | 具体的な物事への興味が強い。 ルールのある遊びを好む。 | ひらがな・カタカナの読み書きの定着。 身近な言葉で挨拶や自己紹介ができる。 | ゲーム性のある活動、カード、アニメやキャラクターの活用。 |
| 小学校高学年 (9-12歳) | 抽象的な思考が芽生え始める。 社会的な事柄に関心を持つ。 | 自分の考えや気持ちを簡単な文章で表現する。 日本文化への理解を深める。 | 会話や発表の機会、文化紹介、短い文章の読み書き。 |
幼児期(0歳〜5歳)向け:遊びを通して言葉の世界に親しむ
この時期の子供たちは、まさにスポンジのように周囲の環境から言葉を吸収していきます。彼らにとって、学習とは遊びそのものです。指導の際は、「教える」というよりも「一緒に楽しむ」という姿勢が何よりも大切になります。
日本語の歌や手遊びは、幼児向けの指導に欠かせません。「むすんでひらいて」や「きらきら星」のような簡単な歌は、楽しいリズムと一緒に体の動きを伴うため、子供たちは夢中になります。歌を通して、日本語特有の音の響きやリズム感を自然に体に染み込ませていくことができます。
また、絵本の読み聞かせは、豊かな語彙と表現に触れる絶好の機会です。「もこ もこもこ」のような擬音語や擬態語が豊富な絵本は、言葉の意味が分からなくても、音の面白さだけで子供たちの心を惹きつけます。
カラフルな絵を指差しながら、「ワンワン、大きいね」「ブーブーが来たよ」とゆっくり語りかけることで、言葉とイメージが結びついていきます。毎日少しの時間でも、絵本に触れる習慣を作ることが、子供の言葉の世界を豊かに広げます。
また、身の回りの物を使った指導も効果的です。食事の時間に「りんご、おいしいね」、おもちゃで遊びながら「あかい、くるま」といったように、実物を見せながら話しかけることで、言葉は生きた情報として子供の中に蓄積されていきます。
小学校低学年(6歳〜8歳)向け:文字への興味を引き出し、世界を広げる
小学校低学年の子供たちは、具体的な物事への興味が旺盛で、ルールのある遊びを好むようになります。この特性を活かして、文字学習をゲームのように楽しく進めることがポイントです。
ひらがなやカタカナの学習では、単調な書き取り練習だけではすぐに飽きてしまいます。ここで活躍するのが、カルタや文字探しゲームです。
先生が「『あ』のつく言葉はなあに?」と尋ね、子供たちが絵カードの中から「あり」や「あめ」を探すような活動は、遊びながら文字と音、そして意味を結びつけるのに役立ちます。自分たちで絵を描いてオリジナルのカルタを作るのも、創造性を刺激する良い活動です。
また、この時期の子供たちは、日本の子供向けアニメや漫画に強い興味を示すことが多いです。これを貴重な教材として活用しない手はありません。好きなキャラクターのセリフを真似して言ってみるロールプレイングは、楽しみながら自然なイントネーションや会話表現を身につけることにつながります。
「こんにちは、わたしは〇〇です」「すきなたべものは△△です」といった自己紹介のフレーズも、キャラクターになりきって発表会形式で行うと、恥ずかしがらずに挑戦できる子供が増えます。文字への興味と、自分の世界を広げたいという欲求を結びつけてあげることが、この時期の指導の要です。
小学校高学年(9歳〜12歳)向け:思考力と表現力を日本語で育む
小学校高学年になると、抽象的な思考が発達し始め、自分の意見を持ったり、社会的な事柄に関心を示したりするようになります。この段階では、単に言葉を覚えるだけでなく、その言葉を使って自分の考えや気持ちを表現する力を育む指導が求められます。
子供たちが関心を持つゲームやスポーツ、好きな音楽などをテーマに、日本語で自由に会話やディスカッションを行う時間を設けましょう。
例えば、「日本のゲームと自分の国のゲーム、どこが違う?」といったテーマは、比較や分析を通して論理的に話す練習になります。先生は会話の進行役に徹し、子供たちが自分の言葉で意見を表現できるよう、質問を投げかけたり、相槌を打ったりしてサポートします。
漢字の学習も、この時期から本格的に始まります。ただ形を暗記させるのではなく、その漢字の成り立ち(象形文字など)をイラストで見せたり、「木」という部首がつく漢字(林、森、机など)を集めて意味の関連性を説明したりすると、知的好奇心が刺激され、記憶に残りやすくなります。
さらに、日本の学校生活や年中行事、食文化といった文化的なトピックを紹介することも、言葉の背景にある社会や人々の考え方を理解する上で非常に重要です。動画や写真を見せながら、「日本では小学校で給食当番があります。皆さんの国ではどうですか?」と問いかけることで、異文化理解を深めると同時に、日本語での表現力を高めることができます。
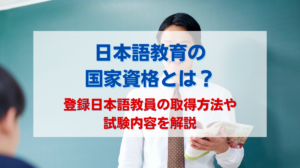
4技能をバランス良く伸ばす指導のポイントと活動例

日本語のコミュニケーション能力は、「聞く」「話す」「読む」「書く」という4つの技能が相互に関連し合って成り立っています。指導の際には、これらの技能が偏りなく、バランス良く伸びていくように意識することが大切です。
ここでは、それぞれの技能を高めるための具体的な活動例を紹介します。
「聞く」能力の育て方
「聞く」力は、全ての言語活動の基礎となる重要な能力です。正確に聞き取る力がなければ、会話も成り立ちませんし、文章を読む際にも音と文字を結びつけることが難しくなります。
活動例としては、先生が短いお話を読み、その内容に関する簡単なクイズを出すというものがあります。例えば、「きのう、たろうくんは、あかいりんごを3つかいました」という文章を読んだ後、「たろうくんが買ったものは何ですか?」「りんごの色は何色でしたか?」といった質問をします。
最初はゆっくり、慣れてきたら少しずつスピードを上げていくと良いでしょう。この活動は、子供たちが話の要点に注意を向け、集中して聞き取る練習になります。
「話す」能力の育て方
知識として言葉を知っていることと、実際に「話せる」ことの間には大きな隔たりがあります。このギャップを埋めるためには、実際に口を動かして話す練習を数多く経験することが必要です。
お店屋さんごっこなどのロールプレイングは、楽しみながら会話練習ができる優れた活動です。まず、店員役と客役に分かれます。そして、「いらっしゃいませ」「〇〇をください」「ぜんぶで△△円です」「ありがとうございます」といった、その場面で使われる基本的なフレーズを書いたカードを用意します。
最初はカードを見ながらやり取りを行い、慣れてきたらカードなしで、さらにアドリブで「これはどこで作られましたか?」といった質問を加えたりと、発展させていくことができます。
「読む」能力の育て方
文字が読めるようになると、子供たちは自分の力で新しい情報にアクセスできるようになり、世界が一気に広がります。しかし、読むことに苦手意識を持ってしまうと、その後の学習全体に影響が出かねません。
子供たちが自分のペースで読み進める楽しさを感じられるよう、ふりがな付きの短い物語や、日本の子供たちが実際に読んでいる漫画などを教室にたくさん用意しておきましょう。そして、自由に手に取って読む時間を作ります。
読んだ後は、「どのキャラクターが好きだった?」「どこが一番面白かった?」といった簡単な感想をクラスで言い合う時間を設けると、内容理解が深まると同時に、自分の意見を発表する練習にもなります。
「書く」能力の育て方
「書く」という活動は、頭の中にある考えを整理し、論理的に表現する高度な能力を必要とします。最初から長い作文を書くのはハードルが高いので、短い文章から始めるのが良いでしょう。
例えば、週末の出来事を絵と一緒に数行の文章で書く「絵日記」は、多くの学校で取り入れられている活動です。楽しい思い出を絵で表現し、それに「どようび、こうえんにいきました。とてもたのしかったです。」といった簡単な文章を添えることから始めます。
先生は、文法の間違いを細かく直すよりも、内容をしっかり読み、コメントを書いて返すことを心がけましょう。先生や友達との交換ノートも、「書く」ことへの動機付けとして、とても良い方法です。

子供が楽しく学べるおすすめのアプリ4選

今日の子供たちにとって、スマートフォンやタブレットは非常に身近な存在です。子供たちの学習意欲を引き出し、授業のサポートや家庭学習にも役立つおすすめのアプリを4つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、子供の年齢や興味に合わせて活用してみてください。
Duolingo

世界中の多くの人が利用している言語学習アプリで、日本語のコースも用意されています。最大の特長は、学習全体にゲームの要素が取り入れられている点です。短いレッスンを一つクリアするごとにポイントがもらえ、連続学習記録が伸びていくなど、子供が夢中になる仕掛けがたくさんあります。
内容は、単語の選択問題や簡単な文章の翻訳など多岐にわたり、基礎から少しずつステップアップしていくことができます。授業の冒頭5分間のウォームアップとして使ったり、家庭学習の習慣づけとして保護者に勧めたりするのに向いています。
キャラクターも可愛らしく、子供から大人まで、幅広い年齢層が楽しめるアプリです。
タッチ!ことばランド

このアプリは、特に言葉を覚え始める幼児期のお子さんに最適です。画面には動物や乗り物、食べ物など、身近なものの可愛いイラストが並んでいます。子供が興味を持ったイラストに指でタッチすると、その名前がはっきりとした日本語の音声で流れるというシンプルな仕組みです。
音と絵が直接結びつくため、子供は直感的に単語の意味を理解することができます。文字がまだ読めない子供でも、一人で遊ぶことができますし、「これは何かな?」と先生や保護者が一緒に会話しながら使うことで、豊かなコミュニケーションのきっかけにもなります。
たくさんの言葉のシャワーを浴びせたい時期に、とても重宝する知育アプリと言えるでしょう。
たのしい!ひらがな

ひらがなの学習を始める段階の子供たちのために作られた、まさに「楽しい」アプリです。お手本となるひらがなが大きく表示され、指で画面をなぞって書き順通りに書く練習ができます。
正しくなぞれると、効果音と共に花丸がもらえたり、キャラクターが褒めてくれたりするため、子供は達成感を感じながら学習を進められます。書き順を間違えると先に進めないようになっており、自然と正しい書き方が身につくよう工夫されています。
単調になりがちな文字練習を、遊びの延長として取り組ませたいときにぴったりのアプリです。まずは自分の名前を書くことを目標にするのも良いでしょう。
たのしい!カタカナ

上記の「たのしい!ひらがな」でひらがなをマスターした子供が、次のステップに進むためのカタカナ版アプリです。基本的な操作方法や画面のデザインはひらがな版と同じなので、子供も迷うことなくスムーズに学習を始めることができます。
カタカナは、外来語や擬音語など、子供たちの身の回りにも溢れています。自分の好きなアニメのキャラクターの名前や、お菓子の名前などにカタカナが使われていることを見つけさせ、その文字をアプリで練習するといったように、実生活と結びつけると学習への関心が一層高まります。ひらがなとセットで活用したいアプリです。
子供たちの成長に合わせて指導方法を変えよう

この記事では、子供向けの日本語の教え方について、指導の土台となる基本的な考え方から、子供の成長段階に合わせた年齢別の指導法、そして学習に役立つ具体的なアプリまで紹介しました。
しかし、ここで紹介した方法は、あくまでも一つの指針に過ぎません。最も重要なのは、目の前にいる子供一人ひとりの表情をよく見て、その子の興味や理解度、その日の気分に合わせて、指導方法を柔軟に変えていくことです。
ある子には響いた方法が、別の子には合わないということも日常茶飯事です。だからこそ、私たち指導者は、常に多くの引き出しを用意し、学び続ける姿勢を持つことが求められます。
先生自身が子供たちとのコミュニケーションを心から楽しみ、日本語の面白さや奥深さを体現する存在であることが、子供たちの学習意欲を何よりも刺激します。
この記事で紹介した方法の中から、何か一つでも「試してみよう」と思えるものがあれば、ぜひ明日からの授業に取り入れてみてください。子供たちの日本語の世界は、先生との楽しい時間を通して、きっと豊かに、そして大きく広がっていくはずです。