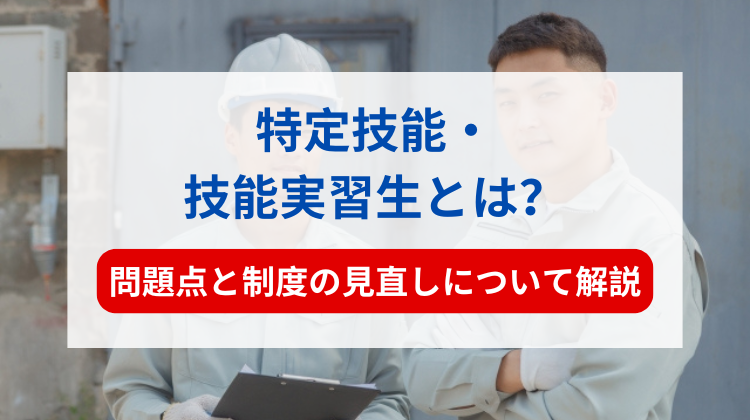現状の特定技能制度や技能実習制度には様々な問題点があること、そして制度が見直されようとしていることはご存じでしょうか?
本記事では、特定技能制度と技能実習制度の違いや制度の問題点、見直しの案などについて解説しています。
受け入れ企業側がすべき対応についてもまとめているので、参考にしてください。
特定技能制度・技能実習制度とは?

まずは特定技能制度と技能実習制度、それぞれの概要を確認していきましょう。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年に創設されました。
制度の目的は、「日本の人手不足を解消するために、技術・技能が一定水準に達している外国人労働者を雇用する」こと。
特定技能制度は、労働力として外国人を雇用するための制度なのです。
在留資格「特定技能」を利用して就労している外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれます。
特定技能は「1号」と「2号」に分かれていて、それぞれ技能や在留可能期間等が異なります。
技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、1993年に施行されました。
制度の目的は、「日本の技能や技術、知識を発展途上地域に移転する」こと。
技能実習制度は日本の技能を海外に広めるための制度であり、労働力として外国人を雇うための制度ではありません。
在留資格「技能実習」を利用して就労している外国人は、「外国人技能実習生」と呼ばれます。
技能実習は「1号」「2号」「3号」に分かれていて、それぞれ実習の年数や受け入れ条件が異なります。
また、以下の2つの条件を満たすことで、技能実習から特定技能に移行することも可能です。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 従事しようとする業務と技能実習2号の業種に関連性が認められる
特定技能と技能実習の違い

ここでは、特定技能と技能実習の違いについて解説しています。
作業内容
<特定技能>
特定技能外国人には、メインの業務だけではなく、清掃や皿洗い等の単純作業を任せられます。
特定技能制度は、人手不足解消や労働力の確保を目的としているからです。
しかし、単純作業だけに従事させることは禁止されているので、十分注意してください。
<技能実習>
外国人技能実習生に任せられるのは専門性の高い業務のみです。
特定技能外国人のように単純作業を任せることはできません。
技能実習制度は、日本の技能や技術、知識を発展途上国に移転することを目的としているからです。
職種
<特定技能>
特定技能の受け入れ対象は、需要が高く、特に人手不足が深刻化している以下の12分野です。
農業や漁業だけでなく、外食・飲食業や宿泊業などのサービス業も含まれています。
- 外食・飲食業
- 宿泊業
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 飲食料品製造業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 農業
- 漁業
<技能実習>
技能実習の受け入れ対象は、2024年9月30日時点で91職種167作業です。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
参考:「移行対象職種・作業一覧」厚生労働省
このように、特定技能と技能実習では、従事できる分野や業種が異なります。
どちらかでしか従事できない業務もあるので、対応可能な業務をしっかりと確認しましょう。
必要知識や技能
<特定技能>
特定技能外国人は即戦力としての活躍が求められるため、入国前から就労する分野の技能や知識を有しています。
<技能実習>
技能実習生は日本で技術や技能を学ぶため、入国前に就労する分野の技能を習得したり、知識を得たりする必要はありません。
試験
<特定技能>
在留資格「特定技能」を利用して就労するためには、日本語能力を測定する「日本語能力試験(N4以上)」に合格するか「国際交流基金日本語基礎テスト」においてA2以上と認められるスコアを獲得しなければなりません。
また、就労する分野の技能を測定する「特定技能評価試験」に合格する必要もあります。
特定技能外国人は、入国後すぐに就労できるレベルに達していなければならないからです。
<技能実習>
技能実習では、介護分野で就労する場合のみ、日本語能力試験N4に合格していることが求められます。
他の分野で就労する場合、試験は必要ありません。
家族帯同の可否
<特定技能>
母国にいる家族を日本に呼び、一緒に暮らすことを家族帯同といいます。
特定技能1号の場合、家族帯同は認められません。
特定技能2号の場合は、配偶者と子に限られるものの、要件を満たせば家族帯同が可能です。
<技能実習>
技能実習生の家族帯同は認められません。
在留期間
<特定技能>
特定技能1号の場合、在留期間に最長5年間の制限があります。
特定技能2号は手続きをすれば日本に永住でき、実質在留期間の制限がありません。
<技能実習>
技能実習生の場合、在留期間は最長で5年間です。
転職の可否
<特定技能>
特定技能制度は労働力の確保を目的としているため、転職が可能です。
同一分野はもちろん、
- 転職先の分野に該当する技能評価試験に合格している
- 日本語能力試験N4に合格している
上記の条件を満たしていれば他の分野にも転職できます。
<技能実習>
技能実習制度の目的は、外国人に実習先で技能を学んでもらうことです。
そのため、技能実習生は基本的に転職しません。
やむを得ない事情があって実習先を変更する場合は、転職ではなく「転籍」という形になります。
受け入れ人数
<特定技能>
特定技能は人手不足解消を目的とした制度なので、基本的に受け入れ人数の制限はありません。
ただし、介護分野と建設分野においては、「日本人等の常勤職員の総数を超えた特定技能外国人は雇用できない」と定められています。
介護分野・建設分野で特定技能制度を利用する場合は注意してください。
また、ここで言う「日本人等」には、介護の在留資格により日本に在留する外国人や、永住権を持つ外国人なども含まれます。
<技能実習>
外国人に技能を学んでもらうことが重要視される技能実習では、きちんと指導できる人数を受け入れることが望ましいです。
そのため、技能実習の受け入れ人数には制限が設けられています。
例えば、常勤職員数が50人の企業の場合、受け入れられる技能実習1号の人数は5人までです。
特定技能・技能実習制度の問題点

ここでは、特定技能制度・技能実習制度の問題点について解説しています。
技能実習制度の目的が果たされていない
技能実習制度の本来の目的は、発展途上国に日本の技術や技能を移転すること。
言い換えれば国際貢献です。
しかし、技能実習制度が国際貢献ではなく、人材確保のために利用されている実態があります。
技能実習制度の目的が果たされず、特定技能制度のように利用されているのです。
技能実習現場の労働環境
技能実習現場で長時間労働や賃金の未払いの事例、暴言・暴行などのトラブルが起こるケースは後を絶ちません。
そのため、技能実習制度は他国から厳しい目を向けられています。
在日米国大使館の「2022年人身取引報告書(日本に関する部分)」は技能実習制度に触れ、「技能実習制度の下に日本国内にいる移住労働者の強制労働」「労働搾取目的の人身取引犯罪」などと批判しました。
支援体制が整っておらず、監査が不十分な監理団体が存在することも指摘されています。
技能実習生の失踪問題
劣悪な労働環境などにより、毎年5000人~9000人の技能実習生が失踪しています。
基本的に転職ができないことや、送出機関等に多額の手数料を支払い、借金を背負って入国している実習生が多いことも、失踪や不法滞在の原因として挙げられるでしょう。
特定技能制度では安定した労働力の確保が難しい
特定技能外国人の採用は、人手不足の解消に繋がります。
しかし、現在雇用されている特定技能外国人の多くは1号です。
特定技能1号の在留期間は最長でも5年間なので、在留期間が終わった特定技能外国人が帰国すれば、企業側はふたたび労働力不足に悩むことになるでしょう。
安定した労働力を確保するためには、長期的に就労できる外国人労働者が必要です。
特定技能・技能実習制度の見直し

ここでは、特定技能制度・技能実習制度の問題点を解決するために進められている見直し案について解説しています。
技能実習制度に代わる新たな制度の創設
2023年、政府の有識者会議は、現在の技能実習制度を廃止し、新たな制度を創設するとした最終報告書をまとめました。
新たな制度は「外国人材の確保と育成」を目的としていて、特定技能制度との繋がりを重視し、受け入れ対象分野を限定していくということです。
また、今まで原則認められなかった「転籍」の条件が緩和されます。
1年以上働き、一定の技能と日本語能力があれば同じ分野に限り転籍が認められるようになります。
さらに、多くの実習生が借金を背負っていることを考慮し、負担軽減のために日本の受け入れ企業と費用を分担する仕組みが導入される予定です。
詳しくは下記をご覧ください。
参考:令和5年11月30日 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書|法務省
監理団体・受け入れ機関の適正化
新たな制度・特定技能制度が適切に運用され、外国人に対する支援や保護が適切に行われるよう、監理団体や受け入れ機関の適正化を行う方針です。
監理団体に対しては、新たな許可要件をもとに厳格に審査を行い、役割が十分に果たせない監理団体には活動の許可がおりません。
優良な監理団体に対しては、各種申請書類の簡素化や届出の頻度軽減などの優遇措置が講じられます。
受け入れ機関については、人数枠を含む育成・支援体制等の要件を適正化して設定するとともに、適切性を確保するために必要な要件を新たに設けることが検討されています。
詳しくは下記をご覧ください。
参考:令和5年11月30日 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書|法務省
「特定技能2号」の対象分野拡大
長期的に就労できる特定技能2号の受け入れ対象分野は、建設業と造船・舶用工業の2分野のみでした。
そのため、在留期間に制限がある特定技能1号の方が多く雇用され、安定した労働力の確保が難しくなっていたのです。
しかし、2023年の閣議決定により、特定技能1号の受け入れ対象である12分野のうち、介護分野以外の全ての分野において、特定技能2号を受け入れられるようになりました。
今後は様々な分野で特定技能2号の受け入れが広がっていくでしょう。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
参考:「特定技能ガイドブック」出入国在留管理庁
参考:特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) | 出入国在留管理庁
受け入れの際に企業側がすべき対応

ここでは、特定技能外国人や外国人技能実習生を受け入れる際、企業側がすべき対応について解説しています。
労働環境を整える
特定技能外国人の報酬額や労働時間は、日本人と同等でなければなりません。
また、研修・福利厚生施設の利用・その他待遇も日本人と同等である必要があります。
技能実習生についても、最低賃金以上の給与・同じ業務を行う日本人と同水準の給与を支払わなければなりません。
労働時間などにも気を配り、外国人労働者が働きやすい環境を整えましょう。
仕事の内容・私生活のルール等を確認する
事前に仕事の内容や現場の状況をしっかり説明することはもちろん、日本で生活する際のルールも外国人と一緒に確認しておきましょう。
外国人労働者には、登録支援機関などによる生活オリエンテーションや入国後講習で日本の生活に関する情報が提供されます。
しかし、それだけでは時間が短く不十分なので、外国人が日本の生活に適合できるよう住居の支援などをして、細かい点は丁寧に指導していく必要があるでしょう。
例えば、ゴミを捨てる際のルールや騒音の防止、近隣住民への挨拶などです。
自転車で通勤する外国人労働者も多いので、自転車の交通ルールだけでなく、実習先周辺の危険な箇所についても伝えておきましょう。
自動車学校などで外国人向けの交通安全教室が実施されていることもあるので、そういった行事も活用すると良いかもしれません。
また、海外の法律と日本の法律は異なるため、日本国内で違法となる行為に関しても説明しておくべきです。
外国人と積極的にコミュニケーションをとる
特に技能実習生の場合、入国前に日本語試験を受けているわけではないので、コミュニケーションがとりづらいかもしれません。
しかし、多くの技能実習生はやる気と目標を持って来日します。
技能実習生のモチベーションを保ったり、日本語能力を向上させたりするためにも、積極的に話しかけて信頼関係を築いていきましょう。
まとめ
本記事では、特定技能制度と技能実習制度の違いや制度の問題点、見直しの案などについて解説してきました。
特定技能制度・技能実習制度の問題点は下記の通りです。
- 技能実習制度の目的が果たされていない
- 技能実習現場の労働環境の悪さ
- 技能実習生の失踪問題
- 特定技能制度では安定した労働力の確保が難しい
上記の点を改善するため、下記のような制度の見直しが進められています。
- 技能実習制度に代わる新たな制度の創設
- 監理団体・受け入れ機関の適正化
- 「特定技能2号」の対象分野拡大
制度が見直されるとはいえ、受け入れ企業側も制度の課題を把握し、雇用契約を結んだ責任を持って外国人労働者が働きやすい環境を作っていくことが大切です。