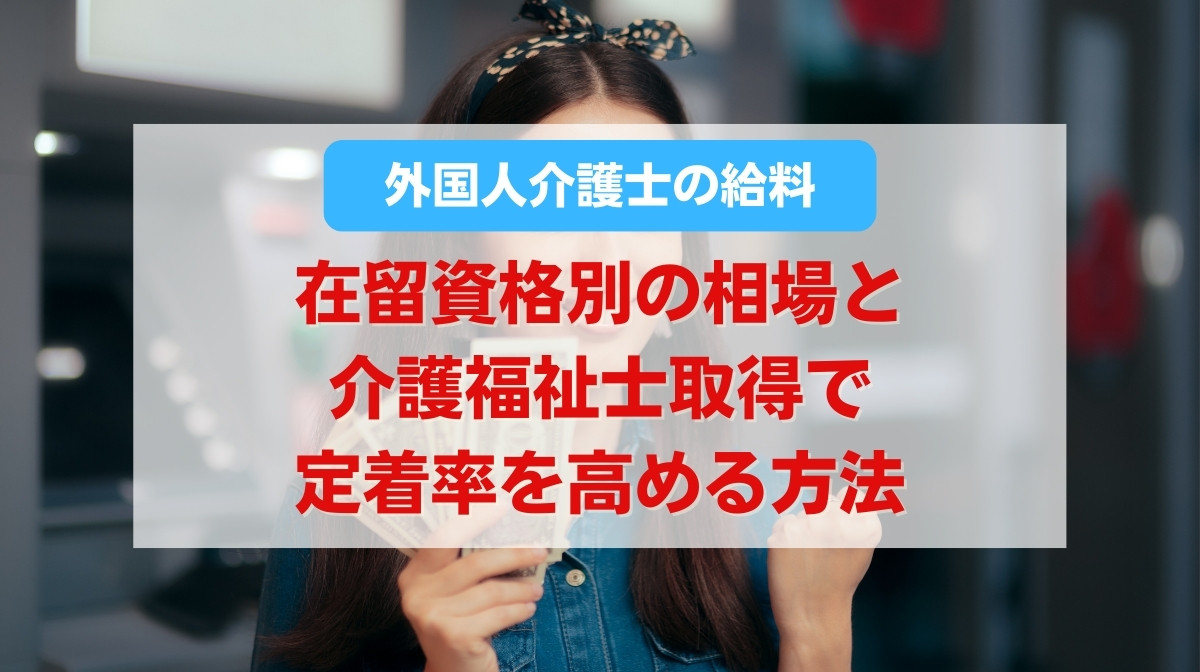「外国人介護士の給料は、日本人と比べてどのくらいが適正なのだろうか?」
「在留資格の制度が複雑で、給与がどうなるのかよくわからない…」
このようなお悩みをお持ちの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
深刻化する介護業界の人手不足を背景に、外国人介護士の存在感は日々増しています。彼らは今や、日本の介護現場を支える不可欠なパートナーです。しかし、その一方で、給与体系やキャリアパスの整備に課題を感じている事業所が多いのも事実です。
この記事では、在留資格ごとの給与相場から、介護福祉士の資格取得が職員と施設の双方にもたらす大きなメリット、そして資格取得の最大の壁となる日本語教育に対する具体的な支援策まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、外国人材の活用と定着率を向上させるための、明確な道筋が見えてくるはずです。
【在留資格別】外国人介護士の給料の現状と相場

まず、外国人介護士の給料を考える上で最も重要なのが「在留資格」の違いを理解することです。在留資格によって業務内容や求められるスキル、そして給与水準も大きく変わってきます。ここでは、介護分野で働く外国人が主に取得する4つの代表的な在留資格について、それぞれの給与の特徴を詳しく見ていきましょう。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人のための専門的な就労ビザです。介護福祉士国家試験に合格した者が対象となります。この資格を持つ人材は、介護に関する専門的な知識と技術を有していることの公的な証明があるため、即戦力として現場の中核を担うことが期待されます。
給与に関しては、当然ながら日本人介護福祉士と同等以上の待遇が求められます。厚生労働省の調査によれば、介護福祉士の資格を持つ職員は、資格を持たない職員に比べて平均給与が高い傾向にあり、この在留資格を持つ外国人も同様の給与体系が適用されます。
給与水準は施設の規模や地域によって異なりますが、各種手当を含めて安定した収入を得られることが一般的です。介護福祉士の平均月収は約35万円程度で、介護職の中では最も高い給与水準となっています。
さらに、在留資格「介護」の最大のメリットは、在留期間の更新に上限がないことです。条件を満たせば永続的に日本で働き続けることが可能であり、「永住者」の資格申請への道も開かれています。また、配偶者や子供を日本に呼び寄せる「家族滞在」ビザの取得も可能になるため、生活基盤を日本に築き、腰を据えて長く働きたいと考える外国人にとって、最終的な目標となる在留資格と言えるでしょう。
在留資格「特定技能1号」
在留資格「特定技能1号」は、深刻な人手不足が課題となっている特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度です。介護分野もその対象の一つであり、多くの施設で特定技能を持つ外国人が活躍しています。
この資格を得るためには、「介護技能評価試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)N4レベル」に合格する必要があります。つまり、介護の基本的な技能と、業務に必要な水準の日本語能力を併せ持っていることが証明された人材です。
給与水準については、法律で「日本人と同等以上の報酬を支払うこと」が厳格に定められています。これは、特定技能制度が、安価な労働力の確保ではなく、日本人と同等の労働者として適正に処遇することを目的としているためです。
したがって、給与額だけでなく、賞与や各種手当なども含めて、同じ業務に従事する日本人職員と比較して不利にならないような待遇を用意しなければなりません。特定技能1号で働く外国人材の給与は、約20.6万〜22.3万円程度となっています。
在留期間は通算で最長5年ですが、この期間中に介護福祉士の国家資格を取得することで、先述した在留資格「介護」への変更が可能になります。多くの特定技能介護士が、働きながら介護福祉士を目指しており、施設側の支援が彼らのキャリアを大きく左右します。
在留資格「技能実習」
技能実習制度は、もともと日本の進んだ技術や知識を開発途上国へ移転することを目的とした国際貢献のための制度です。そのため、労働力の需給調整を目的としたものではない、という点が特定技能とは大きく異なります。介護分野においても、日本の介護技術を学んでもらい、母国に帰国後、その国の福祉の発展に貢献してもらうことが期待されています。
技能実習生は、入国後に一定期間の講習を受けた後、実習実施機関である介護施設で働きながら実践的な技能を学びます。給与については、労働関係法令が適用されるため、最低賃金を上回ることはもちろん、他の日本人職員とのバランスを考慮した適切な設定が求められます。しかし、制度の目的が「実習」であるため、他の在留資格に比べると給与水準は低めになる傾向があります。給与は約17.8万〜18.2万円程度となっています。
技能実習を良好に修了した者は、帰国せずに「特定技能1号」へ移行することも可能です。多くの技能実習生が、日本での継続就労を希望しており、この制度は将来の特定技能人材や介護福祉士候補者を育成する入り口としての役割も担っています。
EPA(経済連携協定)に基づく候補者
EPA(経済連携協定)は、国と国との経済的な連携を強化するための取り組みの一環として、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から介護福祉士候補者を受け入れる制度です。この制度で来日する外国人は、日本の介護施設で就労・研修をしながら、介護福祉士の国家資格取得を目指します。
候補者の給与は、各施設との雇用契約に基づいて決定されますが、日本人職員と同等以上の処遇が原則とされています。また、資格取得までの間は、国からの助成金などの支援が受けられる場合もあります。給与は20万円台前半〜25万円程度が目安です。
EPA候補者は、資格取得への意欲が非常に高く、合格すれば在留資格「介護」を取得して、日本で継続的に就労することが可能です。国を挙げたプロジェクトであるため、入国前の日本語教育などが充実している一方、受け入れ施設側にも手厚い研修体制や学習支援が求められるのが特徴です。
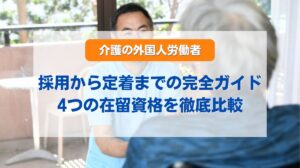
介護福祉士の資格取得が給与アップと人材定着に繋がる理由

「外国人スタッフの給料を上げてあげたいが、何を基準に評価すれば良いのだろうか」
「どうすれば長く私たちの施設で働いてもらえるのだろうか」
こうした悩みに対する最も明確で効果的な答えが、「介護福祉士」の資格取得を施設として全面的に支援することです。資格取得は、職員本人にとって大きなメリットがあるだけでなく、受け入れる施設側にも計り知れない恩恵をもたらします。
【職員側のメリット】キャリアパスと生活の安定
外国人スタッフにとって、介護福祉士の資格を取得することは、単なるスキルアップ以上の、人生を左右するほどの大きな意味を持ちます。
第一に、直接的な給与の大幅なアップが期待できます。多くの施設では資格手当が支給されるほか、専門職として基本給そのものが見直されるケースがほとんどです。これにより、経済的な安定が得られ、仕事へのモチベーションが大きく向上します。
第二に、在留資格の面で大きなメリットがあります。「特定技能」や「技能実習」といった在留期間に上限のある資格から、更新の上限がない在留資格「介護」へ変更できることは、最大の魅力です。これにより、「いつかは国に帰らなければならない」という不安から解放され、日本で長期的なキャリアプランを描くことが可能になります。
さらに、在留資格「介護」を取得すれば、母国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せる「家族滞在」ビザの申請が可能になります。家族と共に日本で生活できることは、何物にも代えがたい喜びであり、日本での定着を強く後押しする要因となります。
そして、専門職としてのキャリアの広がりも重要です。資格を持つことで、サービス提供責任者やチームリーダーといった役職に就く道も開かれ、より専門性が高く、やりがいのある業務に従事できるようになります。これは、彼らのプロフェッショナルとしての誇りを育み、介護という仕事への情熱をさらに深めることに繋がるのです。
【施設側のメリット】サービスの質向上と人材確保
職員への支援は、単なるコストではありません。それは、施設の未来を創るための最も賢明な「投資」です。
最も直接的なメリットは、介護サービスの質の向上です。介護福祉士は、医学、心理学、介護技術など幅広い専門知識を体系的に学んでいます。資格を持つ職員が増えることで、根拠に基づいた質の高いケアが提供できるようになり、認知症ケアや看取りといった専門的な場面での現場対応力も格段に強化されます。
そして、経営上の最大の課題である人材の定着に絶大な効果を発揮します。施設が明確なキャリアパス(=介護福祉士への道)を示し、そのための支援を惜しまない姿勢を見せることで、外国人スタッフは「この施設は自分の成長を応援してくれる」「ここでなら将来を描ける」と感じるようになります。これにより、安易な離職や帰国を防ぎ、経験を積んだ貴重な人材を安定的に確保することが可能になります。
また、資格を取得した外国人スタッフの存在は、組織全体に良い影響を与えます。彼らが後輩の外国人職員を指導する立場になることで、新たな人材の受け入れや教育体制が強化されます。さらに、資格取得という成功体験は、他の日本人職員にとっても良い刺激となり、施設全体の学習意欲や向上心を高めるという、副次的な効果も期待できるのです。
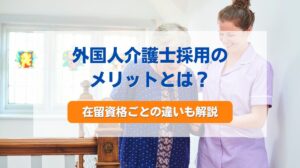
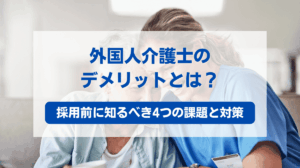
介護福祉士国家試験の壁|多くの外国人がつまずく2つのポイント

多くのメリットがある介護福祉士資格ですが、外国人にとってその合格への道のりは決して平坦なものではありません。特に、多くの受験者が突破できずに涙をのむ、大きな2つの「壁」が存在します。施設として効果的な支援を行うためには、まずこの壁が何であるかを正確に理解しておく必要があります。
専門知識の壁:介護分野の深い理解が必要
介護福祉士国家試験は、単なる実務経験の延長線上で合格できるほど甘くはありません。人間の心と身体の仕組み、認知症や障がいの理解、医療との連携、そして日本の複雑な介護保険制度や関連法規など、非常に広範で深い専門知識が問われます。
日々、現場で優れた介護を実践している外国人スタッフであっても、それらの知識を体系的に学び、試験問題としてアウトプットする訓練は別途必要です。特に、日本の社会保障制度の歴史的背景や文化的文脈を理解することは、海外で育った彼らにとっては大きなハードルとなり得ます。この専門知識の壁を乗り越えるには、計画的な学習と試験対策が不可欠です。
日本語の壁:試験合格には「JLPT N2」レベルの読解力が必要
専門知識の壁以上に高く険しいのが、「日本語の壁」です。日常的なコミュニケーションや業務上の指示が問題なく理解できるスタッフであっても、国家試験の日本語は全くの別次元です。
試験問題で使われる語彙は専門的で硬い表現が多く、独特の言い回しが多用されます。選択肢も紛らわしいものが多く、文章の細かいニュアンスを正確に読み取る高度な読解力がなければ、正答を導き出すことは極めて困難です。
一般的に、介護福祉士国家試験に合格するためには、日本語能力試験(JLPT)のN2レベル以上の日本語能力が必要だと言われています。JLPT N2は、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルと定義されており、新聞の解説記事などを読んで内容を理解できる能力が求められます。
このレベルに達していないと、たとえ介護の知識があったとしても、問題文の意味を誤解してしまい、点数を落としてしまうのです。多くの外国人受験者が、この日本語の壁に阻まれ、合格を逃しているのが現状です。
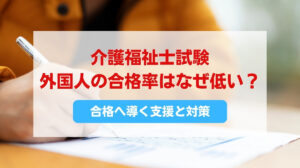
外国人スタッフの資格取得、施設ができる3つの支援策
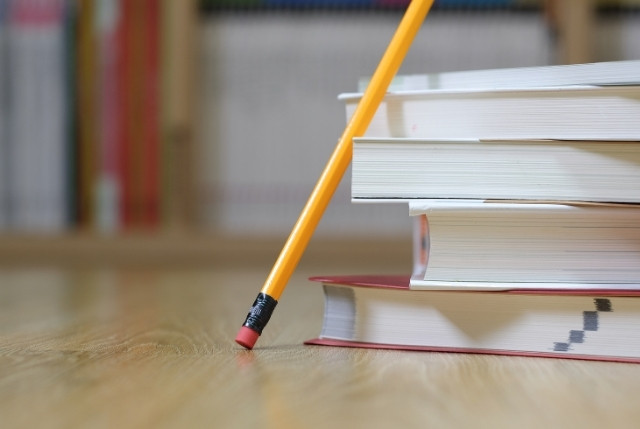
職員が直面する「専門知識」と「日本語」という2つの大きな壁。これを乗り越えるためには、本人の努力はもちろんのこと、雇用する施設側の戦略的なサポートが決定的に重要となります。
職員任せにするのではなく、組織として支援体制を構築することで、合格の可能性は飛躍的に高まります。ここでは、明日からでも実践できる3つの具体的な支援策をご紹介します。
学習時間の確保とシフトの配慮
介護の仕事は心身ともに負担が大きく、不規則な勤務形態も多いのが特徴です。仕事で疲れ切った後に、試験勉強のための時間を確保するのは、本人にとって至難の業です。施設側ができる最も基本的な支援は、彼らが学習に集中できる環境を整えてあげることです。
例えば、試験が近づいてきた時期には夜勤を減らす、連休を取りやすくするなど、シフト面での配慮が有効です。また、施設内の休憩室や空きスペースを自習室として開放したり、外部の研修や模擬試験に参加するための時間を勤務として認めるなどの支援も、職員の学習意欲を後押しできるでしょう。
受験費用や研修費用の補助
外国人スタッフにとって、日本での生活費を賄いながら、高額な受験料や教材費、研修参加費などを捻出するのは大きな経済的負担となります。施設として、これらの費用の一部または全額を補助する制度を設けることは、非常に直接的で効果的な支援策です。
資格取得支援規定などを整備し、「合格した場合には全額支給」「受験費用を無利子で貸与」といった具体的なルールを設けることで、職員は経済的な心配をせずに学習に専念できます。この費用補助は、施設が本気で彼らの成長を応援しているという強いメッセージにもなります。
最も重要!効果的な日本語教育の提供
数ある支援策の中で最も重要であり、かつ合格の成否を分けるのが、効果的な日本語教育の提供です。前述の通り、介護福祉士試験の最大の壁は日本語です。この壁を乗り越えるためのサポートなくして、合格はあり得ません。特に、日常会話レベルではなく、試験問題に対応できる「読解力」と「専門用語の理解」を強化する教育が不可欠です。
しかし、多くの施設にとって、これが一番の悩みどころではないでしょうか。
「日本語を専門的に教えられる日本人が施設内にいない」
「日々の業務が忙しく、教育にまで手が回らない」
「外部の日本語学校に通わせるにも、コストがかかりすぎる」。
こうした課題を抱え、有効な手を打てずにいるケースが非常に多いのが実情です。
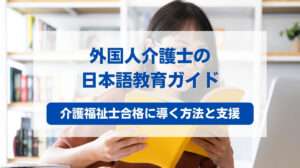
日本語教育の課題を解決!「日本語カフェ」オンライン講座のご案内

現場での日本語教育は難しい、業務が忙しくて教えられない…。そんなジレンマを抱える施設様にこそ、オンライン日本語講座「日本語カフェ」の活用を強くおすすめします。
日本語カフェは、多忙な介護現場のニーズに応え、コストを抑えながら、外国人スタッフ一人ひとりの自発的な学習を最大限に引き出すことができる環境を提供します。
まずは合格への第一歩!「JLPT合格コース」
介護福祉士受験の強固な土台となる日本語能力。特に、合格ラインとされるN2レベルへの到達を最短ルートで目指せるのが、「日本語カフェ」の「JLPT合格コース」です。
このコースの最大の特徴は、合格から逆算して設計された、無駄のない学習カリキュラムにあります。長年の指導経験を持つプロの日本語講師が監修し、「何を、どの順番で学べば合格できるか」が体系化されているため、学習者は迷うことなく効率的に学習を進めることが可能です。
また、学習はスマートフォンやPCで完結するオンライン動画形式。1回10分程度の短い講義も多く、多忙な介護の仕事の合間、例えば通勤時間や休憩時間といったスキマ時間を有効に活用して、自分のペースで学習を続けられます。
反復練習できるドリルや模擬試験も豊富に用意されており、インプットとアウトプットを繰り返すことで、着実に日本語能力が定着していきます。
施設管理者様にとっては、管理の手軽さとコストパフォーマンスの高さも大きなメリットです。スタッフ一人ひとりの学習進捗状況は管理画面で一目で把握できるため、煩雑な管理業務は不要。新たに日本語講師を雇用する高額な人件費や、外部研修への派遣コストを大幅に削減できます。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
試験直結の対策なら「介護福祉士 合格対策集中講座」
すでにある程度の日本語力(JLPT N2レベル)を持つスタッフや、JLPTコースと並行してより専門的な対策を進めたい方には、「介護福祉士 合格対策集中講座」が最適です。
この講座は、4ヶ月間で介護福祉士国家試験の合格を目指す、短期集中型のプログラムです。介護福祉士の資格を持つ専門講師が、膨大な試験範囲の中から「ここだけは押さえるべき」という重要ポイントを絞り込み、動画と豊富な演習問題で徹底的に解説します。
特に、多くの受験者が苦手とする過去問題の演習に力を入れているのが特徴です。講師が一緒に問題を解きながら、なぜその選択肢が正解(または不正解)なのかを論理的に解説するため、本番の試験で応用できる思考力が身につきます。
さらに、この講座の受講期間中は、先にご紹介した「JLPTコース」の全コンテンツも使い放題になります。これにより、介護の専門知識の学習と、その土台となる日本語能力の強化を、同時並行で進めることが可能です。日本語に不安を感じながら専門分野を学ぶ外国人スタッフにとって、これ以上ない心強いサポートとなるでしょう。
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!

- ■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- ■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- ■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
貴施設の外国人スタッフの現在のレベルや目標に合わせて、最適なプランをご提案させていただきます。またはお気軽にお問い合わせください。
\ お問い合わせはこちら/
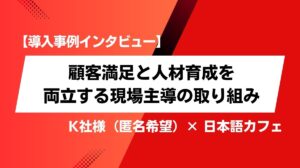
外国人介護士への適切な支援が、施設の未来を創る

今回は、外国人介護士の給与の実態から、彼らのキャリアアップと人材定着を実現するための鍵となる「介護福祉士」資格取得の重要性について、詳しく解説してきました。
外国人スタッフは、もはや単なる「労働力」ではありません。彼らは、これからの日本の介護現場を共に創り上げていく、かけがえのない「パートナー」です。
彼らが経済的な不安なく、キャリアへの希望を持って日本で安心して長く働ける環境を整えることこそが、深刻な人材不足を解消し、ひいては貴施設の介護サービスの質を未来にわたって向上させることに繋がります。
「日本語カフェ」では、個別の課題やスタッフの状況に合わせた、最適な日本語教育プランをご提案いたします。外国人材の教育に関するお悩みやご質問など、どんな些細なことでも、ぜひお気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから/