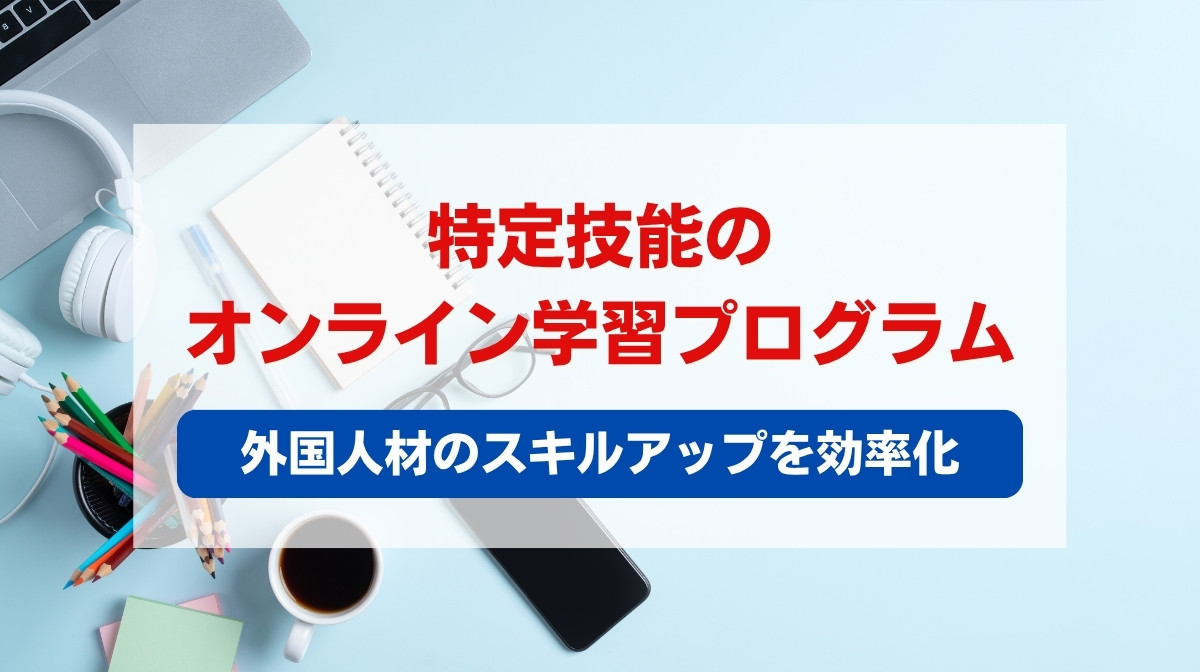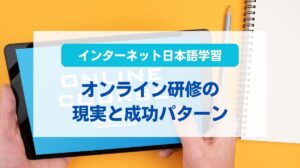少子高齢化が進む日本において、外国人材はもはや事業の維持と発展に欠かせない存在です。中でも、特定技能の在留資格を持つ外国人スタッフは、即戦力として多くの現場で活躍しています。しかし、彼らを雇用し、育成していく過程で、多くの企業の担当者様が共通の課題に直面しているのではないでしょうか。
例えば、日々の多忙な業務の傍ら、外国人スタッフ一人ひとりの学習進捗を細かく管理することに、大きな手間を感じてはいないでしょうか。また、受け入れ人数が増えるにつれて、集合研修の会場費や教材費といったコストが増大し、費用対効果に疑問を感じる場面もあるかもしれません。
さらに、「スタッフが自発的に学んでくれるような、質の高い教材が見つからない」「特定技能1号から2号へのステップアップを支援したいが、高度な専門スキルを教えるための研修体制が整っていない」といった声もよく耳にします。
これらの課題は、一つひとつは小さく見えても、積み重なることで企業の成長を妨げる要因となりかねません。この記事では、そうした課題を解決するための具体的な手法について、詳しく解説していきます。
\ 日本語学習システム/
そもそも特定技能制度とは?1号と2号の違いを解説

課題解決の方法を探る前に、まずは特定技能制度の基本について改めて確認しておきましょう。
特定技能制度とは、国内の人材確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。この制度は「特定技能1号」と、より熟練した技能水準が求められる「特定技能2号」に分かれています。
特定技能1号は、特定の産業分野において「相当程度の知識または経験」を持つ外国人向けの資格です。一方、特定技能2号は、同分野で「熟練したスキル」を持つ人材を対象としており、より高度な業務を任せることが期待されます。両者の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| スキル水準 | 相当程度の知識または経験 | 長年の実務経験等に基づく熟練したスキル |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 上限なし(更新が必要) |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 永住権申請 | 対象外 | 長期的な在留により要件を満たす可能性あり |
2025年現在、政府は特定技能2号の対象分野拡大を積極的に進めており、外国人材が日本で長期的にキャリアを築ける環境が整いつつあります。企業にとっては、1号人材を2号へと育成していくことが、安定した労働力の確保に繋がります。
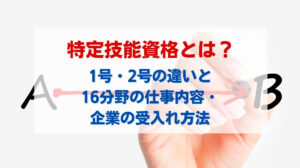
特定技能2号への移行で得られる企業側の大きな価値

特定技能1号の在留期間は通算5年という上限がありますが、2号へ移行することで、この上限がなくなります。これは、企業にとって非常に大きな意味を持ちます。
時間とコストをかけて育成した貴重な人材が、5年で帰国してしまうという事態を避けられるのです。
- 熟練した人材の永続的な確保
-
2号へ移行したスタッフは、在留期間を更新し続けることで、長期的に日本で働き続けることが可能になります。これは、企業が熟練したスキルを持つ人材を安定して確保できることを意味します。技術やノウハウの継承という観点からも、企業の持続的な成長を支える基盤となるでしょう。
- 現場のリーダー育成
-
特定技能2号に求められるのは、単なる作業員としてではなく、現場のリーダーや指導者としての役割です。高いスキルを持つ彼らが他の技能実習生や後輩の特定技能1号スタッフを指導する役割を担うことで、チーム全体の生産性や技術力の底上げが期待できます。
- 事業の安定と拡大
-
外国人材の離職率の高さに悩む企業は少なくありません。しかし、2号への移行という明確なキャリアパスを示すことは、スタッフのモチベーションを高め、定着率を向上させる上で非常に大きな意味を持ちます。貴重な戦力が長く会社に定着することで、企業の技術力は安定し、将来的な事業拡大に向けた力強い土台が築かれます。

特定技能2号の合格に向けて企業ができるサポートとは

スタッフの2号移行を後押しするためには、企業の積極的なサポートが欠かせません。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
まず、スタッフが安心して学習時間を確保できるよう、シフトを調整するといった物理的な配慮です。また、受験料や教材費などを企業が一部または全額補助する費用面のサポートも、スタッフの学習意欲を高める上で大きな後押しとなります。
そして、これらの中でも特に重要なのが、スタッフが効率的に学べる「最適な学習環境の提供」です。特に、特定技能2号の試験では、より高度で専門的な知識が問われます。独学での合格は容易ではありません。
だからこそ、専門分野の知識を体系的に、そして分かりやすく学べるオンライン学習プログラムの活用が、合格への道のりを大きく切り拓くのです。

特定技能2号試験に合格した事例を紹介

特定技能制度の運用が進む中で、実際に外国人労働者が特定技能2号試験に合格した事例が各分野で増えています。ここでは、外食業および建設業での具体的な合格事例を紹介し、企業による支援の取り組みや外国人材のキャリアアップの実例を見ていきます。
磯部クオリティーサービス:従業員の2号試験合格を支援した外食業の事例
外食業を中心に外国人材を受け入れている 有限会社 磯部クオリティーサービス では、特定技能1号として勤務していた外国人従業員が、外食業特定技能2号試験に合格した事例が報告されています。
この取り組みでは、学習支援プログラムを活用し、試験範囲に対応した教材提供や、オンラインでの日本語・専門知識の指導が行われました。従業員は勤務後も学習を継続し、日々の努力の結果、見事に試験に合格。企業側も「合格者の成長が、他の外国人従業員のモチベーション向上にもつながっている」とコメントしています。
磯部クオリティーサービスの事例は、企業が主体的に従業員のスキルアップを支援する姿勢の重要性を示しています。支援は、単に試験合格を目指すためのものではなく、外国人労働者が長期的にキャリアを形成し、組織の中核人材へと成長するための基盤づくりにもつながっています。
出典:Japan Job School「外食業特定技能2号試験合格企業インタビュー」
株式会社A(建設業):技能評価試験に挑戦する外国人材の支援事例
東京都大田区に拠点を置く 株式会社A(仮称・建設業) では、長期間にわたり建設現場で経験を積んできたベトナム出身の従業員3名が、社内および支援機関の協力のもとで試験勉強に取り組みました。
株式会社A(仮称)では、日本語教育や試験対策の支援を提供し、実務経験を通じてスキルの習熟を促進。日常業務を通じて実務力を養いながら、日本語・専門知識面でのサポートも行いました。
結果として全員が評価試験に合格し、さらなるスキルアップと安定した就労につなげています。

外国人材育成の現場で浮き彫りになる企業の共通課題

ここまで紹介した事例からも分かるように、特定技能2号への移行を実現するには、企業のサポート体制が欠かせません。しかし実際の現場では、次のような共通課題に直面している企業が少なくありません。
- 日々の業務が忙しく、外国人スタッフ一人ひとりの学習進捗を継続的に管理する余裕がない
- 専門知識や技能を教えられる指導者が社内におらず、学習が個人任せになっている
- 集合研修の会場費・教材費など、教育コストが増加し続けている
- スタッフの自主的な学習意欲を維持できる教材や仕組みが見つからない
これらの課題は、1つひとつは小さな負担に見えても、積み重なることで大きな組織的課題となります。十分な学習機会を確保できなければ、せっかく育てた人材が2号へのステップアップを諦めてしまうケースや、キャリア停滞による離職リスクを抱える可能性もあります。
では、こうした課題をどのように解決すればよいのでしょうか。その鍵となるのが、特定技能向けのオンライン学習プログラムの活用です。
その課題、特定技能向けのオンライン学習プログラムで解決しませんか?

人材育成に関する数々の課題を解決する手段として、今、多くの企業が注目しているのが「オンライン学習プログラム」の活用です。現在、人材育成の手法は大きく変化しており、特に外国人材向けの研修において、オンラインでの学習はスタンダードになりつつあります。
オンライン学習プログラムの大きな特徴は、時間や場所に縛られずに学べる点にあります。外国人スタッフは、自身のスマートフォンやタブレットを使い、休憩時間や帰宅後などの隙間時間を利用して、自分のペースで学習を進めることが可能です。
企業側にとっても、オンライン学習は大きな価値をもたらします。専用の管理システムを通じて、どのスタッフが、どの項目を、どこまで学習しているのかをリアルタイムで把握できます。これにより、教育担当者の管理業務が大幅に効率化され、より重要な業務に時間を割けるようになります。
画一的な集合研修ではなく、個々のスキルや理解度に合わせた、きめ細やかなサポートを実現するための基盤となるのです。
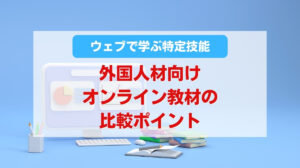
企業がオンライン学習サービスを利用する3つの価値

オンライン学習プログラムを導入することは、具体的にどのような価値を企業にもたらすのでしょうか。ここでは、代表的な3つの側面からその中身を掘り下げていきます。
1. 研修コストの大幅な削減
一つ目は、研修にかかるコストを大きく削減できる点です。従来型の集合研修では、講師への謝礼はもちろん、会場のレンタル費用、全スタッフの交通費、そして資料の印刷費など、多岐にわたる経費が発生していました。受け入れ人数が増えれば、その負担はさらに重くなります。
オンライン学習サービスは、多くが月額制のプランを提供しており、一度導入すれば低コストで質の高い研修を提供できます。これにより、人材育成の費用対効果を大きく高めることが可能になります。
2. 教育担当者の負担軽減
二つ目は、教育担当者の業務負担を劇的に軽くできる点です。多くのオンライン学習プラットフォームには、学習進捗を管理するための機能が備わっています。担当者は管理画面にログインするだけで、スタッフ一人ひとりの学習時間や理解度テストの結果などを一覧で確認できます。
進捗が遅れているスタッフに個別に声をかけるなど、的を絞ったフォローが可能になり、全体の管理にかかる時間を大幅に短縮できるのです。個別の質問対応や習熟度の確認といった業務も、プラットフォームを通じて効率的に行えるようになります。
3. 均一で質の高い教育環境の提供
三つ目は、すべてのスタッフに対して、均一で質の高い教育環境を提供できることです。集合研修では、どうしても講師のスキルや経験によって教育の質にばらつきが生じがちです。しかし、オンライン学習であれば、トップクラスの講師による質の高い解説動画を、誰もがいつでも視聴できます。
さらに、外国人材向けに開発されたサービスの場合、母語の字幕や音声解説が付いていることも少なくありません。言語の壁を感じることなく、専門的な内容でも深い学びを提供できる環境は、スタッフのスキルアップと定着率の向上に大きく貢献します。
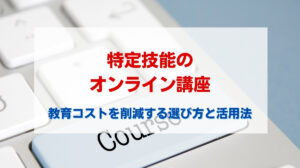
失敗しないオンライン学習プログラムの選び方

では、数あるサービスの中から、自社に最適なオンライン学習プログラムをどのように選べばよいのでしょうか。ここでは、選定時に確認すべき4つの基準を解説します。
1. 対応言語と学習サポートの範囲
まず確認したいのが、スタッフの母語に対応しているかどうかです。特に専門的な内容を学ぶ際、母語での解説があるかないかで理解度は大きく変わります。教材のテキストだけでなく、動画の字幕や音声が多言語に対応しているかを確認しましょう。
また、学習中に生じた疑問を母語で質問できるサポート窓口があれば、スタッフはより安心して学習を進められます。
2. カリキュラムの実践性
次に、カリキュラムが試験合格という目的に沿った、実践的な内容であるかを見極める必要があります。特定技能試験の出題範囲をすべて網羅していることはもちろん、インプットした知識を確認するための演習問題が豊富に用意されているかが重要です。
単に動画を視聴するだけでなく、実際に問題を解くことで、試験本番で通用する力が養われます。
3. 管理機能の使いやすさ
教育担当者にとって、管理機能の使いやすさは非常に重要です。管理者としてログインした際に、スタッフ一人ひとりの学習状況を直感的かつ詳細に把握できるかを確認しましょう。
多くのサービスでは無料トライアルやデモ画面の提供を行っているので、実際に操作してみて、自社の運用に合うかどうかを確かめることをお勧めします。
4. 料金プランの柔軟性
最後に、料金プランが自社の規模や状況に適しているかを確認します。受け入れ人数に応じたプランが用意されているか、将来的に人数が増減した場合に柔軟に対応できるか、といった視点で比較検討しましょう。
必要なサービスだけを選んで組み合わせられる、カスタマイズ性の高いプランを提供しているサービスもあります。
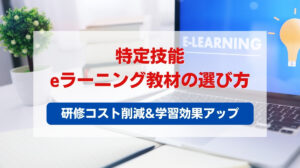
日本語カフェ【特定技能1号・2号合格コース】ですべての課題を解決
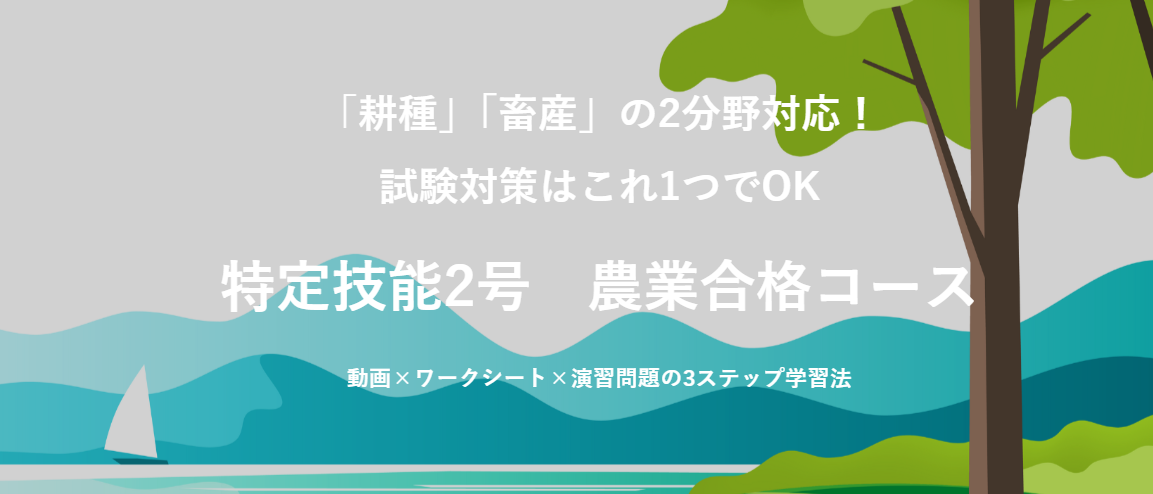
外国人スタッフの特定技能の習得をもっと簡単に、それでいて大幅なコストカットを実現したいなら、日本語カフェ『特定技能1号・2号合格コース』の利用がおすすめです。これまで述べてきた、企業が抱える課題やサービス選定の基準をすべて満たす、最適な学習プラットフォームです。
特徴1:合格に特化した動画カリキュラム
学科試験と実技試験の合格に特化した、分かりやすい動画カリキュラムが使い放題です。1本あたり15分程度と集中力を維持しやすい長さにまとめられており、すべての出題範囲を網羅しています。専門用語や複雑な知識が求められる内容でも、母語のスライドと音声による丁寧な解説で、誰でも体系的に理解を深めることが可能です。
特徴2:独自の「3ステップ学習法」
日本語カフェでは、知識の定着を最大化するために開発された、オリジナルの「3ステップ学習法」を採用しています。
- 解説動画を視聴する
- まず、会員サイトで各国語に対応した解説動画を視聴し、要点をインプットします。
- ワークシートに記入する
- 次に、動画と連動したワークシート(穴埋め問題)に実際に書き込むことで、記憶を強化します。
- 演習問題を解く
- 最後に、本番同様の形式で作成された大量のオリジナル演習問題を繰り返し解き、実践力を高めます。 この学習サイクルを通じて、どんな問題が出ても対応できる確かな学力と自信を育みます。
特徴3:日本語教育のプロが監修
厳しい審査をパスした一流の日本語教師が監修した、N5からN1までの日本語能力試験(JLPT)合格コースも併せてご利用いただけます。特定技能の学習だけでなく、コミュニケーションの基礎となる日本語力の向上も全面的にサポートできるため、幅広いレベルの学習ニーズに応えることが可能です。
特定技能2号・農業に3ヶ月で合格!

特定技能1号として日本で働いていたSさんは、在留期間が最長5年までという制限に不安を感じ、「もっと長く日本で働き、将来は家族とも安心して暮らしたい」という目標を持ちました。
その思いから特定技能2号の取得を決意。毎日欠かさず学習を続け、講師とのレッスンや教材を活用しながら知識を積み重ね、3か月で合格を果たしました。
- 学習方法・スケジュール
- 学習期間:2025年2月〜5月(約3か月)
- 使用教材:2号農業用テキスト、支援機関のビデオ教材(日・技能対応)
- 学習スタイル:
- 週3回、母語講師との日本語レッスンを1時間実施
- 毎朝 6:00~7:30 に集中して勉強
- ビデオ教材を繰り返し視聴し知識を定着させる
- 合格のコツ・アドバイス
- 分からないことは必ず質問すること
- 漢字や専門用語は「書けなくても見て覚える」ことが大切
- 忙しくても、毎日少しずつ継続することが合格への近道
合格後は、これまでの経験を活かしつつ現在の職場で長期的に働き続け、さらにスキルを磨いていきたいと考えています。2号資格によって安定した生活の基盤が整い、将来の可能性が大きく広がったと感じています。
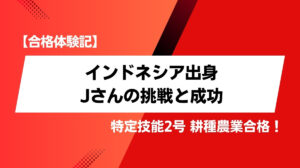
まとめ

2025年以降、日本国内の労働力人口の減少はさらに加速していくと見込まれます。そのような状況下で企業が持続的に成長していくためには、外国人材の活躍が不可欠です。そして、彼らが日本で安心して長く働き続けるためには、企業による継続的な学習環境の提供と、明確なキャリアパスの提示がますます求められます。
オンライン学習プラットフォームの活用は、研修コストや管理の負担を軽減するという企業側の価値だけでなく、外国人スタッフのスキルアップと定着率の向上に大きく貢献します。
まずは資料請求や無料相談から、自社の課題を解決するための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。専門のコンサルタントが、あなたの企業の状況に合わせた最適な活用法を提案します。その他、ご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\ ご相談はお気軽に/