介護現場において、外国人スタッフが利用者さんと円滑にコミュニケーションを取ることは、質の高いケアを提供するために欠かせません。
しかし、日本語の敬語や丁寧な言葉遣い、文化的なマナーに慣れていない外国人スタッフにとって、適切な表現を習得することは容易ではありません。
そのため、外国人スタッフが日本の介護現場で求められる言葉遣いや接し方を体系的に学べるようにサポートする必要があります。
本記事では、外国人スタッフが介護現場で実践しやすい基本の挨拶や声かけ、利用者さんの体調を確認するための会話例、同僚との円滑な連携のためのコミュニケーション方法などを詳しく解説します。
また、実践的な会話練習の方法や、文化的な違いを考慮した指導のポイントについても紹介します。
ぜひ外国人スタッフが自信を持って働ける環境を作るための参考にしてください。
- 介護の現場でよく使う会話例
- 同僚との連携をスムーズにする会話例
- 外国人スタッフ向け 会話練習の方法
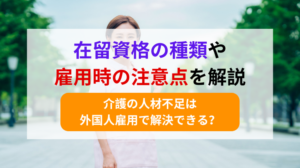
介護現場でよく使う会話例

基本の挨拶・声かけ
介護の仕事は、利用者さんとの信頼関係を築くことが非常に重要です。
そのため、日々の挨拶や声かけを丁寧に行うことが、良好なコミュニケーションの第一歩となります。
- 出勤時、退勤時の挨拶
- 出勤時

「おはようございます。今日からよろしくお願いします。」
「おはようございます。〇〇さんの担当をさせていただきます。」- 退勤時


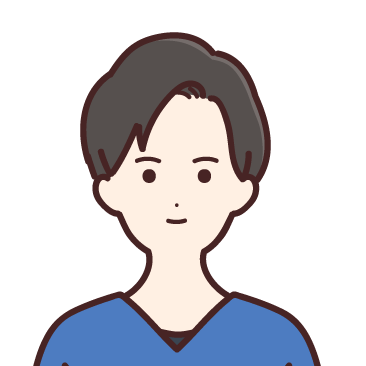
「お先に失礼します。お疲れ様でした。」
「お先に失礼します。何かありましたら、〇〇さんに申し送りしておきます。」
- 利用者さんへの挨拶


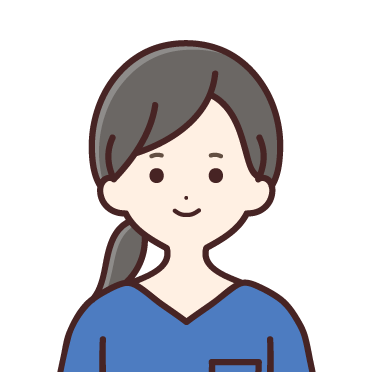
「〇〇さん、おはようございます。今日も良い一日になりますように。」
「〇〇さん、こんにちは。お元気ですか?」
「〇〇さん、こんばんは。ゆっくり休んでくださいね。」
「〇〇さん、お変わりありませんか?」
(入室時)「失礼します。」
(退室時)「失礼しました。」
- 初めて会う利用者さんへの自己紹介


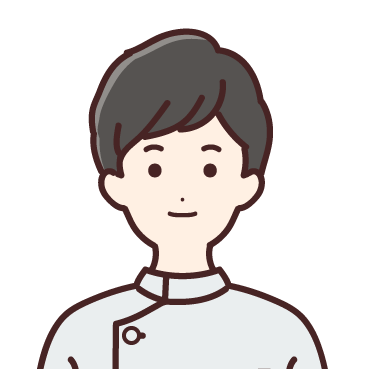
「初めまして。〇〇と申します。今日から〇〇さんの担当をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。」
「〇〇さん、初めまして。〇〇です。何かありましたら、いつでもお声かけください。」
- 名前の確認



「〇〇様でいらっしゃいますね?」
「お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「〇〇さんとお呼びしてもよろしいですか?」
- 体調を気遣う言葉


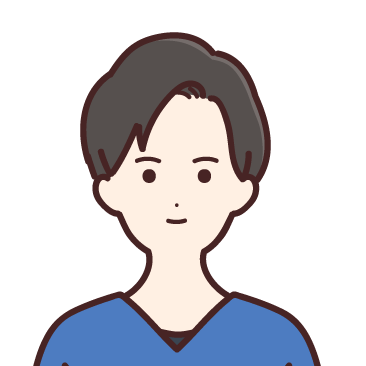
「〇〇さん、今日の体調はいかがですか?」
「何か気になることはありますか?」
「どこか痛いところはありますか?」
「気分は悪くないですか?」
「ゆっくり休んでくださいね。」
利用者さんの状態を把握するための会話
利用者さんの状態を正確に把握することは、適切なケアを提供する上で不可欠です。
体調の変化、痛み、食事、排泄、睡眠など、様々な側面から情報を収集する必要があります。
- 体調に関する質問


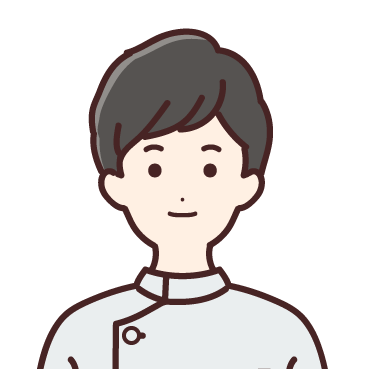
「今日は体調はいかがですか?」
「昨日と比べて、何か変わったことはありますか?」
「熱はありますか?」
「咳は出ますか?」
「息苦しさはありませんか?」
「だるさはありませんか?」
「気分が悪いところはありませんか?」
- 痛みに関する質問


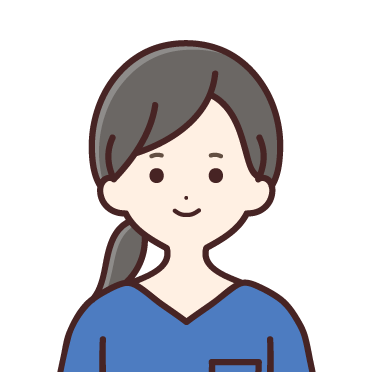
「どこか痛いところはありますか?」
「いつから痛みますか?」
「どんな痛みですか?(ズキズキ、チクチク、ジンジンなど)」
「どのくらいの痛みですか?(痛みの度合いを1から10で表すと?)」
「痛みを和らげるために、何かしていますか?」
「痛み止めは飲みましたか?」
- 食事に関する質問



「今日の食事はおいしかったですか?」
「何か食べたいものはありますか?」
「食欲はありますか?」
「残されたものはありますか?」(食事介助後)
「飲み込みにくいものはありますか?」
「アレルギーはありますか?」
- 排泄に関する質問


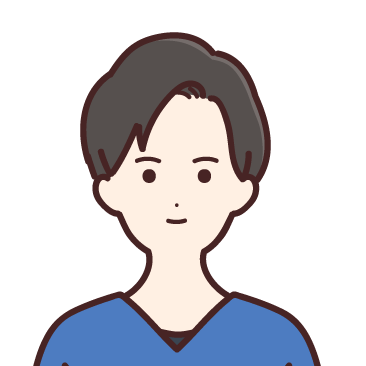
「トイレに行きたいですか?」
「便は出ましたか?」
「尿の色は普通ですか?」
「回数はいつもと変わりませんか?」
「もしトイレに行きたいときは、遠慮なく教えてくださいね。」
- 睡眠に関する質問


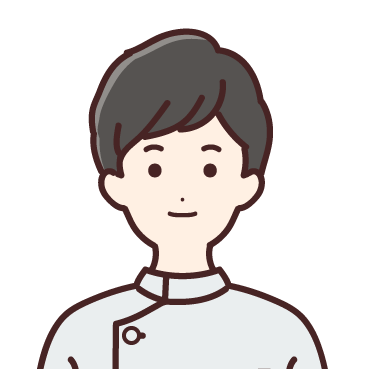
「昨夜はよく眠れましたか?」
「途中で目が覚めましたか?」
「睡眠時間はどのくらいでしたか?」
「寝つきは悪くなかったですか?」
「夜中にトイレに行きましたか?」
- 希望や要望を聞き取る


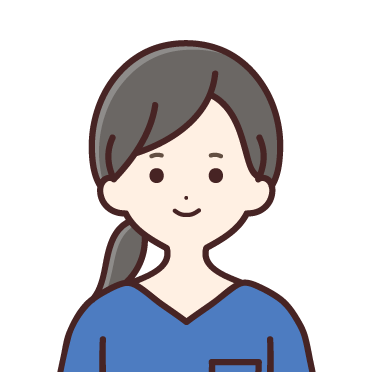
「何かしたいことはありますか?」
「何か困っていることはありますか?」
「お手伝いできることはありますか?」
「何かご希望はありますか?」
「何か気になることはありますか?」
「〇〇さんは、どのようにするのが好きですか?」
介助・ケアで使う指示・説明の会話
介助やケアを行う際には、利用者さんに状況を説明し、協力を得ることが大切です。
丁寧な言葉遣いで、分かりやすく指示を出すように心がけましょう。
- 移動介助



「〇〇さん、これから立ち上がりますよ。ゆっくりいきましょう。」
「少し体を支えますね。」
「(車椅子へ)こちらに座ってください。」
「(車椅子から)ゆっくり立ち上がりましょう。」
「安全のために、ベルトを締めますね。」
「ゆっくり歩きましょう。私が支えます。」
「段差がありますので、お気を付けください。」
「〇〇さん、どちらへ行きたいですか?」
- 食事介助


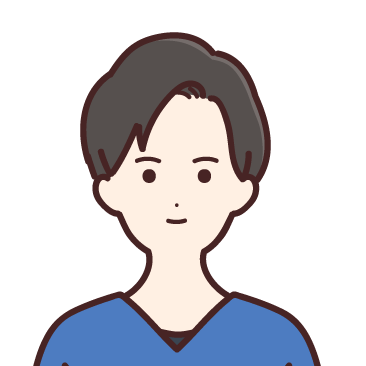
「〇〇さん、お風呂の準備ができました。入りましょう。」
「お湯加減はいかがですか?」
「熱かったら、遠慮なく言ってくださいね。」
「体を洗いますね。どこから洗いましょうか?」
「滑りやすいので、気を付けてください。」
「シャンプーしますね。目に泡が入らないようにします。」
「温まってくださいね。」
「湯冷めしないように、すぐにお着替えしましょう。」
- 更衣介助


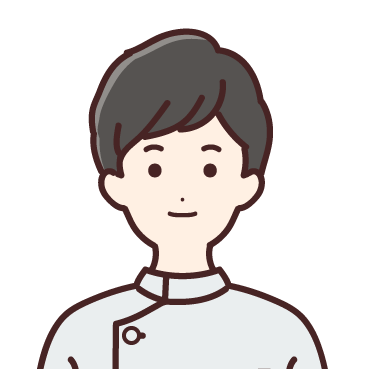
「〇〇さん、お着替えしましょう。」
「腕を上げてください。」
「ボタンを留めますね。」
「どちらから着替えましょうか?」
「着替えやすいように、お手伝いしますね。」
「今日は暖かいので、薄着でも大丈夫ですよ。」
- 排泄介助


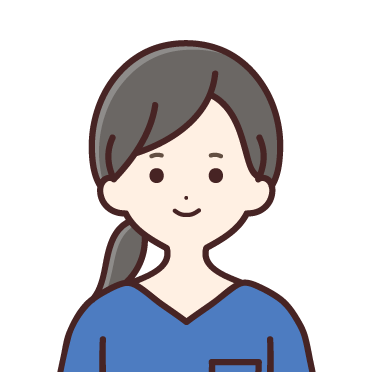
「〇〇さん、トイレに行きましょう。」
「ズボンを下げますね。」
「終わりましたら、声をかけてください。」
「体を拭きましょう。」
「手を洗いましょう。」
「何か困ったことがあれば、いつでも呼んでくださいね。」
- 服薬介助



「〇〇さん、お薬の時間ですよ。」
「これは〇〇(薬の名前)というお薬です。〇〇に効きます。」
「お水で飲んでくださいね。」
「飲み忘れはありませんか?」
- 体位変換


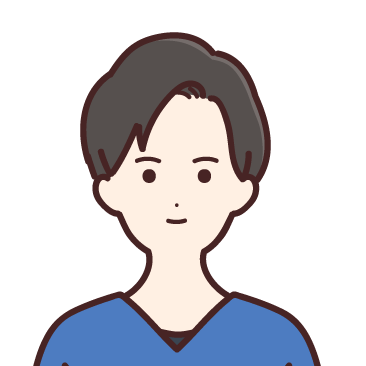
「〇〇さん、少し体を動かしますね。」
「楽な体勢にしますね。」
「少しだけ我慢してくださいね。」
「反対側を向きましょうか?」
- リハビリ


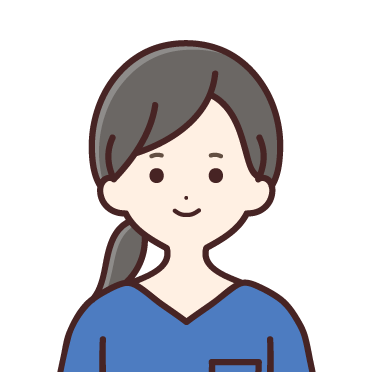
「〇〇さん、リハビリの時間ですよ。」
「無理のない範囲で、ゆっくり動かしてくださいね。」
「痛かったら、すぐに教えてください。」
「頑張っていますね!」
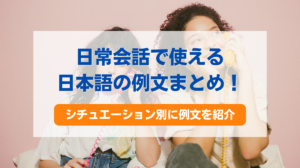
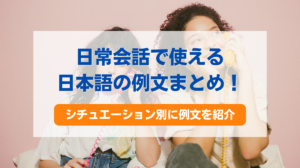
利用者さんの気持ちに寄り添う会話
利用者さんの気持ちに寄り添い、共感や励ましの言葉をかけることで、信頼関係を深めることができます。
- 共感、励ましの言葉


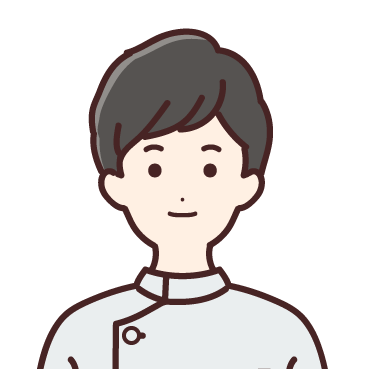
「それはつらいですね。」
「大変でしたね。」
「よく頑張りましたね。」
「無理しないでくださいね。」
「いつもありがとうございます。」
「応援しています。」
- 傾聴、相槌



「はい、はい。」
「そうですね。」
「なるほど。」
「それで、どうなりましたか?」
「お気持ちお察しします。」
- 感謝の言葉


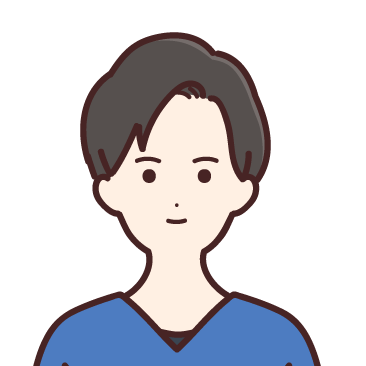
「ありがとうございます。」
「助かります。」
「感謝いたします。」
「いつもお世話になっております。」
- 思い出話を聞く


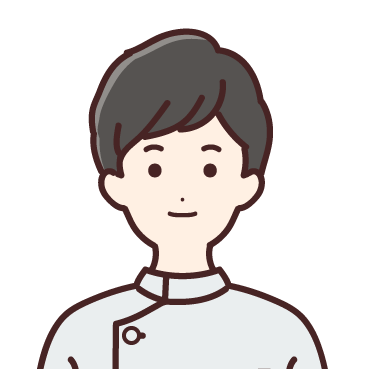
「昔のお話を聞かせてください。」
「〇〇さんは、どんな子供でしたか?」
「〇〇さんの若い頃は、どんな生活をしていましたか?」
「〇〇さんの好きな食べ物は何ですか?」
「〇〇さんの趣味は何ですか?」
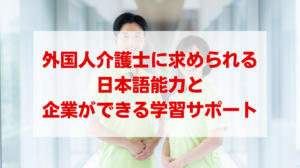
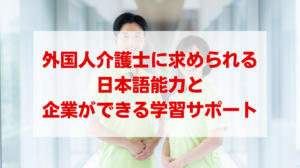
同僚との連携をスムーズにする会話


報告・連絡・相談でよく使う会話
介護の仕事はチームワークが大切です。
同僚への報告、連絡、相談を円滑に行うことで、質の高いケアを提供できます。
- 報告


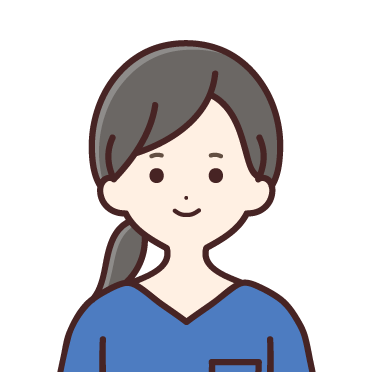
「〇〇さん、〇〇さんのことで報告があります。」
「〇〇さんが、〇〇と言っていました。」
「〇〇さんの体温が〇〇度でした。」
「〇〇さんが、〇〇の痛みを訴えています。」
「〇〇さんが、〇〇をこぼしてしまいました。」
- 連絡


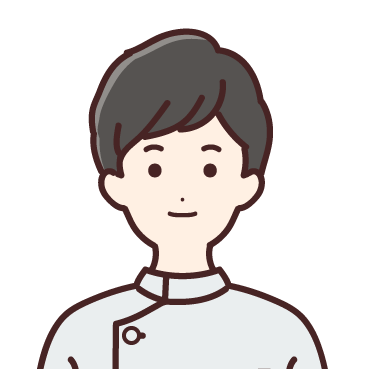
「〇〇さん、〇〇をお願いできますか?」
「〇〇さんの薬がなくなっています。」
「〇〇さんのオムツが足りません。」
「〇〇さんのベッドのシーツが汚れています。」
「〇〇さんの体調が悪いので、看護師さんに連絡してください。」
- 相談


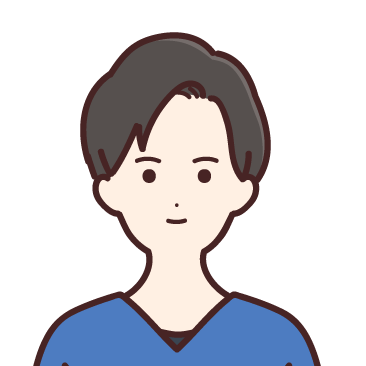
「〇〇さんのことで相談があります。」
「〇〇さんの対応に困っています。」
「〇〇さんのリハビリ方法についてアドバイスをください。」
「〇〇さんの家族から、〇〇について相談を受けました。」
- 指示を仰ぐ



「〇〇さんのことで、どうすれば良いか教えてください。」
「〇〇さんの薬を飲ませても良いですか?」
「〇〇さんを病院に連れて行った方が良いですか?」
「〇〇さんの家族に、どのように説明すれば良いですか?」
- 情報共有


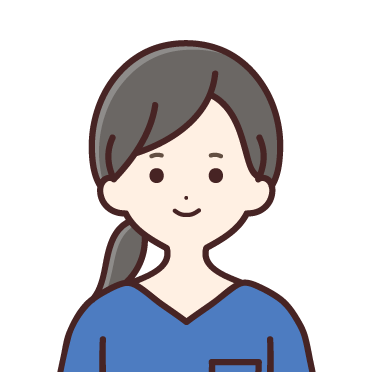
「〇〇さんは、〇〇が好きです。」
「〇〇さんは、〇〇が苦手です。」
「〇〇さんは、〇〇について話すと喜びます。」
「〇〇さんは、〇〇にアレルギーがあります。」
- 申し送り


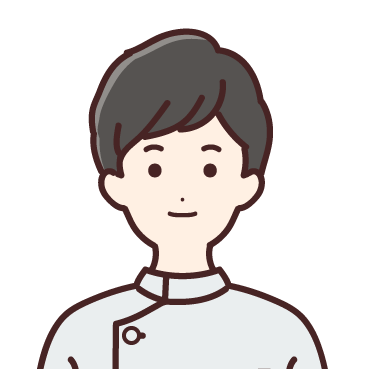
「〇〇さんの状態は、〇〇です。」
「〇〇さんは、〇〇の薬を飲んでいます。」
「〇〇さんは、〇〇に注意が必要です。」
「〇〇さんは、〇〇を希望しています。」
「〇〇さんについて、特に注意してほしいことは〇〇です。」
記録に必要な日本語
介護記録は、利用者さんの状態を正確に記録し、チームで情報を共有するために重要です。
- 観察記録
-
- 「〇時〇分、〇〇さんが〇〇しているのを確認。」
- 「〇〇さんが、〇〇の痛みを訴える。」
- 「〇〇さんの顔色が悪い。」
- 「〇〇さんの食欲がない。」
- 「〇〇さんの排泄状況は〇〇。」
- 介護記録
-
- 「〇〇さんの食事介助を行う。」
- 「〇〇さんの入浴介助を行う。」
- 「〇〇さんの排泄介助を行う。」
- 「〇〇さんの体位変換を行う。」
- 「〇〇さんのリハビリを行う。」
- 事故報告書
-
- 「〇時〇分、〇〇さんが転倒。」
- 「〇〇さんが、〇〇で怪我をした。」
- 「〇〇さんが、〇〇を誤飲した。」
- 「事故の原因は〇〇と考えられる。」
- 略語、専門用語
-
- ADL(日常生活動作)
- IADL(手段的日常生活動作)
- 褥瘡(じょくそう):床ずれ
- 嚥下(えんげ):飲み込み
- 誤嚥(ごえん):誤って気管に食べ物や液体が入ること
- 脱水(だっすい):体内の水分が不足すること
- バイタルサイン:体温、脈拍、呼吸、血圧などの生理的な兆候
緊急時・トラブル発生時の会話
緊急時やトラブル発生時には、落ち着いて対応することが重要です。
必要な情報を正確に伝えられるようにしておきましょう。
- 緊急時の連絡


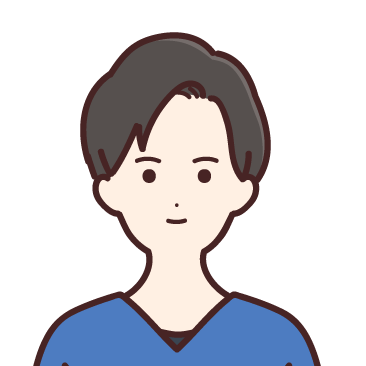
「〇〇さんが倒れました!」
「〇〇さんが意識を失っています!」
「〇〇さんが出血しています!」
「すぐに救急車を呼んでください!」
- 急変時の対応


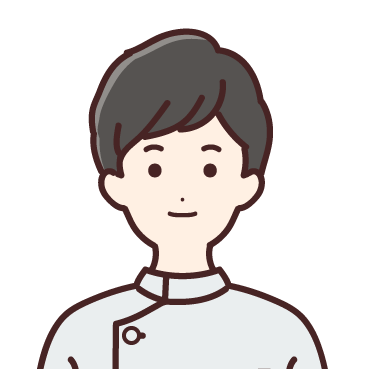
「〇〇さんの呼吸が苦しそうです。」
「〇〇さんの顔色が青ざめています。」
「〇〇さんの脈が弱いです。」
「〇〇さんに声をかけても反応がありません。」
- 事故発生時の対応


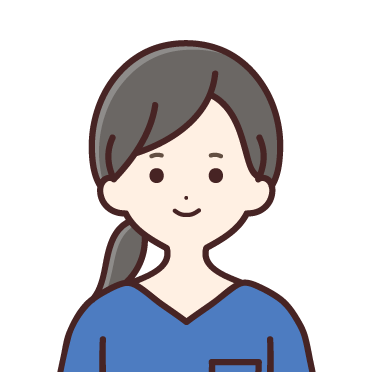
「〇〇さんが転倒しました!」
「〇〇さんが怪我をしました!」
「〇〇さんが薬を誤飲しました!」
「すぐに看護師さんに連絡してください!」
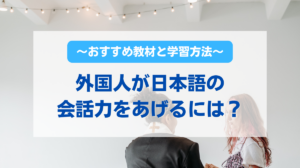
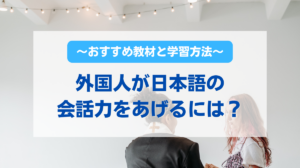
介護特有の言い回し・専門用語


介護現場でよく使う言い回しや専門用語を理解することで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。
外国人スタッフにもわかりやすいように、できるだけ簡単な日本語を使って説明してあげるのがおすすめです。
高齢者特有の病気や症状
- 認知症(にんちしょう)
-
おじいちゃんやおばあちゃんが、昔のことをよく覚えているのに、新しいことを忘れてしまったり、同じことを何度も聞いたりする病気です。
ときどき、時間や場所がわからなくなることもあります。
- 高血圧(こうけつあつ)
-
心臓が血を送る力が強くなりすぎて、血管に強い圧力がかかる病気です。
血圧が高いと、頭が痛くなったり、心臓に負担がかかったりして、体に悪い影響が出ることがあります。
- 糖尿病(とうにょうびょう)
-
体の中で、食べ物の中の糖(さとう)を上手に使えなくなる病気です。
そのせいで血の中に糖がたまりすぎて、のどがかわいたり、疲れやすくなったりします。
- 骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
-
骨の中がスカスカになって、もろくなる病気です。
ちょっと転んだだけで骨が折れたりするので、注意が必要です。カルシウムをとったり、運動をしたりすることが大事です。
- 嚥下障害(えんげしょうがい)
-
食べ物や飲み物をうまく飲みこめなくなることです。
のどにつまったり、間違えて気管に入ってしまうと、せきが出たり、肺炎になったりすることがあります。
介護保険制度(かいごほけんせいど)
- 要介護認定(ようかいごにんてい)
-
体がどのくらい動かしにくくなっているか、どれくらい助けが必要かを決めることです。
この認定を受けると、介護のサービスを受けることができます。
- 居宅介護(きょたくかいご)
-
おじいちゃんやおばあちゃんが、自分の家で暮らしながら、ヘルパーさんなどの助けを受けることです。
ごはんの用意やお風呂の手伝いなどをしてもらえます。
- 施設介護(しせつかいご)
-
家ではなく、介護の施設(特別な建物)に住んで、そこでお世話をしてもらうことです。
自分で生活するのがむずかしい人が利用します。
- 訪問介護(ほうもんかいご)
-
介護のスタッフが、おじいちゃんやおばあちゃんの家に来て、身の回りのことを手伝うサービスです。
ごはんを作ったり、お風呂に入るのを助けたりします。
- 通所介護(つうしょかいご)
-
おじいちゃんやおばあちゃんが、日帰りで介護の施設に通い、いろいろなサービスを受けることです。
体を動かす運動をしたり、みんなでお話したりすることができます。
福祉用具(ふくしようぐ)
- 車椅子(くるまいす)
-
足が不自由な人が、座って移動できるようにするためのイスです。
タイヤがついていて、自分でこいだり、人に押してもらったりして動きます。
- 歩行器(ほこうき)
-
足が弱くなった人が、歩くときに体を支えるために使う道具です。
四つ足がついていて、つかまりながら歩くことができます。
- 杖(つえ)
-
片手で持って、歩くときに体を支えるための棒です。
足が弱くなった人や、バランスをとるのがむずかしい人が使います。
- ベッド
-
体が不自由な人のための特別なベッドです。
ボタンを押すと、頭や足の部分が動くものもあり、楽に起き上がることができます。
- マットレス
-
ベッドの上に敷くやわらかいクッションのようなものです。
特に、長い時間ベッドで過ごす人の体を守るために、やわらかいものが使われることが多いです。
介護施設の種類(かいごしせつのしゅるい)
- 特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)
-
体が不自由で家での生活がむずかしくなったおじいちゃんやおばあちゃんが、ずっと住むことができる施設です。
ごはんやお風呂、お世話をしてもらえます。
- 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)
-
病気やけがの後、家に帰るためにリハビリをする施設です。
お医者さんや看護師さん、リハビリの先生がいて、体を元気にするためのお手伝いをしてくれます。
- グループホーム
-
認知症(にんちしょう)の人が、少人数で一緒に暮らす家のような施設です。
みんなでごはんを作ったり、おしゃべりをしたりしながら、楽しく生活します。
- 有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)
-
お金を払って入る老人ホームです。
食事や掃除、お風呂の手伝いなどのサービスを受けながら、安心して暮らすことができます。
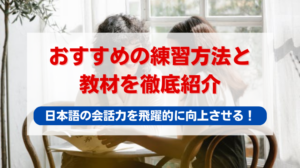
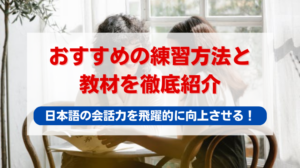
外国人スタッフ向け 会話練習の方法


介護の現場で働く外国人スタッフが、利用者さんとの円滑なコミュニケーションを図るためには、単に言葉を覚えるだけでなく、実際の場面を想定した会話練習を行い、スムーズに対応できるスキルを身につけることが重要です。
特に、介護の仕事では利用者さんとの信頼関係を築くことが不可欠であり、適切な言葉遣いや声かけの習得が求められます。
そのため、教育担当者は、外国人スタッフが日本語での実践的なコミュニケーション能力を向上できるよう、体系的な会話練習の機会を設けることが重要です。
以下では、具体的な場面を想定した会話練習の例と、ロールプレイングを活用した実践的なトレーニング方法を紹介します。
ロールプレイングによる実践的な練習
ロールプレイングは、実際の業務を想定したシミュレーション形式の練習方法で、外国人スタッフが日本語を実践的に学ぶのに非常に効果的です。
リアルな場面を再現しながら、自然な表現や状況に応じた言葉遣いを身につけることを目的としています。
- 利用者さんとの会話練習
-
利用者さん役と介護職員役に分かれ、実際の介護現場を再現しながら会話を行います。
- 例:



「今日は何かご希望はありますか?」


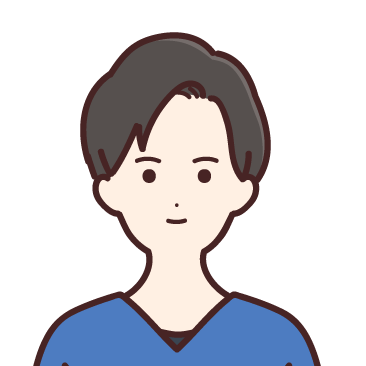
「お散歩に行きたいです。」
- 介護職員同士のコミュニケーション練習
-
介護職員同士の報告・連絡・相談の練習を行い、適切な情報共有ができるようにします。
- 例:


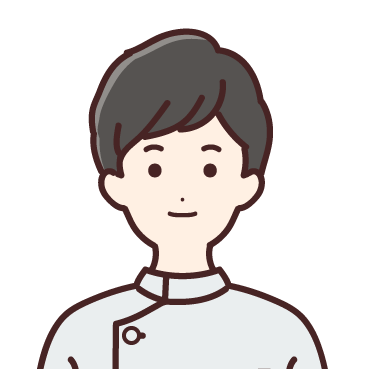
「〇〇さんの昼食の量が少なかったので、少し心配です。」
- 利用者さんの家族との会話練習
-
家族からの質問や相談に適切に対応できるよう、職員と家族役に分かれて練習します。
- 例:


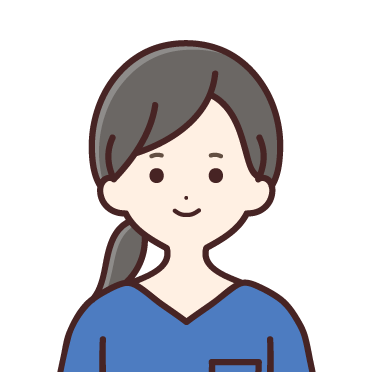
「母の体調はどうですか?」



「今日は少し食欲がないようですが、お元気に過ごされています。」
実践的なフィードバックの方法
ロールプレイングを行った後、外国人スタッフが適切な日本語表現や態度を身につけられるようにするためには、具体的で分かりやすいフィードバックが欠かせません。
以下のポイントを意識して、効果的なフィードバックを行いましょう。
ポジティブなフィードバックを先に伝える
フィードバックを行う際には、まず良かった点を伝えることで、スタッフの自信を育て、モチベーションを高めます。
特に外国人スタッフは、日本語を話すことに不安を感じていることが多いため、「できた部分」に注目して伝えることが重要です。
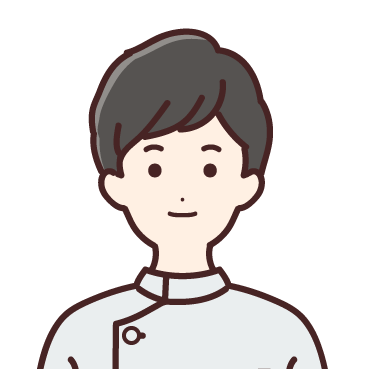
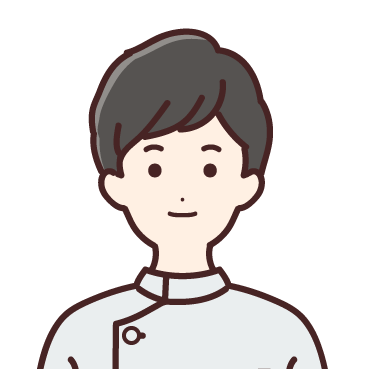
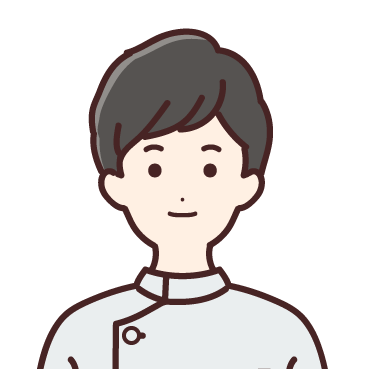
「利用者さんの目を見て、ゆっくり話せていましたね。とても良かったです!」
「挨拶の声が明るくて、利用者さんが安心できそうですね。」
改善点は具体的に伝える
改善すべき点を伝える際は、抽象的な表現ではなく、「どこを」「どう直せばいいのか」を明確に説明します。
また、改善点を指摘する際には、批判的な言い方ではなく、「こうすればもっと良くなる」と前向きな伝え方を心がけます。
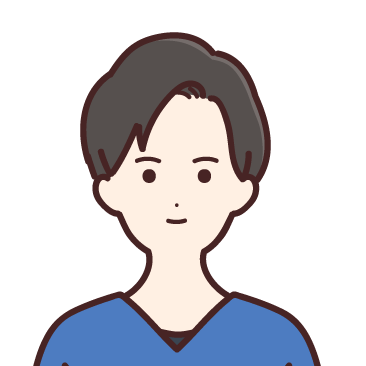
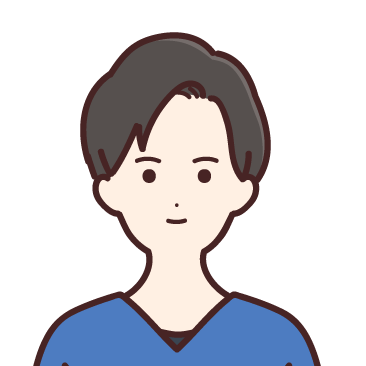
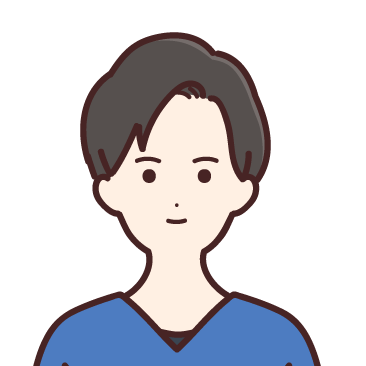
「『おはようございます』の発音が少し速かったので、もう少しゆっくり言うと、利用者さんが聞き取りやすくなります。」
「『大丈夫ですか?』の言い方が少し強く聞こえたので、優しいトーンで言ってみましょう。」
「『お風呂入りましょう』ではなく、『お風呂に入りましょう』の方が自然ですよ」
「『座ってください』よりも、『こちらにお座りください』の方がより丁寧な言い方ですね」
実践を繰り返して定着させる
フィードバックをした後は、実際に改善できるように繰り返し練習することが大切です。
同じシチュエーションを再度ロールプレイングで試したり、短いフレーズを毎日復習する時間を設けたりすることで、適切な表現を身につけることができます。
実施前の問題点
ベトナム出身のAさんは介護職に就いたばかりで、日本語の基礎はできているものの、利用者さんとの会話では、敬語や適切な言葉遣いに自信がなく、緊張してしまうことが多くありました。
特に、利用者さんとの朝の挨拶や体調確認の際、
- 「おはようございます」が小さな声になってしまう
- 体調を確認するときに、「今日は元気ですか?」のようなカジュアルな言葉を使ってしまう
- 利用者さんが何かを答えても、適切な相槌が打てず、会話が続かない
のような問題がありました。
このため、利用者さんとの会話がぎこちなく、利用者さんも「うん…」と短い返事しかしてくれませんでした。
ロールプレイングの内容
教育担当者が利用者さん役を担当し、以下のような練習をしました。
- 明るい挨拶の練習
- 目を見て、笑顔で「おはようございます!」と言う練習
- 名前を入れて「〇〇さん、おはようございます!」とより親しみを込めて話す
- 体調確認の言い方を修正
- 「今日は元気ですか?」 → 「〇〇さん、今日の体調はいかがですか?」
- 「どこか痛いところはありますか?」と、より具体的に質問する
- 利用者さんが答えた後の反応を強化
- 例1:「ちょっと疲れています」と言われたとき
- 改善前:「そうですか…」
- 改善後:「そうなんですね。何かお手伝いできることはありますか?」
- 例2:「元気です!」と言われたとき
- 改善前:「わかりました…」
- 改善後:「それは良かったです!今日も楽しく過ごしましょうね。」
- 例1:「ちょっと疲れています」と言われたとき
実施後の変化
Aさんは、自信を持って挨拶できるようになり、利用者さんも笑顔で返してくれるようになりました。また、「おはようございます!」としっかり声を出して言えるようになり、利用者さんとの会話が弾むようになりました。
さらに、体調を聞いた後も適切なリアクションができるようになったことで、利用者さんが「ちょっと足が痛いんだけど…」と、以前よりも積極的に体の状態を話してくれるようになり、ケアの質も向上しました。
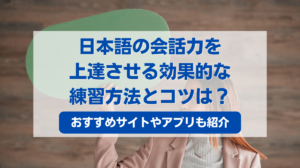
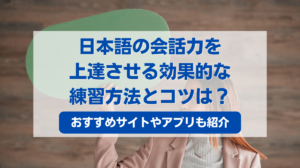
まとめ


外国人スタッフが介護の現場で活躍するためには、正しい日本語表現と、利用者さんに安心感を与える適切な声かけが重要です。
本記事では、日常の挨拶や体調確認、介助時の声かけ、同僚とのコミュニケーションなど、介護現場で役立つ実践的な会話例を紹介しました。
また、外国人スタッフが日本の文化や敬語に慣れるためには、実際の場面を想定したロールプレイングや、具体的なフィードバックを通じた学習が効果的です。
教育担当者は、スタッフ一人ひとりの言語レベルや文化的背景を考慮しながら、継続的にサポートすることが大切です。
外国人スタッフが安心して働き、利用者さんとの信頼関係を築けるよう、職場全体での理解と協力を深めていきましょう。














