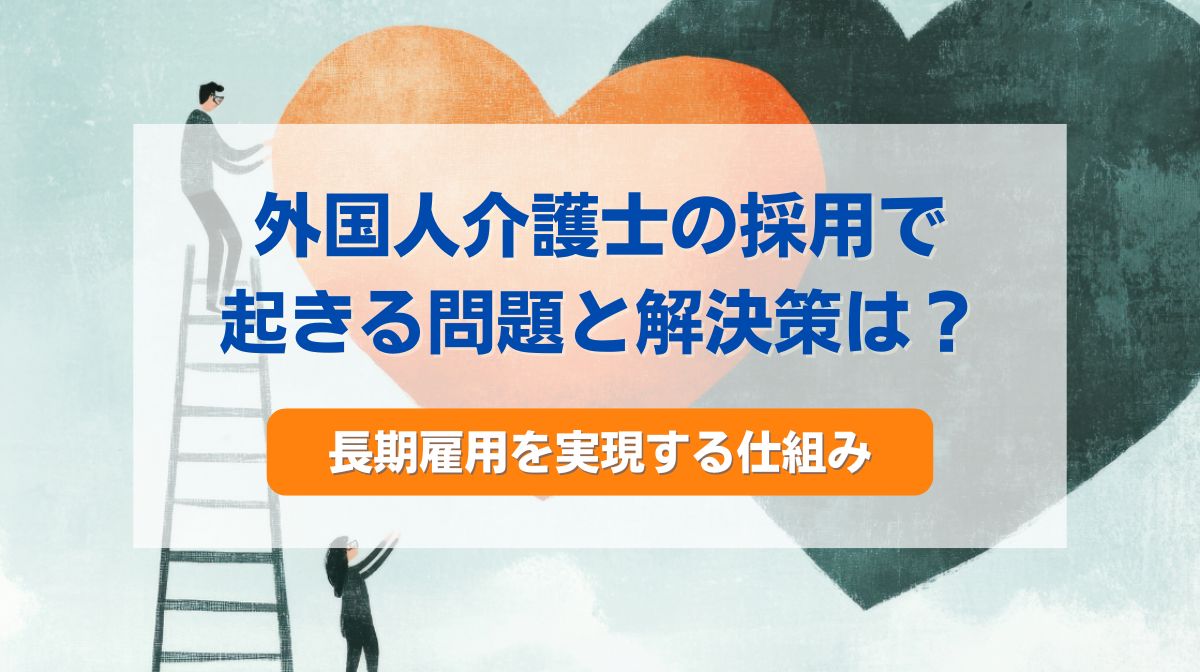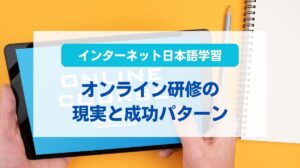日本の介護現場では、深刻な人手不足を背景に、外国人介護士の採用が急速に広がっています。厚生労働省の発表を見ても、介護分野で働く外国人は年々増加しており、特に「特定技能」制度が開始されて以降、その傾向はますます顕著になっています。
しかし同時に、介護施設や事業所の現場からは、外国人スタッフとのコミュニケーションの難しさ、業務理解のズレ、育成体制の不足、あるいは早期離職など、様々な課題が語られることがあります。
本記事では、外国人介護士を巡ってよく起きる問題と、採用企業が実践できる具体的な解決策を解説します。さらに、外国人介護士の長期雇用を実現するために必要な「日本語力」と「介護福祉士資格の取得」、そしてそれらを強力にサポートする実効性のあるオンライン学習サービスの活用方法まで詳しくご紹介します。
\ 日本語学習システム/
外国人介護士を巡る問題とは?

外国人介護士の受け入れが進む一方で、実際に受け入れた企業では、共通した課題に直面することが多くあります。
日本語でのコミュニケーションの壁
外国人介護士の受け入れで最も多く聞かれる課題が、日本語コミュニケーションの壁です。
介護現場では、曖昧な表現や省略された言い回し、状況判断を含む指示が日常的に使われています。例えば「しっかり見ておいてね」「いい感じにお願いね」など、具体的な行動が分かりにくい表現は、外国人スタッフにとって戸惑いの原因になります。
さらに、外国人スタッフの中には、分からないことをその場で聞き返すことを「失礼ではないか」「できない人だと思われるのではないか」と感じる人も少なくありません。結果として、理解が曖昧なまま作業を進めてしまい、ミスや事故につながるリスクが生まれます。
また、記録業務や報告書の作成など、日本語の文章を扱う業務は負担が大きく、精神的ストレスの原因になることもあります。
業務理解の差から生じる戸惑い
介護の仕事は「手順通りに行えばよい」という単純なものではありません。利用者の身体の状況や気分に応じて支援内容を変える必要があり、行動の背景には常に「なぜそのケアが必要なのか」という根拠が存在します。
しかし、受け入れの初期段階では、忙しい現場の中で十分な説明が行き届かず、手順だけを教えてしまうケースが多く見られます。背景理解が不足していると、応用的な判断が求められる場面で対応に困り、結果的に周囲に負担をかけてしまうこともあります。
また、「覚えたことと違う状況」が現場では頻繁に発生するため、柔軟な判断ができず不安を感じ、モチベーションが低下することもあります。
チーム内のコミュニケーションの難しさ
日本の介護現場では、「気づいたことはすぐに報告する」「チーム全体で情報共有を行い、連携して動く」という文化が重視されます。ところが、外国人スタッフの中には、上司の指示を待つ文化で育った人や、独断で判断することを避ける国民性の人も多く、報連相のタイミングに大きな違いが生じることがあります。
例えば、「些細な変化でも報告するべき」という考え方が共有されていないと、「自分では判断できない」「言わないほうがいい」と考えてしまい、必要な情報がチームに伝わらないままになってしまうことがあります。
こうしたすれ違いは、本人の意欲の問題ではなく、育ってきた文化的背景や価値観の違いであり、双方が理解していないと誤解やストレスにつながります。
日本での生活そのものが大きなハードル
外国人介護士にとって、日本で働くということは「仕事を覚える」だけでなく、「日本で生活する」というもう一つの大きな挑戦を意味します。日本人にとって当たり前のことも、初めての外国人にとっては大きなハードルとなります。
また、母国の家族から離れて暮らす孤独感や、日本の気候・食事・生活習慣への適応など、精神的な負担が重なると、どれほど仕事に意欲があっても離職につながってしまうことがあります。
職場での悩みと生活上の悩みは密接に結びついており、どちらかがうまくいかないと総合的な満足度が下がりやすいという点も、外国人介護士受け入れの難しさの一因になっています。
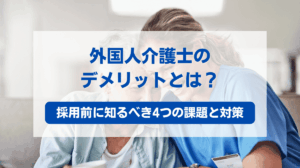
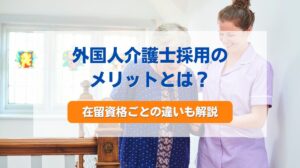
問題を未然に防ぐための受け入れ体制の整備

外国人介護士を迎え入れる際、問題が起きてから対処するのでは遅く、離職や現場の混乱を防ぐためには、採用前から綿密に準備された受け入れ体制が必要です。企業側がどれだけ計画的に、そして丁寧に環境を整えられるかが、外国人スタッフの働きやすさにも、職場全体のスムーズな運営にも直結します。
事前準備で現場の混乱を防ぐ
受け入れ前に最も重要となるのが、業務内容や職場のルールを明確に可視化しておくことです。介護の仕事は「身体介助」「生活支援」など、多岐にわたります。
そのため、言葉だけで説明するのではなく、写真やイラストを活用したマニュアルを作成し、誰が見ても理解しやすい形で業務内容を整理しておくことが効果的です。
あわせて、採用が決まった段階で日本語レベルを正確に把握しておくことも欠かせません。「どの程度の語彙が理解できるのか」「現場用語はどのくらい通じるのか」といった事前の認識があることで、現場側が対応しやすくなり、本人にとっても余計な負担が減ります。
現場で多用する言葉を「やさしい日本語」に言い換えたリストを準備したり、多言語翻訳アプリやタブレット端末を用意したりすることで、初期のコミュニケーションギャップを最小限に抑えることができます。
日本語・コミュニケーション支援を仕組みとして整える
現場での困りごとの多くはコミュニケーションのズレから生じるため、受け入れ側である日本人スタッフへのサポートも非常に重要です。
ゆっくり、はっきり、明確に伝えることを全員が意識するだけでも、理解度は大きく変わります。曖昧な表現を避け、具体的な行動を伝える習慣をつけることで、現場のストレスは格段に減少します。
とはいえ、日常業務と並行して日本語教育まで担うのは現場にとって大きな負担になります。介護用語の指導や文法学習を職場内だけで完結させるのは非現実的であり、結果として教育が中途半端になってしまうことも少なくありません。
そのため、日本語教育やコミュニケーション研修は外部の専門サービスやオンライン学習教材を活用し、効率的かつ継続的に支援できる仕組みを整えることが、長期的な成功につながります。
計画的な育成体制で成長の実感を与える
外国人介護士が安心して働き続けるためには、ただ業務を教えるだけでなく、成長が実感できる育成体制が必要です。最初の段階では簡単な業務からスタートし、習熟度に応じて徐々に難易度を上げていく段階的なOJTを行うことで、本人の負担を抑えつつ確実なスキルアップにつなげることができます。
さらに、定期的な面談を設けて困りごとや不安を丁寧に聞き出し、小さな問題でも早期に解決していくことも大切です。スキル評価シートを利用して「できるようになったこと」を可視化する仕組みがあると、本人の自信やモチベーション向上に大きく寄与します。
加えて、将来的なキャリアパスを明確に示すことも重要なポイントです。「特定技能から介護福祉士へ」という道筋が分かりやすく示されている職場は、外国人スタッフにとって将来を描きやすく、長く働きたいという意欲にもつながります。
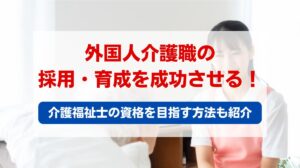
外国人介護士の長期雇用には介護福祉士資格が必要

外国人介護士の安定的な雇用を実現する上で、介護分野における唯一の国家資格である「介護福祉士」の取得は極めて重要な位置づけとなります。日本の介護現場でプロフェッショナルとして認められ、長期的なキャリアを歩むためには、この資格の有無が大きく影響します。
資格を取得することで、在留期限がなくなり、将来的には永住権の取得も視野に入るため、日本で生活基盤を築きたいと考える外国人スタッフにとっては大きな安心材料となります。また、資格取得によって給与や職務範囲が広がり、職場からの信頼も高まり、やりがいや責任感を持って働ける環境が整います。
しかし、この資格を取得するためには、高度な専門知識に加えて、JLPTのN2以上に相当する高い日本語力が求められます。国家試験の問題文は長文かつ専門用語が多く、単に「会話ができる」というレベルでは到底太刀打ちできません。
現場での業務に慣れながら、同時に日本語の読解力や専門知識を身につけていくことは大きなチャレンジであり、本人の努力だけで達成するのは難しいという実情があります。そのため、企業側が計画的かつ継続的に学習をサポートできる体制を用意できるかどうかが、長期定着の分岐点となります。
介護福祉士資格の取得は、単に個人のキャリアアップにとどまらず、企業にとっても介護の質の向上、離職率の低下、そして将来のリーダー候補を育てるという大きなメリットがあります。
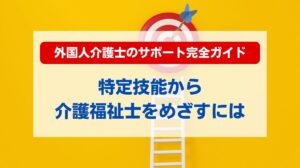
外国人介護士の成長を後押しするeラーニング講座の活用

介護福祉士になるためのサポートが必要とわかっていても、現場の業務と並行して日本語教育や国家試験対策を行うのは簡単ではありません。
教える側の日本人スタッフも忙しく、体系的な指導を継続するには大きな負担がかかります。こうした課題を解消しつつ、外国人スタッフの成長を確実に支える方法として、今、多くの企業が注目しているのがオンライン学習サービスの活用です。
eラーニング講座などのオンライン教材を使えば、専門講師による高品質な学習を、場所や時間に縛られずに受講することができます。介護現場で多忙なスタッフでも、通勤時間や休憩時間、帰宅後など、自分のペースで無理なく学習を続けられるため、継続率が大幅に向上します。
また、管理者側は学習進捗をデータで把握でき、誰がどこでつまずいているのかを視覚的に確認できるため、サポートも効率的に行えます。
特に日本語教育と介護福祉士試験対策を一体化させたeラーニング講座は、現場の負担を軽減しながら確実に実力を伸ばせる仕組みとして非常に効果的です。一般的な日本語学習ではカバーしきれない「介護現場ならではの専門用語」や、「国家試験に特化した読解・問題演習」などを専門的に学べることは、外国人スタッフにとって大きな強みとなります。
企業にとっても、優秀な外国人スタッフをより早く戦力化できるだけでなく、国家資格の取得率が上がることで将来のリーダー育成にもつながります。加えて、「資格取得を支援してくれる職場」というイメージは採用力の向上にもつながり、他社との差別化にも大きく貢献します。
現場の負担を増やさず、外国人介護士の成長を確実にサポートするオンライン学習は、これからの介護業界において、最も実効性の高い育成手段のひとつと言えるでしょう。
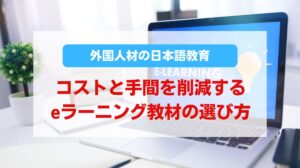
日本語学習・資格取得支援に最適な「日本語カフェ」のeラーニング講座

現場で日本語教育を行うリソースがない、どうやって介護福祉士の勉強をサポートすればいいか分からない。そんな企業様の悩みを解決し、スタッフの学習を強力に後押しするeラーニング講座をご紹介します。
日本語カフェ「JLPT合格コース」
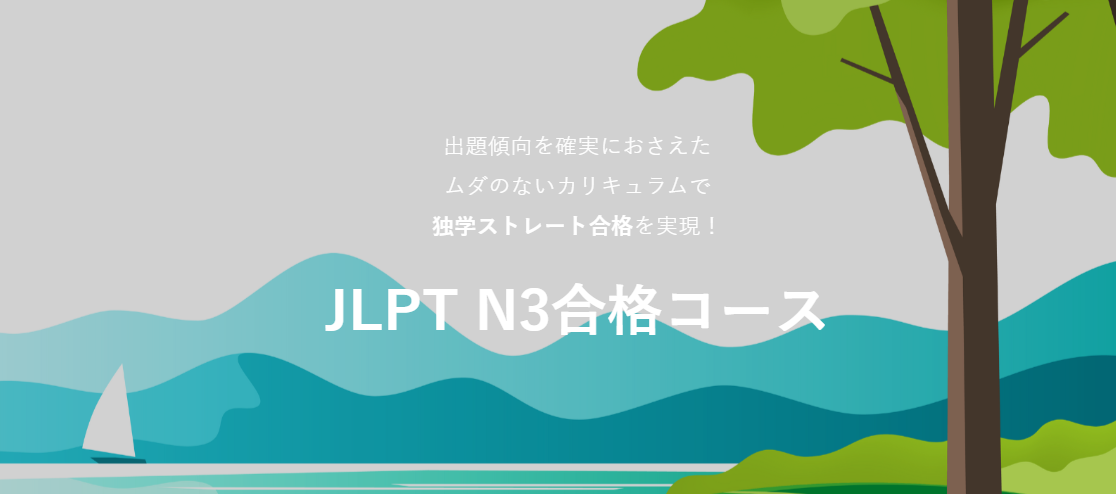
介護福祉士試験の土台となる「確かな日本語力」を養成するためのコースです。
主な特徴
- 一流講師が監修した”合格特化”カリキュラム
-
「何を、どの順番で学べば合格できるか」が明確なので、迷うことなく最短ルートで学習を進められます。
- 文法・語彙・読解・聴解を網羅
-
試験に必要な全スキルをバランス良く学習できます。
- 模試やシャドーイング教材も豊富
-
アウトプットのための練習教材が充実しており、実践力が身につくきます。
- スマホ・PCで24時間視聴可能
-
通勤時間、休日など、好きな時に好きな場所で学習できます。
- 学習状況を一括管理でき、教育コストを大幅削減
-
管理画面でスタッフ一人ひとりの学習状況が一目でわかるため、教育担当者の進捗管理の手間を大きく削減できます。
厳しい審査をパスしたプロの日本語講師が監修した高品質な動画カリキュラムとドリルが使い放題。コストを抑えながら、スタッフの自発的な学習を力強くサポートします。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
日本語カフェ「介護福祉士 受験対策講座」
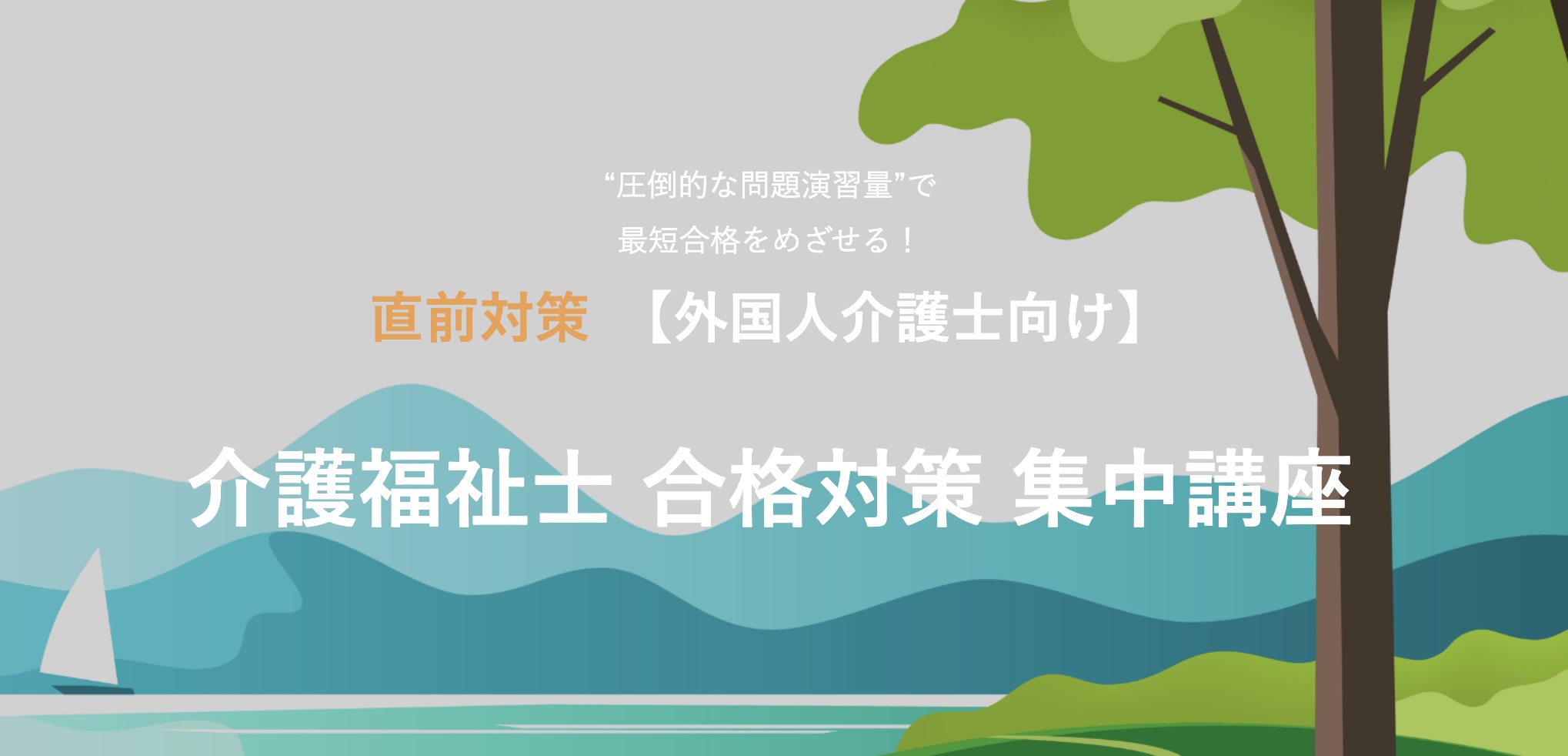
介護福祉士国家試験の合格に特化し、専門知識と試験対策を強化する集中講座です。
4ヶ月で介護福祉士合格を狙える集中講座
- 介護の専門知識を強化
-
難しい介護用語をわかりやすく丁寧に解説
- 膨大な過去問を講師と一緒に解説
-
合格の鍵を握る過去問演習を、動画解説付きで徹底的に実施
- 模擬試験で本番を完全再現
-
時間配分や出題傾向を把握し、本番での実力を最大限に発揮
- JLPTコースも使い放題で語学面も強化
-
基礎的な日本語力に不安がある場合でも、JLPTコースで同時に復習・強化が可能
企業側のメリット
- 合格率・定着率が大幅に上がる
-
体系的な学習支援により、スタッフの国家資格合格を強力に後押しし、長期雇用を実現
- 介護福祉士を確保できるため管理者育成にもつながる
-
資格を持つ優秀な外国人スタッフは、将来のリーダーや管理者候補として活躍が期待できる
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!

- ■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- ■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- ■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
日本語カフェでは、貴社の状況やスタッフのレベルに合わせた最適な学習プランをご提案します。 介護福祉士取得までを見据えた長期的な教育計画についても、お気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから/
外国人介護士の長期定着を実現するには受け入れ体制の構築が必要

外国人介護士の受け入れが進む中で、長期的に安心して働いてもらえる環境を整えることは、介護業界全体の課題となっています。日本語でのコミュニケーションの難しさ、業務理解のギャップ、文化や価値観の違い、さらには生活面での不安など、外国人スタッフを取り巻く課題は一つひとつが大きく、本人の努力だけで解決することは困難です。だからこそ、企業側がどれだけ丁寧に準備し、支えられる仕組みを整えられるかで、定着率が変わってきます。
受け入れ前の段階から分かりやすいマニュアルや業務フローを整え、初期の不安を取り除くこと、現場で働く日本人スタッフが「やさしい日本語」や明確な指示を心がけ、円滑なコミュニケーションを意識すること、そして、場当たり的な指導ではなく、段階的に成長を実感できる育成体制を用意すること。こうした準備が整った職場ほど、外国人スタッフは安心して業務に取り組むことができ、早期離職やミスのリスクも大きく減少します。
そのうえで、外国人介護士のキャリア形成において最も重要な鍵となるのが、介護福祉士資格の取得です。この資格は働き方を大きく広げると同時に、在留資格の安定や収入アップ、専門職としての自信など、多くのメリットをもたらします。しかし、高度な日本語力と専門知識が求められることから、本人だけでは乗り越えるのが難しく、企業側の支援が不可欠となります。
こうした負担を軽減し、確実な成長を後押しする方法として、オンライン学習サービスの活用は非常に効果的です。日本語力の基礎強化から専門用語の習得、国家試験対策まで、働きながら無理なく続けられる学習環境は、企業とスタッフ双方にとって大きな価値を生み出します。現場の負担を増やすことなく、外国人スタッフが自信を持って働ける未来をつくるための実効性の高い仕組みと言えるでしょう。
\ 日本語学習システム/