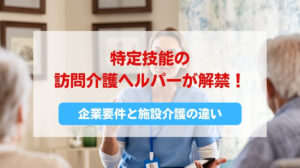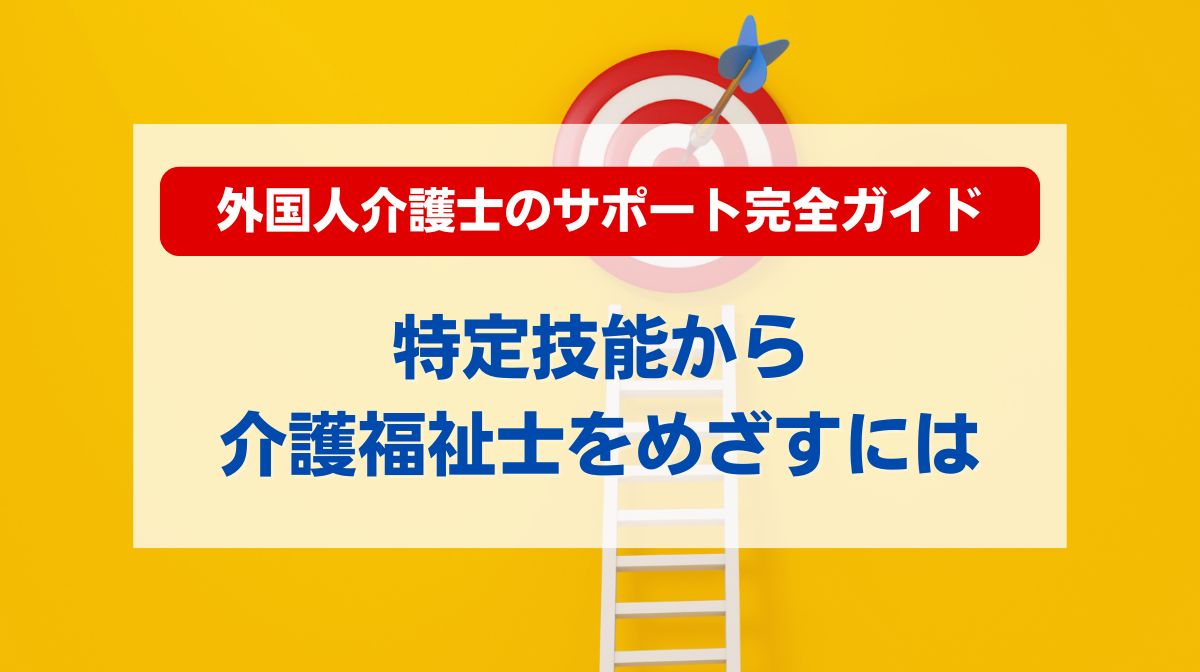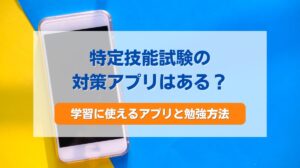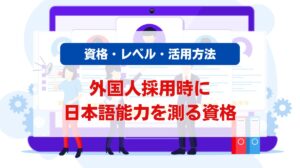「特定技能で外国人介護スタッフを採用したが、具体的にどうサポートすれば良いのかわからない」
「現場での日本語コミュニケーションや、業務指導の方法に課題を感じている」
「特定技能」の在留資格で外国人介護人材の雇用に取り組む、あるいは検討されている施設の採用・教育担当者様の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
特定技能の外国人材は、一定の技能と日本語能力を持っていますが、彼らが日本で安心して働き、キャリアを築いていくためには、施設側の手厚いサポート体制が必要です。
特に「特定技能1号」の在留期間(通算上限5年)の先に、永続的な就労(在留資格「介護」への移行)を見据える場合、国家資格である「介護福祉士」の取得が実質的に必須となります。
この記事では、特に「特定技能」の介護士に焦点を当て、法律で定められた支援内容から、介護福祉士の資格を取得し、長期的に活躍してもらうために最も重要な「日本語教育」の具体的な進め方までを、解説します。貴施設の大切なスタッフを、専門性の高い介護福祉士へと育成するための一助となれば幸いです。
\ 日本語学習システム/
「特定技能」法律で定められた支援(義務的支援)

「特定技能1号」の在留資格で外国人材を受け入れる場合、受入れ機関(つまり貴施設)には、外国人が日本で安定的に生活し、働くための「支援」を行うことが法律で義務付けられています。
これらの支援は、専門の「登録支援機関」に全て、または一部を委託することも可能ですが、自社で支援を行う場合も、委託する場合も、その内容を正確に把握しておくことが極めて重要です。
この支援は、外国人スタッフが日本での生活基盤を確立し、安心して業務に集中するために重要なサポートであり、ひいては早期離職を防ぎ、定着率を高めるための基盤となります。
ここでは、法律で定められている義務的支援を中心に、定着のために重要となるサポート内容を3つの側面に分けて解説します。
生活オリエンテーションと生活支援
まず基本となるのが、日本での生活をスムーズにスタートさせるための支援です。特定技能のスタッフは一定の日本語能力があるとはいえ、日本の複雑な行政手続きや生活習慣に一人で対応するのは困難です。
業務以前に、生活の基盤が揺らいでいては、仕事に集中することはできません。出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」において、受入れ機関(または登録支援機関)は以下の支援を行うことが義務付けられています。
- 事前ガイダンスの実施
-
雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前(または在留資格変更許可申請前)に、労働条件、活動内容、日本での生活上の注意点などについて、本人が十分に理解できる言語で説明します。(対面、テレビ電話、Zoom等のビデオ通話などで行う必要があります)
- 出入国する際の送迎
-
- (入国時) 外国人が入国する空港(または港)から、事業所または住居まで送迎します。
- (帰国時) 外国人が帰国する際、保安検査場の前まで同行し、スムーズに出国できるようサポートします。
- 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約支援
-
- 外国人が希望する場合、社宅やアパートなどの物件探しを手伝ったり、受入れ機関等が連帯保証人になったりする形で、住居の確保をサポートします。
- 銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などのライフラインの契約について、必要書類の準備や窓口への同行などを行い、手続きをサポートします。
- 生活オリエンテーションの実施
-
- 入職後、日本で安定的・円滑に生活できるよう、日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法、ゴミの分別ルール、医療機関の利用方法、災害時の対応(避難場所や連絡方法)などについて、本人が理解できる言語で説明します。(目安として8時間以上)
- 日本の行政手続き(社会保障、税、住民登録など)について説明し、必要な手続きを行う窓口の案内や同行サポートを行います。
業務(OJT)とメンタルサポート
次に、現場での業務を円滑に進めるためのサポートです。特定技能のスタッフは「介護技能評価試験」に合格しているため、基本的な介護技術は有していますが、日本の介護現場特有の文化や、施設ごとのローカルルールに適応するには時間がかかります。外国人スタッフが孤立せず、安心してスキルアップできる環境を整えることが重要です。
まず、業務マニュアルの整備は欠かせません。その際、専門用語や曖昧な表現を避け、「やさしい日本語」を用いたり、可能であれば母国語の翻訳を併記したりする工夫が効果的です。
また、業務上の指導体制も明確にする必要があります。「わからないことがあった時、誰に聞けばよいか」が明確でないと、スタッフは不安を感じ、小さな疑問を放置してしまいがちです。日本人スタッフをメンター(指導・相談役)として設定し、マンツーマンでサポートする体制を組むのも良い方法です。
さらに、精神面でのサポートも非常に重要です。法律で定められた支援として、「外国人からの相談・苦情への対応」が義務付けられています。
これは、職業生活上(仕事内容、職場の人間関係など)だけでなく、日常生活上(生活の不便さ、差別的待遇など)の相談や苦情についても、本人が十分に理解できる言語で対応し、必要な助言や指導を行う体制を整えることを意味します。
この義務を果たすためにも、定期的に面談の機会を設けることが求められます。この面談は、単なる業務の進捗確認ではなく、本人が安心して悩みを打ち明けられる「相談窓口」として機能させることが大切です。
異国の地で働くストレスや孤独感を察知し、早期にケアすることが、早期離職の防止に繋がります。
日本社会への適応支援と日本語学習の機会提供
生活や仕事の場だけでなく、より広い「日本社会」に適応していくための支援も必要です。職場と自宅の往復だけでは、日本での生活の質は向上せず、孤立感を深めてしまう可能性もあります。
義務的支援としても、「日本人との交流促進に係る支援」が定められています。これは、地域のお祭りやイベント、ボランティア活動、あるいはスポーツ交流会など、地域の日本人住民と交流できる機会について情報提供し、必要に応じて参加の手続きを手伝ったり、同行したりすることを指します。
特に重要となるのが、日本の文化や習慣への理解を促すサポートです。日本の介護現場には、マニュアル化が難しい特有の文化が存在します。
例えば、相手の気持ちを「察する」コミュニケーションや、利用者様に対する細やかな「敬語の使い方」、あるいはチームワークを重んじる姿勢などです。これらは、外国人スタッフにとって理解が難しい部分であり、時には「なぜそうするのかわからない」と戸惑いの原因にもなります。
こうした文化的な背景を丁寧に説明し、日本で働く上での「暗黙のルール」を理解してもらうことも、施設側が担うべき重要なサポートの一つです。そして、これら全ての支援の基盤となり、かつ義務的支援としても明記されているのが、「日本語学習の機会の提供」です。
具体的には、地域の日本語教室や民間の日本語学校に関する情報を提供し、入学手続きの手伝いをすることや、自主学習のためのオンライン教材やテキストの情報を提供すること、あるいは受入れ機関が日本語教師と契約して学習の機会を提供することなどが含まれます。
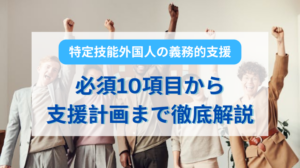
介護現場で求められる専門的なサポート

法律で定められた義務的支援は、いわば日本で生活し、働くための「土台」です。しかし、介護という高い専門性が求められる現場で長期的に活躍してもらうためには、この土台の上に、さらに「介護現場ならでは」の専門的なサポートを積み重ねる必要があります。
一般的な事務職や製造業とは異なる、介護職特有の課題に対応するサポート体制こそが、特定技能スタッフの定着率を大きく左右します。
高齢者・認知症の方とのコミュニケーション支援
外国人スタッフが最初に直面する大きな壁の一つが、利用者様とのコミュニケーションです。N4レベルの日本語力は、あくまで基本的な日常会話のレベルであり、介護現場で求められる複雑なコミュニケーションに対応するには不十分です。
例えば、高齢の利用者様特有の話し方(声が小さい、発音が不明瞭、方言や訛りが強い)を聞き取る訓練が必要です。また、認知症の方とのコミュニケーションでは、言葉そのものよりも、表情や声のトーン、寄り添う姿勢といった「非言語的コミュニケーション」が重要になります。
これらはマニュアルだけで教えるのが難しいため、日本人スタッフがOJTの中で「なぜ今、こういう声かけをしたのか」「利用者様のこの表情は、何を求めているサインか」を具体的に解説し、見本を見せ続けることが極めて重要です。
「察する文化」と「敬語」への適応サポート
日本の介護現場では、「相手が言葉にする前にニーズを察して動く」ことが美徳とされる側面があります。しかし、これは多くの外国文化の背景を持つスタッフにとって、非常に理解しにくい「暗黙のルール」です。
彼らの文化では「要求は言葉で明確に伝える」ことが当たり前である場合も多く、日本的な「察する」コミュニケーションは、何をすべきか分からず戸惑う原因となります。
また、「敬語」や「丁寧語」の使い分けも大きな課題です。利用者様やそのご家族には敬語を使い、同僚や上司には丁寧語を使うといった使い分けは、非常に高度な日本語スキルを要します。
これらを「間違っている」と単純に指摘するのではなく、なぜ日本ではそのような言葉遣いが大切にされるのか、その文化的背景(相手への尊敬や思いやりを示すため)から丁寧に説明し、OJTで繰り返し練習する機会を設けるサポートが必要です。
介護の専門用語・現場の略語のフォロー体制
介護現場は、専門用語と「略語」の多いです。「褥瘡(じょくそう)」「嚥下(えんげ)」「拘縮(こうしゅく)」といった教科書的な専門用語だけでなく、「エンシュク(円背)」「臥床(がしょう)」「デク(デクビタス=褥瘡)」「(おむつ交換の)全交(ぜんこう)」など、その施設や現場だけで使われる無数の略語が存在します。
日本人スタッフにとっては当たり前のこれらの言葉も、外国人スタッフにとっては理解不能な「暗号」に聞こえてしまいます。これが原因で申し送りが正確に伝わらなかったり、業務の指示が理解できなかったりすることは、重大な事故にも繋がりかねません。
施設内で使われている専門用語や略語のリストを作成し、意味や使い方を解説した資料を整備する、あるいはメンターが定期的に「最近わからなかった言葉はなかった?」と積極的に拾い上げるフォロー体制が求められます。
介護職特有のメンタルヘルスケア
介護の仕事は、「命」と向き合う仕事であり、他の職種にはない特有の精神的ストレスが伴います。特に「看取り」に関わる経験は、文化や死生観の違いから、外国人スタッフにとって日本人スタッフが想像する以上の精神的負担となる場合があります。
また、残念ながら、一部の利用者様やそのご家族から、外国人であることを理由とした差別的な言動や、ハラスメント(セクシャルハラスメントを含む)を受けてしまうケースもゼロではありません。
こうした介護職特有のストレスに対し、施設側は明確なサポート体制を築く必要があります。定期的な面談で精神的な落ち込みがないかを確認するだけでなく、「看取りの後は必ず専門職(例:心理カウンセラーや経験豊富な上司)と話す機会を設ける」「ハラスメントを受けた場合は、スタッフ個人で対応させず、必ず施設が間に入って対応する」といった具体的なルールを定め、スタッフを守る姿勢を明確に示すことが、異国の地で働く彼らの大きな安心感に繋がります。
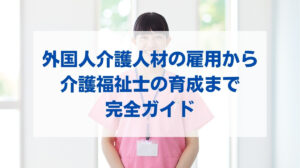
義務的支援の中でも「日本語サポート」が最も重要

前章では、法律で定められた義務的支援と、介護現場ならではの専門的サポートについて解説しました。その中でも、特定技能の介護士が長期的に定着し、さらに介護福祉士へとキャリアアップする上で非常に重要と言えるのが、義務的支援の一つでもある「日本語サポート」です。
なぜなら、日本語力は、現場のあらゆる課題を解決する基盤であり、同時に特定技能の次のステップである介護福祉士国家試験という最大の壁を突破するために必要だからです。
現場のコミュニケーション課題を解決する
介護の現場は、人と人とのコミュニケーションそのもので成り立っています。日本語の壁は、この根幹を揺るがす深刻な課題となります。
特定技能のスタッフはJLPT N4程度の日本語力を持っていますが、これはあくまで「基本的な日本語を理解することができる」レベルです。実際の介護現場で求められる日本語力は、それより遥かに高度です。
まず、「利用者様との壁」です。高齢の利用者様との会話は、外国人スタッフにとって非常に難易度が高いものです。はっきりとした発音でない場合や、方言や訛りが強い場合、あるいは耳が遠い方とのコミュニケーションには苦労が伴います。
うまく意思疎通ができないと、スタッフ本人が自信を失うだけでなく、利用者様側も「この人に任せて大丈夫だろうか」と不安を感じてしまう可能性があります。
また、「スタッフ間の壁」にもつながります。介護はチームで行う仕事であり、スタッフ間の正確な情報共有が不可欠です。業務の指示や、利用者様の状態変化に関する「申し送り」、あるいは「ヒヤリハット報告」などが日本語の壁によって不正確に伝わった場合、それは単なるコミュニケーションエラーでは済まされず、重大な介護事故に直結する危険性をはらんでいます。
これらの課題を解決するためには、業務に必要な「介護の日本語」(例:「移乗します」「臥床(がしょう)介助」など)を覚えるだけでは不十分です。利用者様のちょっとした体調の変化に気づいたり、日本人スタッフと円滑な人間関係を築いたりするためには、日常会話や雑談ができるレベルの日本語力が必要です。
円滑なコミュニケーションは、本人の職場への安心感や帰属意識を高め、利用者様との信頼関係を構築する上で最も大切なポイントなのです。
介護福祉士 国家試験の「壁」を超えるため
日本語サポートが重要なもう一つの理由は、キャリアアップの目標である「介護福祉士」の国家試験合格に高い日本語力が必要だからです。
特定技能1号の在留期間(通算5年)が終了した後も日本で介護士として働き続けるためには、実務経験3年に加えて介護福祉士の資格を取得し、「在留資格『介護』」へ移行することが王道のルートとなります。
しかし、介護福祉士の国家試験は、日本人であっても十分な対策が必要な難関試験です。外国人にとっては、介護の専門知識を問われる以前に、試験問題そのものを読み解く「日本語の壁」が立ちはだかります。
試験問題には、専門用語が頻出します。さらに、一つの問題文が長く、事例問題などでは状況を正確に把握するための高い読解力が要求されます。この試験問題に対応するため、合格ラインとして最低限必要とされるのが、日本語能力試験(JLPT)の「N2」レベルの日本語力であると言われています。
N2は、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルと定義されており、新聞や雑誌の記事、平易な評論などを読んで内容を理解できる能力が求められます。まさに、国家試験の問題文を読み解くための土台となる日本語力です。
しかし、多くの特定技能スタッフが直面する現実は厳しいものです。日々の介護業務、時には夜勤もこなしながら、疲れた体で試験勉強の時間を確保することは容易ではありません。
施設側が「資格取得を目指して頑張ってね」と声をかけるだけでは、この高い壁を越えることは非常に困難です。合格を本気で目指すのであれば、施設側が具体的な学習環境を提供し、計画的に日本語力と専門知識の両方をサポートしていく必要があります。
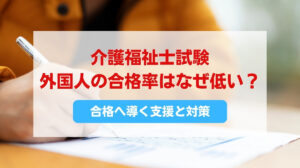

介護福祉士を目指すための「日本語学習ロードマップ」

前章で述べた通り、特定技能のスタッフが介護福祉士の資格を取得するには、現場のOJT任せではなく、施設側が計画的な学習サポートを提供することが成功の鍵となります。
「日本語学習」と「介護福祉士試験対策」は、同時並行ではなく、段階を踏んで進めるのが最も効率的です。ここでは、合格への最短ルートとなる学習ロードマップを2つのステップでご紹介します。
最初のステップは、介護福祉士試験の土台作りとして、日本語能力試験(JLPT)の「N2」合格を明確な目標に設定することです。特定技能の入職要件であるN4レベルから、N2レベルへと日本語力を引き上げることが最優先課題となります。
介護福祉士の勉強をいきなり始めても、テキストや問題文が読めなければ学習効率は非常に悪く、すぐに挫折してしまいます。まずは試験の「土俵」に上がるための日本語力を徹底的に鍛えることが先決です。
ここで注意したいのは、現場のOJTで日常的に使っている日本語と、N2試験で求められる日本語は異なるという点です。現場でのコミュニケーションは実践的ですが、それだけでは体系的な文法知識や、長文を論理的に読み解くスキルは身につきにくいものです。
そのため、N2合格という目標に向けては、スタッフ本人のレベルに合わせ、「語彙」「文法」「読解」「聴解」をバランスよく学べる体系的なカリキュラムが必要です。インプット(講義)とアウトプット(演習)を効率よく繰り返し行える学習環境を整えることが重要になります。
JLPT N2レベルの日本語力という強固な土台ができたら、いよいよ次のステップである「介護福祉士 受験対策」に進みます。特定技能のスタッフは「実務経験3年」という受験資格も、日々の業務を通じて満たしていくことができます。
ここでは、N2レベルの日本語力を前提として、介護福祉士の国家試験に特化した専門知識を学んでいきます。出題範囲は非常に広いため、やみくもに勉強するのではなく、試験の出題傾向を分析し、頻出分野や重要用語に絞って効率的に学習することが求められます。
このステップでの課題も、やはり「仕事との両立」そして「モチベーションの維持」です。日本語の壁を乗り越えたとしても、今度は膨大な専門知識の暗記という次の壁が待っています。
独学でこの広い範囲をカバーするのは困難であり、試験のポイントを絞って解説してくれる講義や、本番同様の過去問・模擬試験を繰り返し演習できる環境が、合格を大きく左右します。
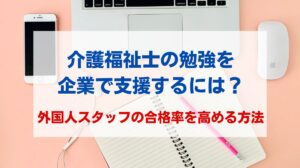
企業の日本語教育は「オンライン講座」が効率的

「特定技能スタッフに日本語教育が必要なのは痛いほどわかるが、コストや管理の手間が大きな負担になっている」 「施設内に日本語を教えられる講師がいないし、外部から採用・管理するリソースもない」
このような悩みを抱える施設担当者様も多いのではないでしょうか。
確かに、業務を行いながらの日本語教育は、現場の日本人スタッフにとっても大きな負担となります。そこで、最も効率的かつ現実的な解決策として、オンライン日本語講座の活用をおすすめします。
オンライン講座であれば、施設側が講師を採用・管理する必要がなく、コストを大幅に抑えることが可能です。また、スタッフはスマートフォンやPCを使い、通勤時間や休憩時間などの「スキマ時間」を活用して、自分のペースで学習を進めることができます。教育担当者の管理負担を軽減しつつ、スタッフの自発的な学習を促すことができます。
「日本語カフェ」が選ばれる理由
数あるオンライン講座の中でも、特定技能スタッフの日本語教育と介護福祉士取得支援のシンプル化、効率化、そしてコストカットを実現したいなら、「日本語カフェ」の活用が最適です。
「日本語カフェ」が選ばれているのには、明確な理由があります。 第一に、レベル別に最適化された完全カリキュラム(N5〜N1対応)が用意されている点です。厳しい審査をパスした一流のプロ講師が監修した、合格に特化した動画カリキュラムが使い放題となります。
何をどの順番で学べば合格できるかが全て整理されており、特定技能スタッフの「N4からN2へ」というステップアップに最適な学習プランを提供します。
また、忙しい介護士のライフスタイルに合わせた学習が可能です。スマートフォンやタブレットに対応しており、1回10分からのスキマ学習も設計されています。通勤中や休憩時間を活用し、毎日少しずつでも確実に前進できる環境を提供します。
さらに、教育担当者の管理コストを大幅に削減できる点もメリットです。オンラインの管理画面で、スタッフ一人ひとりの学習状況を一目で確認できます。これまで管理にかかっていた時間を短縮し、他の重要な業務に充てることが可能になります。
そして最大の強みは、「JLPTから介護福祉士まで」を一気通貫でサポートできる点です。 まずは「JLPT合格コース」で、介護福祉士試験の土台となるN2レベルの日本語力を徹底的に固めます。その後、次のステップとして「介護福祉士 合格対策集中講座」にスムーズに移行できます。
この「介護福祉士 合格対策集中講座」は、日本語学習サポートとして「JLPTコース」の機能も講座期間中は使い放題になるため、日本語に不安が残る方でも安心です。知識豊富な講師陣が、合格まで徹底的にサポートします。
\ 無料体験はこちら/
このたび、当社支援機関を通じて学習を続けていた外国人介護職の方が、見事「介護福祉士国家試験」に合格されました!
外国人受験者にとっては言語の壁もあり、合格は決して簡単なものではありません。それでもこの方は、目標に向かってコツコツと努力を積み重ね、見事に合格を勝ち取りました!

- ■ 介護福祉士を目指した理由
「日本で安心して長く働き、家族を支えたい」という強い思いから、介護福祉士を目指しました。
資格を取れば、より安定した働き方ができ、将来的なキャリアアップにもつながると考えたからです。
- ■ 1日3時間、仕事と両立しながらの学習
勉強は約1年前からスタート。
本業の合間や休日も使いながら、毎日3時間以上コツコツと学習を積み重ねていきました。
特に役立ったのが、支援機関から紹介された「日本語と介護のビデオ教材」です。
スマホでいつでも見られるため、通勤時間や休憩時間も有効に使え、自分のペースで理解を深めることができました。
ビデオで全体の流れを理解した後に問題集を解き、間違いを丁寧に復習することで、確実に実力がついていくのを実感できました。
- ■ 教材だけでなく、現場からも学ぶ
教科書や試験対策アプリも活用しつつ、職場の先輩に積極的に質問し、現場での経験を通じて実践的な知識も習得していきました。
学習と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、「自分を信じて、最後まであきらめないこと」が何より大切だったと振り返っています。
\ 詳しくはこちら/
外国人のサポートまとめ

この記事では、特に「特定技能」の介護士に焦点を当て、施設側が行うべきサポート体制と、介護福祉士取得に向けた学習ロードマップを詳細に解説しました。
特定技能のスタッフに長く活躍してもらうためには、法律で定められた支援義務を誠実に実行し、日本で安心して働ける生活基盤を整えることが不可欠です。
その中でも、最も重要かつ戦略的に取り組むべきなのが「日本語サポート」です。それは、現場のコミュニケーション課題を解決して日々の業務の質を高めるためだけでなく、彼らが「特定技能」の次のステップである「在留資格『介護』」を取得し、貴施設で永続的に活躍するための「介護福祉士」国家試験合格に直結するからです。
特定技能スタッフの日本語教育の仕組み化や、介護福祉士の資格取得支援に関して、具体的な進め方やコスト面でお悩みの施設様は、ぜひ一度「日本語カフェ」にご相談ください。
\ お問い合わせはこちらから/