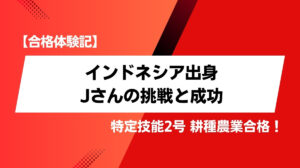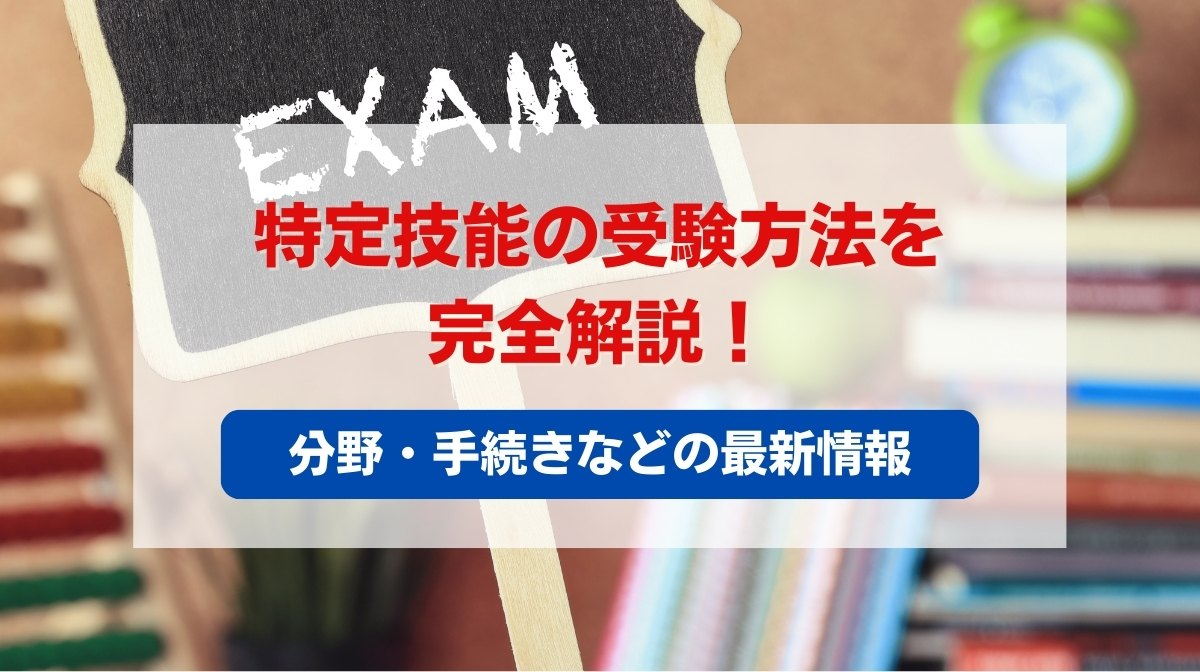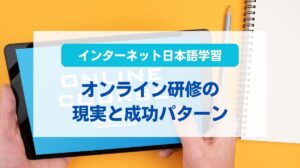特定技能を持つ外国人材の採用や、現在雇用しているスタッフの特定技能2号への移行をお考えではありませんか。「特定技能の試験について調べても、情報が複雑で分かりにくい」「外国人スタッフの受験に向けて、企業として何をどこまで支援すれば良いのか判断に迷う」といった疑問や悩みを抱える企業の担当者様も多いのではないでしょうか。
外国人材の受け入れは、企業の人手不足を補うだけでなく、組織の活性化にも繋がる重要な取り組みです。しかし、その第一歩となる在留資格の取得、特に特定技能制度における試験の仕組みは、分野ごとに異なり、全体像を把握するのが難しい側面もあります。
この記事では、特定技能外国人の雇用を検討する企業の皆様に向けて、特定技能の受験に必要な情報を一から分かりやすくご案内します。
試験の基本的な概要から、分野ごとの確認方法、申し込み、そして合格後の手続きに至るまで、企業の担当者が知りたいポイントをまとめました。この記事を最後までお読みいただくことで、特定技能の受験に関する疑問が解消され、自信を持って外国人材の受け入れ準備を進められるようになります。
まず確認|特定技能の受験とは?企業が知るべき3つの基本
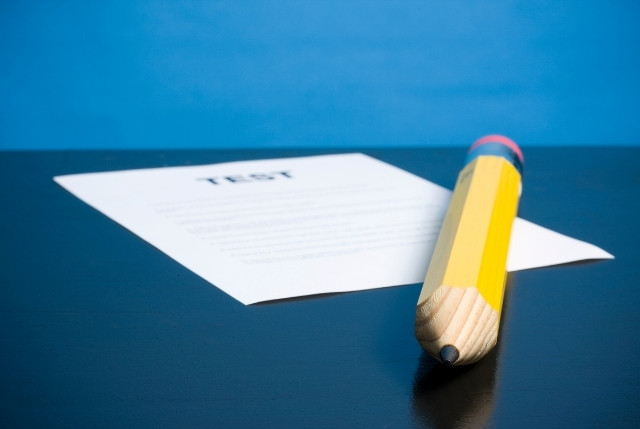
特定技能の受験について理解を深めるため、まずは制度の根本的な部分から押さえていきましょう。ここでは、企業担当者として必ず知っておきたい3つの基本事項を解説します。
1. 特定技能制度の概要と技能実習との違い
特定技能制度とは、国内において人材の確保が難しい産業分野で、専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格です。深刻化する人手不足に対応するための制度であり、即戦力となる人材が対象となります。
ここで、多くの企業担当者様が混同しやすい「技能実習制度」との違いを明確にしておきましょう。
技能実習制度の主な目的は、日本で培った技能や技術、知識を開発途上地域へ移転することによる「国際貢献」です。実習という形で技術を学び、母国でその技術を活かしてもらうことが期待されています。
一方、特定技能制度の目的は、「国内の人手不足の解消」です。そのため、外国人材は労働者として受け入れられ、企業と直接の雇用契約を結びます。目的が「国際貢献」か「労働力の確保」かという点で、両者は根本的に異なります。
2. 受験が必要な2種類の試験
特定技能の在留資格を得るには、原則として2種類の試験に合格しなくてはなりません。それは、専門技能を測る「技能評価試験」と、日本語でのコミュニケーション能力を測る「日本語能力試験」です。
この試験は、それぞれの産業分野で求められる専門的な知識や経験、技能を持っているかを証明するためのものです。試験内容は分野ごとに大きく異なり、学科試験だけでなく、実技試験が課される場合もあります。まさに、その分野で即戦力として働ける水準にあるかを評価するテストです。
業務上の指示を理解したり、同僚とコミュニケーションを取ったり、日本で安全に生活したりするために必要な日本語のレベルを証明する試験です。この基準を満たすためには、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
-
主に就労のために来日する外国人を対象とした試験で、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」が求められます。コンピュータ・ベースト・テスティング(CBT)方式で、受験機会が多いのが特徴です。
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上
-
幅広い層を対象とした日本語能力を測定する試験です。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされており、特定技能で求められる水準を満たします。
3. 試験が免除されるケース
原則として上記2つの試験合格が必要ですが、特定の条件を満たす外国人は、技能・日本語の両方またはいずれかの試験が免除されます。企業にとって、試験免除の対象となる人材は採用プロセスを簡略化できるため、非常に重要なポイントです。
最も一般的なケースは、「技能実習2号を良好に修了した方」です。技能実習2号を終えた外国人が、実習時に行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合、技能評価試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
その他、介護分野においては特例が設けられています。「介護福祉士養成施設」を修了した場合は両試験が免除されます。自社が受け入れたい人材が、これらの免除要件に当てはまるかどうかを事前に確認することが大切です。

【分野別】特定技能試験の対象分野と情報確認先一覧

特定技能制度は、験の日程や内容、申し込み方法は、これらの分野ごとに定められた試験実施機関が管理しています。したがって、自社が属する分野の正しい情報を得るためには、管轄機関の公式サイトを直接確認することが重要です。
主な分野の試験情報・問い合わせ先
以下に、分野ごとの試験概要と、情報を確認できる公式サイトをまとめました。詳細な試験情報や最新の案内は、各機関の公式サイトでご確認ください。
| 介護分野 | 所管省庁は厚生労働省です。 「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の2つに合格する必要があります。 試験に関する最新情報は厚生労働省のウェブサイトで案内されています。 |
|---|
参考:介護技能評価試験、介護日本語評価試験|PROMETRIC
| ビルクリーニング分野 | 所管省庁は厚生労働省です。 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があり、試験は公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会が実施しています。 |
|---|
参考:ビルメンWEB 特定技能
| 工業製品製造業 | 所管省庁は経済産業省です。 「製造分野特定技能1号評価試験」という名称で、分野横断的な試験が実施されます。 詳細は経済産業省のウェブサイトで確認できます。 |
|---|
参考:試験概要|特定技能外国人材制度 (工業製品製造業分野)ポータルサイト
| 建設分野 | 所管省庁は国土交通省です。 「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があり、試験は一般財団法人 建設業振興基金(JAC)が実施しています。 |
|---|
参考:建設分野特定技能の評価試験情報と申し込み|Japan Association for Construction Human Resources
| 造船・舶用工業分野 | 所管省庁は国土交通省です。 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」という名称で、溶接、塗装、鉄工など職種別の試験が行われます。 試験実施機関は一般財団法人 日本海事協会です。 |
|---|
| 自動車整備分野 | 所管省庁は国土交通省です。 「自動車整備分野特定技能評価試験」に合格する必要があり、試験は一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会が実施しています。 |
|---|
参考:自動車整備分野特定技能評価試験|一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
| 航空分野 | 所管省庁は国土交通省です。 「航空分野特定技能評価試験」という名称で、空港グランドハンドリングや航空機整備に関する試験が行われます。 試験は一般財団法人 日本航空協会が実施しています。 |
|---|
| 宿泊分野 | 所管省庁は国土交通省です。「宿泊業技能測定試験」に合格する必要があり、試験は一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しています。 |
|---|
| 農業分野 | 所管省庁は農林水産省です。 「農業技能測定試験」という名称で、耕種農業全般または畜産農業全般に関する試験が行われます。 試験は全国農業会議所が実施しています。 |
|---|
| 漁業分野 | 所管省庁は農林水産省です。 「漁業技能測定試験」という名称で、漁業と養殖業の2種類があります。 試験は一般社団法人 大日本水産会が実施しています。 |
|---|
| 飲食料品製造業分野 | 所管省庁は農林水産省です。 「飲食料品製造業技能測定試験」に合格する必要があり、試験は一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。 |
|---|
参考:飲食料品製造業国内試験|OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
| 外食業分野 | 所管省庁は農林水産省です。 「外食業技能測定試験」に合格する必要があり、飲食料品製造業と同じく、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が試験を実施しています。 |
|---|
参考:外食業国内試験|OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
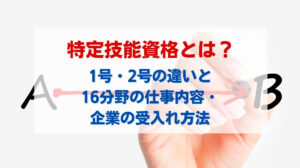
特定技能の受験手続き|日程確認から合格後までの4ステップ

実際に外国人スタッフが試験を受ける際の手続きの流れを、4つのステップに分けて具体的に見ていきましょう。企業担当者として、各ステップでどのようなサポートが必要になるかをイメージしながらご確認ください。
試験日程と開催場所の確認
まず初めに、受験を希望する分野の試験が「いつ」「どこで」実施されるのかを確認します。試験は日本国内だけでなく、フィリピンやベトナム、インドネシアといった海外でも開催されています。国内在住者か海外在住者かによって、受験地を選択することになります。
最新の試験日程や開催地、受験要綱に関する情報は、前述した各分野の試験実施機関の公式サイトで公表されます。定期的にサイトを確認し、申し込み期間を逃さないようにすることが重要です。また、企業の採用活動を支援する登録支援機関などに相談し、情報を提供してもらう方法もあります。
受験の申し込み方法
試験日程を確認したら、期間内に受験の申し込みを行います。申し込みは、基本的に各試験実施機関のウェブサイト上にある専用ページから行います。多くの場合、最初にIDとパスワードを設定して個人のアカウント(マイページ)を作成し、そこから受験申請や結果確認を行う仕組みになっています。
申し込みの際には、氏名や国籍といった個人情報に加え、パスポート情報などの入力が求められます。入力ミスがないよう、外国人スタッフ本人と企業担当者が一緒に確認しながら進めると安心です。申し込みが完了すると、後日、受験票が発行されます。
試験の準備と実施
申し込みを済ませたら、試験本番に向けて準備を進めます。技能評価試験の対策としては、各機関が公開しているサンプル問題やテキストを活用するのが一般的です。日本語能力試験についても、レベルに応じた教材を用いて学習を進めることになります。
この段階で、企業の支援が大きな意味を持ちます。学習時間を確保できるようシフトを調整したり、教材費を補助したり、あるいは勉強会を社内で開いたりといったサポートは、受験するスタッフのモチベーションを高めます。外国人材が安心して学習に集中できる環境を整えることが、合格への近道となるでしょう。
合格の確認と次の手続き
試験後、定められた日に合格発表が行われます。これもマイページ上で確認するのが一般的です。無事に合格していたら、合格証明書を取得します。この証明書は、次の在留資格申請で必要となる重要な書類です。
試験合格後、企業は出入国在留管理庁に対して、在留資格「特定技能1号」の交付申請(海外在住者の場合)または変更許可申請(国内在住者の場合)を行います。企業の事業内容に関する書類や、外国人材との雇用契約に関する書類など、多くの提出物が必要になります。計画的に準備を進めましょう。
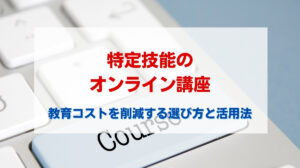

特定技能2号への移行|必要な試験と手続き

特定技能1号で経験を積んだ外国人材は、さらに高い専門性が求められる「特定技能2号」へ移行する道が開かれています。
特定技能2号は、熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間の更新に上限がありません。条件を満たせば家族の帯同も可能になるなど、外国人材が日本で長期的にキャリアを築いていく上で重要な資格です。
この特定技能2号へ移行するためにも、分野ごとに定められた技能評価試験に合格する必要があります。試験は1号よりも難易度が高く、現場のリーダーとして活躍できるレベルの技能・知識が問われます。
2号試験の実施状況や手続きに関する詳細も、各分野の公式サイトで案内されていますので、1号からのステップアップを考える際には必ず確認してください。
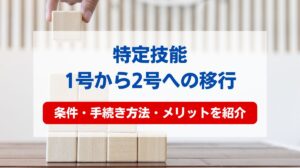
特定技能の受験に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、企業の担当者様から寄せられることの多い、特定技能の受験に関する質問とその回答をまとめました。
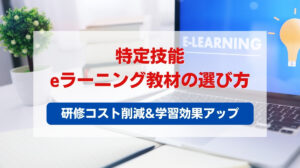
外国人スタッフの学習支援にお悩みの企業様へ
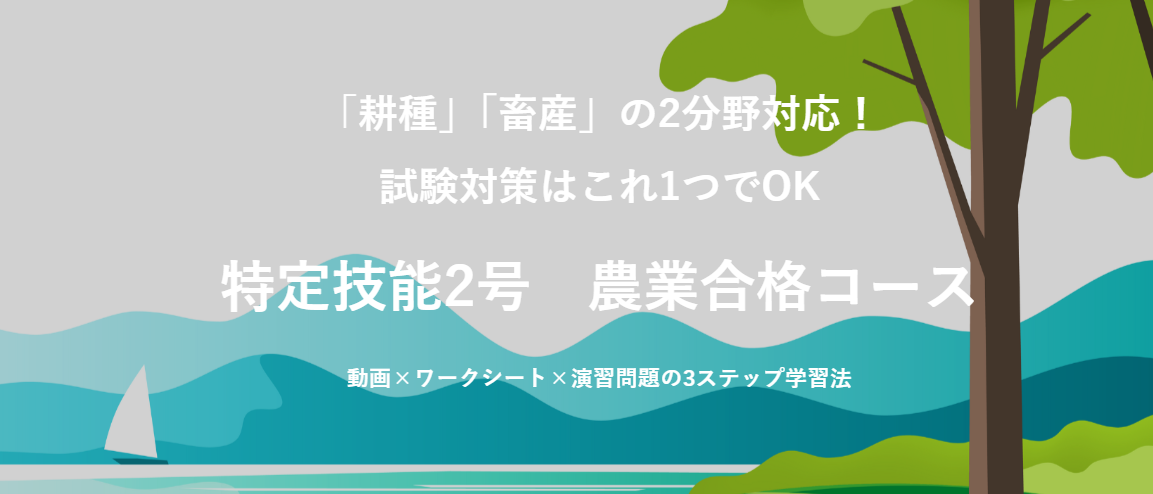
「スタッフの学習モチベーションの維持や管理が大変…」
「受け入れ人数が多く、教材の費用がかさんでしまう…」
「外国人スタッフが自発的に学習を進めてくれる教材が欲しい…」
もしあなたが外国人スタッフの特定技能資格の習得をもっとシンプルで簡単に、それでいてコストを抑えたいとお考えなら、『特定技能1号・2号合格コース』の利用がおすすめです。
学科試験と実技試験の合格に特化した動画カリキュラムが使い放題。利用者一人ひとりの学習状況を一目で確認できるので、管理にかかっていた時間も大幅に短縮できます。 また、厳しい審査を通過した日本語教育の専門家が監修した、N5〜N1試験の合格コースも併せてご利用いただけます。
- 体系的な理解を促す動画と教材
-
日本語カフェでは1本あたり15分程度のオリジナル解説動画をご用意しており、すべての出題範囲を網羅しています。
専門用語や専門知識が求められる内容でも、母語のスライドと音声による解説で分かりやすく体系的に学ぶことができます。
- 実践力を養うオリジナル演習問題
-
複数パターンのオリジナル問題を豊富に用意しているため、本番と同様の形式で何度でも練習が可能です。
どのような問題が出ても対応できる実力と自信を育てます。
- 独自の「3ステップ学習法」で着実にステップアップ
-
日本語カフェではオリジナルの教材を用いた「3ステップ学習法」で学習を進めていきます。
- 解説動画を視聴する: 各国語のスライドと音声でインプット
- ワークシートに記入する: 動画と連動した穴埋め問題で知識を定着
- 演習問題を解く: 独自制作の問題で繰り返しアウトプット
特定技能2号・農業に3ヶ月で合格!

特定技能1号として日本で働いていたSさんは、在留期間が最長5年までという制限に不安を感じ、「もっと長く日本で働き、将来は家族とも安心して暮らしたい」という目標を持ちました。
その思いから特定技能2号の取得を決意。毎日欠かさず学習を続け、講師とのレッスンや教材を活用しながら知識を積み重ね、3か月で合格を果たしました。
- 学習方法・スケジュール
- 学習期間:2025年2月〜5月(約3か月)
- 使用教材:2号農業用テキスト、支援機関のビデオ教材(日・技能対応)
- 学習スタイル:
- 週3回、母語講師との日本語レッスンを1時間実施
- 毎朝 6:00~7:30 に集中して勉強
- ビデオ教材を繰り返し視聴し知識を定着させる
- 合格のコツ・アドバイス
- 分からないことは必ず質問すること
- 漢字や専門用語は「書けなくても見て覚える」ことが大切
- 忙しくても、毎日少しずつ継続することが合格への近道
合格後は、これまでの経験を活かしつつ現在の職場で長期的に働き続け、さらにスキルを磨いていきたいと考えています。2号資格によって安定した生活の基盤が整い、将来の可能性が大きく広がったと感じています。
外国人材の教育に関するお悩みや、具体的なコース内容の詳細は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
\ お問い合わせはこちらから/