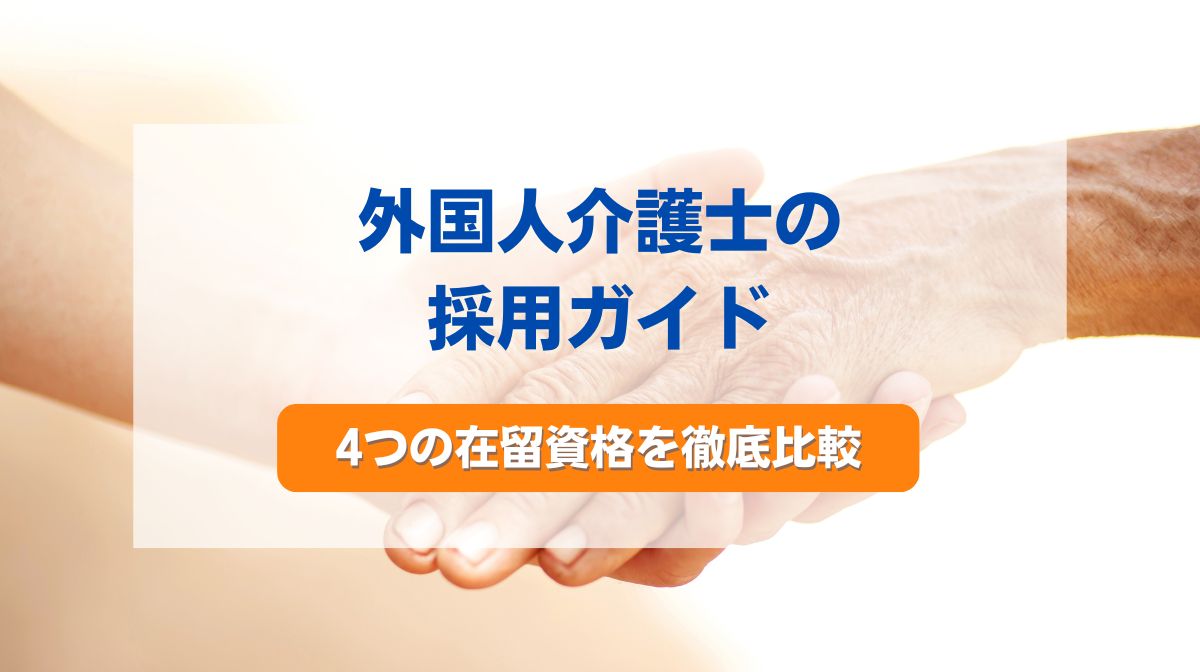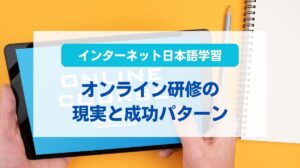日本の介護業界は、今、大きな変化の時を迎えています。高齢化の進行に伴い介護サービスの需要は増え続ける一方で、担い手となる人材の確保が追いついていない状況です。そのような中で、事業所の未来を支える新たな担い手として、外国人介護人材への期待が高まっています。
「外国人材の採用を考えたいが、制度が複雑で何から始めればいいかわからない」「現在雇用している特定技能の職員に、できるだけ長く日本で活躍してもらいたいが、どうすれば良いのだろうか」。このようなお悩みをお持ちの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人介護士の受け入れに関する制度を分かりやすく解説します。4つの主要な在留資格の違いから、採用の具体的な流れ、そして採用後の定着支援まで、貴社の状況に合った受け入れ方を見つけ、採用から定着までの道筋を描くための情報を提供します。
外国人介護士を受け入れるための4つの在留資格

「外国人介護士」と一括りにいっても、受け入れのルールとなる在留資格は複数存在します。ここでは、介護分野で就労が認められている主要な4つの制度の概要と、それぞれの目的の違いを見ていきましょう。
| 特定技能 | 介護分野の人手不足に対応するため創設された、即戦力となる人材向けの制度。 |
|---|---|
| 技能実習 | 日本で培った技能や知識を母国へ持ち帰り、経済発展に貢献してもらう国際貢献を目的とした制度。 |
| EPA(経済連携協定) | インドネシア、フィリピン、ベトナムとの二国間協定に基づき、介護福祉士候補者を受け入れる制度。 |
| 在留資格「介護」 | 日本の国家資格である介護福祉士を持つ、専門人材向けの制度。 |
それぞれの制度は目的や対象となる人材、活動範囲が異なります。貴社の理念や人材育成の方針、求める人物像と照らし合わせて、どの制度が最も適しているかを見極めることが、外国人材雇用の第一歩となります。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習 | EPA介護福祉士候補者 | 在留資格「介護」 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 介護分野の人手不足解消 | 国際貢献(技術移転) | 経済活動の連携強化 | 専門職としての就労 |
| 対象者 | 技能試験・日本語試験合格者 | 技能実習計画の認定を受けた者 | EPAの要件を満たす候補者 | 介護福祉士資格の取得者 |
| 業務内容 | 身体介護、支援業務全般 | 実習計画に基づく技能習得活動 | 研修を受けながら介護業務に従事 | 介護業務全般 |
| 在留期間 | 通算上限5年 | 最長5年 | 原則4年(滞在中合格で移行) | 更新上限なし |
| 日本語要件 | 介護日本語評価試験+N4程度 | N4程度(入国時) | N5程度(入国時、研修あり) | -(資格取得課程で習得) |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 原則不可 | 原則不可 | 可能 |
①在留資格「特定技能」:即戦力として期待される人材
特定技能は、国内での人材確保が難しい特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。介護分野もその対象職種の一つです。
「介護技能評価試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の両方に合格していることが求められます。これにより、入職時点である程度の日本語能力と介護技能を有しているため、比較的早い段階で現場の戦力として活躍することが期待できます。
また、受け入れ機関(企業)には、外国人材が安定して働けるようにするための「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。この計画には、生活オリエンテーションの実施、住宅確保の支援、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応などが含まれます。
支援体制を自社で整えるのが難しい場合は、国の登録を受けた「登録支援機関」に支援業務を委託することも可能です。
在留期間は通算で上限5年ですが、介護福祉士の国家資格を取得することで、在留期間の更新上限がなく、家族の帯同も可能となる在留資格「介護」へ移行できます。特定技能は、長期的なキャリア形成を見据えた受け入れの入り口となる制度といえるでしょう。
②在留資格「技能実習」:日本の技術を母国へ伝える人材
技能実習制度は、日本の介護現場で技能を習得し、その技術や知識を母国に持ち帰ってもらうことを目的とした、国際貢献のための制度です。そのため、受け入れにあたっては、技能実習計画を作成し、国の認定を受ける必要があります。
実習生は入国前に一定の日本語教育を受けますが、現場では実践的な技能と日本語を学んでいく形が中心となります。技能実習を良好に修了した人材は、帰国せずに特定技能1号へ移行したり、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」を目指したりすることも可能で、多様なキャリアパスが描けます。
③EPA(経済連携協定):二国間の協定に基づく介護福祉士候補者
EPAは、日本がインドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で結んだ経済連携協定に基づき、介護福祉士の候補者を受け入れる制度です。候補者は、日本の介護施設で働きながら研修を積み、介護福祉士の国家試験合格を目指します。
受け入れには国が関与しており、他の制度とは異なる枠組みで運用されています。候補者は訪日前に手厚い日本語研修を受けますが、専門的な介護用語やコミュニケーションには更なる学習が必要です。在留期間中に国家試験に合格すれば、在留資格を「介護」に変更し、日本で継続して働くことが可能になります。国家資格取得という明確な目標があるため、学習意欲の高い人材が多い傾向にあります。
④在留資格「介護」:専門学校等を卒業した高い専門性を持つ人材
在留資格「介護」は、日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を持つ外国人が対象となる専門職向けの在留資格です。この資格を取得するルートは、主に2つのパターンがあります。
一つは、日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し、資格を取得するルートです。留学生として来日し、養成施設で2年以上、専門的な知識と技術、日本語を学んでいるため、非常に高い専門性を持っています。
もう一つは、特定技能1号や技能実習、EPAといった他の在留資格で日本の介護現場に従事し、実務経験を積みながら介護福祉士の国家試験に合格するルートです。現場での実践力を備えた人材が、このルートを通じてキャリアアップを目指します。
どちらのルートで資格を取得した場合でも、在留資格「介護」を持つことで在留期間の更新に上限がなくなり、家族を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能になります。そのため、長く安定して日本で働くことができ、将来的には介護現場の中核を担う人材としての活躍が期待されます。
【目的別】自社に合うのはどの制度?ケーススタディで考える

制度の概要を理解したところで、「具体的にどの制度を選べば良いのか」という疑問にお答えします。事業所のよくあるニーズを3つのケースに分け、最適な選択肢を考えます。
ケース1:できるだけ早く、業務経験のある人材を確保したい場合
この場合は「特定技能」での受け入れが選択肢になるでしょう。特定技能の在留資格を持つ人材は、技能試験と日本語試験に合格しているため、基礎的なスキルとコミュニケーション能力が担保されています。
国内にいる他の介護施設で就労経験のある特定技能外国人を採用することも可能で、比較的スピーディーに人材を確保できる可能性があります。
ケース2:未経験者を受け入れ、時間をかけて育てていきたい場合
自社の介護理念やケアの進め方を、ゼロから丁寧に指導していきたいと考える事業所には「技能実習」が向いているかもしれません。実習計画に基づいて段階的に技能を習得していくため、事業所の方針に沿った人材育成が可能です。
育成には時間と労力がかかりますが、その分、事業所へのエンゲージメントが高い人材に育つことも期待できます。
ケース3:将来的に介護福祉士として中核を担う人材を求めたい場合
高い専門性を持ち、将来的に現場のリーダーや教育担当者としての活躍を期待する人材を求めるなら、「EPA」が適しています。EPA候補者は国家資格取得という明確な目標を持っており、モチベーションが高いです。

【5ステップで解説】外国人介護士の受け入れから就労開始までの流れ
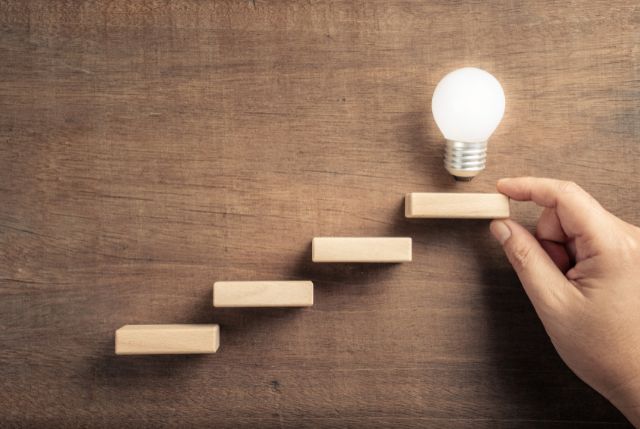
受け入れる制度が決まったら、次は具体的な手続きです。海外にいる人材を募集してから、日本で就労を開始するまでの標準的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。
海外の送出機関や国内の人材紹介会社を通じて、候補者を探します。面接では、介護への思いや日本語能力はもちろん、異文化への適応力や学習意欲なども確認します。日本の介護がチームで行う仕事であることを伝え、協調性があるかを見極めることも大切です。
採用が決まったら、候補者と雇用契約を結びます。賃金や労働時間、業務内容などを記した「雇用条件書」は、本人が十分に理解できる言語で作成することが求められます。日本人と同等以上の待遇とすることが法律で定められており、待遇に差を設けることは認められません。
受け入れ機関(事業所)が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。事業所の経営状況を示す書類や、本人の学歴・職歴を証明する書類、前述の支援計画書など、提出書類は多岐にわたります。審査には数ヶ月かかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを候補者に送付します。候補者は現地の日本大使館や領事館で証明書を提出し、ビザの発給を受けます。ビザが発給されれば、来日の準備は完了です。航空券や、生活の基盤となる住居の手配を進めます。
空港への出迎えから新生活のサポートが始まります。市区町村での住民登録、電気・ガス・水道の契約、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、日本での生活に必要な手続きを支援します。就労を開始する前に、日本の生活ルールや交通機関の使い方、職場の規則、具体的な業務内容についてオリエンテーションを丁寧に行うことが、スムーズなスタートにつながります。
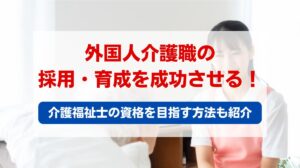
採用後の定着と活躍を支える環境づくりのポイント

外国人材の受け入れは、採用して終わりではありません。職員が能力を発揮し、長く働き続けてもらうために、事業所側ができるサポート体制や環境づくりについて3つの観点からご紹介します。
コミュニケーションの壁を乗り越えるための工夫
介護現場では、利用者様との細やかな意思疎通や職員間の情報共有が求められます。ふりがな付きの業務マニュアルや、写真・イラストを多用した手順書を用意すると、視覚的に理解を助けることができます。また、介護記録のテンプレートを作成し、記入例を示すことも役立ちます。
大切なのは、外国人職員だけに日本語の習得を求めるのではなく、日本人職員側も「やさしい日本語」を使う、ゆっくり話すといった配慮をすることです。お互いの文化を理解するための研修を実施し、チーム全体のコミュニケーションを円滑にする意識を持つことが望ましいです。
文化や生活習慣の違いへの配慮とサポート体制
宗教上の理由(お祈りの時間の確保、ハラルなど食事への配慮)や、日本特有の生活習慣(ゴミの分別、騒音への配慮など)で、外国人職員が戸惑うことがあります。母国の文化を尊重する姿勢を示すとともに、日本のルールを丁寧に伝え、相互理解を深めることが大切です。
生活上の困りごとを気軽に相談できるメンター役の職員を決め、定期的な面談を行うと良いでしょう。病気になった際の病院への同行や、行政手続きの補助、同郷の出身者が集まるコミュニティの情報提供など、業務外のサポートも職員の安心感につながります。
明確なキャリアパスで仕事への意欲を向上させる
日本で働き続ける上で、将来のキャリアが見えることは、仕事への意欲を維持する上で大きな支えとなります。小さなステップアップを重ねられるように、後押ししましょう。
そして最終的な目標として、介護福祉士の国家資格取得を位置づけます。資格を取得したら、どのような役割(例:チームリーダー)を任せるのか、給与などの待遇がどう変わるのかを具体的に示すことで、学習へのモチベーションはさらに高まります。
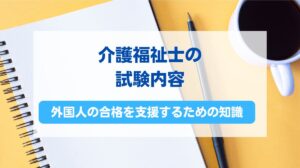
【特定技能から在留資格「介護」へ】優秀な人材に長く活躍してもらうために

5年という期間の定めがある特定技能1号。しかし、その先のキャリアパスを用意することで、優秀な人材に永続的に活躍してもらうことが可能です。ここでは、そのための重要なステップである在留資格「介護」への移行について詳しく見ていきます。
在留資格「介護」へ移行する意味
特定技能1号の在留期間は通算で5年という上限があり、永続的な雇用を約束するものではありません。しかし、その間に実務経験を積み、介護福祉士の国家試験に合格することで、在留資格を「介護」に変更することが可能です。
在留資格「介護」に移行すると、
- 在留期間の更新に上限がなくなる
- 配偶者や子供など、家族の帯同が可能になる
といった大きな変化があります。これにより、職員は生活基盤を日本に置き、腰を据えて長期的にキャリアを築くことができるようになります。
企業にとっても、育成した優秀な人材に永続的に活躍してもらえる体制を構築できるため、双方にとって価値のあるステップアップです。
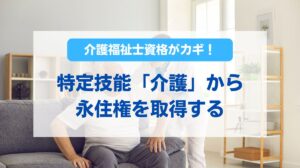
介護福祉士の資格取得に向けた企業側の準備
特定技能1号の職員が介護福祉士を目指せるように、企業側が計画的な支援を行うことが求められます。
実務経験ルートで受験資格を得るには、3年以上の実務経験に加えて「実務者研修」の修了が必要です。企業ができる具体的な支援としては、実務者研修の受講費用の補助や貸付制度の導入、研修日の出勤扱いなどが考えられます。
また、国家試験の勉強は専門的な内容も多く、一人で乗り越えるのは簡単ではありません。事業所内で過去の試験問題を使った勉強会を開いたり、日本語が得意な職員が学習のサポートをしたりするなど、チーム全体で応援する雰囲気を作ることが大切です。
試験日が近づいてきたら、夜勤を減らすなどのシフト上の配慮も、本人が学習に集中できる環境づくりとして大きな助けとなるでしょう。
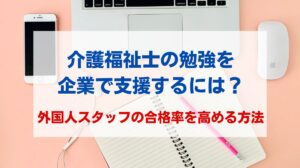
外国人介護士の定着と活躍を支える日本語教育の重要性
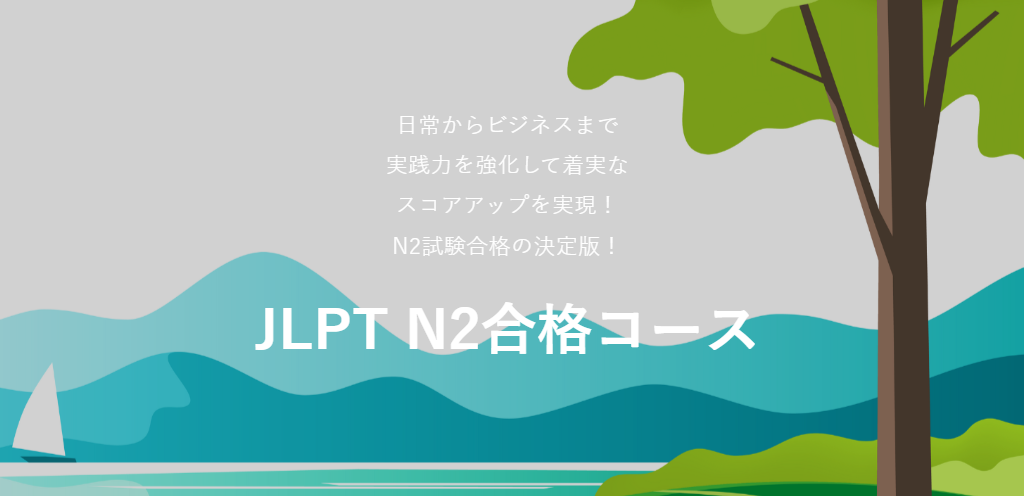
外国人介護士が日本で長く安心して働き続けるためには、介護スキルだけでなく、日本語での円滑なコミュニケーションが不可欠です。利用者様とのやり取りや職員同士の情報共有、介護記録の作成など、日常業務のあらゆる場面で日本語力が必要となります。
しかし、事業所が独自に日本語講師を雇用したり、研修を定期的に実施したりするのは、コストや運営面で大きな負担になりがちです。そんな課題を解決し、効果的かつ継続的に日本語力を伸ばせるのが、日本語カフェの「JLPT合格コース」です。
このコースは、厳しい審査を通過した一流日本語講師が監修した、合格に特化したオンライン動画カリキュラム。レベル別(N5〜N1)に最適化された学習プランで、語彙・文法・読解・聴解をバランスよく習得できます。学習状況は管理画面で一目で確認でき、受講者の進捗管理も簡単。繰り返し視聴できる動画と豊富な演習問題により、忙しい介護現場でも無理なく継続できます。
ゼロから3ヶ月でJLPT N3に合格

「日本語カフェ」で学習したフィリピン人受講者4名は、日本語学習未経験からわずか3ヶ月の学習で、日本語能力試験(JLPT)N3に全員合格しました。2025年4月に学習を開始し、1日平均6時間の自主学習を継続した結果、6月にはN5・N4を突破。そして7月には、通常半年以上かかるといわれるN3レベルに到達しました。
実際の試験結果では、文字語彙・文法読解・聴解のすべての分野で合格点をクリアしており、「日本語カフェ」のカリキュラムが短期間で成果を出せることを証明しています。
一般的に学習効果のばらつきやモチベーション維持に課題がある日本語教育ですが、明確な合格目標と効率的な学習設計により、4人全員が同時にN3合格を果たしました。
「JLPT合格コース」を導入すれば、外国人スタッフの語学力を着実に伸ばし、現場での即戦力化と長期定着を同時に実現できます。外国人スタッフの日本語教育をもっと効率的に、そしてコストを抑えて行いたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\お問い合わせはこちらから/
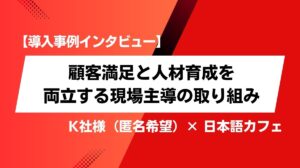
外国人介護士 まとめ

日本の介護業界では、高齢化の進行に伴い外国人介護人材の活躍がますます重要になっています。特定技能、技能実習、EPA、在留資格「介護」など、制度ごとに目的や条件、在留期間、キャリアパスは大きく異なります。自社の理念や人材育成方針と照らし合わせ、最も適した制度を選ぶことが成功への第一歩です。
採用後は、生活面や言語面のサポート、文化的配慮、明確なキャリアパスの提示が定着率を高めます。さらに、特定技能から在留資格「介護」への移行支援を行うことで、育成した人材に長く活躍してもらえる環境を整えられます。
制度の理解と計画的なサポート体制づくりを両輪として進めることで、外国人介護士が安心して力を発揮できる職場を実現し、介護現場の未来を支える強いチームを築くことができるでしょう。