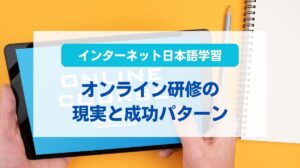「畜産現場で外国人材を受け入れたいけど、どうしたらいい?」と疑問を感じていませんか?
特定技能「畜産農業」は、日本の深刻な人手不足に悩む畜産現場で、外国人材が専門的なスキルを活かして活躍できる在留資格です。
この制度は、働く外国人材にとっても安定した就労機会とキャリアパスを提供し、受け入れ企業にとっては即戦力となる人材確保の大きな力となります。
この記事では、特定技能「畜産農業」の外国人を採用したい人向けに、取得方法から仕事内容の詳細、受け入れ要件、特定技能2号への移行の情報まで、ポイントを詳しく解説します。
特定技能「畜産農業」とは

日本の畜産農業は、高齢化と若年層の労働力不足により、深刻な人手不足に直面しています。
このような状況を打開するため、2019年に創設されたのが「特定技能制度」です。
この制度は、特定の産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としており、畜産農業もその対象となっています。
人材不足の現状と特定技能制度の役割
日本の食料供給を支える畜産農業は、飼育管理から畜産物処理まで多岐にわたる作業が必要であり、季節や天候に左右されない安定した労働力が求められています。
しかし、労働人口の減少により、必要な労働力を確保することが難しくなってきています。
特定技能制度は、このような人材不足を解消するための有効な手段として注目されており、畜産農業の現場に新たな活力を吹き込むことが期待されています。
特定技能「畜産農業」の基本的な概要
特定技能「畜産農業」は、畜産農業分野で働く外国人に与えられる在留資格です。
| 在留期間 | 特定技能1号として、最長5年間日本に滞在し、就労することができます。 |
|---|---|
| 業務範囲 | 畜産農業における「飼養管理」と「畜産物処理」の業務に従事できます。 |
| 家族帯同 | 特定技能1号の期間中は原則として家族の帯同は認められません。ただし、特定技能2号へ移行すると家族帯同が可能になります。 |
| 転職の可能性 | 同じ畜産農業分野内であれば、転職も可能です。 |
| 特定技能2号への移行 | 一定の条件を満たせば、特定技能2号へ移行し、在留期間の上限なく日本で働き続けることが可能になります。 |
特定技能「畜産農業」の仕事内容
特定技能「畜産農業」で働く外国人が従事できる業務は、大きく「飼養管理」と「畜産物の集出荷・選別等」の2つに分けられます。
飼養管理
これは、家畜(牛、豚、鶏など)を育てるための日常的な作業全般を指します。
| 餌やり・給水 | 適切な量とタイミングで餌を与え、清潔な水を提供します。 |
|---|---|
| 清掃・衛生管理 | 畜舎の清掃、糞尿処理、換気を行い、家畜が快適に過ごせる環境を維持し、病気の発生を防ぎます。 |
| 健康管理 | 家畜の健康状態を観察し、異常の早期発見に努めます。必要に応じて、簡易な処置や獣医への報告を行います。 |
| 繁殖管理 | 繁殖サイクルに基づいた交配補助、分娩・孵化の補助、子畜のケアなどを行います。 |
| その他 | 畜舎の簡単な修繕、敷料の交換、資材の運搬なども含まれます。 |
畜産物の集出荷・選別等
生産された畜産物を、食品として出荷できる状態にするための作業です。
| 牛乳・乳製品の加工 | 搾乳、牛乳の運搬、冷却、殺菌、充填、チーズやバターなどの乳製品製造補助など。 |
|---|---|
| 食肉の処理 | 解体補助、加工、パック詰め、運搬など。 |
| 卵の選別・包装 | 鶏卵の回収、選別(サイズ、品質)、パック詰め、出荷準備など。 |
参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁
特定技能「畜産農業」で働くための要件

特定技能「畜産農業」の在留資格を取得するには、「技能試験の合格」と「日本語能力試験の合格」が必要です。
要件1: 技能試験の合格(または技能実習2号修了)
畜産農業分野で働くための専門的な知識と技能があることを証明するために、以下のいずれかの要件を満たす必要がありますので、確認しておきましょう。
- 農業技能測定試験(畜産)の合格
-
この試験は、畜産農業に必要な基本的な知識と技能を測るものです。
具体的な試験内容には、家畜の飼養管理(餌やり、清掃、健康チェックなど)、繁殖管理、畜産物処理(乳加工、食肉加工など)に関する問題が出題されます。
- 技能実習2号からの移行
-
畜産農業分野の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験が免除されます。
これは、すでに実務経験と一定の技能が認められているためです。
スムーズな移行のためには、技能実習期間中に真摯に業務に取り組み、必要な知識と技能を習得することが重要です。
要件2: 日本語能力試験の合格
日本で生活し、働く上で必要な日本語能力を証明するため、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格
-
日常生活や就労に必要な日本語能力があるかを測る試験で、特定技能ビザの取得要件として広く認められています。
オンラインで受験可能で、結果も試験後すぐに分かります。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格
-
「基本的な日本語を理解できる」レベル(N4)またはそれ以上の合格が必要です。
JLPTは年に2回(7月と12月)実施されており、世界中で受験が可能です。
日常会話や業務指示の理解に必要となるため、語彙、文法、読解、聴解のバランスの取れた学習が求められます。
その他の要件
上記試験の合格に加え、以下の一般的な要件も満たす必要があります。
- 年齢
- 18歳以上であること。
- 健康状態
- 健康であり、畜産農業の業務に従事できること。
- 欠格事由
- 日本の法令に違反する行為(過去の犯罪歴や不法滞在歴など)がないこと。
これらの要件をクリアすることで、特定技能「畜産農業」の在留資格を取得し、日本で畜産農業に従事する道が開けます。
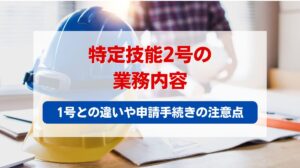
外国人を受け入れるための要件と手続き

畜産農業分野で特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、様々な要件と手続きが求められます。
受け入れ機関の要件
外国人材を適正に雇用するため、受け入れ機関は以下の要件を満たす必要があります。
- 労働関係法令の遵守
-
労働基準法、労働安全衛生法など、日本の労働関連法令を遵守していること。
- 外国人への報酬基準
-
日本人と同等の業務内容・責任を持つ日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
- 過去の不正がないこと
-
出入国・労働関係法令に関する重大な違反や不正行為がないこと。
- 外国人材の生活支援体制の整備
-
特定技能外国人が安心して日本で生活・就労できるよう、支援を行う体制を整えること。
支援計画の作成と実施
特定技能外国人を受け入れる企業は、在留中に安定した生活を送れるよう「支援計画」を作成し、実施することが義務付けられています。
- 入国前の生活オリエンテーション
- 空港等への送迎
- 住居の確保に係る支援
- 生活に必要な契約に係る支援(銀行口座開設、携帯電話契約など)
- 生活オリエンテーション(入国後)
- 公的機関への手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流の促進
- 転職支援(やむを得ない場合に限る)
登録支援機関に委託するメリット
これらの支援業務を、専門知識を持つ「登録支援機関」に委託することができます。
自社で支援体制を構築する手間やコストを削減でき、法令遵守の面でも安心です。
登録支援機関は、支援計画の作成から実施、出入国在留管理庁への報告までを一貫してサポートします。
雇用契約と重要事項説明
特定技能外国人を雇用する際は、日本の労働基準法に基づいた雇用契約書を作成します。
この雇用契約書や労働条件通知書は、外国人材が理解できるよう母国語に翻訳して説明することが義務付けられています。
また、重要事項説明も行い、業務内容、労働時間、給与、休日、安全衛生など、労働条件について十分に理解してもらうことが大切です。
申請手続きのステップ
特定技能外国人を受け入れるための主なステップは以下の通りです。
企業と外国人材の間で雇用契約を結びます。
自社で支援を行うか、登録支援機関に委託して支援計画を策定します。
- 海外から呼び寄せる場合は、企業の所在地を管轄する出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
- 日本に在留中の外国人(例:技能実習生、留学生など)を受け入れる場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
申請には、雇用契約書、支援計画書、企業側の登記事項証明書、決算書、外国人材のパスポートや学歴・職歴を証明する書類など、多くの書類が必要です。

畜産農業分野での受け入れ事例を紹介

外国人材の長期的な活躍に期待 ― 鎌田牧場の取り組み
外国人材の受け入れと定着に積極的に取り組む鎌田牧場の事例をご紹介します。特定技能制度を活用し、地域や職場に根ざした支援体制を整えることで、外国人材が安心して長期的に働ける環境づくりに成功しています。
肉牛3,900頭を飼育し、年間売上8〜9億円を誇る鎌田牧場では、日本人15名以上に加えて外国人6名が働いています。外国人材の在留資格は「特定技能(畜産)」3名(いずれもカンボジア人男性)、「技能実習」2名、「特定活動」1名。特定技能人材の導入により、長期雇用が可能になり、現場の安定と即戦力としての期待が高まっています。
以前は技能実習制度を利用していたものの、肉牛肥育では制度上2年目以降の継続が認められず、せっかく育った人材も1年で帰国していました。こうした背景から、特定技能制度には大きな期待を寄せており、ファーマーズ協同組合で実習を終えたカンボジア人3名が牧場での就労を希望したことをきっかけに導入が進みました。
外国人材の能力を高く評価しているため、雇用条件も日本人と同等以上。車の運転が生活に欠かせない地域性を考慮し、自動車免許の取得費用や軽自動車の購入費用も牧場が負担しています。1年ごとの契約更新としながらも、原則5年以上の雇用を想定し、相互の信頼関係を大切にしています。
生活面では、新築の寮を整備し、地域の草刈り活動などにも参加することで、地域とのつながりづくりにも積極的です。休日は自己管理制で、自由に外出が可能です。
安全衛生面では、牛舎作業は基本的に2人1組。将来的には大型機械を扱う可能性もあるため、必要な指導を行っています。就労開始から半年ですが、今後は外国人材を管理する責任者として育成し、ピラミッド型の体制づくりも構想中です。
また、外国人材の能力向上にも力を入れており、元公務員で教育学部卒の日本語講師を招き、毎週日本語学習の時間を設けています。教科書はN1レベルを使用しており、非常に高度な学習が行われています。
労働条件も日本人と同様で、休憩や休日の取得、残業代の支払い、福利厚生面も配慮されています。歓迎会や懇親の場も設けるなど、働きやすい環境づくりが進められています。昇給については1年目のため未定ですが、今後は年に3%程度の昇給を検討中です。
鎌田牧場では、外国人材を単なる労働力としてではなく、長く共に働き、育成していく仲間として位置づけています。その姿勢が、農業・畜産分野における持続的な人材確保のモデルとなりつつあります。
特定技能1号から2号へキャリアアップ

特定技能制度の大きな魅力の一つは、特定技能1号から特定技能2号への移行というキャリアパスが用意されていることです。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 在留期間の上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者、子) |
| 取得分野 | 16分野 | 11分野 |
| 試験 | 技能試験・日本語試験に合格 | 熟練した技能(専門級試験など)を証明 |
畜産農業分野における2号移行の要件
畜産農業分野で特定技能2号へ移行するには、特定技能1号の在留期間中に以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能1号で2年以上の実務経験
-
畜産農業分野で特定技能1号として2年以上継続して就労していること。
- 熟練した技能の証明
-
農業技能測定試験の「専門級(仮称)」に合格すること、またはそれに準ずる評価を受けること。
これは、より高度な技能と経験を持つことを証明するものです。
- 監理技術者等、一定の役職経験など
-
特定技能2号は、現場で熟練したリーダーシップを発揮できる人材が対象となるため、特定技能1号の期間中に一定の役職経験や責任ある業務を経験していることが求められる場合があります。
特定技能2号取得のメリット
特定技能1号から2号へ移行するメリットは、外国人労働者にとってはもちろん、受け入れ企業にとっても非常に大きいです。
- 在留期間の制限がなくなる
-
特定技能1号では最長5年までしか日本に滞在できませんが、2号では在留期間の更新に上限がなく、更新し続ける限り日本で働き続けることができます。
事実上、永住することも可能になります。
- 家族の帯同が可能になる
-
特定技能1号では原則として家族の帯同は認められていませんが、2号では配偶者と子を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能になります。
これは精神的な安定にも繋がり、長期的な就労を支える大きな要因となります。
- 永住権取得の可能性が開ける
-
在留期間に制限がなくなるため、特定技能2号として日本で10年以上働き続けることで、日本の永住権取得の条件を満たす可能性が出てきます。
- キャリアアップと責任ある仕事
-
特定技能2号は、1号よりも高い技能水準が求められます。
そのため、より高度な業務や、現場のリーダーとして指示・監督を行うなど、責任あるポジションに就くことが期待されます。
- 日本語能力試験の免除(一部分野を除く)
-
特定技能2号の在留資格取得にあたっては、原則として日本語能力試験が不要となります。
- 長期的な人材確保
-
在留期間の制限がなくなるため、企業は特定技能2号の外国人材を長期的に雇用することができます。
これにより、人材の定着率が向上し、採用や教育にかかるコストを削減できます。
- 熟練した即戦力の確保
-
特定技能2号は、より高い技能水準を持つ人材であるため、即戦力として期待できます。
生産性の向上や技術力の強化に繋がる可能性があります。
- 支援義務の軽減
-
特定技能1号では、受け入れ企業または登録支援機関による外国人労働者への支援(生活オリエンテーション、相談対応など)が義務付けられていますが、特定技能2号ではこれらの支援が不要となります。
これにより、企業の管理コストや手間を削減できます。
- 離職率の低下
-
家族帯同が可能になることで、外国人労働者の日本での生活の安定性が増し、離職率の低下に繋がることが期待されます。
- マネジメント層の育成
-
技能レベルの高い特定技能2号の外国人材には、将来的にマネジメントなどの重要なポジションを任せることも可能になり、組織全体の強化に繋がります。
このように、特定技能1号から2号への移行は、外国人労働者にとっては日本での安定した生活とキャリアアップの機会を、受け入れ企業にとっては優秀な人材の長期雇用と経営の安定をもたらす、双方にとって大きなメリットのある制度と言えます。
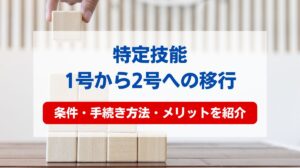
日本語カフェの特定技能2号「畜産農業」試験対策講座
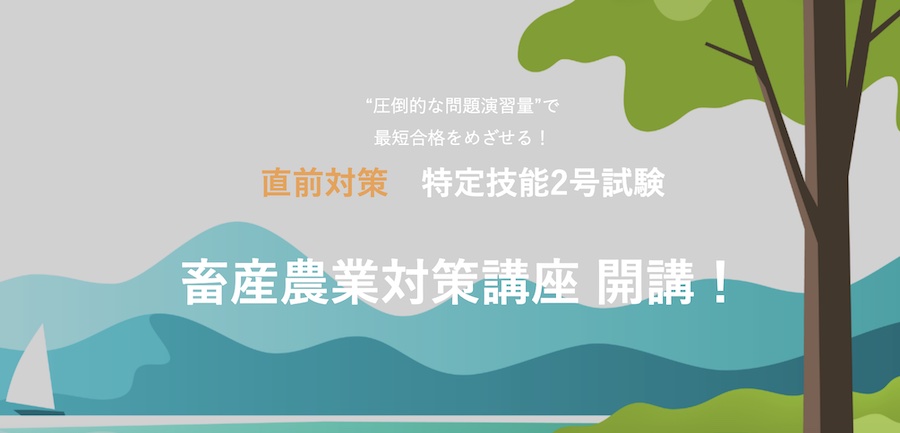
最短ルートで合格を目指すなら、”日本語カフェ”の「畜産農業対策講座」が圧倒的におすすめです!
「試験内容がよくわからない」
「学習に限界を感じている」
「確実に合格してキャリアアップしたい」
そんな方のために、日本語カフェでは、プロ監修のカリキュラムと経験豊富なコーチによる徹底サポートで
試験対策を支援します!
- わかりやすい解説動画と演習問題で理解が深まる
- 模擬試験で本番対策もバッチリ
- スマホでスキマ時間に学習できるから、働きながらでも安心
今すぐ一歩を踏み出して、確実な合格とキャリアアップを実現しましょう!
特定技能「畜産農業」まとめ

特定技能「畜産農業」は、日本の畜産現場が抱える人材不足の課題を解決し、同時に外国人材が日本で安定的に働き、キャリアを形成するための重要な制度です。
この制度を正しく理解し、活用することで、外国人材は安心で充実した日本での就労生活を送ることができ、受け入れ企業は持続可能な事業運営のために不可欠な労働力を確保できます。
外国人材にとって魅力的な職場環境を整備し、共に日本の畜産の未来を築いていきましょう。