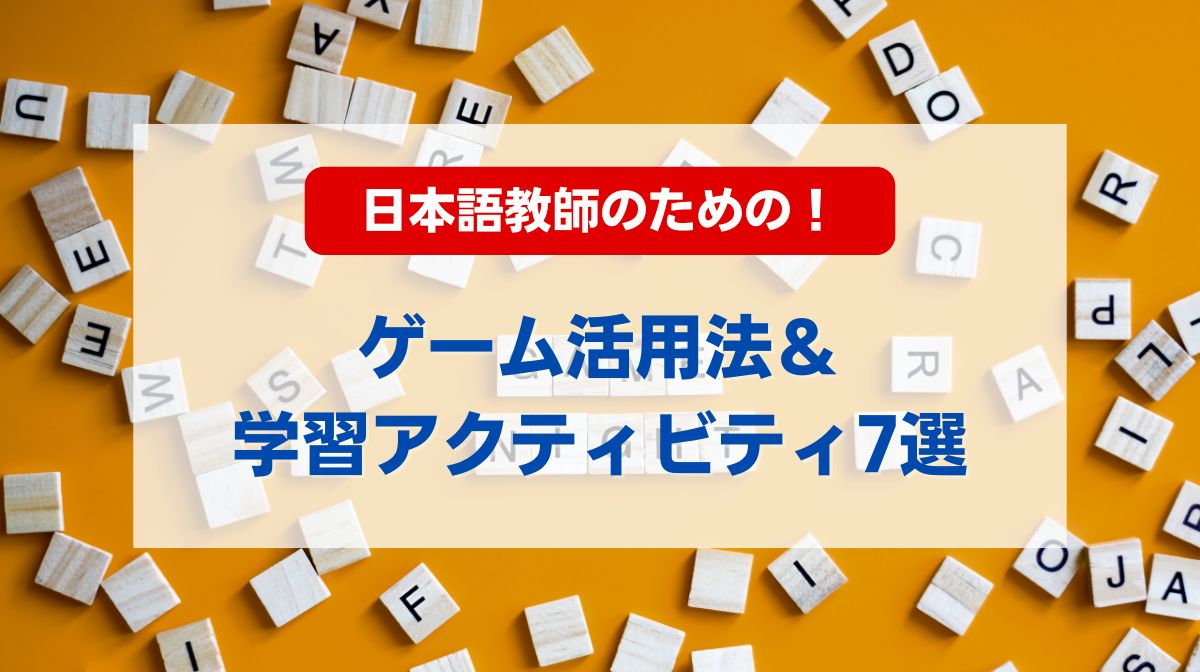「また今日も教科書の例文を読んで、練習問題を解いて…」そんな授業に、学習者の目がだんだん曇っていくのを感じたことはありませんか?日本語教育の現場で長く教えていると、どうしても授業がパターン化してしまいがちです。
しかし、ちょっとした「ゲーム」を取り入れるだけで、教室の雰囲気は一変します。学習者の表情が明るくなり、積極的に日本語を使おうとする姿が見られるようになります。
本記事では、日本語教育にゲームを取り入れるメリットと、明日からすぐに使える具体的なアクティビティを7つご紹介します。
\ 日本語学習システム/
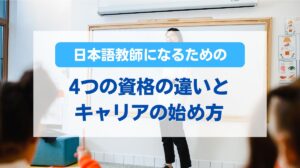
日本語教育に「ゲーム」を取り入れるメリット

「ゲーム」と聞くと、「遊びの時間」「学習効果が低い」と思われる方もいるかもしれません。しかし、教育的に設計されたゲームは、従来の教授法では得られない多くの学習効果をもたらす、非常に効果的な指導手法なのです。
能動的な学習への効果
講義型の授業では、学習者は受動的に情報を受け取るだけになりがちです。一方、ゲームを取り入れた授業では、学習者自身が考え、判断し、実際に日本語を使って行動する必要があります。
この「能動的な学習」は、言語習得において極めて重要です。脳科学の研究でも、自ら考えて使った言葉は、ただ聞いたり読んだりした言葉よりも記憶に定着しやすいことが分かっています。
ゲームの中では、学習者は「日本語を使わなければゴールできない」「相手に伝えるにはどう表現すればいいだろう」と自然に考えます。この思考プロセス自体が、深い学びにつながるのです。
また、ゲームには明確な目標と達成感があります。「勝つ」「クリアする」「答えを当てる」といった目標に向かって努力することで、学習へのモチベーションが自然と高まります。ゲームに勝つために自発的に日本語を使おうとする姿勢が生まれるのです。
失敗を恐れない環境を作る
日本語学習者、特に初中級レベルの学習者の多くは、「間違えたら恥ずかしい」という心理的な壁を抱えています。教室で手を挙げて発言することに、強いプレッシャーを感じる学習者は少なくありません。
ゲームの素晴らしい点は、この心理的な壁を下げてくれることです。ゲームという枠組みの中では、間違いは「失敗」ではなく「ゲームの一部」として受け入れられます。誰かが間違えても、クラス全体で笑いに変えられる雰囲気が生まれます。
言語習得においては、この「間違いを恐れない環境」が非常に重要です。不安やプレッシャーが高い状態では、言語習得が阻害されてしまいます。ゲームによってリラックスした雰囲気が作られることで、学習者は安心して日本語を使うことができ、結果として学習効果が高まるのです。
クラスの一体感を高める
多国籍の学習者が集まる日本語教室では、文化的背景の違いからコミュニケーションがうまく取れないこともあります。しかし、ゲームには言語や文化の壁を超えて、人と人をつなぐ力があります。
チーム対抗のゲームでは、学習者同士が協力し合う必要があります。お互いにサポートし合い、一緒に喜び、時には悔しがる。こうした共通体験が、クラスの一体感を生み出します。
特に学期の初めやクラス替え後など、まだ学習者同士が打ち解けていない時期には、ゲームは「アイスブレイク」として非常に効果的です。
また、ゲームの中では普段あまり発言しない学習者も、自然と参加しやすくなります。教師から指名されて答えるのではなく、ゲームのルールに従って自然に順番が回ってくることで、プレッシャーが軽減されるのです。結果として、すべての学習者が平等に発言の機会を得られるようになります。
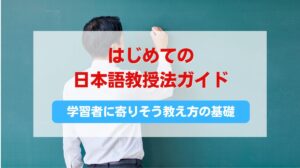
授業が盛り上がる!日本語学習アクティビティ7選

ここからは、実際に教室で使える具体的なゲームアクティビティを7つご紹介します。それぞれのゲームについて、必要な準備、進め方、そして指導のポイントを詳しく解説していきます。
1. しりとり(テーマ縛り)
| 対象レベル | 初級後半〜中級 |
|---|---|
| 学習目標 | 語彙の活性化 発音練習 瞬発力の向上 |
日本の伝統的な言葉遊び「しりとり」は、日本語教室でも大変有効なアクティビティです。基本ルールは皆さんご存知の通り、前の人が言った言葉の最後の音で始まる言葉を言っていくというものです。
進め方のコツは、ただのしりとりではなく「テーマ縛り」を設定することです。例えば「食べ物だけ」「動詞だけ」「学校に関係する言葉だけ」など、学習している語彙カテゴリーに合わせてテーマを決めます。これにより、単なる語彙の羅列ではなく、特定の分野の語彙を集中的に復習することができます。
さらに応用として、「形容詞しりとり」では、前の人の言葉を形容詞で修飾してから、その形容詞でしりとりを続けます。例:「りんご」→「おおきい りんご」→「いぬ」→「かわいい いぬ」といった具合です。これにより、語彙だけでなく文法の練習にもなります。
- 指導のポイント
学習者が答えに詰まった時は、クラス全体でヒントを出し合う時間を設けましょう。また、出てきた言葉をホワイトボードに書き留めておくと、後で復習に使えます。
2. 絵カード・ジェスチャーゲーム
| 対象レベル | 初級〜上級 |
|---|---|
| 学習目標 | 語彙の定着 説明力の向上 |
このゲームは、カードに書かれた言葉を、その言葉を使わずに説明したり、ジェスチャーで表現したりするアクティビティです。テレビのバラエティ番組でもよく見られる形式で、学習者にも馴染みやすいでしょう。
- 準備する物
-
語彙カード(動詞、名詞、形容詞など)、タイマー
- 進め方
-
クラスを2〜3チームに分けます。各チームから1人ずつ前に出てきてカードを引き、制限時間内(1〜2分)にチームメイトにその言葉を当ててもらいます。ジェスチャーのみのルールにすることもできますし、説明OKにすることもできます。
初級レベルでは「動詞」に絞ってジェスチャーゲームにすると効果的です。「泳ぐ」「料理する」「掃除する」など、動作を表す動詞はジェスチャーで表現しやすく、見ている方も楽しめます。
中上級レベルでは、抽象的な概念や慣用句を言葉で説明させることで、高度な日本語力を鍛えることができます。例えば「責任」という言葉を説明する際に、「何かをしなければならない気持ち」「自分がやらなければいけないこと」など、様々な表現を駆使する必要があります。
- 指導のポイント
説明が難しい場合は、「〜のような」という例示表現や、「〜じゃないけど、〜に似ている」という対比表現を使うようにアドバイスしましょう。
3. 私は誰でしょう?
| 対象レベル | 初級後半〜上級 |
|---|---|
| 学習目標 | 質問文の作成 推測力の向上 会話のやりとり |
このゲームは、自分の額や背中に貼られた紙に書かれている人物や物を、質問をして当てるアクティビティです。参加者は自分が「何者」なのかを知らないため、他の人に質問をして情報を集めなければなりません。
- 準備する物
-
付箋やカード、ヘアバンド(額に固定する場合)
- 進め方
-
各学習者の額や背中に、有名人、職業、動物、物などの名前を書いた紙を貼ります(本人には見えないように)。学習者は教室内を歩き回り、他の学習者に「はい/いいえ」で答えられる質問をして、自分が何者かを推測します。
質問例

「私は人間ですか?」
「私は日本人ですか?」
「私は歌手ですか?」
「私は生きていますか?」
このゲームの優れた点は、学習者が自然と質問文を作る練習ができることです。また、他の学習者の答えから推理する過程で、批判的思考力も養われます。
初級では「〜ですか?」の疑問文に限定し、中級以上では「〜とき」「もし〜なら」などの複文を使った質問も促しましょう。
- 指導のポイント
事前に「効果的な質問の仕方」について簡単に説明しておくと、ゲームがスムーズに進みます。大きなカテゴリーから絞っていく戦略を共有しましょう。
4. うそ(本当)はどれ?
| 対象レベル | 初中級〜上級 |
|---|---|
| 学習目標 | 自己表現 物語る力 聴解力の向上 |
このアクティビティは、各学習者が自分について3つの文を言い、そのうち1つが嘘であることを他の学習者が見抜くというものです。シンプルながら、自己紹介や会話の練習として非常に効果的です。
- 進め方
-
- まず、各学習者に自分について3つの文を準備してもらいます(2つは本当、1つは嘘)
- 一人ずつ前に出て、または席で3つの文を発表します
- 他の学習者は質問をして、どれが嘘かを推測します
- 最後に答え合わせをして、多くの人を騙せた人が勝ち
例



「私は3か国語を話せます」(本当)
「私は富士山に登ったことがあります」(嘘)
「私は料理が得意です」(本当)
このゲームの魅力は、学習者の個性や背景が自然と共有されることです。お互いのことをより深く知ることができ、クラスの親密度が高まります。また、「本当に?」「どこで?」「いつ?」といった追加質問が自然と生まれるため、会話が活性化します。
「私の週末」「私の国の文化」など、テーマを決めて行うこともできます。過去形や未来形の練習にも応用可能です。
- 指導のポイント
嘘を考えるのが難しい学習者には、「実際の経験をちょっと変える」「本当はしたいけどまだしていないことを言う」などのヒントを与えましょう。
5. 文法すごろく
| 対象レベル | 初級〜中級 |
|---|---|
| 学習目標 | 文法の定着 文作成能力の向上 |
市販のすごろくを使ってもいいですし、教師がオリジナルのすごろくボードを作成することもできます。各マスには文法項目や指示が書かれており、止まったマスの指示に従って文を作ります。
- 準備する物
-
すごろくボード(手作りでOK)、サイコロ、コマ
- マスの例
-
- 「〜たことがあります」を使って文を作る
- 「〜ながら」を使って文を作る
- 「もし〜なら」で始まる文を作る
- 「1回休み」
- 「2マス進む」
- 「自由に文を作る」
- 進め方
-
3〜4人のグループに分かれ、サイコロを振って進みます。止まったマスの指示に従って正しい文を作れたら進めますが、作れなかったり間違えたりしたら元の位置に戻ります。
このゲームの良い点は、繰り返し同じ文法項目に触れることで、自然と定着が図れることです。また、他の人が作った文を聞くことで、表現のバリエーションを学ぶこともできます。
- 指導のポイント
グループメンバー同士で答えが正しいかチェックさせましょう。教師は巡回して、難しい場合にヒントを出します。また、特に良い例文はメモしておき、授業の最後に全体で共有すると効果的です。
6. ストーリーテリング(リレー作文)
| 対象レベル | 初級後半〜上級 |
|---|---|
| 学習目標 | 物語構成力 文脈把握力 創造力の育成 |
一人が物語の最初の一文を言い、次の人がそれに続く一文を加えていく、リレー形式のストーリー作りです。予測不可能な展開が生まれ、非常に盛り上がるアクティビティです。
- 進め方
-
- 教師が最初の一文を提示します(例:「ある日、田中さんは不思議な箱を見つけました」)
- 学習者が順番に一文ずつ追加していきます
- ストーリーが完成したら、全体で振り返ります
- バリエーション
-
- 文法縛り
- 「〜から」「〜ので」など、特定の接続詞を必ず使う
- 時制縛り
- 過去形のみ、または現在形と過去形を交互に
- 登場人物カード
- カードを引いて、その人物を必ず登場させる
- 文法縛り
中上級レベルでは、より複雑な文法や語彙を盛り込むように指示を出すこともできます。また、ストーリーの途中で「この後どうなると思いますか」と予測させたり、「もし〜だったら」と別の展開を考えさせたりする活動も効果的です。
口頭だけでなく、紙に書いて回す「書きリレー」の形式にすることもできます。これは特に、書く練習をさせたい場合に有効です。
- 指導のポイント
ストーリーが行き詰まった時のために、「魔法のカード」(ストーリーを大きく展開させるイベントが書かれたカード)を用意しておくと良いでしょう。完成したストーリーは記録して、次回の授業で読み直すのも楽しい復習になります。
7. 背中合わせで絵を描こう
| 対象レベル | 初級後半〜上級 |
|---|---|
| 学習目標 | 指示文の作成 位置関係の表現 聴解力の向上 |
このアクティビティは、一方の学習者が絵を見ながら口頭で説明し、背中合わせになったもう一方の学習者がその説明だけを頼りに絵を描くというものです。コミュニケーションの難しさと大切さを実感できる素晴らしい活動です。
- 準備する物
-
簡単な絵や図形が描かれた紙、白紙、筆記用具
- 進め方
-
- ペアを作り、背中合わせまたは仕切りを挟んで座ります
- 一方の学習者(説明者)に絵を渡します
- 説明者は絵を見ながら、もう一方の学習者(描き手)に口頭で説明します
- 描き手は説明だけを頼りに絵を描きます
- 終わったら絵を比較して、どれだけ正確に伝わったか確認します
- 役割を交代して繰り返します
このゲームを通じて、学習者は「真ん中に」「左上に」「大きい円の中に小さい三角が3つ」など、位置や形を表す表現を実際に使う必要性を実感します。また、「もっと右」「もう少し大きく」といった調整の表現も自然と出てきます。
初級では簡単な図形の組み合わせ、中級では風景画、上級では抽象的な概念図などを使用します。
- 指導のポイント
最初に「位置を表す言葉」「大きさを表す言葉」「形を表す言葉」などをリストアップして提示しておくと、活動がスムーズに進みます。また、描き手からの質問もOKにすることで、双方向のコミュニケーション練習になります。
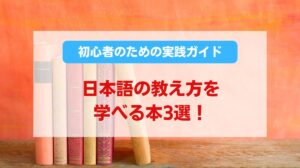
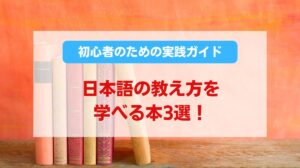
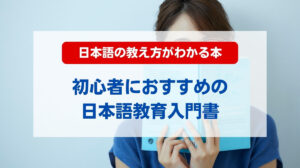
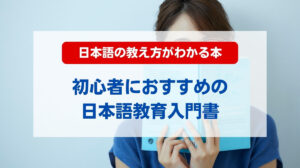
学習効果を3倍にする!ゲーム活用の指導テクニック


ゲームは取り入れるだけでも効果がありますが、以下のポイントを押さえることで、学習効果はさらに高まります。
ゲームを始める前に、「このゲームで何を学ぶのか」を学習者に明示しましょう。
例えば「今日のしりとりでは、先週学んだ食べ物の語彙を復習します」と伝えることで、学習者は意識的にその語彙を思い出そうとします。単なる「遊び」ではなく「学習活動」であることを認識してもらうことが重要です。
ゲームが簡単すぎると学習効果が薄れ、難しすぎると学習者が挫折してしまいます。クラスのレベルに合わせて、ルールを調整する柔軟性を持ちましょう。
例えば、同じ「しりとり」でも、初級では「名詞のみ」、中級では「全品詞OK」、上級では「4文字以上の言葉のみ」など、制約を変えることでレベル調整ができます。
また、クラス内にレベル差がある場合は、チーム分けを工夫したり、レベルの高い学習者にサポート役を任せたりすることで、全員が参加できるようにしましょう。
ゲームの後には、必ず振り返りの時間を設けましょう。「どんな表現が難しかったか」「新しく学んだ言葉は何か」「次回はどう工夫したいか」などを話し合います。また、ゲーム中に気づいた良い表現や、よくあった間違いを全体で共有することも大切です。
教師は、ゲーム中に学習者の発言をメモしておき、特に良かった表現や、よくある間違いをピックアップして、ゲーム後に取り上げると効果的です。「〇〇さんのこの表現、とても自然でしたね」と具体的にフィードバックすることで、他の学習者にも学びが広がります。
ゲームは盛り上がると予定時間を超過してしまうことがあります。しかし、授業の目標を達成するためには、時間管理が不可欠です。タイマーを使って明確に時間を区切り、「あと3分です」などのリマインダーを出しましょう。
また、予想以上に早く終わった場合の「予備のゲーム」や、逆に時間が足りなくなった場合の「簡略版ルール」も準備しておくと安心です。
ゲームの成功には、安心して失敗できる教室の雰囲気が不可欠です。教師自身が楽しむ姿勢を見せ、間違いを笑いに変えられるポジティブな空気を作りましょう。「間違いは学びのチャンス」というメッセージを常に伝え、失敗を恐れずチャレンジできる環境を整えます。
また、ゲームでは必ず勝者と敗者が生まれますが、勝敗そのものではなく「全員が日本語をたくさん使えた」という点を評価することが大切です。小さな賞品やスタンプなど、全員が何らかの達成感を得られるような工夫も効果的です。
ゲームは単発で終わらせるのではなく、定期的に授業に組み込むことで、学習者も「次はどんなゲームかな」と楽しみにするようになります。例えば、「毎週金曜日の最後の15分はゲームタイム」と決めておくのも良いでしょう。
また、同じゲームでも内容を変えて繰り返すことで、学習者は安心してルールを理解した上で参加でき、より深い学習が可能になります。
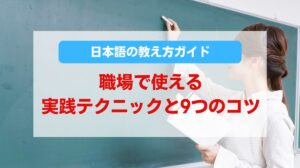
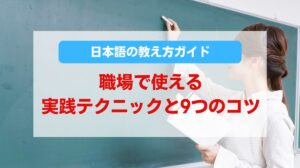
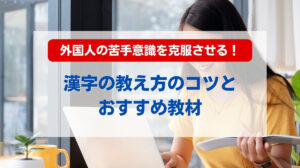
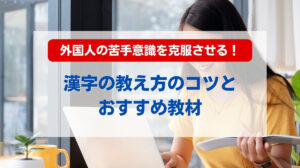
まとめ:ゲームで「教える」から「学びたくなる」授業へ


日本語教育にゲームを取り入れることは、単なる「息抜き」や「楽しい時間」ではありません。それは、学習者が能動的に参加し、失敗を恐れずに日本語を使い、仲間との絆を深める、非常に効果的な学習手法なのです。
今回ご紹介した7つのアクティビティは、どれも特別な教材や準備を必要とせず、明日からでも実践できるものばかりです。最初は小さなゲームから始めて、徐々にバリエーションを増やしていけば大丈夫です。
大切なのは、「学習者が楽しみながら、自然と日本語を使いたくなる」環境を作ること。教師が一方的に知識を「教える」授業から、学習者が自ら「学びたくなる」授業への転換です。ゲームは、その転換を実現するための強力なツールになります。
ぜひ、次回の授業で一つでも試してみてください。学習者の目が輝き、教室に笑い声が響く瞬間を、きっと体験できるはずです。そして、その変化こそが、私たち日本語教師にとって最高の喜びではないでしょうか。
\ 日本語学習システム/